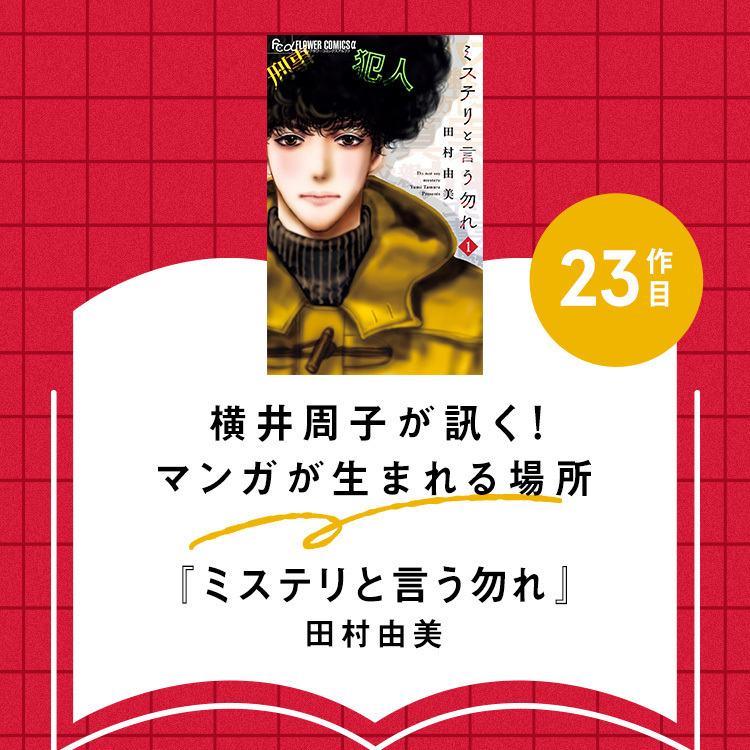『女の子がいる場所は』やまじえびね ¥814/KADOKAWA
“知ること”が、考えつづける力になる
「女の子らしくする」のが苦手な子どもだった。お人形遊びではなく木登りが、スカートではなくズボンが好きで、休み時間は室内にいるよりも、校庭へ飛び出してドッジボールをするのが大好きだった。自分でもうっすらと「男の子みたい」と感じていたものの、好きなものは好きだったし、誰もそれを口に出してはとがめなかった。だから私は、私のままでいられた。
それが恵まれた幸運のひとつだったことに気づくのは、本作のような物語に触れたときだ。主人公は宗教も文化も異なる国で暮らす、10歳の5人の少女たち。各話読み切りで描かれる日常は、「女という性に生まれた」という一点によって、さまざまな制約に満ちている。その理不尽さに戸惑いながらも、彼女たちのまっすぐな視線は、目の前にある現実から決して離れない。
最初に登場するのは、サウジアラビアの首都・リヤドに住む「サルマ」だ。彼女の父は週末にだけ帰宅する。ある日、ミサンガをもっとうまく作りたいと父に話したサルマは、父からミサンガ作りの名人を紹介してもらうことになる。その言葉に反応した母の表情はサルマの心をざわつかせたものの、さっそく会った「アミーラ」は教え上手ないい人で、車の運転もこなす先進的な女性だった。
あとがきによると本作は、新たに担当となった編集者に「これから何を描けばよいのか考えてください」と著者が相談し、提示されたふたつの案のうちのひとつだそう。テーマは、「女性差別を受けている海外の少女たちの日常を描く」こと。著者は多くの参考文献を読むうち、「ここで得た知識を読者と共有したい」という思いがわくことで、作品の輪郭が見えてきたそうだ。
その後サルマは両親の様子から、アミーラが父の第一夫人であることに気づく。一夫多妻制の国で親によって決められた結婚ながら、裕福な夫の支えと理解に感謝していたアミーラ。だが子どもに恵まれなかったことから、彼女はある時、第二夫人を迎えるよう夫に懇願した。アミーラにとってそれは、彼女らしい生き方をするために必要な手段だった。
一方、離婚歴があるサルマの母にとって、父との縁談は貴重な機会。サルマという子を得た結婚生活は、第二夫人である母にとっても“幸福”で、アミーラには感謝している──穏やかにそう語る母に対し、サルマは内心で静かに問いを投げかける。〈わたしたちは結婚しないと生きていけないのママ?〉。将来は父のような医者か弁護士になりたいと願うサルマにとって、母やアミーラのような生き方は、理解はできても共感しがたい選択だった。
「女性だから」というだけで、生き方を決められてしまう国がある。それは私たちのいるこの場所でも、遠い話ではない。最終話の舞台は日本──それが何よりも雄弁に物語る。また、当たり前のように押し付けられる差別や固定観念に対し、「なぜ?」「どうして?」と考えつづけるためには、力や知識が要る。著者は本作を通じて、現実の一端を教えてくれた。その投げかけに、一人では乗り越えきれない困難に、私たちはどうやって手を伸ばし、共に歩んでいくのか。想いを受け止めた先にある未来を、あきらめることなく想像したい。

文/田中香織 編集/国分美由紀