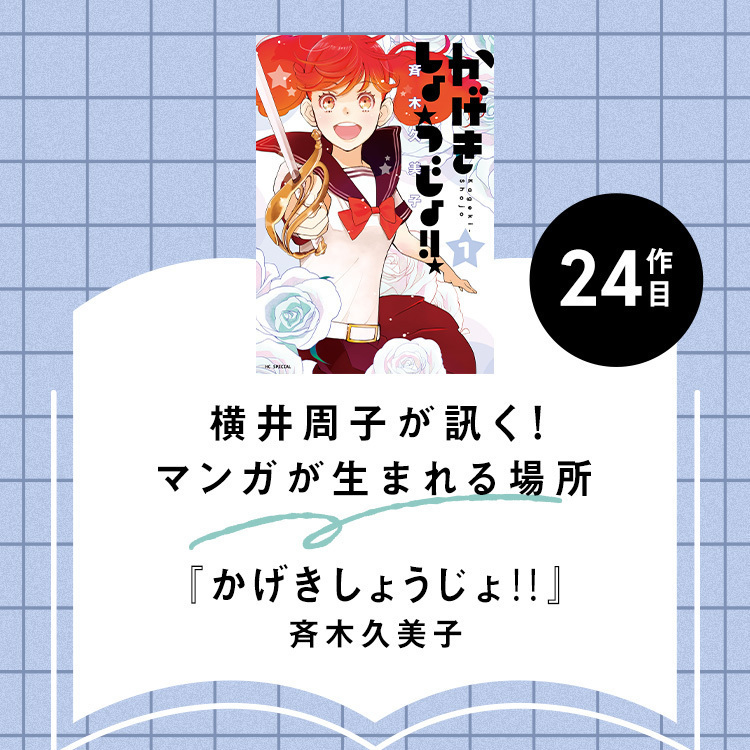日々、当たり前のように行なっている「睡眠」。実は、私たちが健康に過ごすうえで欠かせない重要な役割を担っています。その仕組みや役割はもちろん、睡眠不足のデメリットから“質のいい眠り”を手に入れるためのアドバイスまで、医学博士の西野精治先生に教えていただきました。今回は、「睡眠の役割」について。

Bibadash/Shutterstock.com
Q2.睡眠=単なる休息、じゃない? そもそもの役割を教えて!
医学博士
スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学睡眠生体リズム研究所所長。日本睡眠学会専門医。ブレインスリープの創業者兼最高研究顧問。著書に『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版)、『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社)など。
A2.睡眠は脳の休息や自律神経の調整、記憶の定着など、重要な役割を担っています
そもそも、人はなぜ眠るのでしょうか。実は睡眠には、健康に生きるために欠かせない5つの大きな仕事(役割)があります。
①脳をしっかり休ませ、体をメンテナンスする。
②自律神経やホルモンバランスを整える。
③記憶を整理して定着させる。
④免疫力を上げて抵抗力を高める。
⑤脳の老廃物を除去する。
かつては「睡眠=単なる休息」と考えられてきました。しかし、脳の活動が活発な「レム睡眠(脳は起きているが体は眠っている浅い眠り)」の時間帯があるとわかってからは、眠っている間中「完全な電源オフ」の状態になるのではなく、何かあればすぐに起動できる「アイドリングモード」があると考えられるようになりました。
睡眠が自律神経をリラックスモードに切り替える
自律神経は、心臓をはじめとする内臓の働きや体温、代謝などの調節を24時間休むことなく行なっています。交感神経と副交感神経があり、1日の中でも時間帯や活動状況によって、どちらか一方が30%ほど優位に働きます。
交感神経が優位になると、血圧が上がり、筋肉や心臓の動きも活発になるため、脳も体もアクティブな興奮状態となります。一方、副交感神経が優位になると血圧が下がり、心臓の動きや呼吸も穏やかな状態になります。健康な状態であれば、日中は活動モードの交感神経が優位となり、食後や睡眠中はリラックスモードの副交感神経優位に自然と切り替わります。
ところが、現代人のライフスタイルは、 緊張やストレスから交感神経優位の状態が続きがちで、脳も体も疲れやすくなっています。睡眠は活発な状態の交感神経を弱めて、副交感神経を優位にする役割を担っているので、その機能をうまく生かしたいところです。
睡眠はホルモンとの関係も密接です。代謝や体の成長を促進する「成長ホルモン(グロースホルモン)」は、入眠直後の「ノンレム睡眠(脳も体も眠っている深い眠り)」で分泌が活発になります。生殖や母性行動にかかわる「プロラクチン」は、入眠直後から分泌が始まり、睡眠の後半に増加します。つまり、正しい睡眠が自律神経を整え、正しいホルモンバランスをみちびくのです。
深いノンレム睡眠やレム睡眠が、嫌な記憶を消してくれる
脳には日々膨大な量の情報が入ってきます。すべてを記憶することは不可能なので、“覚えておくこと”と“忘れること”を区別して、必要と判断した情報のみを「記憶」として残します。新しい記憶は、脳の「海馬」という部分に一度入って整理され、「大脳皮質」という部分で古い記憶となり、固定されます。
海馬から大脳皮質への情報の伝達は、眠りはじめの深いノンレム睡眠のときに行なわれます。自転車の乗り方やスポーツ技術の習得など体で覚える記憶(手続き記憶)は、浅いノンレム睡眠で定着します。
一方、「レム睡眠」のときには、経験したことをかつての記憶と関連づけたり、いつでもスムーズに記憶が引き出せるようにひもづけたりと、記憶を整理していると考えられています。特に「レム睡眠」は、電話番号や漢字のように頭で覚える記憶(陳述記憶)と関係が深いと考えられています。
また、ネガティブな感情にとらわれないためにも忘れることは重要です。記憶の消去が行なわれるのも最初の深いノンレム睡眠のときとされていますが、最近の研究ではレム睡眠もかかわっていることがわかりました。
このように、記憶の整理と定着には、睡眠すべての段階が必要なのです。資格試験の勉強やスポーツの練習の後は、特にしっかり眠って、脳が持つ記憶の働きを助けましょう。
構成・取材・文/国分美由紀
出典/『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社)