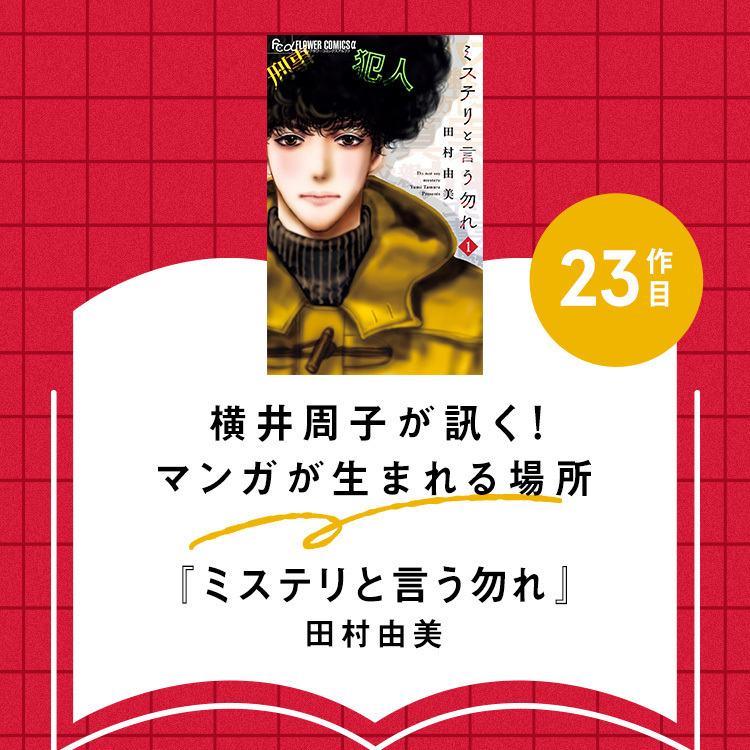「わたしの道はけわしく さみしく 標もなく 先行く人も共連れもなく だがその『何もない』ということこそがいずれ わたしが自由である証であり 標になるのだった」(10巻より)
風変わりな叔母と高校生の姪の二人暮らしを通じて、名前のつけられない関係性やそれぞれの心の傷、社会に対する疑問などをあたたかくも真摯に描くマンガ『違国日記』。静かな感動が読者の間で広がり、累計125万部を超える大人気作となっています。
クライマックス直前の今、作者のヤマシタトモコさんにご自身のさまざまな体験とともに作品に込めた思い、いびつな自分自身や他者との違いを認めながら“わたし”として生きることについて、じっくりお話を伺いました。

©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
違国日記 ¥748/祥伝社
少女小説家の「高代槙生(こうだいまきお)」は、姉夫婦の葬式で遺児の「田汲 朝(たくみあさ)」が親戚間をたらい回しにされているのを見過ごせず、勢いで引き取る。だが槙生は、誰かと暮らすには不向きな自分の性格を忘れていた…。対する朝は、“大人らしくない大人”に見える槙生との暮らしを素直に受けいれていく。不器用人間と子犬のような姪がおくる年の差同居譚。
漫画家
2005年にデビュー。2010年、「このマンガがすごい! 2011」オンナ編で『HER』が第1位に、『ドントクライ、ガール』が第2位に選出される。『さんかく窓の外側は夜』は2021年に実写映画化&TVアニメ化。現在連載中の『違国日記』は2019年から2年連続で「マンガ大賞」にランクインしたほか、「第7回ブクログ大賞」のマンガ部門大賞を受賞。「全人類に見てほしい」など、共感や絶賛の声多数。
人と人はわかりあえない。それでも、超えていこうとすることの美しさ

©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
――『違国日記』では、「他者との距離」がテーマのひとつになっていますよね。年齢も性格も異なる槙生と朝の二人暮らしを通して、お互いの違いを認めながらどう折り合いをつけていくかが丁寧に描かれています。なぜこのテーマを選ばれたのでしょうか。
デビュー前だったかな、講談社の四季賞(『アフタヌーン』主催の新人賞)をいただいたあと、最初の打ち合わせで、当時の担当編集者から「どんなものが描きたいの」って聞かれた時に、「人と人は絶対にわかりあえないっていうことを描きたいです」と言ったんです。
――おいくつくらいの頃ですか。
23歳とかでしたね。たぶん質問の本質から外れた答えではあったんですけど、時間が経ってもその思いは変わらず私の中にあって。私の根本的な考え方として、現実的に人間はわかりあえないものであるし、それを大前提にしたうえで、「それでも」と超えていこうとすることが、物語においてすごく美しいパートじゃないかと思っているんです。


©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
――槙生と朝だけでなく、それぞれの友人とのやりとりなども通して、さまざまな関係性の中に起こる「人と人はわかりあえない。…それでも」という瞬間が描かれていて、心を揺さぶられます。
最初は、中年に差しかかるぐらいの女性と10代の女の子のイメージが漠然とあったんです。年代の違う女性同士の連帯であるとか、ひと言でカテゴライズできない愛情・友愛・敬意みたいなものを描けたらと考えていました。
――35歳の槙生と15歳の朝。なぜ年齢差のある二人を主人公にしようと思われたんですか。
描き始めたときの私はちょうど35歳で、その頃から自分より若い人たちのことをすごく考えるようになったんですね。これは自戒を込めてですが、こんなに中年が無責任でいいのかという気持ちがありました。若い人たちにこの社会を悪いまま渡していいのか、私にお渡しできるものがあるとしたらなんだろうか、と。そういう思いも含めて、若い人たちが困難にぶつかったとしても「それで終わるわけじゃないよ」「一回の失敗では終わらないよ。まだまだまだ」って伝えたい気持ちがあったかもしれない。
だから、優しいマンガを目指しました。みんなが疲れていてしんどい時代なので、あまり悲しませたりとか精神的な負荷をかけず、楽に読めるように。…と考えて描き始めたんですが、最近は「読んでいると本当にエネルギーを使います」と言われることが増えましたね(笑)。
――『違国日記』というタイトルも、お話の本質に触れるすごくいいタイトルですよね。異なる価値観を持つ他者に対するリスペクト。
耳慣れた言葉でも、一文字違うと違和感が生まれて面白いし、検索で見つけやすいから(笑)。当時ずっとやっていた「ファイナルファンタジーXIII」シリーズのネーミングにも影響を受けたと思います。


©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
「自分に似てる」と思える登場人物がくれる居場所
――作家の槙生は、凛然としつつも不器用なキャラクターですよね。すごく素敵な人だなと感じるけれど、生きづらさも抱えています。亡くなった姉からの「なんでこんなこともできないの」という言葉が呪いのように引っかかっていたり。
私は30歳ぐらいのときに「発達障害」という概念を知って、「えっ、私これじゃん!!」ってめちゃめちゃびっくりしたんです。自分はダメな人間だと思っていたことが、たまたま持ち合わせた特性によるものかもしれないと気づいたときに、これまでフィクションでこういうキャラクターが描かれたことはあったかなと思って。槙生は、もともとはそのプレゼンテーションとしてのキャラクターでもありました。当時はまだ今ほど発達障害が知られていなかったので、「これは私だ」って思ってくれる人が一人でもいればラッキーだと思いながら描いたんです。いろいろな対処法にたどり着くきっかけにもなりえるし、もしかしたらお話の中で魅力的にも見えるのではないかと思って考えたキャラクターですね。
――知ったことで楽になれることってたくさんありますね。
対処法の選択肢が増えますからね。ただ、槙生がちょっと良い人に見られすぎているなと思ったら嫌な部分を描いたりして、微調整はしているつもりです。キャラクターのことを崇拝してしまうのはあまりよくないと思うので。
――フィクションの中でそうしたキャラクターを描く際に意識されたことはありますか。
啓蒙するために描いているわけではないので、面白く読めることが第一ですが、「ああ、この人はこういう人なんだな」と読者が理解できる程度には説明をしつつ、過剰に説明しないことでしょうか。まわりにはオープンにしていない状態だけど、あなたの近くにもこういう人がいるんじゃないかと想起させるような描き方をなるべくしようと。というのも、私は小さい頃に物語からの疎外感がすごくあった人間なので。
冒険に出るのはみんな男の子で、お姫様はみんなかわいくてたおやかで。その中に私はどうしたって入れないし、それでも憧れてしまうというジレンマがありました。自分と似たキャラクターはどこにもいない。すごく寂しくてくやしい思い出です。だから小さな脇役でも「あ、自分に似てる」と思える人がいたら、それだけでもうその物語は成功なんじゃないかと思っているんです。いろんな属性の人にとってそういう体験があるべきで、『違国日記』ではそこを意識的に描いているところはありますね。
――さまざまなセクシュアリティの人たちが登場するほか、朝を「最大公約数の主人公」と仰っているのも同じ理由からでしょうか。
そうですね。朝は最大公約数のよいところも悪いところも両方持っているというか、高校時代だけ少し光るようなものがある気がしないでもないけど、結果的には本当に平凡。そういう人が主人公になるシチュエーションが好きですね。それこそが輝かしい人生だとも思うし。

©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
女性の性欲も、パートナーシップも、社会への違和感も描く
――槙生と、元パートナーである笠町くんの「衛星」のように縮まらない距離感や、朝の親友・えみりとしょうこの女性同士の恋。どちらのパートナーシップにも、はっとする描写があります。
「一見すごく強そうに見えるけど弱くて、その弱さを自分で受け入れていることこそがかっこいい」男性を描きたいと思ったんですよね。笠町は、そういう新しいかっこよさを備えている人。彼と槙生の関係は名前をつけづらいものだけれど、そこにちょっとときめいていただけたら。4巻で二人のキスシーンを描いたら、担当編集者がすごく喜んでくれました(笑)。
――槙生が笠町くんにムラムラする回(20話)ですね。
あの回は、「女の性欲を全肯定していくぜ」って気持ちで描きました。
――日本では“女性の性欲”がないことにされすぎていますよね。そして、えみりとしょうこが雨の日にデートするエピソード(47.5話)では、結婚という未来の選択肢が今の彼女たちにはないことが示唆されていて切なかったです。
あの話は「心が温まった」という感想もたくさんいただいたけど、本当は逆のことを描いたんですね。彼女たちがいちばんしたい約束ができない社会に今私たちが生きていて、それを「私たちが」許してしまっているのだと。そこを描きたかったけれどうまく伝わらなかったかもしれないという反省があったので、53話で少しだけ補足をしました。もし現実社会の婚姻制度が変わったら、私は彼女たちの後日譚を描きたい。でも変わらない限りは絶対描きません。


©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
――そういう社会に変えていきたいですよね。作中ではこうした問いかけも自然に描かれていますが、政治や社会に対するスタンスを意識されたきっかけはありますか。
いつのまにか変わっていったので何が契機か自分でもよくわからないのですが、この10年くらいのあいだに自分も身近な友人たちも政治への関心が強くなっていった気がします。友人たちとは、「あの映画が面白かった」「この服が好き」と同じレベルで政治の話をしますね。あと、マンガが政治的になってつまらなくなるということはないだろうとも思っているので。
――まったく賛成です。政治や社会に触れずに成り立つ表現はないですから。
何年も前に「ポリコレ」(※ポリティカル・コレクトネス。人種、信条、性別などの違いによる偏見や差別を含まない中立的な表現や用語を指す)が話題になったときに、マンガ家の友人同士で「これは、より面白くなるってことだよね」って話していたんです。差別的な表現によって物語から排除されてしまう人が少なくなれば、より読者が増えて、物語を面白いと思える人が増えていくわけですから。
――本来はポジティブなことですよね。『違国日記』の10巻でも、基本的人権に触れるすごくいいシーンがありました。
自己肯定感が下がっていく朝に向けて、高校生だって社会の一部なんだということをどう表現しようか考えていて湧いたアイデアでした。人間が文明社会の中で考えうる、究極的に人道的な基礎を明文化したものの大事さ、みたいな。ひいてはそれが社会全体につながって、よくも悪くも私たちが社会から切り離されることはない。物語としてはうまく収まった一方で「読んでいる方たちに煙たがられてしまうかも」という懸念があったのですが、すごく肯定的に受け止めていただきました。あのシーンは、私にとっては小さいけれど新しい成功でしたね。


©ヤマシタトモコ/祥伝社フィールコミックス
続く後編では、誰かを愛することやさみしさ、作中にもたびたび登場する「なりたいわたしになる」ことについて、ヤマシタトモコさんに伺っていきます。
取材・文/横井周子 編集/国分美由紀