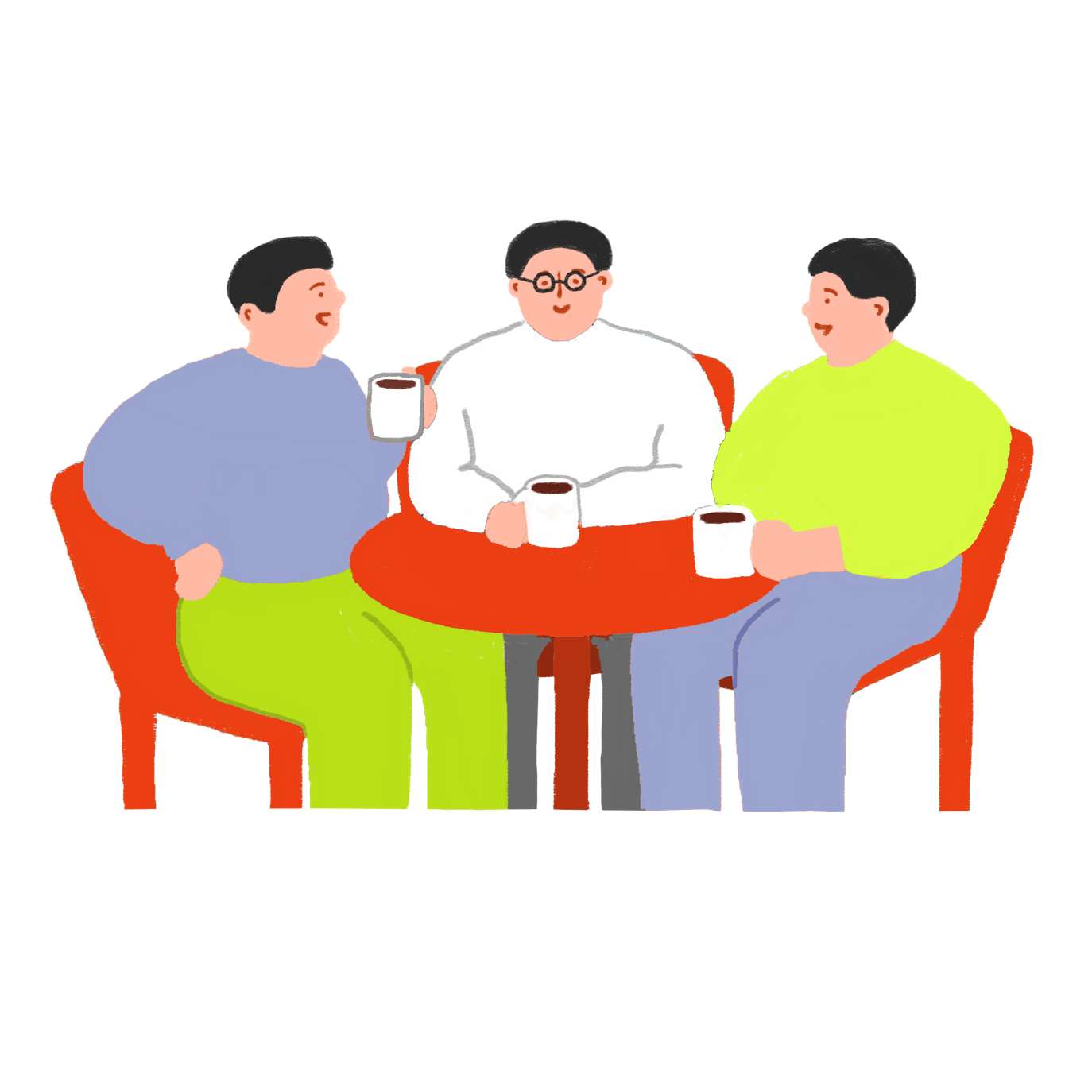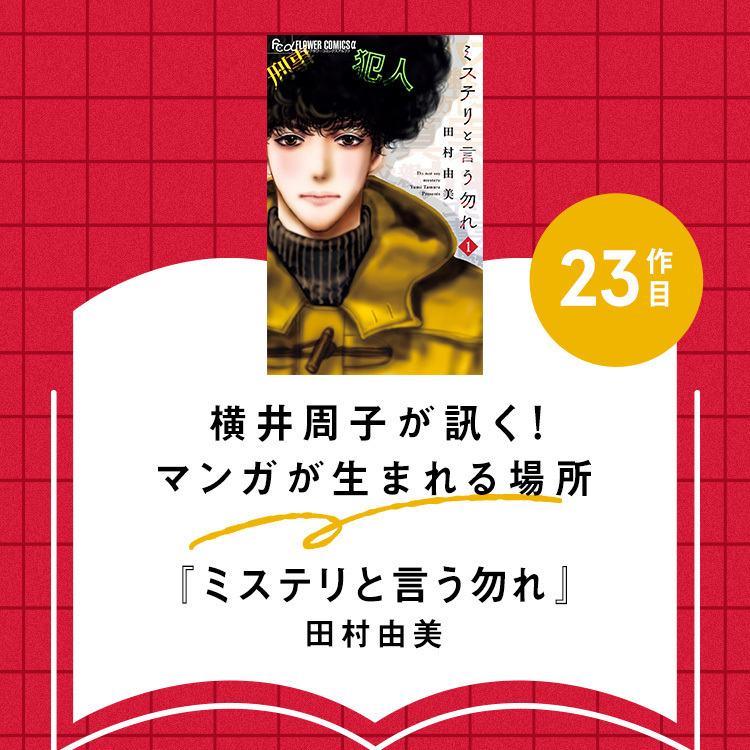『希望の灯り』
デジタル配信中 DVD ¥4180/発売:彩プロ/販売:TCエンタテインメント
© 2018 Sommerhaus Filmproduktion GmbH
日常にきらめく、かけがえのない瞬間
毎日同じ職場に通い、同僚と顔を合わせ、同じ動作を繰り返す。それは一見、単調で退屈な日々のよう。だけどそこにこそ美しくかけがえのない瞬間を見つけだそうとする。そんな映画が、私は大好きだ。
ドイツ出身のトーマス・ステューバー監督の『希望の灯り』は、まさに日常のなかの美しさに目を凝らした映画。原題は『In den Gängen(通路にて)』。タイトル通り、主な舞台は、旧東ドイツ、ライプツィヒ近郊の田舎町に立つ巨大なスーパーの通路。ただし、映し出されるのは、客が皆帰ってしまった閉店後の姿だ。ひと気のないスーパーは暗く寂しい場所に思えるけれど、だだっ広い店内にほのかに灯りがともる様は驚くほど美しく、荘厳だ。整然と並ぶ大きな棚と通路を上から眺めれば、そこはあたかも宇宙基地のよう。走り回るフォークリフトの音と、従業員の一人が趣味でかけるクラシック音楽が重なり、アンサンブルが奏でられる。
このスーパーに、背中や腕にたくさんのタトゥーを入れた寡黙な青年「クリスティアン」が新人としてやってくる。飲料部の在庫管理係に配属された彼は、無愛想だが面倒見のいい上司「ブルーノ」のもとで仕事を学んでいく。棚に商品を補充する方法、台車の使い方、必要なものの見分け方、フォークリフトを自由に操るコツ。ブルーノとその仲間たちは、仕事中のささいな楽しみ方も教えてくれる。休憩時間にこっそりとサボったり、ゴミの中からごちそうにありついたり。互いに教え、学びながら、クリスティアンとブルーノたちは徐々に絆を深めていく。
そしてこの通路で、クリスティアンは、棚の向こう側にいた菓子部の女性「マリオン」と出会う。彼女に夫がいると知りながら、ひかれていくのを止められない。二人の距離がぐっと近づくのは、クリスマスイブの夜。終業後に開いたパーティーで、クリスティアンは、以前の職場でボスを殴りクビになったと、マリオンに打ち明ける。なぜ殴ったのかと聞かれた彼は、ためらいながらも、ボスから「この用無し」と罵倒されたからだと告白する。
〈僕は“用無し”じゃない〉。マリオンの手をそっと握りながら、クリスティアンはつぶやく。それは、若い頃に荒んだ生活を送っていたらしい彼が、ずっと心に秘めていた思いだ。その彼の背中を、彼女はぎゅっと抱きしめ返す。彼が必死の思いでこの言葉を絞り出したのがわかったのだ。だがこの日を境に、マリオンの態度は急変する。理由もわからぬまま突然距離を置かれたクリスティアンは困惑し、荒んだ生活に戻りはじめる。かつての心の傷が再び開いたかのように。
誰にも言えない痛みを抱えているのは、クリスティアンだけではない。マリオンにも、そして彼らを心配そうに見守るブルーノにも、心の奥底に仕舞い込んだ傷がある。〈僕は“用無し”じゃない〉というクリスティアンの言葉は、ここで働く誰もが、心の中でつぶやいている言葉かもしれない。
実は、このスーパーで古くから働く従業員たちは、東ドイツ時代に同じトラックの運送会社で働いていた旧知の仲。ベルリンの壁が崩壊し東西ドイツが再統一したあと、運送会社が大型スーパーに変わり、彼らはそのままここで働くことになった。だが、全員がその変化をすんなりと受け入れられたわけではない。時代が変わり、自分が“用無し”だと感じた人もいるだろう。過去への郷愁に耐えきれなくなることもあるはずだ。ブルーノもまた、時代の変化をいまだ受け入れられずにいた。それでも、ここには自分を必要としてくれる場があり、孤独を分かち合える仲間がいる。それを支えに、今日も明日も、彼らは通路へやってきては、同じ動作を繰り返すのだ。
人生には時に悲劇が起こる。痛みに打ちのめされながらも、クリスティアンは毎日仕事に通い、同じ動作を繰り返す。作業着を着て、道具をポケットに入れ、鏡の前で襟をただし、棚の商品を確認しては補充する。繰り返される日常のなかで、彼はゆっくりと新しい一歩を踏み出していく。ここが自分の居場所なのだと、ブルーノが教えてくれた。すでに見慣れた通路で、彼は今日もかけがえのない一瞬を発見する。
文/月永理絵 編集/国分美由紀