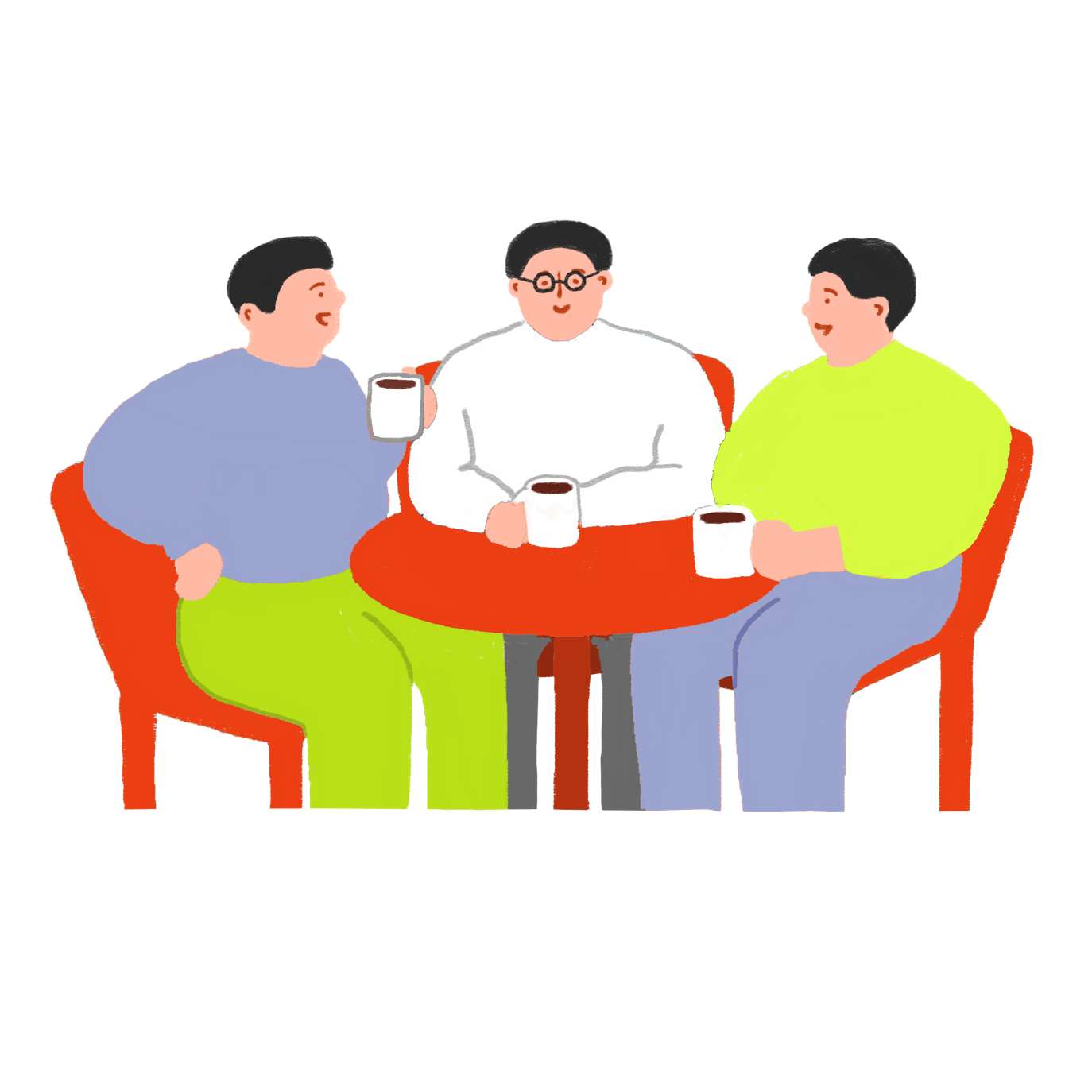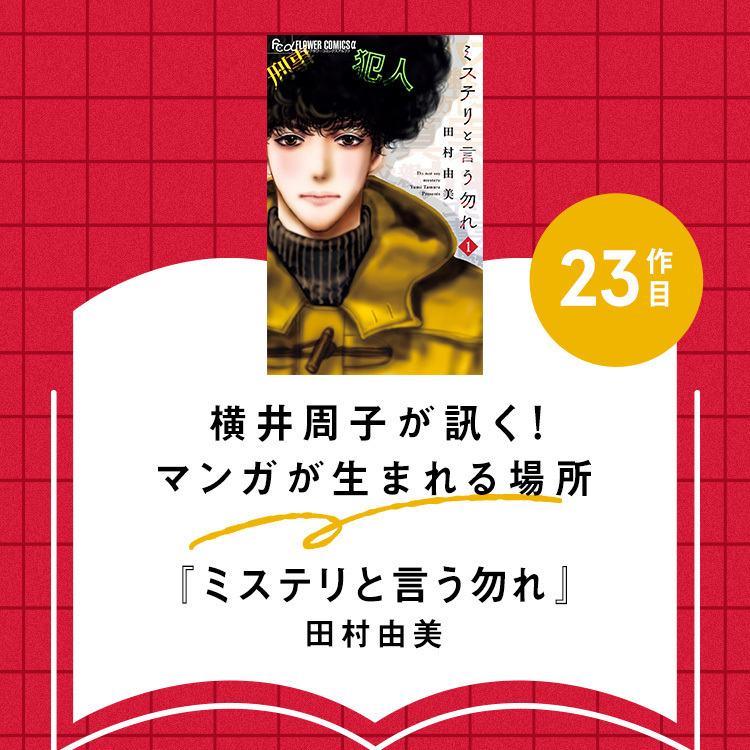『信仰』村田沙耶香 ¥1,320/文藝春秋
「信じること」をめぐる8つの短篇&エッセイ
信じるものがあるということは、人を強くさせるのだろうか。それとも脆くさせるのだろうか。村田沙耶香さんの最新刊『信仰』は、6つの短編小説と2つのエッセイを通して、信じることの危うさと不確かさを描く。
表題作は、「原価いくら?」が口癖の現実主義者「永岡ミキ」が、同級生の「石毛」から「カルト商法」を始めようと誘われるシーンから始まる。あまりにも杜撰なその計画に呆れ、後日ミキは友人とのお茶会で笑いのネタにするが、一緒になって石毛を嘲笑う友人たちをよく見れば、原価にしたら安価な化粧品やアクセサリー、数年前まで誰もやってなかった鼻の穴のホワイトニング、聞いたこともないブランドの高級皿に大枚をぽんぽんはたいている。それだけのものを捧げる価値があるはずだと、皆それぞれに信じているのだ。
かつてその非合理性を指摘したことが原因で友人も恋人も離れていってしまった過去を持つミキは、以降「原価いくら?」を封印しているが、それでもやっぱり彼らを理解できない。
〈お姉ちゃんの『現実』って、ほとんどカルトだよね〉
妹から言われた一言が頭から離れず、「現実」へ勧誘できないのならそっち側に行こうと決意し、〈騙される才能がある人間になりたい〉と自らカルト商法に踏み込んでいく。
かくしてミキは「天動説セラピー」なるものに10万円を支払い、白い布を体に巻きつけ変な踊りをしながら仲間とともに「洗脳」の瞬間を待つのだが――。その姿のなんと哀しく、切実であることか。
そう感じてしまうのは、私自身が信仰の心地よさを知っているからだ。
例えば自分にとって心地良い考えや耳障りのいい言葉に出合ったとき、人はもっと強くそれを感じ取れるようになりたいと考える。そうして「仲間」ができれば、そこが「居場所」になって、「正義」が生まれる。時に異物となる声が聞こえてくれば、大ボリュームで音楽をかけるように正義を叫んで「一体感」を保つ。それは時に、異なった考えや言葉、趣味嗜好を持つものを軽んじたり否定したり、あるいは社会から排除したりする危うさをも含む。
だから私は何かを信じることがとても怖い。その怖さとは、自分が何かを信じているときの「いい感じ」を侵されたくないあまり振りかざしてしまう、正義に対するものでもある。
さらに読み進めていくと、どんな言葉を使って生きるかもまた、その人の信仰につながっていくことに気づく。例えばそれは「多様性」という言葉。エッセイ『気持ちよさという罪』では、多様性という言葉の本当の意味をわかっていないと自覚しながらも、気持ちよさに負けて安易に用いた罪を綴る。
また、『彼らの惑星へ帰っていくこと』では、自分を地球上の異物だと感じていた著者が、〈イマジナリー宇宙人〉との出会いによって、地球で起きている奇跡を見つめられるようになった幸福を綴る。そしてこう語るのだ。
〈地球は、私が現実に触ることができる唯一の星だ〉
子供の頃から「普通」ができず、まわりになじめず、異常なほど繊細で神経質で気が弱く、目立たないよう必死でふるまっていたにもかかわらず「異物」のままだった著者が、それでも唯一触れることのできる現実として、地球という星を思おうというのだ。
大げさでなく、私にはこの一文が美しく発光して見えた。
村田沙耶香の信仰に触れ、ふたたび、信じることについて考えてみる。

1980年生まれ。中央大学大学院にて太宰治を研究。10代から雑誌の読者モデルとして活躍、2005年よりタレント活動開始。文筆業のほか、ブックディレクション、イベントプランナーとして数々のプロジェクトを手がける。2021年8月より「COTOGOTOBOOKS(コトゴトブックス)」をスタート。
文/木村綾子 編集/国分美由紀