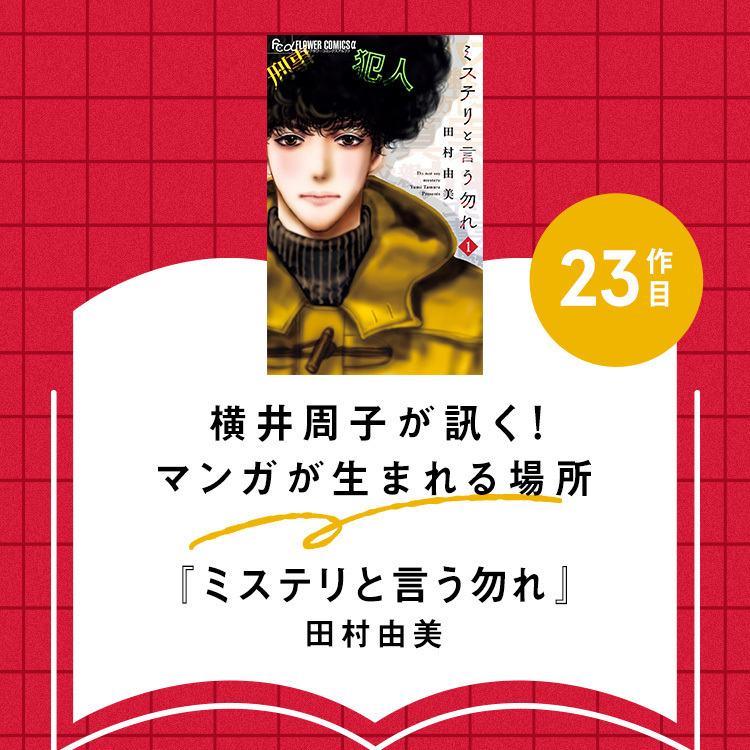「BAILA」「クーリエ・ジャポン」ほか数々のメディアで執筆するライターの今祥枝さん。yoiの連載「映画というグレー」では、正解や不正解では語れない、多様な考えが込められた映画を読み解きます。第1回はイザベル・ユペール主演、現代の社会問題がテーマのこちら。

国家を揺るがすスキャンダルへ発展した内部告発者の実話

『ピアニスト』『エル ELLE』ほかで国際的にも高く評価されているイザベル・ユペール。「正しいと信じること」のために声を上げたことから国家的スキャンダルへと発展する実話で、主人公のモーリーン・カーニーを熱演。映画の冒頭で、原子力企業アレバの労働組合代表を務めるモーリーンは、同社の傘下にあるハンガリーのパクシュ原子力発電所で女性組合員たちのために闘う意志を力強く示す。
フランスを代表する演技派俳優の一人、イザベル・ユペールが主演を務める『私はモーリーン・カーニー 正義を殺すのは誰?』は、2010年代にフランスで起きた、国家を揺るがすスキャンダルに基づく衝撃的な実話だ。
世界最大の仏総合原子力企業アレバ(現オラノ)社のCFDT(フランス民主労働組合連盟)代表モーリーン・カーニーは、2011年、EDF(フランス電力)の人間から、アレバとEDFが中国と手を組み、低コストの原発を建設するという契約が水面化で進んでいるという内部情報を得る。
それはフランスの原子力技術が中国に渡り、従業員5万人の雇用が失われる可能性のあるハイリスクな技術移転契約だった。モーリーンはリスクを顧みず、自らの正義を信じて内部告発者となる。しかし、そこである事件が起きる。モーリーンが自宅で何者かに襲撃され、レイプされ、酷い身体的、精神的暴力を受けたのだ。
しかし、捜査の結果、警察は襲撃事件は彼女の自作自演の虚偽だと断定。モーリーンは権力に屈して自白を余儀なくされ、有罪となってしまう。このあまりにも理不尽な状況に直面した彼女は、その後、長きにあたる冤罪をはらすための過酷な闘いに身を投じていく。
劇中でも言及される福島の原発事故後の世界で、フランスの原子力発電と中国との問題は、現在の経済的な不安定さにもつながる深刻な問題だろう。そうした事情を背景にした物語は、監督が語っているようにアメリカの政治サスペンスの名作『大統領の陰謀』や『インサイダー』を彷ふつさせる。
これらの作品の内部告発者、権力に挑む側は男性だ。一方、本作でモーリーンが受けた数々の理不尽で残酷な仕打ちは、フランスの男性優位社会と特権階級による権力の濫用を前にして、社会や組織における女性の立場の圧倒的な弱さをあらわにしている。その最たる例が、多大な犠牲を払い、勇気を持って声を上げた女性に対して、レイプでその口を塞ごうとしたこと。
その心身の苦痛も癒えぬ間にモーリーンは嘘つきに仕立てあげられ、世間もまたそのミスリードに同調し、モーリーンという一人の女性が何重にも貶められ、傷つけられたという事実である。

パリの本社で、盟友であり現社長アンヌ(マリナ・フォイス)から大統領命令で解任され、後任には能力に疑問のある会社役員ウルセル(イヴァン・アタル)が就任するらしいと聞かされるモーリーン。6期目の組合代表に再選された彼女は、ウルセルにとっては煙たい存在だ。そうした事情を背景に、告発後にさまざまな脅迫が続く中、モーリーンは2012年12月17日、ナイフで腹部に「A」と刻まれるなどひどい暴行を受け、椅子に縛りつけられた状態で自宅で発見された。
被害者に追いうちをかける権力の濫用と“話が通じない人々”からの二次被害

心身ともにショックを受け、回復などほど遠い状態で、モーリーンは刑事らから被害者としてではなく、最初から容疑者であるかのように扱われる。
モーリーンが襲撃された事件の警察による捜査の過程は、二次被害も甚だしく見るにたえない。心身ともに傷を負っている被害者に対して、警察の目的は最初から彼女の信用を損なうことにあるようにしか思えないものだ。実際に、上層部には政治的圧力がかかっていただろう。
そして、冤罪が生まれるパターンとしてよく語られることだが、徹底して彼女を精神的に追い詰めた挙句、一秒でも早くこの苦しみから解放されるために「罪を認めろ」という構図は、まだこの時代にも通用するのかと歯噛みしたくなる。
モーリーンはほとんどの人間がそうであるように、完璧な人間ではない。しかし、たとえ上から圧力がかかっていたとしても、ここまであからさまにモーリーンの言動に疑いを投げかけ、自作自演だと決めつけ告訴することに対して、男性が多くをしめるとはいえ警察の誰も何も言わなかったかと思うと暗澹たる気持ちになる。
日本でも圧力があるかないかにかかわらず、こうした無神経かつ横暴な警察のふるまいによる二次被害は、よく見聞きすることだろう。
普段から同じ言語の話者同士でも「話が通じない」と思わせる相手に出会うことは、多くの人が日常的に感じていることではないだろうか。あるいはSNS上でなら、日々目にしていることかもしれない。「同じ星の住人なのか?」と思うほどの他者と闘うこと、まっとうな会話を試みようとする不毛さは、本作でもいやというほど思い知らされる。
加えて、この映画で私がもっとも自分ごととしてとらえたのは、モーリーンの冤罪、彼女を意図的に貶めようとするメディアなどの情報に安易に乗っかってしまう世間や関係者たちの反応だ。
バックラッシュの時代に今一度考えたいこととは?

モーリーンはうつ病を発症しながらも闘いを挑み続けた。あり得ないほどの過酷で長期にわたる闘いを支えたものとは?
モーリーンは、自分の周囲の人々の態度の変化にも苦しめられる。いわゆる「梯子を外された」ことがわかったとき、あるいは自分の言葉を否定し、自作自演だと信じる人々の心ない言葉の数々が、どれほど彼女の心を蝕んだのかを想像するだけで胸が痛くなる。世間からも信じていた人々からも、人格を否定されるとは。
被害者の主張を貶めようとする者=敵は、常にそれがあたかも「個人的な問題」であるかのように、個人への攻撃を次から次へと繰り返し、被害者の周囲の人間や法律の信用さえも失わせる。実に狡猾だが効果的なやり口だ。ここで問題にしたいのは、その手口にいとも簡単に乗っかってしまう一般の人々、私たち自身についてである。
例えば、日本でも伊藤詩織さん、自衛隊での性被害を訴えた五ノ井里奈さん、または若い女性やトランスジェンダーへの支援活動・団体などへの常軌を逸した攻撃は後を絶たない。あたかもそうした非難・攻撃には正当性があるかのような、もっともらしいデマや論点ずらしの言説は、被害を訴える人たちの声よりもはるかに多くの賛同者を得て巨大な渦となり、勇気をもって訴えた人々(被害者)に襲いかかる。
これは誰もが加担する可能性のあることなのだ。そのひとつの「いいね」が、1度の拡散が、誰かを苦しめる可能性、最悪死に至らしめることの可能性について、もっと人は自覚的になるべきではないだろうか。
徹底的に痛めつけられたモーリーンにとって、闘いを続けることができた原動力。それは現在、“女性に対する暴力と闘う団体”で働く彼女が、暴力を受けた女性にアドバイスしている「友情をあきらめないで」という言葉に集約されているように思う。おそらく彼女が頼りにできる友情を示した筆頭は、警察も見出すことのできなかった事実を探し出した仏雑誌「L’Obs」の記者で、本作のもとになっている本の著者でもあるカロリーヌ・ミシェル=アギーレだろう。
もし自分が当事者、関係者ではなかったとしても、匿名の人々=私たちにもできることはあるのだと思う。
2017年以降、急速に#MeToo運動は広まった。しかし、今はバックラッシュの時代だ。だからこそ、「私たちは誰の声にまず、耳を傾けるべきなのか?」という原点に立ち返る必要があるのではないだろうか。勇気を持って声を上げた人々に対しては、まずは自分たちと同じコミュニティの一員であるということを前提として向き合う。そのことを再認識する必要があるのではないか。モーリーンの壮絶な闘いの一部を映画でたどりながら、改めてそんなことを思うのだった。

監督は、イザベル・ユペール主演作品『ゴッドマザー』を手掛けたジャン=ポール・サロメ。襲撃事件後のモーリーンに寄り添い続けた仏雑誌「L’Obs」の記者、カロリーヌ・ミシェル=アギーレの著書『LA SYNDICALISTE(組合活動家)』に出合い、本作の企画を立ち上げた。