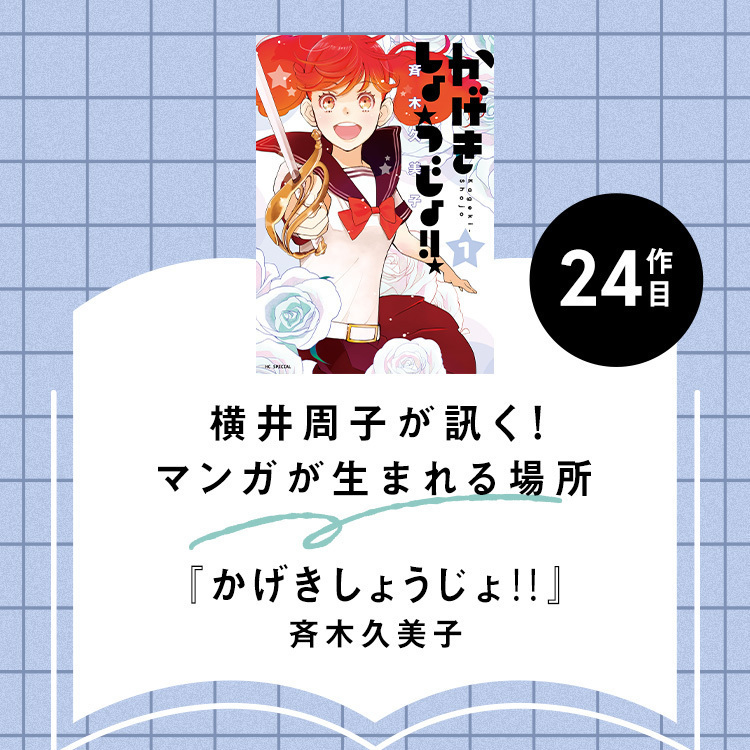日々、当たり前のように行なっている「睡眠」。実は、私たちが健康に過ごすうえで欠かせない重要な役割を担っています。その仕組みや役割はもちろん、睡眠不足のデメリットから“質のいい眠り”を手に入れるためのアドバイスまで、医学博士の西野精治先生に教えていただきました。今回は、「睡眠負債」について。

Alphavector/Shutterstock.com
Q5.最近よく聞く「睡眠負債」ってなんですか?
医学博士
スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学睡眠生体リズム研究所所長。日本睡眠学会専門医。ブレインスリープの創業者兼最高研究顧問。著書に『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版)、『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社)など。
A5.「睡眠不足」が借金のように積み重なっている状態です
「人間は一定の睡眠時間を必要としており、それより睡眠時間が短ければ、足りないぶんが蓄積する。つまり、眠りの借金が生じる」
これは、私が在籍するスタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の創設者であるウィリアム・C・ディメント教授が1990年代から使いはじめた「睡眠負債(sleep debt)」の概念です。
あえて「負債」と表現しているのは、すぐに補えるイメージの「不足」とは違い、気づかないうちにどんどんふくれ上がってしまうことを強調し、警告しているからです。
ペンシルバニア大学が、21〜38歳の健康な48人を4つのグループに分け、それぞれに睡眠時間を決めて行った実験によると、次のようなことがわかりました。
◆6時間睡眠を続けていると、10日後の集中力や注意力は、1日徹夜したときとほぼ同じになる。
◆4時間睡眠を2週間続けると、集中力や注意力は3日間徹夜したときとほぼ同じレベルまで衰える。
徹夜した後なら、疲れや眠気によるパフォーマンスの低下を自覚できますが、ペンシルバニア大学の実験で4時間睡眠と6時間睡眠を続けたグループは、必ずしも脳の働きの衰えを自覚できていませんでした。
小さな睡眠不足が積み重なり、知らないうちに大きな「睡眠負債」におちいっていたのです。気づかないことこそが、睡眠負債の恐ろしさです。
蓄積された「睡眠負債」は、休日の寝だめでは返済できない
睡眠負債がたまると、脳や体にダメージを与える危険因子が蓄積されていくだけでなく、 眠りたい欲求(睡眠圧)も強くなっていきます。平日の睡眠不足を、「休日に寝だめして解消する」という人がいますが、これは、たまりにたまった負債のほんの一部を返済しているにすぎません。
普段から平均7.5時間睡眠の健康な人を対象に、毎日14時間ベッドに入って好きなだけ寝てもらう実験を行なったところ、最初は13時間近く眠るのですが、睡眠時間は徐々に減少していき、3週間後に平均睡眠時間は8.2時間に落ち着きました。
この8.2時間が、実験を行った人の体が生理的に必要とする睡眠量であり、必要な睡眠量より1日40分短い睡眠を続けていると、不足が蓄積されて負債となり、この場合、睡眠負債が清算されるまでに3週間かかったことが判明したのです。
しかも、睡眠負債が解消されると、「好きなだけ寝てもいい」といわれても、体が必要とする睡眠時間以上には眠れない、つまり「睡眠預金」はできないことも明らかになりました。休日の寝だめでは、長くたまった睡眠負債を完全に解消することはできません。“寝だめ”とは呼ぶものの、睡眠を前もってためておく預金ではなく、負債をほんの一部返済しているに過ぎないのです。
構成・取材・文/国分美由紀
出典/『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社)