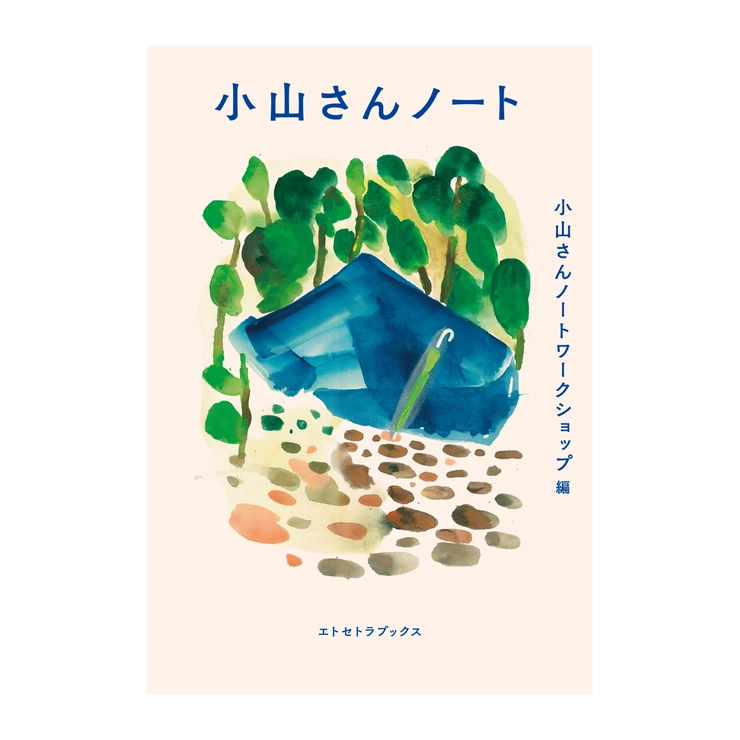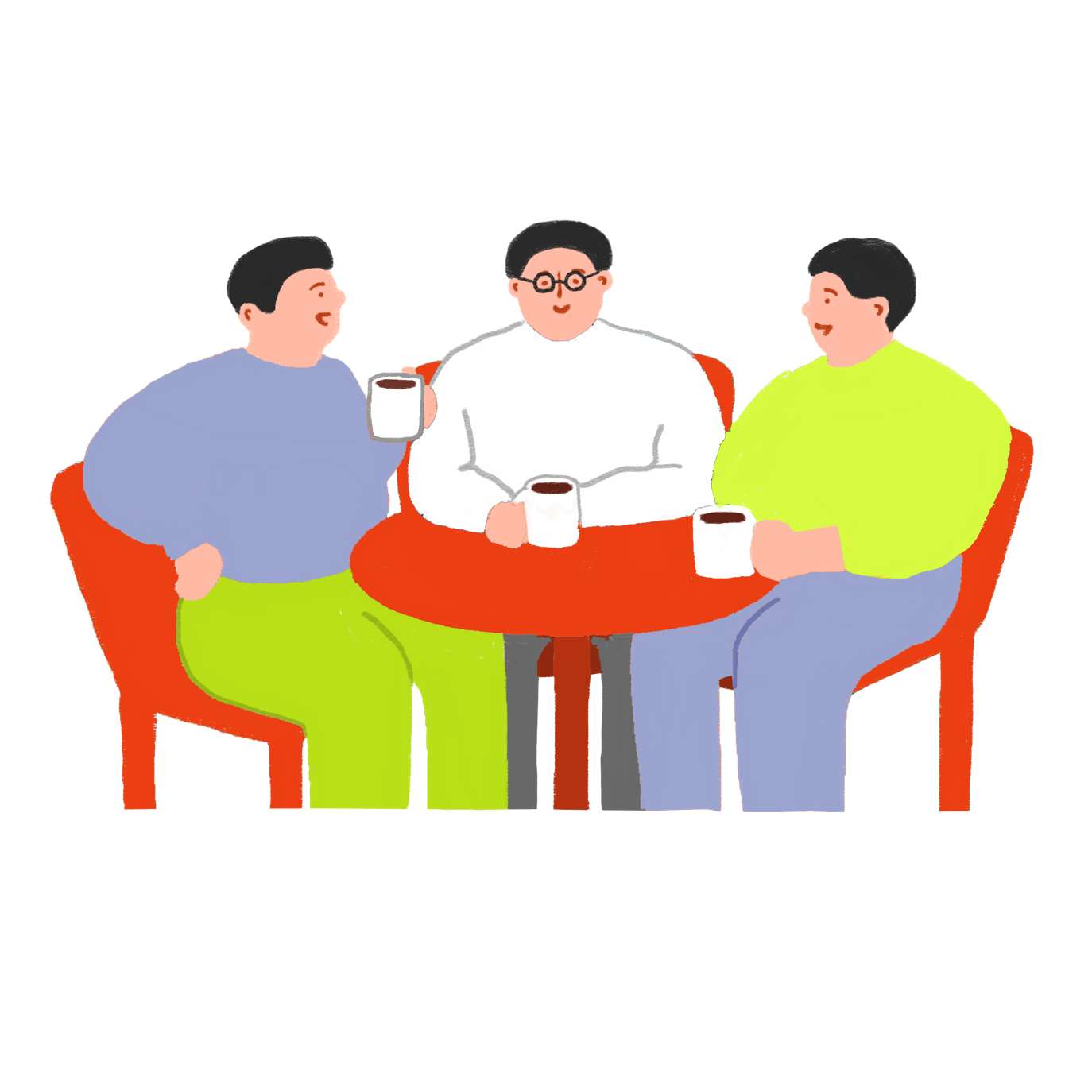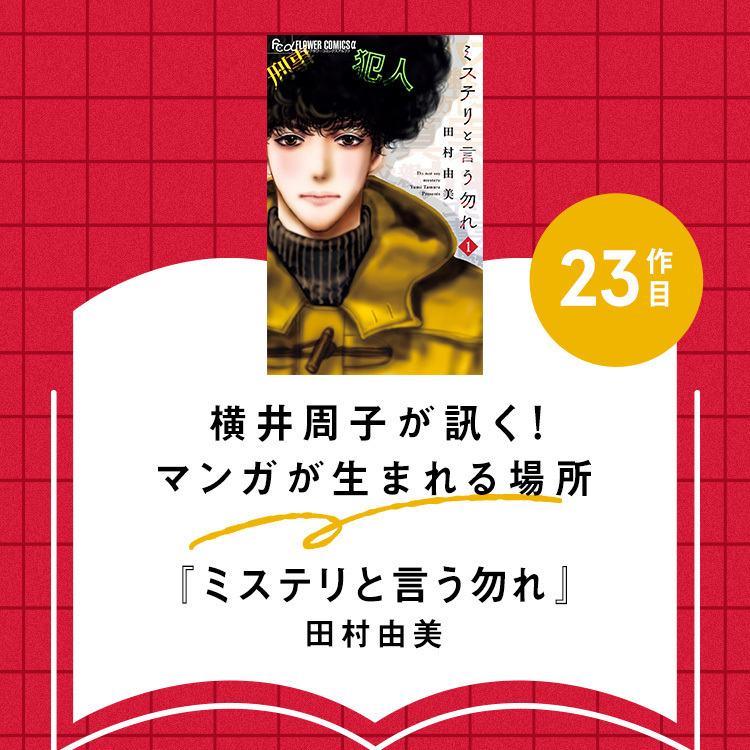日々の暮らしで感じる疑問や喜び、悲しみ、怒り。そうした感情が生まれるのは、わたしたちが「社会」とつながっているから。わたしと地続きにあるこの社会について、それぞれの形で発信を続ける方に、社会とのつながりを意識するようになったきっかけと、これからについて伺っていきます。第2回は、フェミニズム専門の出版社「エトセトラブックス」とフェミニストのための書店「エトセトラブックスBOOKSHOP」の代表を務める松尾亜紀子さん。
エトセトラブックス代表
1977年、長崎県生まれ。編集プロダクションを経て、出版社で編集者として15年間勤務したのち、2018年に独立しフェミニズム出版社「エトセトラブックス」を設立。2021年1月、フェミニストのための書店「エトセトラブックスBOOKSHOP」をオープン。性暴力に抗議する「フラワーデモ」の発起人。
Photo:©SAMSON YEE
「男に負けない女の子」であることを誇りにしていた少女時代

──大手出版社を経て2018年にフェミニズム専門の出版社「エトセトラブックス」を立ち上げ、花を手に性暴力根絶を訴える「フラワーデモ」の呼びかけ人でもある松尾さんが、社会への違和感を感じたのは、いつ、どんなタイミングでしたか?
松尾さん ひとつ挙げるなら、私は九州の生まれで、幼い頃から日常に男尊女卑の空気が満ちていました。ただ、生活する中で「これは男尊女卑だ」と認識していたわけでも「自分は差別されている」と気づいたわけでもなく、むしろ違和感すら感じてこなかったというほうが正しいと思います。
高校生までは成績もよかったし、部活も楽しくやっていて、いわゆる “声がでかい(発言する)”女の子でした。「女のわりによくできる」「男みたいに元気がある」といった褒め言葉を小さい頃から浴びてきた結果、「男に負けない女の子」であることを誇りにしてしまっていたところがあって。
──その刷り込みは実感としてわかる気がします。松尾さんは、その状態からどうやって気づきを得たのでしょうか?
松尾さん 私が10代を過ごした1980〜90年代は、女性の裸や性的に強調した体が普通にテレビで映され、セクハラめいた笑いが当たり前のように消費されていました。10代半ばになると、そうしたカルチャーをはじめ、漫画やアニメ、ドラマなど、見るもの聞くものすべてにおいて、自分が性的に消費される側にいることを自覚すると同時に、「男に負けない女の子」だったはずなのに、男性との性的な関係においては「NO」と言えない自分がいて、「どうしてこうなってしまったんだ?」と。
そうしたモヤモヤを抱えていたとき、確か上野千鶴子さんの社会学の本でしたが、大学の図書館でジェンダーという概念を知り、「このモヤモヤは、ジェンダーの問題だったんだ」と気づいたのが、たぶん最初の自覚です。
フェミニズムは本来の自分を取り戻すプロセスでもある
──本との出合いが大きなきっかけになったのですね。
松尾さん 私は小さいときから何よりも本を読むのが好きで、いつも本と一緒にいる感覚があります。編集者になったのはその延長ですし、いまフェミニズムやジェンダーの本を作っているのも、編集者として今後の人生、どんな本を手がけていきたいかを考えた先にあります。フェミニズムの本を作りたいと思いはじめたのは、出版社に勤めていたときに池澤夏樹=個人編集「世界文学全集」というシリーズの編集部に配属されて、そこで20世紀の女性作家たちによる、それまでの男性中心文学を書き換えてきた素晴らしい文学を知ってからです。ジーン・リースや、クリスタ・ヴォルフ、石牟礼道子などの作品ですね。私もこんな本を誰かと作りたいと思って。
本を作る過程で、当然いろいろなフェミニストにも本にも出会います。そのなかの一人、作家の松田青子さんが薦めてくれた本のひとつに、男性中心だった文学の世界で女性が文学を書くというのはどういうことかを検証した『女性自身の文学 ブロンテからレッシングまで』(みすず書房)がありました。日本の女性解放運動における重要な理論家・山川菊栄の『山川菊栄評論集』(岩波書店)は、自分が編集した本が山川菊栄賞の候補になってから、初めて読んだ一冊です。1890年生まれの山川菊栄は、100年以上前からいまのフェミニズム理論につながることを書いています。
──100年前以上も前から…それは読んでみたくなります。
松尾さん こうした本を読んでいると、社会はいまだに変わっていないんじゃないか…という絶望はありつつも、連綿と連なってきた女性たちの思想や人生に、自分もつながっているんだと感じられるんです。その実感が私を前に進ませているというか。知れば知るほど、こんなにもたくさんの女性たちが「フェミニズム」という言葉が生まれる前から行動し、言葉を残してきたという事実が、私の力になります。それに、最近よく思うのですが、「フェミニズム」ってアップデートしていく作業だけではなくて、それと同じくらい強く、自分を取り戻していくプロセスでもあるよなと。
──そのお話、もう少し詳しく伺ってもいいですか。
松尾さん うーん、例えば、私は小さい頃から、差別がどうしても許せなくて、小学生の頃は「そういうこと、やめなよ!」とか、それはもう頻繁に言っていたんですね。それでいじめられていた子と仲よくしてた。でも、自分もそれによって結構えげつない嫌がらせを受けたり、いじめられていた子に偽善だと見抜かれたのか、「あんたがいちばん嫌いだ」って言われて、がーんとなったり。そのうち、学校や社会の中にある「そういうことを声高に言うのはダサい」とか「自己責任」といった空気に負けた気がします。自分が考える「正しさ」からどんどん離れていくというか、大きくなるにつれて、理不尽な目に遭っても見聞きしても、そういうこともあるよねと黙って見過ごす癖がついていきました。
だから、私は、フェミニズムを知ったことで、あの頃手放してしまった自分にとっての「正しさ」を、私なりに取り戻している気がするんです。あと、「女性はマウントを取り合うし、女の友情なんて存在しない」みたいな刷り込みも世間では強いけれど、私はずっと女友達に恵まれてきたので、それがフェミニズムを信じられる基礎になっているのだろうと振り返ったり。私にとってのフェミニズムは、成長するにつれ浴びてきた刷り込みや抑圧から抜け出して、本来の自分に戻る意味合いも大きいなと感じます。
私たちを「社会」から引き離そうとしているのは誰?

──この連載では、自分と社会とのつながりをテーマにしていますが、松尾さんのお話を伺っていると、刷り込みや抑圧によって生み出される分断や距離感も、目を向けていかなければいけない問題だと感じます。
松尾さん 誰もが生まれたときから相互関係なく死ぬまで一人とはいかないので、社会と自分って、本来は当たり前につながっているものなんですよね。でも、「自分と社会は関係ない」とか「自分と政治は関係ない」とか、いまの私たちはものすごく「社会」という概念から引き離されようとしている。じゃあ、いったい誰がそうさせているのか? と疑うことが重要かなと思います。自分と社会のつながりを自覚するのも大事ではありますが、そこから断絶されようとしている、その現状を認識することも大切だと思います。
私は子どもの頃から、周囲の大人に「政治の話は親しい間柄でもしちゃいけない」って言われて育ってきたけど、いま思うとなんだそりゃ…じゃないですか。私の世代は、いまだにいちばん話さなきゃいけない政治や社会のトピックを「話してはいけない」「話しても意味がない」と思っている人も多い。いまは、それをどう取り戻していくかという過程なんでしょうね。
──その意味では、フェミニズムも「女性が男性並みになるためのもの」や「男性性の否定」といった誤解から偏ったイメージを持たれたり、否定されたりすることも少なくありません。松尾さんがコミュニケーションや発信において大切にされていることはありますか?
松尾さん 基本的に私のまわりはフェミニストが多いので、呼吸をするのがとても楽なのですが、もちろん「どうしてもわからない」と言ってくる人ともたくさん出会います。そういうときは、自分に引きつけて考えてみてほしいなと思います。フェミニズムとは、すべてのジェンダーの人権・尊厳にかかわる思想と運動です。ジェンダーが理由で「自分が自分でなくなる」と感じた場面や、「女性だから/男性だからこうあるべき」と思わされてきたことはたくさんあるはずで。
その背景にある構造も含めて、ひとつずつ変えていこうというのがフェミニズムの運動だから、「私も、私の目の前にいるあなたも、そうやって自分が自分でないことを強いられていたことがありますよね。それを一緒になくしていきましょうよ」というふうにこたえられるといいのかなと。これは、信頼する知人が教えてくれた呼びかけなんですけど。
──フェミニズムは「一人一派」といわれるほど、その形は多様ですからね。
松尾さん だからこそ同時に、“絶対的に正しいひとつの答え”があるわけじゃないということも伝えていく必要があると思っていて。フェミニズムに正解があると考えてしまうと窮屈に感じたり、「自分は足りない」と考えてしまったり、否定されているように感じたりするし、そうすると、なかなか他者の言葉に耳を傾ける気にはなりませんよね。これもフェミニストから学んだことで、「私たちが正しくて、あなたはまちがっている」みたいな差異化は、やってはいけないことだと思っています。
あなたはあなたがやれることを、私は私がやれることを
──本当にそう思います。エトセトラブックスではイベントも積極的に開催されていますが、先のアメリカ大統領選後、SNSなどで「your body, my choice(お前のからだは、俺が決める)※」という言葉があふれたとき、緊急配信された「私のからだは、あなたが決めない my body, my choice. NOT YOURS!」にとても力をもらいました。フェミニズムを取り巻く現状はしんどいことも多いと思いますが、松尾さんはどんなふうにご自身をケアされていますか?
※かつて中絶の権利を守るために闘ってきた女性たちが掲げるスローガン「my body, my choice(私のからだは、私が決める)」を逆の意味でもじったもの。
松尾さん フェミニストの仲間たちと山に登っています。フェミニズムとか読んだ本とか、最近観たドラマとかおいしかった食べ物とか、いろんな話をしながら登り、下山後にビールを飲んでまたねと解散するんですけど、その時間は私にとって大事なケアのひとつになっています。もうひとつは、SNSから離れることですかね。ニュースは見ますし、宣伝などもしますが、SNSに時間を取られないようにしています。
いま、フェミニズムや運動にまつわるいろいろなシーンを見ていると、「自分は足りていない」と怖がる人が多いというか、それだけならいいのですが、「あの人がやっていることを自分もやらなきゃ」と比較して焦ってしまうのかなと感じます。それはひいては、他人への口出しにつながることもあり。本来なら、自分のペースや範囲で動いている人に対して「もっとやれるのに」とか「こういうやり方をすればいいのに」と否定する必要はありませんよね。無理せず、「あなたはあなたがやれることを、私は私がやれることを」っていうスタンスはすごく大事だと思います。
──これまで“エトセトラ(その他)”とされてきた女性の声や、さまざまなフェミニズムの形を届けるために立ち上げられた「エトセトラブックス」は、そうした想いを体現する場でもあると思います。出版社として7年目、書店として4年目を迎えられましたが、「場」としての想いについても伺えますか。
松尾さん まず、私たちの書店には、フェミニズムについて書かれたり、フェミニズムを感じられたりする本が棚に3000冊以上もあるということを見てほしいですね。フェミニズムにはさまざまな形があって、到底一冊の本で完結するものではありません。なかにはいま読むと、「当時は著者の中にもこういう差別意識があったのだな」と感じるものや、現代から考えると古くてまちがっていると思える記述もあります。だけど、それをまた別の誰かがアップデートしたり検証したりして、新たな形で世に出していく。批判もあれば、誰かの考えに影響されて新たな考えが生まれることもある。そんなフェミニズムの歴史も知って、楽しんでもらえたら。
そして、できれば、訪れた人が自分を解放できる場所でありたいと思っています。フェミニズムの話ができて、誰もそれをジャッジしない場所。いまの社会は、みんながまちがえることをものすごく恐れている感じがしていて。相手を尊重することは大前提ですが、「この社会をよくするためにはどうしたらいいか」を一緒に考えていくうえで、意見の違いってすごく大事だと思うんです。ジャッジではなく、批判もし合いながら、一緒にことばを育ていきましょうというプロセスが大事なのかなと。
──松尾さんがおっしゃるように、「批判」とは考えなどを一緒に練っていく過程で、いい点や悪い点をきちんと見つめて検討することですよね。それがいまは、誰かを否定することや、自分の意見を通す手段としての意味合いにすり替わってしまっている気がします。
松尾さん そうですね。ただ、大事にすべきことを共有できるベースがあって初めてお互いに言い合えると思うので、そういう場をエトセトラブックスでつくっていけたらいいなと思います。
Recommended for yoi
「私は韓国ドラマが大好きなのですが、好きな理由のひとつに、あらゆる世代の女性たちが自分の尊厳が踏まれたときに相手に抗議したり、ものすごい悪態をつくからなんです。日本と同じく根強い家父長制の社会の中で女性がつらい目に遭うシーンも多いけれど、自分たちの言葉を持っているのがすごくいいし、励まされるんですよ。ちょっと前のドラマですが、女性同士が助け合う『椿の花咲く頃』とか、最近だと警察官や消防士などフィジカルを鍛えている女性たちの陣地争奪戦を見せるリアリティショー『サイレン〜炎のバトルアイランド〜』。これも松田青子さんが言っていたのですが、フィジカルやメンタルが強い女性って、男性より家庭環境や動機といったドラマを求められがちですが、この作品では彼女たちの職業以外、結婚しているかどうかとか、余計なプライベートが何も明かされない。本はどちらもエトセトラブックスのものですが、『小山さんノート』は、2013年に亡くなるまで公園で暮らしながら膨大な文章を書き綴っていたホームレスの女性が遺したノートを抜粋した一冊。個人の尊厳や自由といったものを、小山さんは生活の営みをノートに記すことで表現したのだと思います。そして、ヴァージニア・ウルフの『月曜か火曜』は、およそ100年以上前に刊行された短編小説集です。歴史を遡ったときに、こんなふうに言っている女性がいたということを知ってもらえたら」(松尾さん)
イラスト/三好愛 画像デザイン/前原悠花 構成・取材・文/国分美由紀