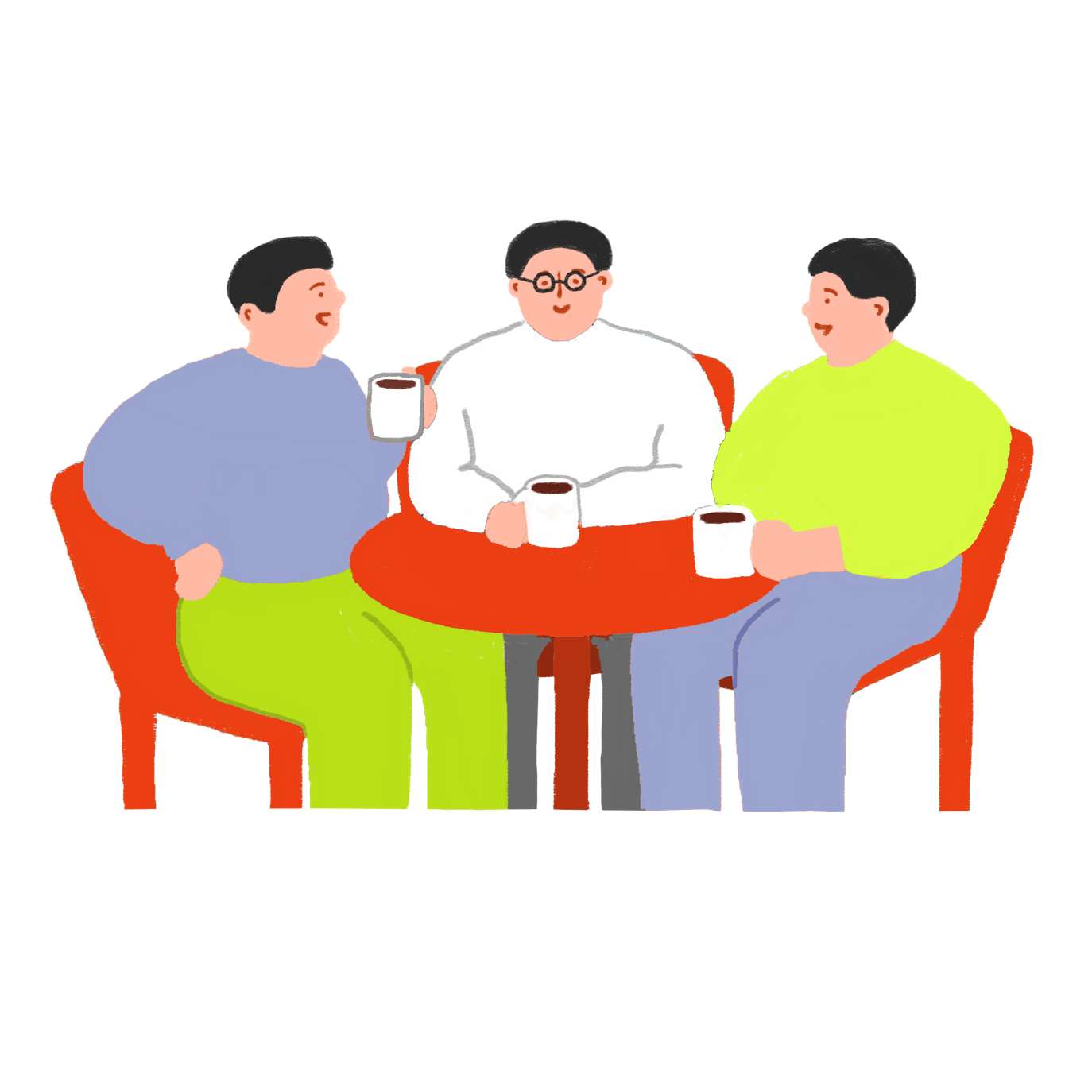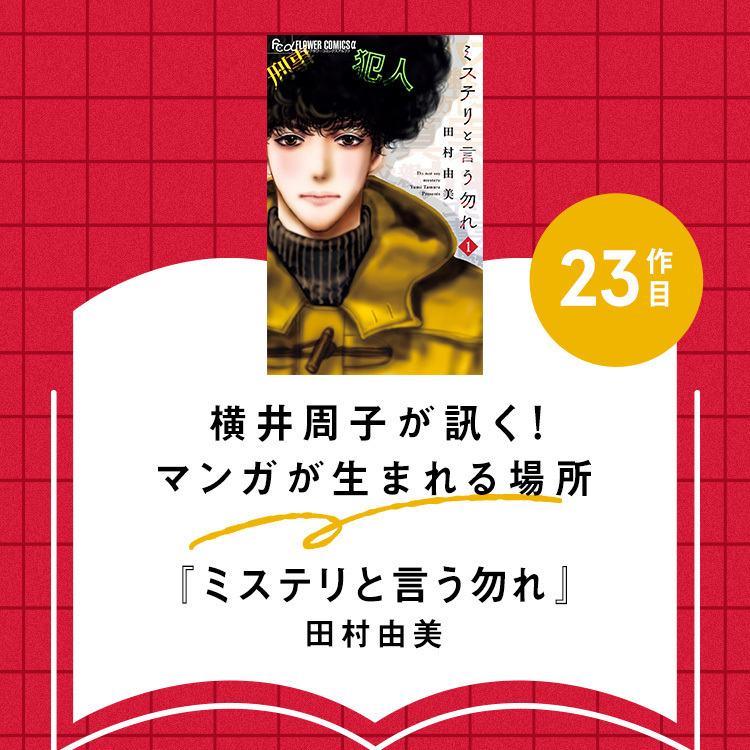『生理用品の社会史』の著者、田中ひかるさんへのインタビュー第2弾は、生理用品の進化を妨げてきた月経タブー視にフォーカス。神秘的領域だった月経が、男性の畏怖感を刺激し、月経禁忌とみなされたのはなぜなのか? 月経禁忌にまつわる驚きの慣習や、使い捨てナプキンがもたらした変化など、現代の私たちの生活につながる月経観の歴史を解説していただきました。


歴史社会学者
1970年、東京都生まれ。女性に関するテーマを中心に、執筆・講演活動を行う。著書に『明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語』(中央公論新社)、『生理用品の社会史』(角川ソフィア文庫)、『「毒婦」和歌山カレー事件20年目の真実』(ビジネス社)、『明治のナイチンゲール 大関和物語』(中央公論新社)などがある。
「タブー」の語源は、実はポリネシア語の月経?

——月経は、古くから世界各地で「穢れ(けがれ)」とされてきたことが田中先生の著書『生理用品の社会史』では明かされています。なぜ、人々から忌み嫌われるようになったのでしょうか。
田中先生:現代でも使われる「タブー」という言葉の語源は、ポリネシア語で月経を意味する「タブ(tabuまたはtapu)」と言われています。月経や経血に対する「タブー視」「不浄視」、言い換えると「月経禁忌」は、世界各地で見られます。
月経がタブーとされるようになった起源については、畏怖心の裏返しだとか、経血が病気を媒介することから危険視されるようになったとか、諸説あります。
——月経禁忌にともない、さまざまな慣習が作られたそうですね。
田中先生:月経禁忌にともなう慣習は、つい最近まで世界各地に存在しており、現在もそうした慣習が見られる地域があります。例えば、ネパールの一部地域では、月経中の女性は穴ぐらや小屋に隔離されます。その間に猛獣に襲われた女性や、蛇にかまれて亡くなった女性もいます。暖をとるために火を焚き、煙を吸って亡くなる事件も何度も起きたため、法律で禁止されましたが、長い間の慣習は根強く残っています。こうした地域では、生理用品が普及していません。月経中は学校へ行けないという地域も世界各地にあります。
日本における月経禁忌の歴史は?

——日本においては、月経禁忌はどのように広まったのでしょうか。
田中さん:歴史学者の成清弘和さんや藤田きみゑさんの研究に見られるように、日本における月経禁忌は、権力者が案出、もしくは大陸から移入したのではないかという説が有力です。その後、室町時代に大陸から伝来した「血盆経(けつぼんきょう)」によって月経不浄視が一般社会に広まりました。血盆経とは、10世紀ごろに中国で成立した偽経です。女性は月経や出産の際に経血で地神や水神を穢すため、死後は血の池地獄に堕ちるが、血盆経を信仰すれば救われる、と説かれました。
血盆経は、江戸時代には女性信者の獲得を目的として、唱導が行われました。近代以降も、血盆教信仰の強かった地域で、より多くの月経禁忌に伴う慣習が確認されています。
生理用品の進化を阻んだ月経不浄視
——月経禁忌が薄れ始めたのは、いつ頃だったのでしょうか。また、そのきっかけは?
田中先生:明治時代に入ると、月経は“富国強兵”を実現するための重要な生理現象と見なされるようになります。月経不浄視は月経を管理することの妨げとなっていたため、当時の医師たちは、月経禁忌の払拭に努めました。
しかし、1000年以上も続いた月経不浄視は、人々の生活に根強く残りました。大正時代に初経を迎えたある女性は、母親や姉とも月経の話をしたことがなく、経血処置の方法も教わったことがなかったそうです。さらに、経血処置用品は「不浄なものだからお日様にあててはいけない」ため洗濯後は物置きに干していた、などの体験談は枚挙にいとまがありません。
経血処置用品は隠すべきもの、月経は“シモのこと”という認識はその後も続き、女性たちの「もっと快適な処置用品を使いたい」という思いを封じ込めていました。生理用品の進化、そして女性の社会進出を阻む、大きな要因であったと言えるでしょう。
明治時代の生涯月経数は50回ほどだった!

——日本では、大正時代の1920年ごろから、生理休暇獲得運動が始まりました。生理中の女性の体を労わるための制度を求める一方で、生理のタブー視が続いていたのは、とても不思議な現象のように感じます。
田中先生:当時は、現代のような生理用品がなかった上に、鎮痛剤も女性用トイレもありませんでした。そのような環境で、女性教師や「看護婦」たちが生理休暇を切実に求めたのは当然でした。
ところで、妊娠・出産を繰り返していた女性たちの月経回数が現代ほど多くなかったということも、生理用品が長い間、進化しなかった理由のひとつです。あくまで平均値での比較となりますが、明治時代の女性は、初経は現代女性より遅く、閉経は早かった。子どもの数を5人とした場合、現代よりも長かった「授乳性無月経」の期間を考慮すると、生涯の月経回数は50回程度だったと言われています。
「アンネ」と呼ぶことで、月経を話題に出しやすくなった

——戦後まで経血処置用品は月経帯などと呼ばれていましたが、月経の代わりに生理という言葉が使用されるようになったのは、いつ頃でしょうか。
田中先生:「生理」という言葉が用いられるようになったのは、労働基準法に「生理休暇」が規定されていたからだという説がありますが、間違いです。生理休暇獲得運動が始まった1920年代にはすでに使われていました。
その後も長らく「生理」という言葉すら憚られる時代が続きましたが、1961年に初めて使い捨て生理ナプキンを発売したアンネ社に、ユーザーから「生理をアンネの日と呼んでいる」というお手紙があったそうです。アンネ社がそれをキャッチコピーとして採用したことから、「アンネ」は月経の代名詞として広く使われるようになりました。月経を「アンネ」と呼べるようになったことで、女性同士でも月経について話をしやすくなり、恥ずかしいことという感情も薄れていきました。
今日「アンネ」は死語となりましたが、「アンネ」と口に出して言えるようになったからこそ、「生理」と自然に口にできる時代が訪れたのだと思います。
快適な生理用品が女性の社会進出を後押しした
——生理に対する女性の意識が変わったことで、女性の生活はどのように変化したのでしょうか。
田中先生:アンネ社の急成長は、それまで停滞していた生理用品市場を刺激し、5年後には後続会社が300社以上にのぼりました。後続会社のひとつ、ユニ・チャーム社が1979年のナプキンの広告で起用した俳優の松島トモ子さんは、生理用品の性能がよくなったことで、長時間の仕事もしやすくなったと語っています。
広告なので多少の誇張はあるかもしれませんが、ナプキンの性能向上が、女性を家庭から職場へと後押しし、すでに働いていた女性たちには安心感と積極性を与えたことは間違いありません。また、1947年に労働基準法に定められた生理休暇が徐々に形骸化した背景にも、生理用品の進化があったと言えるでしょう。
女性の活躍を後押ししたのは、法律や制度のおかげだと思われがちですが、それだけではありません。高度経済成長期の女性の社会進出を促したのは、生理用ナプキンの登場です。あまり顧みられませんが、女性の社会進出を陰で支えてきたのが、生理用品なのです。
イラスト/minomi 取材・文/中西彩乃 企画・構成/木村美紀(yoi)