望まない妊娠はなぜ起こる?妊娠期における男性は“透明人間”なのか?妊娠・出産・育児の生殖における男性の当事者性とは——? ジェンダーの研究を専門とし、ベストセラーとなった『射精責任』(太田出版)の解説を担当された社会学者の齋藤圭介先生にお話を聞きました。聞き手は、yoiで「やわらかジェンダー塾」を連載中の福田フクスケさんがつとめます。
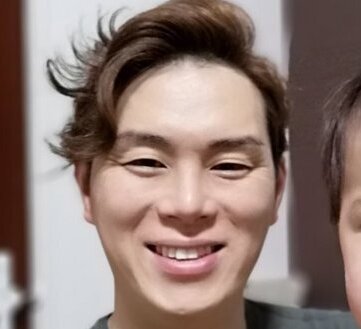
社会学者
1981年、神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。東京大学大学院医学系研究科(医療倫理学分野)特任研究員等を経て、現在は、岡山大学大学院学術研究院社会文化科学学域 准教授をつとめる。専門分野はジェンダー研究、社会学。
『射精責任』は世の中にどう影響を与えたか?
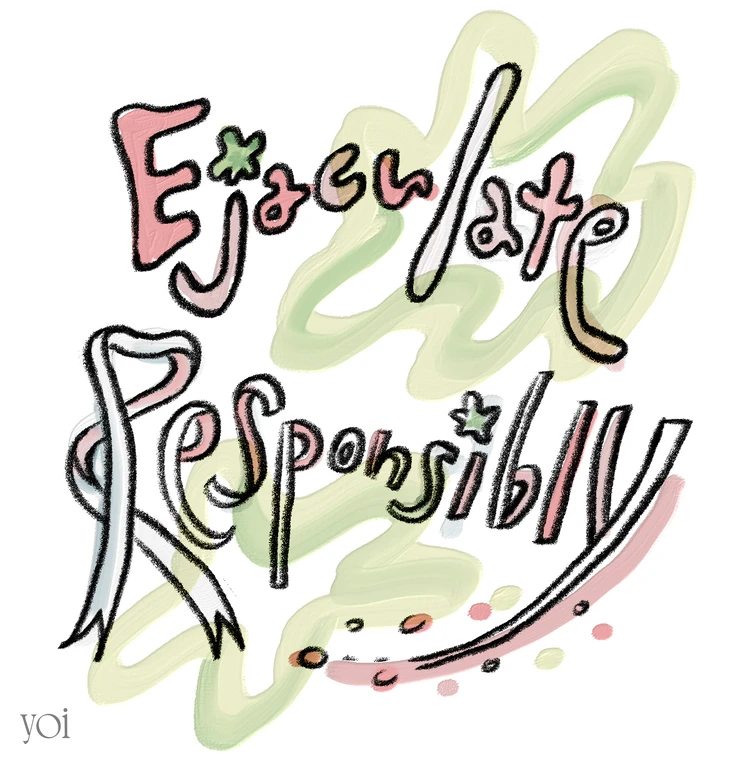
『射精責任』とは?
アメリカの作家ガブリエル・ブレアによる著書『Ejaculate Responsibly: A Whole New Way to Think about Abortion』(2022)の全訳。日本では、2023年7月に『射精責任』(ガブリエル・ブレア著、村井理子訳、齋藤圭介解説)の書名で太田出版から翻訳・出版。
「望まない妊娠は、セックスが原因ではない。男性が無責任な射精をした場合にのみ、望まない妊娠が起きる。彼自身と、彼のパートナーが妊娠を望んでいない状況なのに、男性が精子を女性のヴァギナ(膣)に放出した場合にのみ、それが起きるのだ──」というセンセーショナルな書き出しから始まる本書は、発売前からSNSを中心に話題となり、発売後は各種メディアで盛んに取り上げられた。発売後すぐに重版がかかり、その後発売から2か月を経ずに3刷重版となった。
——齋藤先生が解説を書かれた『射精責任』は、出版当時に大きな話題となりました。
「望まない妊娠の原因は男性にある」「男性にとって望まない妊娠を避けるのは難しくない」―無責任な射精をしなければよいだけなのだから―と主張する本書によって、生殖に関する男性の当事者意識に変化はあったのでしょうか?
齋藤先生:変化があったかについては、やや心もとない部分があります。この本をわざわざ読んで「なるほど」と気づきを得ることができるような男性は、もともと当事者意識が高かった人たちともいえます。本当にこの本を読んでほしい男性たちに本書のメッセージが届いたかというと、そこは課題として残っていると思います。
一方で、明るい変化について話せば、これまで私たちが漠然と思っていたけれどもうまく言い表せなかった「避妊は男性に責任があるよね」という感覚に、「射精責任」という明確な言葉を与えたのは大きな意義だと考えています。
言葉が生まれたことで、さまざまな会話やコミュニケーションが生まれるきっかけになったといえます。実際、「パートナーの枕もとにこの本を置いておくだけで一つのメッセージになる」と言っていた若い人もいました。
——実は、日本では約25年前から、ブレアの『射精責任』と同じような議論がすでにあったそうですね。
齋藤先生:そうなんです。日本の射精責任にまつわる議論については、今年(2025年)の秋に、『日本の「射精責任」論』(太田出版)として刊行されます。今その最終準備を目下進めています。
『射精責任』が出版されたときは、アメリカ社会の本だからとか、著者がモルモン教徒だからとか、いろんな理由でこれが日本社会には当てはまらない特異な議論であるかのように言われました。
けれども、2000年前後にピル解禁論争や人工妊娠中絶の是非論争が巻き起こったとき、日本でもまったく同じようなことが複数の研究者によって議論されていたんですよね。それらを今の大学生たちに読んでもらうと、すごく新鮮に受け止めています。この25年間、射精責任をめぐる私たちのジェンダー意識自体は大きく変わっていないのかなと思うくらいです。
「女性の権利」と「男性の当事者性」はときに対立する
——そもそもの話になりますが、なぜ射精に対する責任感や、妊娠に対する当事者意識を持ちづらい男性がいるのでしょうか?
齋藤先生:これは答え方がかなり難しい問題です。というのも、生殖は男女が共同で責任を負うべき営みだと考えることができますが、「共同であってほしくない」、つまり「女性だけの問題であってほしい」と思っている人もいるのが事実です。しかも、それは生殖における責任を女性に押し付けたいと思っている男性だけではなく、一部の女性たちの主張でもあるんです。
ここでは異性愛の男女を前提に話しますけれども、生殖は男女の共同の営みであるということを強調すればするほど、女性のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(SRHR。性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、女性が自分自身で選択し決められる権利のこと)とは緊張関係が高まってしまう論理構造にあるのです。
「生殖は男にも責任がある」「生殖は男女の共同の営みである」と言ってしまうと、それは一見女性のためでありながら、相当注意深く議論をしないかぎり、生殖において男性に口出しをさせる家父長制的な支配に戻る口実を与えてしまうことになりかねないからです。
男性に積極的に当事者意識をもってもらって、生殖にかかわってほしいと考える女性もいれば、女性だけで生殖が完結する(男性が一切かかわらない)ことが望ましいと考える女性もいるわけです。
——フェミニズムも一枚岩ではないわけですね。
齋藤先生:その通りですね。例えば、母体保護法では中絶に配偶者の同意を求める規定があります。これを女性のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツを無視した人権侵害だと批判する意見がある一方で、産婦人科医にアンケートを取ると、生殖は男女の共同の営みなんだから、当然パートナーの意思決定も必要だ、と考える人も少なくないようです。
また、日本では避妊方法の主流はコンドームですが、これは女性が主体的に選べる避妊手段が少ないという批判がある一方で、裏を返せば生殖において男性に責任感を持たせるチャンスが多いと評価する立場もあります。コンドームの使用率が高いことを評価する際、男性が当事者意識を持っているとしてポジティブに評価することも、女性の避妊手段が限定的であるとしてネガティブに評価することもできます。
男性も当事者として責任感を持って生殖に関われと言われる一方で、生殖は女性の自己決定の領域だから男性は関わらないでくれとも言われる。両方の声がある中で、ジレンマに置かれて、男性個人のレベルでは「じゃあどうすればいいんだ」と思ってしまうこともあるのだと思います。
生殖と性行為が切り離されてしまうのは必然!?
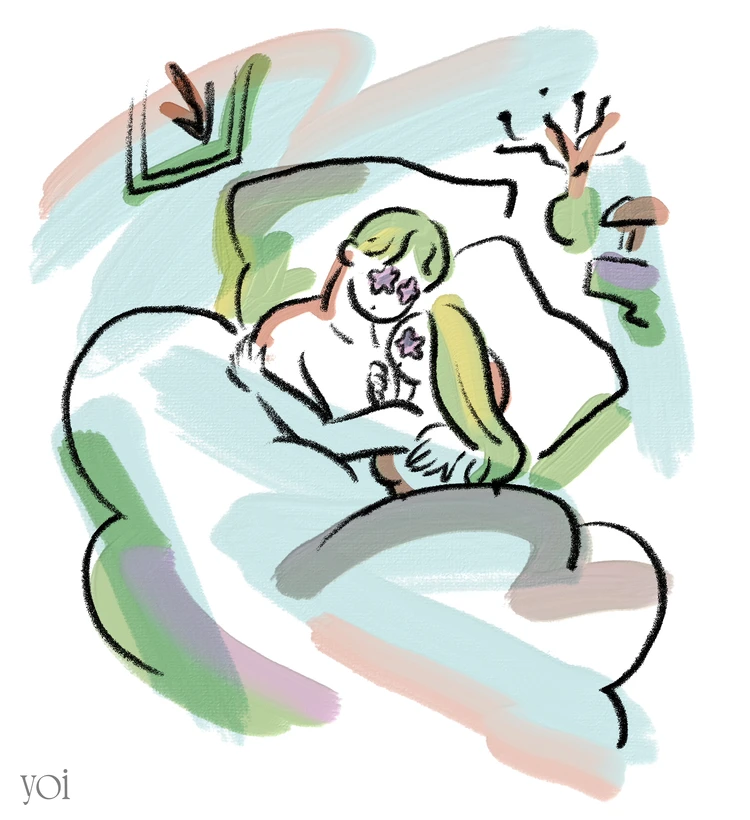
——男性の間では、ときに射精というものが生殖と切り離され、ある種のファンタジーとして消費されている側面もあるように思うのですが、なぜだと思われますか?
齋藤先生:これについては、生殖における男性の無責任さや、有害な男らしさとは別の部分に原因があるのではないかと私は考えています。
というのも、生殖と切り離された「コミュニケーションとしての性行為」の存在を私たちの社会が認めていて、それについての情報をメディアが積極的に発信している以上、射精と生殖が結びつかない人が出てきてしまうのは必然だと思うからです。
どういうことかというと、性行為をすれば必ず妊娠するリスクはあります。何らかの避妊手段を講じていても、実際はそれが不十分で望まない妊娠が数多く起きている。極端な話、妊娠を望まないならば性行為しないことを当たり前にする社会の方が、望まない妊娠は確実に減らせるはずです。でも、みんなそうしようとはしないんですよ。
実態としては、「生殖としての性行為」とは切り離された「コミュニケーションとしての性行為」を多くの人がしています。決して禁欲主義にするべきだとは思いませんし、歴史的にそういうことを試した社会もありましたがことごとく失敗しています。私たちは「コミュニケーションとしての性行為」を求めてしまうんでしょうね。
だとしたら、それは男性の無責任さや男性性の問題というよりも、人類みんなが抱えた矛盾なのではないでしょうか。
——なるほど。とはいえ、生殖と性行為がつながっていることのリスクは、女性の方がよりリアルに感じているのではないかと思います。それを踏まえた上で、男性はどうすれば女性と足並みを揃えて、妊娠のリスクにおける当事者意識を持つことができるでしょうか?
齋藤先生:男性が当事者意識を持つためには、「予期しない妊娠を避ける」ことが大切だと思います。予期しない妊娠、つまり父親になるつもりがないのに子どもができてしまうことこそが、妊娠時だけでなく、妊娠中や出産時、育児も含めて、男性の生殖における当事者意識をかなり下げていると思うからです。
今の若い世代は共働きが非常に多く、計画的に妊娠を目指す方がたくさんいると思います。特に男性不妊の患者さんに顕著ですが、妊活などを経験すると、相対的に父親としての当事者意識は持ちやすいと思います。いつ妊娠していつ出産をして、産休・育休をどれくらい取っていつ職場復帰して保育園はどうする?といったことを夫婦で考えざるを得ないわけですから。
実際は、妊娠・出産・育児は計画的にいかないことの方が多いでしょう。しかし、少なくとも目指すべきロードマップを持っておくことで、父親であることを強く意識する契機にはなると思います。
妊娠中の話し合いが、当事者意識を高める
——男性は、女性に比べて親になる自覚や実感を持つのが遅いと言われることもありますが、妊娠中に当事者意識をきちんと持つにはどうしたらいいでしょうか?
齋藤先生:おっしゃる通り、自覚や実感は母親よりも遅いといわれることがあります。生殖を妊娠前、妊娠中、妊娠後の3つの時期に分けた場合、妊娠前は避妊や射精で男性は当事者になるし、妊娠後は育児で当事者になるべきという話になります。他方、妊娠中は多くのケースで男性が“透明人間”のようになってしまうこともあるのではないでしょうか。
私は一時期NIPT(新型出生前診断)を受けたカップルを対象にインタビュー調査をしていました。出生前診断——お腹の中にいる子に特定の障害があるかどうかが分かる検査——を受けるのかどうか、二人で徹底的に話し合い、父親も母親と同じように悩むことで、妊娠中も男性が当事者になる場面をたくさん見てきました。
当然、結果が出たらどうするかも話し合わなければいけないわけです。子どもに障害があるとわかって、母親がすごく決断に悩んでいたときに、父親も同じように悩んで葛藤し、産むという決断を一緒にしたことで、絆が深まったケースがありました。もちろん、生まれた後も二人で協力して育児をされていらっしゃいました。
妊娠中もお腹の子についての夫婦の会話が増えれば、男性も当事者意識を持ちやすいのではないかと思います。
——父親としてまだ実感がわきにくい時期に、お腹の中の子どもと向き合わざるを得ない機会を得たことで、結果的に当事者意識が強く芽生えたと。
齋藤先生:NIPTを受けたいろんなカップルに話を聞くと、当然かもしれませんが、妊娠中の子どもに対する想いって母親だけが抱くものではないのですよね。父親も母親と同じか、あるいは母親以上に悩む父親もいるんです。
NIPTの例はあくまで一例であり、NIPTを受けた方がいいということではまったくありませんが、妊娠期に話し合う姿勢を持っている夫婦は、結果的に関係性がうまくいっているケースが多かった印象があります。
イラスト/ハタケヤマモエ 構成・取材・文/福田フクスケ 企画/木村美紀(yoi)































