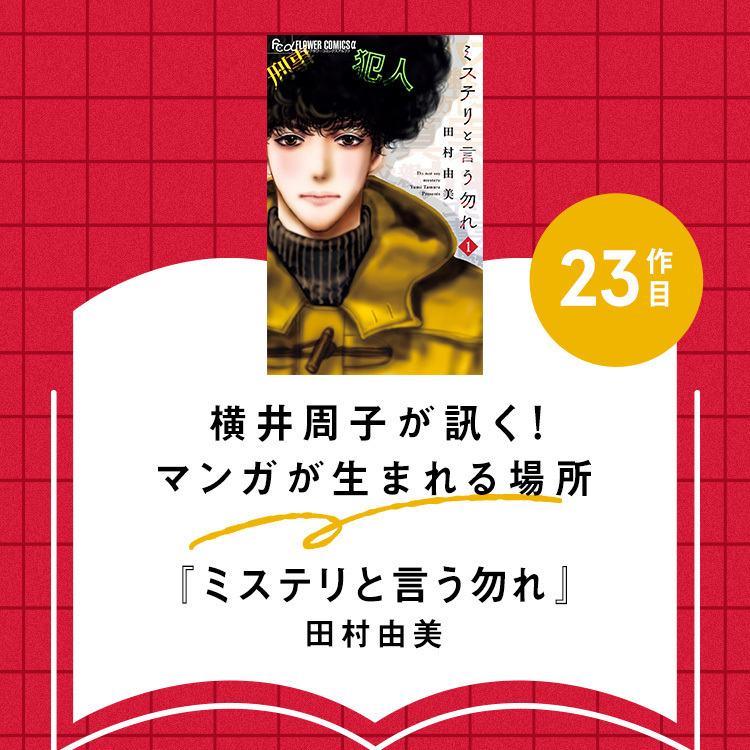今年3月、10年間の日々を綴った書籍『こんな大人になりました』を発売された写真家・長島有里枝さん。その書評を長田杏奈さんが寄稿したことをきっかけに、今回のスペシャル対談が実現しました。前編では長島さんの幼少期から写真家としてキャリアをスタートさせるまでの道のり、妊娠・出産を経て、今の活動にいたるまでのお話を伺いました。
後編となる今回は、エッセイの中でもたびたび取り上げられていた、“年齢を重ねること”について向き合っていきます。二人が憧れていた大人の姿、大人になったからこそできるようになったこと、変化していく外見との向き合い方とは———。

憧れていた女性は、自立していてちょっと派手な“友達のお母さん”
――長島さんは幼少期、どんな「大人」に憧れていました?
長島:友達のお母さんたちに憧れていました。その人はたぶん、夜のお仕事をしていて。放課後、その子のおうちに遊びに行くと、「いらっしゃい」と迎え入れてくれるんです。頭にカーラーを巻いて、アッパッパーを着て、タバコを吸いながら食卓にトランプを並べてソリテアを延々とやってる。その姿がもう、本当にかっこよくて。
土曜の昼間、別の友達に「ごはん食べにおいでよ」と誘われて家に行ったときは、お母さんがいなくて。「お母さんが用意してってくれてる」って、カップラーメンとパックに入ったままのハムをごちそうになりました。カップラーメンに自分でお湯を注ぐのも、ハムをパックからそのまま食べるのも初めてで、楽しかった。そんなことができる友達も「かっこいい!」と思ったのを覚えています。
その子たちのお母さんは、どちらもシングルマザーでした。カップラーメンのお母さんはパーマ屋さんで働いていました。外で見かけたことがあったけど、茶髪でパーマで真っ赤な口紅でした。二人とも、本当にかっこよかった。
長田:それでいうと我が家は、長島さんを遊びに招く側だったかも。母はシングルマザーで美容部員をしていて、かなり派手でした。当時はバブルだったから、金のボタンがついた紫のツーピースを着ていたりして。授業参観で、同級生たちから二度見されていました(笑)。
長島:わ、絶対かっこいい…! 羨ましいです。
――ご著書『こんな大人になりました』には、「子供のときああなりたいと憧れた大人みたいに、わたしもなれるかもしれない」と書いていらっしゃいましたね。
長島:どうだろう。“シングルマザー”ではありますね。
長田:実際は“シングルマザー”の数は多いのに、それが見過ごされていますよね。“夫と子どもがいて、仕事があること”が前提になっていたり、そういう人がメディアなどでも取り上げられやすかったり。
長島:そうなんですね。自分はずっと「嫌なことを言う父の話をおちゃらけて聞き流す母」を見て、モヤモヤしながら思春期を過ごしたんですよね。だから絶対、一人で生きていける人になろうと思っていました。家にいて、おやつからパン、服やバッグまで手作りする母が好きだったけれど、恩着せがましくて面倒だなと思うことも多かった。今思えば、デパートの婦人服売り場で夢をかなえようと仕立ての仕事をしていた若い女性が、結婚して専業主婦になったわけだから、行き場を失った創作意欲をそこに注いでいたんでしょうね。
“よいもの” とされている姿からはみ出した、“オルタナティブ”な大人が必要

――『こんな大人になりました』の中で、「挫折とはみ出しを繰り返してきた」とおっしゃっていましたが、長島さんの「挫折」と「はみ出し」はどのようなものでしたか?
長島:ほとんど全部ですね。むしろ、どこかにうまくはまれた、という実感とか記憶がないです。
――憧れていた大人の話を聞くと、“はみ出している”雰囲気をかっこいいと思っていたのかなと感じたのですが。
長島:たぶん、共感したし、ホッとしたんでしょうね。
長田:そう考えると、長島さんが体験したように、ホッとできるようなリアルな大人の姿がもっと見られるといいのにと思います。社会で“普通”とか“よいもの”とされている姿からはみ出した、“オルタナティブな大人の姿”はあまり提示されない気がする。例えばですが、白髪を生かしたグレイヘアは人気だけど、白髪がまばらに混じっているような、“中間地点の姿”は、メディアなどではあまり見かけないですよね。
長島:私としては、グレイヘアまで“かっこいい”に向かうんだと、ちょっと残念です。
長田:その話、気になります。
長島:そんなになにもかもかっこよくなくてもいいのに、って。なにやっても素敵な自分って、窮屈じゃないですか? わたしの場合、「面白い」のほうが上位なんです。「かっこいい」って、そんなに面白くはないじゃないですか。
昔、ファッション誌の編集長で10本全部の指に大きな指輪をしている人がいたんです。とてもお洒落な方だったんですが、なんかもう見た目のインパクトが尋常じゃなくて、気になってしまって。手を洗うとき石鹸が詰まりそうとか、行進したら重くて指抜けそうになるかなとか、指輪10個で生活する彼女の姿を想像しはじめたら、なんだか面白くなってきて。そこまで苦労しての指輪だと思ったら、急にかっこよく見えました。そうまでしてやりたいことする大人って、魅力的だなぁって。
まわりも自分もケアできる場所をつくりたかった

――3月まで名古屋で開催していたプロジェクト『ケアの学校』について教えていただけますでしょうか?
長島:『ケアの学校』は、役割が一方通行ではない関係性や、一緒に楽しむことでケアされたと感じるような、さりげないかかわりについて考えるための場所でした。完成した作品を見せるというよりわたしがずっとそこにいて、パフォーマンス的に人とかかわっていくプロジェクトです。具体的には、編みものやバレエレッスン、知り合いを招いてのワークショップなんかをやりました。
学校といっても先生はいない、放課後の教室みたいなイメージです。フェミニストと認知されるようになってから、他者のために働く人って思われてるのかな、と感じることが増えたんですが、実はそういうの苦手で。居心地悪いのがすごく嫌、という気持ちだけで、基本は自分のためにやってきたことだと思っているので、イメージが一人歩きしていることにまた居心地の悪さを感じていました。それならいったん、好きなことを再確認しよう! みたいな気持ちで、このプランが生まれました。
長田:プロジェクトの名前を聞いて、最初は長島さんがケアの方法を教えるのかなと思っていました。
長島:いや、むしろわたしが教えてほしいぐらいだったんです。何か相談されても結局、人のことはよくわからないや、で終わるし。隣にいることぐらいしかできないよなぁ、って考えて、だったら設営だけして会期中は作家がいない、通常の展覧会の逆をやろうと閃いたんです。それでも、悩み相談の場みたいにはしたくなかったから、人の話を適当に聞き流せる仕組みをつくりたいなぁ、と思って、編みものやお絵描き、読書やバレエレッスンができるようにしました。
――前編では、今日の長島さんのメイクについてのお話もありましたが、『ケアの学校』でもドラァグ・メイク講習会をされていましたよね。長島さんがこのメイクに興味を持ったきっかけはなんだったのでしょうか?
この投稿をInstagramで見る
長島:理由はよくわからないんですが、子どもの頃から異性装にはひかれていたんです。小学校のお楽しみ会で役と演者の性別が逆転した劇を作ったこともありました。高校のときに『ピンク・フラミンゴ』とか『ロッキー・ホラーショー』のような映画と出合ってハマったり。20代の初めには、ドラァグをやっている友人もできました。ヘテロセクシュアルの性別二元論に、見る人も楽しませながら対抗している彼らに共感と魅力を感じたんだと思う。女性のドラァグクイーンも活躍していることは、最近まで知りませんでした。それまではドラァグって、「女」の自分は属せないカルチャーなのかなと思っていたんです。『ケアの学校』に講師として来てくれたモチェさんがかっこよくて、実際やってみたらすごく楽しかった。自分じゃない人になれる感覚も気持ちよくて、誰に見せるわけでもないけれど、今も日々メイクの研究を継続中です。
「大丈夫と言ってね!」と伝えてから、話を聞いてもらう

――『こんな大人になりました』の中で「歳を取るというのは、暴れ馬のような自分を少しずつ、楽に乗りこなせるようになることなのかもしれない」と書かれていました。長島さんにとって「歳を重ねる」ということは、ご自身にどのような変化をもたらしていますか?
長島:気づかないうちに保守的になっている部分もあると思います。経験値が上がって、「こうしたらこうなる」みたいなことがだいたいわかってくるから、わざわざリスクを取らないで済むことも増えましたし。相手に自分の気持ちを伝えるのは上手になったかもしれない。ここから先はわたしの問題じゃないから任せよう、ということも今のほうが上手かもしれない。自分を大切にすることに、罪悪感を抱かなくなりました。自分のことを好きじゃないとややこしくなるし、そのほうがいざというとき、他の人の気持ちも素直に大事にできるかなと思うので。自分が我慢しない分、他の人が我慢することになるんだとも思わなくなりました。我慢の分量って、ものの質量みたいに決まっているわけじゃないし。どうせ頑張るなら、みんなが楽しい世界を目標にしていいよね、と思います。
――yoi読者のなかには、年齢を重ねることで社会的な立場やまわりから求められる立ち居振る舞い、外見などが変化することに不安を感じている方も多いと思います。長島さん、長田さんならどのような言葉をかけますか?
長島: 不安に思うこと、私もあります。そういうときは誰かに話して、「大丈夫」と言ってもらうかも。
長田:確かに。自分で自分に「大丈夫」というのには限界がありますよね。
長島:そう。そういうときはわたし、「今から話す話、最後は絶対『大丈夫!』って言ってね」ぐらい、パートナーにあらかじめお願いしておきます(笑)。「何それ」って突っ込まれますが、笑いながら応じてくれますよ。言わせたことでも不思議と安心して、なんだか元気になります。ぜひ、誰かとやってみてください。
長田:それ、すごくいいですね!

踊るように闘い、祈るように働く——。気づけばティーンエージャーの息子、生活を共にするようになった恋人。自分だけのために作るナポリタン、国会中継へのやるせない憤り、20年ぶりにこじ開けた鼻ピアス。女性として、写真家として、シングルペアレントとして、生活者として。アラフォーからアラフィフの10年間を月々ありのままに記録した、伸びやかでパンクなレジスタンス・エッセイ! 長島 有里枝(著)/集英社
取材・文/浦本真梨子 撮影/上澤友香 企画・編集/種谷美波(yoi)