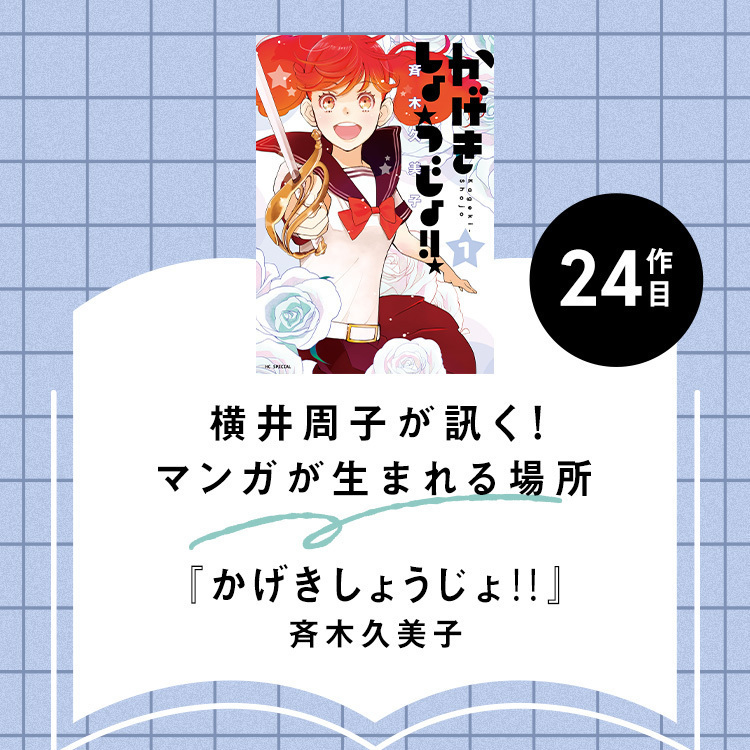創作と性加害をめぐる話題作『恋じゃねえから』。作者の渡辺ペコさんは、公認心理師・臨床心理士としてアディクション(依存症)やDV、家族の問題などに取り組む信田さよ子さんの著書に少なからず影響を受けてきたといいます。『恋じゃねえから』の完結を記念して、作品から立ちのぼるさまざまな問題提起について、お二人が語り合いました。
※本記事では作品ストーリーのほか、性加害やDVなどの暴力について触れています。

公認心理師・臨床心理士
1995年に原宿カウンセリングセンター(HCC)を設立。アルコール依存症、摂食障害、ドメスティック・バイオレンス(DV)、子どもの虐待などの問題に取り組む。2022年より日本公認心理師協会会長。『家族と国家は共謀する サバイバルからレジスタンスへ』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン 自己責任の罠を抜け出し、私の人生を取り戻す』(学芸みらい社)、『タフラブ 絆を手放す生き方』(dZERO)『家族と厄災』(生きのびるブックス)、『暴力とアディクション』(青土社)、『母は不幸しか語らない 母・娘・祖母の共存』(朝日新聞出版)など著書多数。

漫画家
北海道生まれ。『YOUNG YOU COLORS』(集英社)にて『透明少女』で漫画家としてデビュー。『ラウンダバウト』(集英社)が第13回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品に選ばれる。2020年に完結した『1122(いいふうふ)』(講談社)は紙+電子累計210万部を突破し、実写ドラマも話題となった。その他の著書に『にこたま』(講談社)、『ボーダー』(集英社)、『おふろどうぞ』(太田出版)などがある。『モーニング・ツー』(講談社)での連載『恋じゃねえから』完結巻が2月21日に発売。
『恋じゃねえから』あらすじ
40歳の主婦・茜は、ある日、中学時代に通った学習塾の講師・今井が彫刻家になったことを知る。彼が発表した「少女像」は、かつての親友・紫(ゆかり)の姿によく似ていた。蘇る26年前の記憶、封印していた1枚の写真。そして私の犯した罪と願い。過去をひもとく現在の3人の運命が動き出す──。『1122(いいふうふ)』の渡辺ペコが描く、創作と性加害をめぐる問題作。
社会が許容してきたアートと性暴力の構造

──最初に、渡辺さんが『恋じゃねえから』でアートと性暴力をテーマとして選んだ理由をお聞かせいただけますか。
渡辺 長いこと、自分も含めて「アーティスト」「作家」と呼ばれる職業の人たちの傲慢さが気になっていたんです。例えば若い女性を被写体にすることや、少女との年の差恋愛などのタブーを扱うことが、「創作」「アート」と言った途端に他者が介入しづらい領域になるというか、善悪を倫理的に問うこと自体が「野暮」であるかのような雰囲気にモヤモヤしていました。大人になった今、暴力を暴力として認識できない社会を含めて、この問題の構造をちゃんと考えてみようと思って描きはじめました。
信田 この作品には、芸術の世界で野放しにされている暴力やハラスメントが描かれていますが、それに関連する形で摂食障害や親子の問題など、いろんなテーマが出てきますよね。どこをとってもひとつの作品になるくらい大きな問題がつながり合う形で遍在していて、読み応えがありました。私の仕事からすると、極端なことが描かれている感じはまったくなくて、よく見聞きする「あるある」な話ばかり。この複雑な現実を、よくこういう表現でひとつの物語としてまとめられたな、素晴らしいなと思いましたね。
渡辺 ありがとうございます。うれしいです。
信田 多様なテーマが埋め込まれているけれど、どの話も興味深くて一気に読みました。これはマンガという表現だからこそ描けた作品じゃないかという気がします。
「作品」の少女像を叩き壊すという決断

──信田さんが特に印象に残っているシーンはどこですか。
信田 やっぱり、紫(ゆかり)と茜が、紫の少女時代の裸を模した彫刻をバーンと叩き壊したシーン。もちろん彼女たちの中に壊したい気持ちはあっただろうけど、本当に壊すとは思わなかったからびっくりして引き込まれましたね。
渡辺 物語の山場として彫刻を壊すイメージは最初からあったんですが、迷いもありました。実際に彫刻家の方に取材させていただいた際に、「もし作品を壊されるようなことがあったら」と質問を投げかけただけでもちょっと硬直される感じがあったので…。誰かが心血を注いだ作品を壊していいのだろうかと何度も考えましたし、主人公たちが明らかな暴力行為を働くことについて、読者に納得してもらえる形に収束できるのかという不安もありました。でも今は、このマンガの中では壊してよかったと思っています。

©︎渡辺ペコ/講談社
──連載開始から間もない頃にお話を伺ったとき、「社会的にも、どうしても女性は男性より力が弱い。物語の中でちょっとそれをひっくりかえしてみたい」と仰っていたのを覚えています。その契機となるシーンでもありましたね。
渡辺 うーん。でも私が描いた物語の中ではひっくりかえせていないんですよね。抵抗は示したつもりだけれども、やっぱりそこを逆転させるのはすごく難しかった。ただ、最近のニュースを見ていると、むしろ現実のほうが先に変わりはじめているのかもしれないと感じます。
自分の加害者性に気づくことの苦しさと難しさ

──2017年にハリウッドの大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインのセクハラに対して起きた「#MeToo運動」などをきっかけに、さまざまな性暴力が少しずつ明るみに出て問題視されるようになってきました。アートやエンターテインメントの世界で、時としてこうした暴力や搾取が起きてしまうのはなぜなのでしょうか。
信田 どうしてなんでしょうね…これはアートやエンターテインメントの世界に限った話ではありませんが、私は、やっぱり加害する側が「自分はいいことをやっている」と考えてしまっていると危ないと思うんですよ。自分は「アート」という特別なものを創っていて、もしかしたら「相手を援助したい」とすら思っているかもしれない。そしてまわりも、被害を受けた当人でさえも「あの人はいいことをやっているんだから」と思ってしまう。「危ない人だ」という認知がどこにもないですよね。
渡辺 私も、加害者をいかにも搾取しそうな悪人として描いたら、この問題はとらえきれないだろうと考えていました。信田さんが仰ったように、一見いいことのように見えるケースが多いから問題なんですよね。グルーミング(性的な接触を図る目的で大人が子どもを手なずけること)を含めて、経緯や信頼、社会的地位など、いろんなものが混ざった関係性の中で搾取が起こる。
さらにそれが「表現者」と「モデル」というアートの世界になると、社会が「芸術だから“あり”」と肯定して受け入れてしまうケースもたくさんあったと思うんです。だから『恋じゃねえから』の加害者である今井は、時代に推されている気鋭の芸術家に設定して、本人も「これは表現だ」と考えている状況を描きました。

©︎渡辺ペコ/講談社
信田 今井を「優しい」と見る人もいるでしょうね。でも、私は気持ち悪かった。救済を求めている女性にすごく敏感で、そこに寄っていって助けてあげる。そして相手がすがってきたところを利用して、自分の欲望を満たす。人によっては「優しくていい先生じゃない。おまけに素敵な作品のモデルにしてくれて」といった見方をするかもしれないし、それを彼自身も内面化していると思う。こういう人は、よくいます。『恋じゃねえから』がすごいのは、そこで被害者が迷いながらも、「これは自分にとっての加害行為だ」ってちゃんと突きつけるじゃないですか。お友達に支えられながらね。
渡辺 それでも今井は、自分の加害者性をなかなか認められなかった。マンガでは、自分の家族が被害に遭うことで初めて今井がはっとする流れを描いたんですが、結局それって家族を自分自身の延長だと思っているから傷つくわけですよね。本当はそれじゃダメだと思うんです。でも、今井はそれぐらいのことでもないと認めないんじゃないかっていう気がしましたね。
信田 自分の加害者性に気づくって、ものすごく苦しいことですから。だからこそ一篇の作品になりえる。今井は幼い息子が被害に遭ってしまったところから、自分の作品が壊されたり加害を突きつけられたりした理由を徐々に理解していきましたが、こういうことは現実にはなかなか起きませんよね。
救いがないと思うかもしれないけれど、性暴力に対しては刑罰しかないと私は思っています。「自分がどれだけ酷いことをしたか」を理解させるより、「これからの人生のために、ああいうことをしてはいけない」という実にプラグマティック(実用的)な動機を持たせることでしか変わらないんじゃないかと思いますね。

『恋じゃねえから』 渡辺ペコ ¥759/講談社
撮影/山本あゆみ 画像デザイン/前原悠花 取材・文/横井周子 構成/国分美由紀