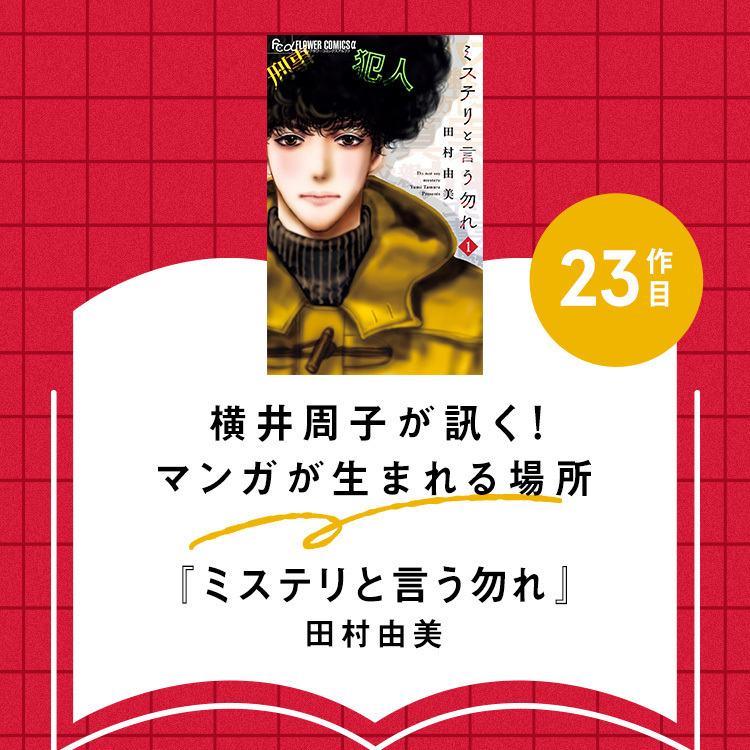著者の石田夏穂さん(左)と長田杏奈さん(右)
前回につづき、先日の第166回芥川賞候補作にも名を連ね、第45回すばる文学賞佳作を受賞した『我が友、スミス』にまつわるインタビュー。著者の石田夏穂さんと長田杏奈さんの対談は、石田さんの思わぬ逆質問から、筋トレと美容の共通点へと移っていきます。
言葉にすることで、新しい価値観が生まれる
石田さん 普段、美容の本はほとんど読まないんですが、今回の対談が組まれる前から長田さんの著書『美容は自尊心の筋トレ』は拝読しておりました。「筋トレ」ってなんだろうと思って手に取って(笑)。読んでみたら、すごくいいタイトルだな、ぴったりだなと思いました。やっぱり筋トレって美容に通じるところがあるのかなと。
長田さん うれしい! 私は美容ライターをしているけれど、もともとどこか「自分に対して美容を施すなんておこがましい」という気持ちがあったんです。そんな自身の屈託を乗り越えていくために、あらためて美容がくれたものってなんだろうと振り返ると、毎日自分に「大丈夫」と言い聞かせるように、己と向き合って積み重ねるスキンケアだったり、「このリップの色とテクスチャー、最高!」みたいな、自分にしかわからないささやかなアゲみだったり…。そうやって、日々自分を大切に思えるような瞬間を積み重ねて、「おこがましい」に負荷をかけて超えていく感じだなぁって。それで、私には「筋トレ」って言葉がしっくりきたんです。でも、最初は「筋トレという言葉は強すぎる」という反対意見もあったんです。救ってほしい人をはじいてしまうんじゃないかって…。でも、ほかにぴったりくる言葉がなくて。他人を救うとか大風呂敷を広げる前に、まずは自分を救う概念を大事にしたいし!
石田さん そうだったんですね。私は、美容における反復具合とか自己に向き合う感じが、「筋トレ」という言葉にぴったりだなと思いました。文章を書くとき、長田さんは何か意識されていることはありますか?
長田さん 特に美容という分野は、ひとつキーワードが決められるとみんないっせいにその“正解”に向かって走るようなところがあるので、あえて少し言葉をずらす意識はしているかもしれません。例えば、現代の感覚では寝起きのむくんでて目力がない顔がビフォーで、美容を施した顔がアフターみたいに設定されがちで、ありのままのむくんだ顔は“間違った状態”と決めつけられてしまう。でも、時系列をズラして“能が流行った時代の、霞とともに現れる幽玄美”と言ってみたりとか(笑)。言葉をずらしてとらえてみるのは大事かなって。
石田さん 言葉にすることで、そういう価値観もあるって思えますよね。
長田さん かつては美容って、女性が美しさを当たり前に求められ、審査される価値観のうえで成り立っていた側面もある。最近はそういうコンプレックス産業みたいなことはやめようというコンセンサスができつつありますよね。

出どころ不明のジェンダーバイアスにどう向き合うか
―――そもそも、石田さんがジェンダーバイアスといった社会課題に興味を持ったきっかけは?
石田さん 誰しもが生きてると思うことからだと思います。「なんで女子生徒の制服はスカート一択なんだろう」とか、そんな小さな気づきからだと思います。
長田さん どこにクレームをつけたらいいかわからないバイアスってありますよね。「いつスカートって決まったの?」「誰の責任でスカートなの?」と、問い詰める先もない。
石田さん そういうものだから、みたいな。
長田さん ある学校に、詰襟のボタンを全部とめなきゃいけない校則があるらしくて、首が締まるから物理的に窮屈で苦しいじゃないですか。なんで全部留めなきゃいけないかというと、近所の人から「学生らしくない」ってクレーム電話がかかってくるからなんだって。一部の知らない人の、出典も年代も不明な「学生らしさ」に合わせて、たくさんの生徒が首をギュッとされるの変じゃないですか? あとは、小学校の卒業式で、いまだに男子は脚を体の幅に開き、手はこぶしをにぎって太ももの上に置く。女子は両足を閉じて右手に左手を添えるって教えられて、ジェンダー感覚がちゃんとした小学生が怒ってました。
石田さんは、そういった“出どころ不明のバイアス”にモヤモヤしたらどうしていますか?
石田さん 私はモヤモヤしたら、書きますね(笑)。
長田さん いつも、どんなタイミングで執筆しているんですか?
石田さん 私は明け方とか朝に書くことが多いです。夕方は疲れているし、余計なことを考えてしまって、なんかダメかなと。
長田さん 『我が友、スミス』には、そうした石田さんの明け方に研ぎ澄まされたモヤモヤへの知見が散りばめられているんですね。
石田さん そうですね。たとえ誰にも読まれなくても、書いたら満足するほうです(笑)。でも、作品として読んでもらえて、誰かに共感してもらえたらなおうれしいですね。
長田さん ボディ・ビルや筋肉には疎くても、このモヤモヤは覚えがあるぞ、って自分ごとに引きつけられる作品の秘密に、ちょっと触れられた気がします。
1991年埼玉県出身。東京工業大学工学部卒。現在は会社に勤めながら執筆活動を行なっている。2021年「我が友、スミス」で第45回すばる文学賞佳作、第166回芥川賞候補作にノミネート。
撮影/花村克彦 企画・文/高戸映里奈