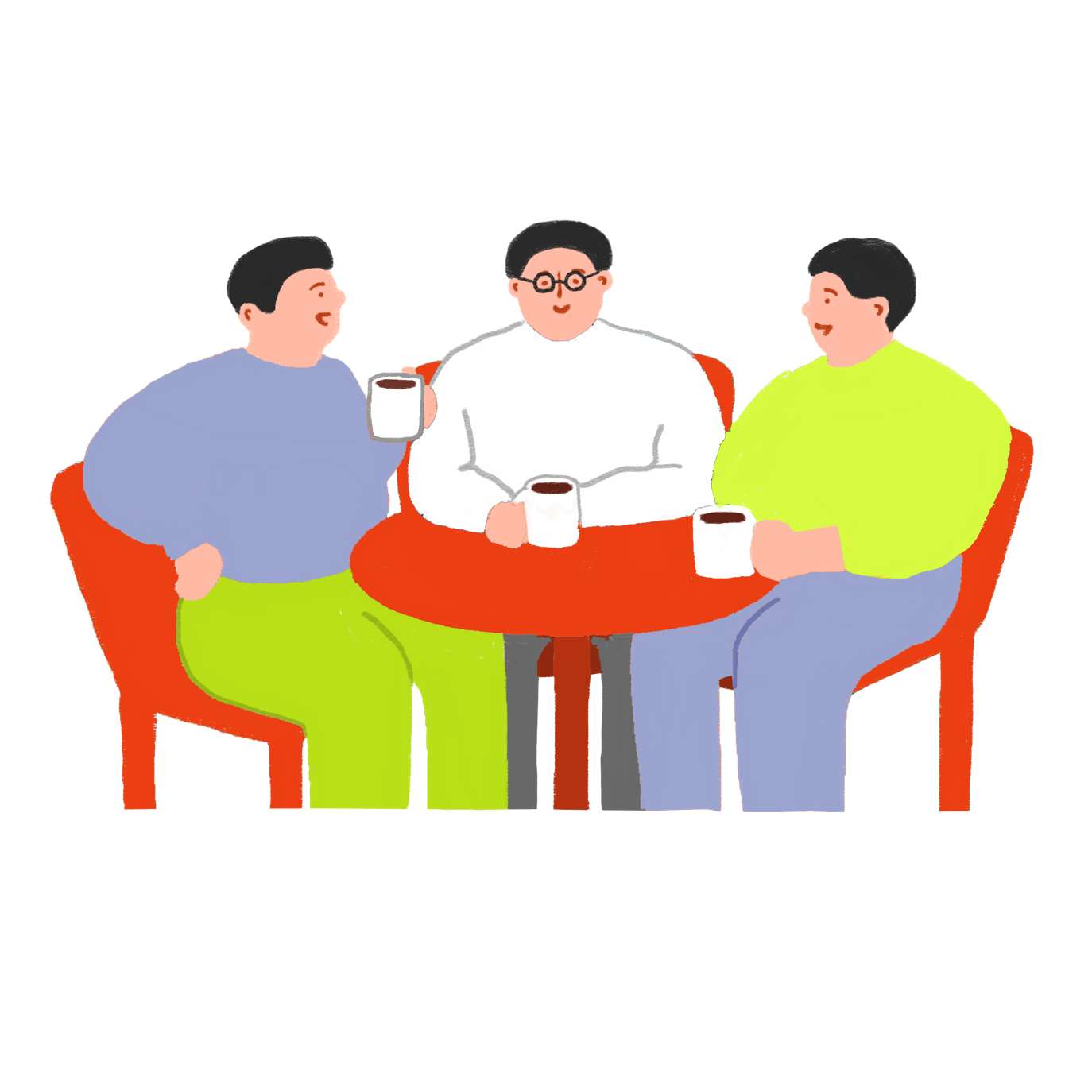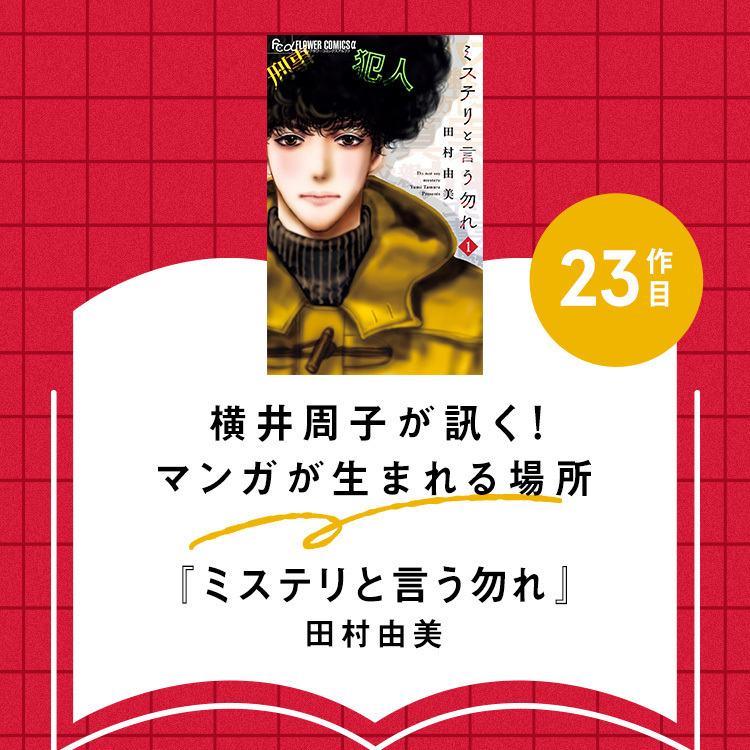1972年に『週刊マーガレット』(集英社)にて始まった『ベルサイユのばら』。わずか2年の連載期間ながら、少女マンガ界に旋風を巻き起こした愛と革命の物語は、連載から50年以上たった今なお国境や時代を超えて読者の心を揺さぶり続けています。来春には劇場アニメ『ベルサイユのばら』が公開されるなど、今なお存在感を放ち続ける名作を生み出した、マンガ家・声楽家の池田理代子先生にインタビュー! 元マンガ誌編集者で、京都精華大学新世代マンガコース非常勤講師も務めるライターの山脇麻生さんが聞き手となってお話を伺います。〈yoi3周年スペシャルインタビュー vol.4 前編〉


マンガ家・声楽家
1947年生まれ。1967年にマンガ家デビュー。1972年に『週刊マーガレット』にて連載を開始した『ベルサイユのばら』が空前の大ヒットに。そのほか、代表作に『オルフェウスの窓』『おにいさまへ…』『栄光のナポレオン エロイカ』などがある。45歳で音大受験を決意し、1995年に東京音楽大学声楽科に入学。現在も声楽家として活躍している。また、歌人としても活動しており、2020年に第一歌集『寂しき骨』(集英社)を発表。
自分が描きたいから描く。編集部が反対しても、ヒットする確信があった

『ベルサイユのばら』story
1770年、オーストリア帝国・ハプスブルグ家の皇女マリー・アントワネットは、14歳でフランスのブルボン家に嫁ぐ。王太子妃となったマリーを護衛するのは男装の麗人オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ。その傍らには幼い頃より魂を寄せ合ってきた使用人のアンドレ・グランディエがいた。ある夜、アントワネットは仮面舞踏会でスウェーデンの貴公子フェルゼン伯爵に出会い、ひと目で恋に落ちる。一方、街では困窮した市民による革命の気運が高まっていた——。
——今回は、「yoi」の3周年のスペシャルインタビューとして、全3回に渡って池田先生にお話を伺っていきたいと思っています。「yoi」のメインの読者は20代後半から30代ではありますが、幅広い層の方に読んでいただいています。
池田先生:そんな若い方、私のことなんて知らないでしょう。
——いえいえ。来春は劇場アニメ『ベルサイユのばら』が公開されますし、韓国で公演中のミュージカル『ベルサイユのばら』も大好評だとか。企業とのコラボも多く、つい先日、友人からレトルトの『ベルサイユのばらカレー』をもらったばかりです。30代の「yoi」編集部員も先生の大ファンで、『ベルばら』とSNIDEL HOMEのコラボグッズを買ったとうれしそうに見せてくれたりして、もはや私たちの生活に浸透している感すらあります。池田先生は、ご自身の作品がそうやって愛され続けている状況をどのようにとらえていらっしゃるのでしょう?
池田先生:50年も前の作品ですし、47歳で音大(東京音楽大学声楽科)に入学して、『ベルサイユのばら』40周年のとき(2012年)に、「これは描きたい」ということで『ベルサイユのばら エピソード編』を描いて、そこからすっかり遠ざかっていますので——。ただ、イタリアの文学フェスティバルに呼ばれたときに、「今、イタリアの中堅作家で、『ベルばら』の影響から逃れた人はいません」と仰っていただいたことは印象に残っています。
——過去のインタビューで何度か答えていらっしゃいますが、高校生のときにシュテファン・ツヴァイクの『マリー・アントワネット』を読んで、いつか彼女の話を描きたいと思っていらしたそうですね。連載の話がきたのでそれを提案したところ、編集部から「歴史ものはあたらない」と言われたとか。
池田先生:はい。「必ずヒットさせること」が条件でした。そこで、手当たり次第に本を読んで、2年ぐらい準備期間を取ってから連載を始めました。
——当時は男性編集者が多く、今以上に女性の意見が通りにくい現実があったかと思います。その時、どうやって連載への道を切り開かれたのでしょう?
池田先生:そうですね……。私はね、割と幼い頃から、大抵のことはどうでもよかったんです。だから、自分が描きたいから描く。それだけ。シンプルなんです。それに絶対に当たるとも思っていました。ですから、もし、集英社に「ノー」と言われたら、よその出版社に持っていっていたと思います。
オスカルのセリフには、当時の自分の気持ちが表れていました

©池田理代子プロダクション
——オスカルをはじめ、先生がお描きになる女性は、困難な状況下でも自分で自分が進むべき道を選び取ります。その存在が、多くの女性読者に勇気を与えたと思うのですが、いかがでしょう?
池田先生:いやいやいや、あまりそういうことは考えたことがなくて。
——鯱張った主義主張になると人はなかなか耳を傾けないものですが、エンターテインメント性の高い作品の中の躍動するキャラクターを通して、より広く、より多くの人に、そういったことが届いたのではないかと思います。
池田先生:作品を読むことで、自然に身についていくということはあったかもしれませんね。
——名ゼリフが多いオスカルですが、特に衛兵を率いたオスカルがテュイルリー宮広場に向かうシーンの「人間はその指先1本、髪の毛1本にいたるまで すべて神のもとに平等であり 自由であるべきなのだ」が印象に残っています。
池田先生:オスカルのセリフは、当時の自分の気持ちが表れていることが多いので、思い入れがありますね。
——そうなんですね。このセリフにどれほど勇気づけられたことか。自分を大事にすることの大切さを教えてもらった気がしていて、「誰の心にもいちオスカルさまを」と思っています。
池田先生:ふふふ(笑)。
夢をあきらめるために描いた『オルフェウスの窓』

『オルフェウスの窓』Story
ドイツの古都・レーゲンスブルクにある音楽学校の塔には、「オルフェウスの窓」と呼ばれる古い窓があり、そこから外を見下ろして最初に視界に入った女性と運命の恋に落ちるが、悲劇的な結末を迎えるという言い伝えがある。女性でありながら男性として育てられたユリウスは、この学校のピアノ科に入学し、この窓を通してピアノの天才・イザークとバイオリン科のクラウス(アレクセイ)と言葉を交わす。ロシア革命の史実と実在の人物を織り交ぜながら、足かけ7年にわたり連載された大河ロマン。
——実は学生時代に世界史を選択してこなかったのですが、先生の作品からおおよそのヨーロッパ史を学んだ気でいます。なかでも音楽を愛しながらもロシア革命に翻弄される若者たちを描いた『オルフェウスの窓』は、『ベルばら』と肩を並べる先生の代表作ですよね。
池田先生:『オルフェウスの窓』は、なんていうんだろう……いちばん大切な作品です。
——愛蔵版の前書きに、「(連載をしていた7年の間に)作者である私自身の上にも大きな生活の変化の波が幾度か押し寄せ、その過程で、少しずつ愛や人生に対する考え方に変化が生じていった。今、この愛蔵版の出版にあたってあらためて自分の作品を読み返してみると、随所にそういった生々しい変化の痕跡をうかがうことができる」と、書かれていました。ご自身の人生を、どのようにこの作品に落とし込まれたのでしょう?
池田先生:幼い頃からクラシック音楽の勉強をしてきて、大学は音大に行こうと思っていたんですけど、それが叶わなくて。『ベルばら』の連載がひと段落ついて、友人たちとドイツ旅行に出かけたときに、この作品のモデルとなる音楽学校の生徒さんたちにお会いして、「音楽学校のマンガを描いて、この夢をあきらめよう」と思ったんです。結局、あきらめきれなくて音大に入りましたけど。
——音大に入られたのは、47歳のときですよね。『オルフェウスの窓』は歴史の描写もさることながら、複雑な人間関係の描写も胸に響きます。そのあたりも、人生経験が反映されているのでしょうか? 先生ご自身は、以前のインタビューで、人づき合いはあまり好きじゃないとおっしゃっていましたが……。
池田先生:人づき合いは好きじゃないけど、人を観察するのは好きなんです(笑)。一方的かもしれないけれど、人と会って、「あの人はあんなことを言っているけれど、内心は違うだろうな」とか、考えていることを、つい想像したりしてしまいますね。
——メインのキャラクターはもちろん、脇のキャラクターにも血が通っているというか、物語を走らせるためだけにそこに配置されたのではなく、その人自身の人生を生きているなぁと感じられるのは、そういった先生の観察力のたまものですね。
池田先生:私も脇のキャラは好きです。いろんなキャラがいますね。
——私はロベルタとイザークの一連のエピソードが好きで。この二人が結ばれて、息子のユーベルが生まれる展開になるとは思いませんでしたし、ロベルタがイザークの治療費のために妊娠を告げないところとか、もう……。

Episode
ピアノの才能に恵まれたイザークだが、妹フリデリーケとの生活費と学費のため、街の酒場でピアノを弾き始める。その酒場で働く、貧しい家庭育ちのロベルタは、ひそかにイザークに憧れを抱く。フリデリーケが急死したため、音楽家になる夢を叶えるべくウィーンへ飛んだイザーク。彼を追い、誰一人知る人のないウィーンにやってきたロベルタは娼婦になり、稼ぎを花に換えて匿名でイザークに送り続ける。やがて、身分を超えて二人は結婚するが、過度な負担をかけていたイザークの指は動かなくなり……。
池田先生:ロベルタは教育を受ける機会に恵まれず、思慮が浅いところもありましたが、とても愛情深い人だと思います。普通だったら、色々考えると思うんです。釣り合いとか、将来性とか。だけど、そういうことを一切考えずにひたすら愛した人ですよね。一途で、私も好きです。
ユリウスの子どもは、実は生きていた…!? 池田理代子先生が描きたかった、もうひとつの『オルフェウスの窓』

——ロベルタとイザークのエピソードは、思い出すだけで、うるっときてしまいます。
池田先生:だからね、イザークの息子ユーベルのその後のお話を描こうと思っていたんです。史実では一人も弟子をとらなかったバックハウス(ベートーヴェン直系の弟子のピアニスト)ですが、イザークのことを気にかけて、「ユーベルくんをぼくにあずけてみる気はありませんか?」と言うシーンがあるじゃないですか。
——はい。その道がとても険しいものだと知りつつ、イザークはバックハウスの元にユーベルを送り出しますよね。ピアノを弾く者が望みうる最高の師の元へ、「きみは芸術の王道を歩むんだ」と言って。
池田先生:旧約聖書の中でアブラハムが息子のイサクを生贄に捧げようとしたように、イザークは自分の息子を神に捧げるわけです。だから、ユーベルのことは描きたかったんですけど、時間もなくて。
——どんなお話になる予定だったのでしょう?
池田先生:ユリウスはアレクセイが亡くなったショックでお腹の子を死産しますが、実はユリウスの子どもは生きていたんです。そして、イザークの息子と最後に結ばれるというプロットだけはできていて…。
——おぉぉ! すごい公式情報きました。先生は『ベルサイユのばら エピソード編』で、マリー・アントワネットの処刑後、娘のマリー・テレーズがフェルゼンとウィーン宮廷で邂逅するお話を描かれていますから、期待してしまいます。いずれは短編でも…。
池田先生:子どもを産んだユリウスに主治医が「死産だった」と告げますよね。ところがその裏で、ユスーポフ侯(記憶を失ったユリウスの面倒を見ていたロシア陸軍の幹部)が赤ん坊を取り上げて、「死んだことにしろ」と、ばあやに告げていたんです。ばあやの娘にもユリウスの娘と同じ年に生まれた赤ん坊がいるのですが、その子とユリウスの娘を取り替えて。
だから最初は、ユリウスの娘は貧しい農家の子どもとして育って、ばあやの孫はユスーポフ家から預かったお嬢さまとして育つんです。そして悲劇が…。
——悲劇が起きるんですか!?
池田先生:その頃の政治的背景も絡めつつですけどね。ところでユリウスって、割と歌がうまいじゃないですか。ユリウスの娘もやたらと歌がうまくて、なんのかんのあってイザークの息子と出会うという。
——ぜひ読んでみたいです!
撮影/森川英里 取材・文/山脇麻生 企画・構成/木村美紀(yoi)