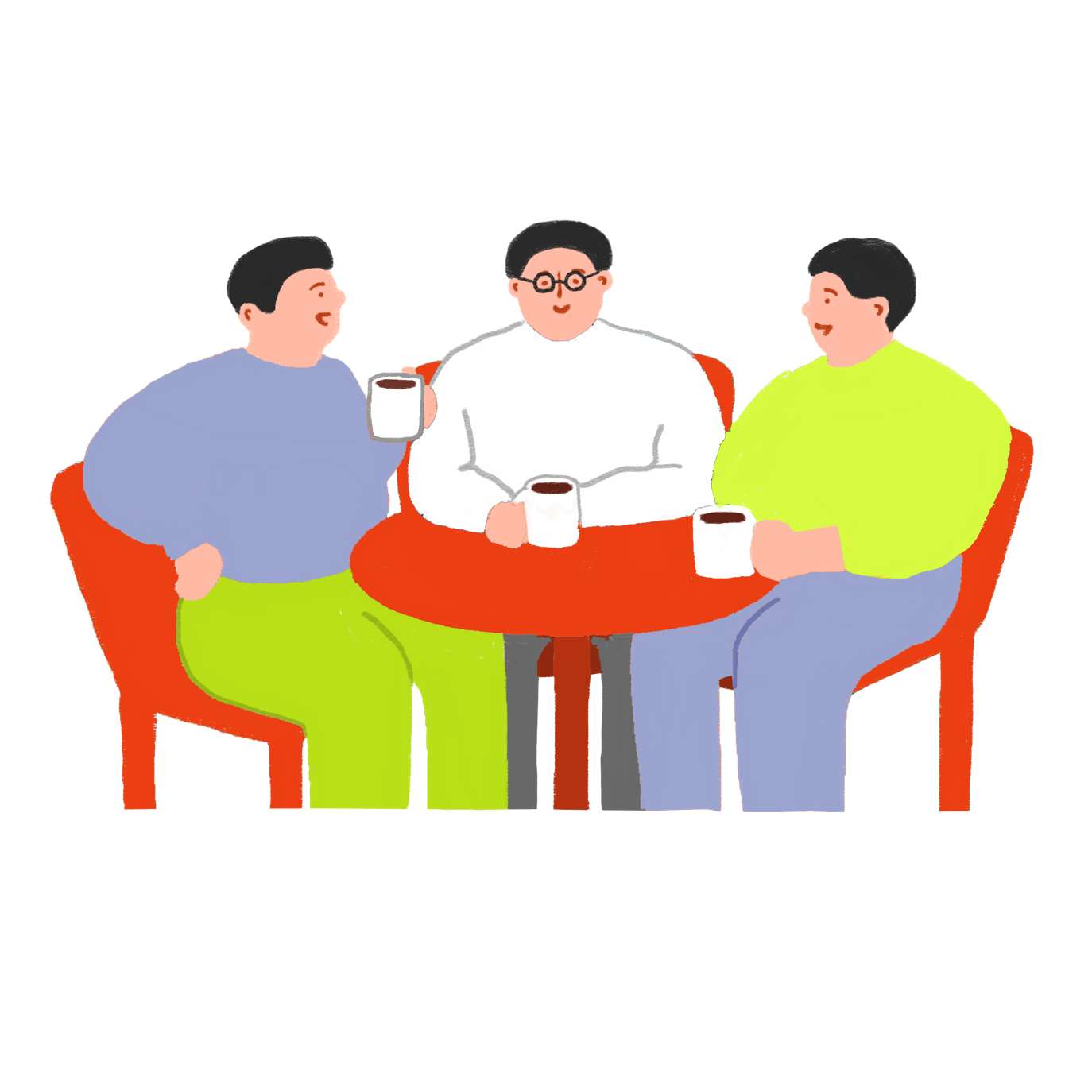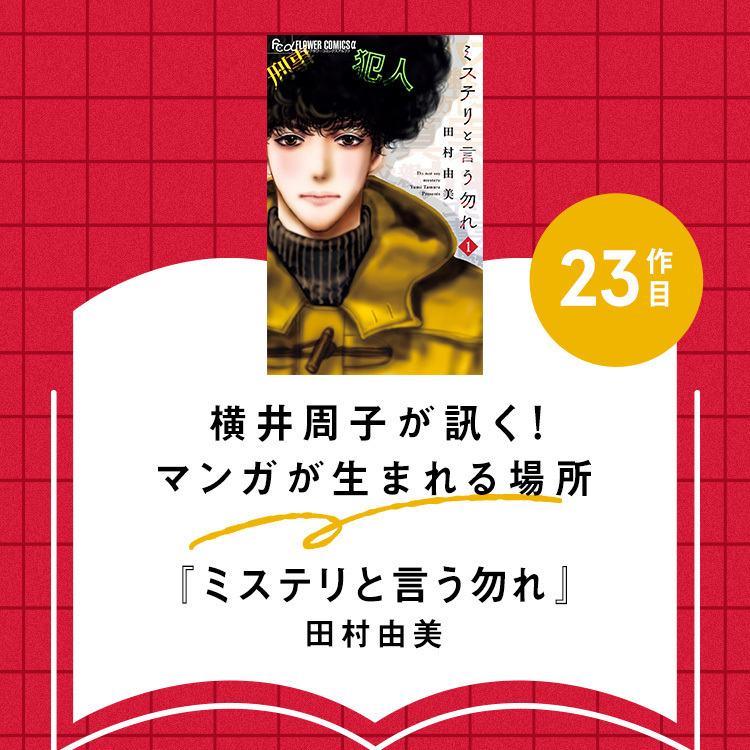2003年に『蛇にピアス』でデビューしてから、およそ20年。社会の空気をとらえ、つねに“私たちの物語”を執筆し続けている金原ひとみさん。読者から圧倒的な信頼を得ている金原さんが自分を守るためにしていたこと、そして日々の暮らしで感じたことを「覚えておく」ことの大切さについて伺います。

2003年に『蛇にピアス』ですばる文学賞を受賞し、デビュー。翌年同作で芥川賞を受賞。2010年『TRIP TRAP』で織田作之助賞、2012年『マザーズ』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、2020年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞、2021年『アンソーシャル ディスタンス』で谷崎潤一郎賞を受賞、2022年『ミーツ・ザ・ワールド』で柴田錬三郎賞を受賞。
過去の自分が守ってくれたから今がある

——金原さんはデビューから一貫して、社会にフィットするのが難しいと感じている人物を描き続けていて、作品には「闇は闇のままでいいし、無理に成長しなくていいんだよ」というメッセージが込められているように感じます。
金原さん:そう読んでもらえるのはうれしいです。私自身、幼い頃から集団生活になじめず、協調性を持ち合わせていなかったんです。いわゆるマジョリティー側に入れないまま、ここまで生きてきました。
母は、世間体を気にするタイプだったので、いわゆる「普通の子ども」に育ってほしいと思っているんだろうな、というのはひしひしと感じていて。学校に行けという圧力もあったし、当時はまだあまりフリースクールもなかったので、とにかく居場所がなかった。子どもって世界がとても狭いので学校に行かないと、本当に家にいるしかないんですよね。学校にも家庭にも行き詰まっていたので、苦しい時期は長かったです。
でも苦しみがあったからこそ、「無理やり成長しなくてもいいんじゃないか」って思えたのかもしれない。無理に成長してもどこか別のタイミングでつらい経験を踏まなくてはいけないのではないかと気づけたというか。自分に何ができるのか、何をしたいのか考える時間を与えてもらったのかなぁ。自分を守れたのは認めてあげたいですね。
坂元裕二さん脚本の『初恋の悪魔』というドラマが大好きで。そのドラマで、社会に疎外されながら生きてきた登場人物が、小学生の頃の自分に「僕を守ってくれてありがとう」と言うシーンがあるんです。私、それを見たときに号泣してしまって。過去の自分が、自分自身を守るために戦ってくれたから今があるんだって改めて痛感させられたんです。その時の気持ちを忘れないでおこうと胸に刻みました。

——金原さんは「フィクションがないと生きていけない」と、さまざまなところで発信されています。そう思うようになったのはいつ頃からでしょうか。
金原さん:私は小説を読み始めたのが遅くて、小学6年生のときに父親の仕事の都合でアメリカに滞在していた頃、「日本語を忘れないように」と父親がたくさん小説を与えてくれたのがきっかけでした。小説を読むことで、現実から逃れられる時間が生まれて、すごく救われました。さらに自分で小説を書いてみることで、受けている抑圧や感じている圧力を発散することができました。アウトプットしてもなお癒されない怒りや苦しみももちろんあるのですが。
小説は中学生になったくらいでやっと最後まで書けるようになって、今までずっと書き続けています。それからはずっと現実とフィクションの両輪で生きています。おそらく小説を読むことと書くことでバランスを取り始めた中学生の頃には、なくてはならないものになっていたと思います。
怒ったことは忘れなくていい。自分自身の歴史のひとつ

——小説とは異なりますが、「yoi」の読者にも日記を書いたり、気持ちを書き出したりすることを習慣にしている方が多いです。書くという行為からしか得られないものはありますか。
金原さん:あると思います。刺激を受けることがあっても、寝てまた新しい一日を過ごすことで、どんどん忘れていってしまうし見過ごされてしまう。でもそれを言葉にすることで自分がどんなことに憤りを感じたのか、何が苦しかったのかを明文化できますし、自分という人間を知ることにもつながります。文字にすることが支えになることもありますし、今の社会のどんなことに違和感を感じて苦しんでいるかがはっきり見えてくる。書くことは、暮らしに句読点を打つことに近いのではないでしょうか。
私は日記を書く習慣はないんですが、気持ちが悪かったこと、どうしても許せないことがあれば必ず書き留めています。それが蓄積されるとテーマになっていって、登場人物が生まれ、ストーリーができあがっていく。
怒りって、戦うってことだと思うんですよね。怒ったり許せないことが生じるということは、それを受け入れたら自分の心が死んでしまうと気づいているから。何かに怒りを覚えたその時の気持ちは、自分自身の歴史のひとつでもあるので、忘れたくないです。
——金原さんにとって、フィクションが生きる支えでもあるし、軸になっているんですね。まだ人生の支えを見つけられていない子どもには、どのような声をかけますか。
金原さん:その子が何に悩んでいるかにもよりますし、支えを他人が見つけて教えるのは難しいですが、もしその子の今抱えている問題が親関係なら、「距離をとるのが一番」と伝えます。
私自身、母親とは魂を突き合わせるようなコミュニケーションは諦めていて、虫のような存在と認識してやり過ごしているので。「いつかは通じるかな、どこかではわかりあえるかな」と期待していると苦しくなるから、心を守るためにもどこかで割り切るしかない。物理的に距離をとることが難しければ、せめて心の距離だけでも取ってほしいと思います。
ありきたりですが、趣味や夢中になれることを持つのもいいですよね。さまざまなことを経験することで、今とは異なる自分を見つけることができる。私は音楽が好きなので、ライブやフェスに行って楽しんでます。あと、飲みに行くのも大好き。最近は集中して料理を作るとか、気になっているレストランに足を運ぶのが楽しくなってきました。もちろん漫画やゲーム、小説でもいい。今置かれている状況からちょっと離れられるものがあれば。

『ナチュラルボーンチキン』1760円(河出書房新社)
撮影/川島小鳥 取材・文/高田真莉絵 構成/渋谷香菜子