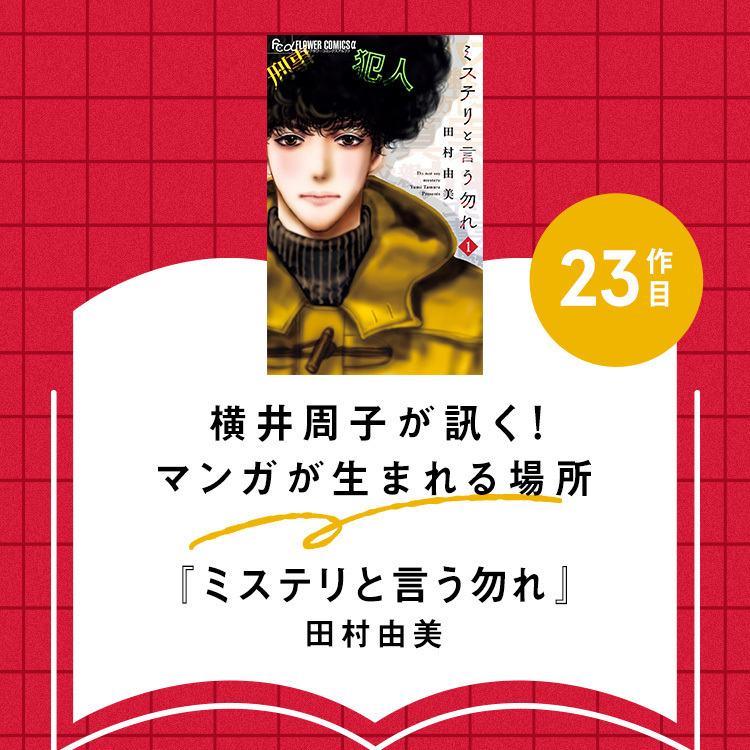数々のメディアで執筆するライターの今祥枝さん。本連載「映画というグレー」では、正解や不正解では語れない、多様な考えが込められた映画を読み解きます。第7回は、第96回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたドイツ映画の秀作『ありふれた教室』です。
生徒思いで理想主義的な若い教師が起こした波紋

新たに赴任した学校で、カーラは生徒や同僚の信頼を獲得しつつある中、ある事件をきっかけに窮地に陥っていく。監督・脚本はトルコ系移民の息子として、ドイツ・ベルリンに生まれ、12歳でイスタンブールに移り、現地のドイツ系高校を卒業したイルケル・チャタク。自身の経験も反映した本作で、アカデミー賞ほか国内外のアワードで高く評価された。
『ありふれた教室』の面白さを説明するのは難しい。第96回アカデミー賞のドイツ代表として、国際長編映画賞にノミネートされたほか、国内外の有力なアワードの受賞歴を見れば優秀な作品であることは疑いようもない。
日本の配給会社は「サスペンス・スリラー」と紹介している。確かにその要素は強いが、学校という場所を「現代社会の縮図」に見立てて正義や真実の曖昧さについて、多角的な視点で描かれたエピソードの積み重ねは正解のない問いの連続だ。
始まりは、とある中学校で頻発している金品の盗難事件。
問題があれば徹底的に調査する“不寛容方式”を掲げる校長ベームは、授業中に抜き打ちで生徒の持ち物検査を行う。新任のポーランド系ドイツ人教師のカーラ(レオニー・ベネシュ)は、トルコ系の教え子が犯人だと疑われたことで生徒の気持ちを傷つけかねない強引なやり方に疑問を抱く。
そんな中、同僚教師の一人が何気ないようすで募金箱の小銭をくすねるのを目撃したカーラは、金品の盗難事件の犯人は教員の中にいるのかもしれないと考え、職員室で自分のノートパソコンのカメラをオンにして、犯行の決定的瞬間を撮影しようと試みる。やがて離席して戻ってくるとお金が抜き取られていた。動画に写っていた服の模様から、カーラはベテランの事務員クーン(エーファ・レーバウ)の仕業だと確信する。
クーンは穏やかに「表沙汰にしませんから」と語りかけるカーラに対して、憤然として犯行を全面否定する。この両者の軋轢は、学校全体と保護者らを巻き込み、思いも寄らない大きな余波を生む。
クーンの息子であり、カーラの教え子でもある優秀なオスカー(レオナルト・シュテットニッシュ)は、やがてカーラに反抗的な態度を取るようになりやがて母親に何が起きたのかを問い詰める。
保護者や同僚はもとより、長年クーンに親しみを持っていた生徒たちの間でカーラへの不信感が黒い染みのように広がっていく。
こじれてしまった事態を俯瞰したとき、どうすればここまで大きな問題にならなかったのかについて、明確な答えを求めることは不可能に近い。その複雑さこそが本作の醍醐味ではあるが、明らかに大きなテーマのひとつとして、カーラが“自分の正義”を疑わない姿勢が挙げられるだろう。

生徒たちから親しまれている気さくなベテラン事務員のクーン。カーラの隠し撮りビデオにクーンと同じ模様のブラウスが映っていたが、容疑を全面否定する。真実は、どこに……?

事務員クーンの息子オスカーは、カーラの教え子で最も成績優秀な生徒。母親が家に引きこもり、泣き暮らしているが理由は説明されておらず、学校では反抗的な態度を取るようになる。
自分の正義が唯一絶対の正義であると信じる傲慢さ

授業中に、生徒たちの抜き打ち持ち物検査をした校長と、隠し取りした映像を確認するカーラ。その正義感は、どこで道を間違えたのか?
カーラは仕事熱心で責任感が強く、新たに赴任した中学校では1年生のクラスを担当してやる気に満ちている。同僚に対しては彼女の理想主義的な考えがやや空回りしているようにも見えるが、生徒の信頼をしっかり獲得しつつある中で、生徒に行われた抜き打ち検査を不当だと考えたカーラが自ら犯人を探そうとするのは理解できる。
しかし、まず録画するという行為がどうだったのか。さらに、目論見通りに犯人が録画されていると思われる映像を見て、顔が映っていないにもかかわらず、我が意を得たりと犯人はクーンと断定してしまった点に軽率さはなかっただろうか?
さらに言えば、自分は「温情を持って相手に接している」と信じるカーラのクーンへの態度は、独善的でどこか優位に立った空気が感じられる気もする。そう思わせるのは、この事件が起きる前段階として、ベテラン事務員のクーンと新任教師カーラの微妙な関係性が描かれているからだ。つまり監督が意図していることでもあると考えられるが、映画はこうした感情や人間関係の微妙なレイヤーを丁寧につむぐことで、人が正解である、真実であると信じることに違った側面から光を照射する。
逆に言えば、映画として俯瞰的に考えられるからこそ、私たちはカーラの言動のひとつひとつに疑問を抱くことができるとも言えるだろう。
クーンの反応にはっとさせられ、カーラは自分の言動に対する信頼が急に揺らぎ始めるのだが、自分を善良だと信じる多くの人々は、カーラのように行動する可能性は十分にある。実際にSNSなどを眺めてみても、明らかに「善意」であり「正義感」に駆られているであろう人々の、どこか独善的だと感じられる投稿をしばしば目にするはずだ。何よりも恐ろしいのは、そうした自分の正義が唯一絶対の正義であると信じる傲慢さや、他者をジャッジする権利が自分にあると自負する驕り、ある種の勘違いというものは、他人からは容易に見えるが、往々にして当の本人が最も気づきにくいことである。
一方で、カーラに関して言えば、そんなに彼女が悪いのだろうかと疑問に思う気持ちも拭えない。この社会の善悪の境界は非常に曖昧なのだ。
そこかしこに火種がくすぶる社会の映し鏡としての学校

保護者、同僚、そして生徒たちからの信頼も失い、精神的にも追い詰められていくカーラ。ミヒャエル・ハネケ監督の『白いリボン』やドラマ『80日間世界一周』などに出演するレオニー・ベネシュが、カーラ役を熱演。
カーラ以外にも、もやもやとするグレーゾーンはある。多様なルーツを持つ人々が集まる社会の縮図である学校という場所もその一つだ。
本作では特に保護者が登場するパートで強調されているが、同僚や生徒の中にもドイツ語を母国語としない移民などのマイノリティの存在が大きな位置をしめている。カーラには当たり前だと思うことでも、人種マイノリティとして生きる人々にとってはどうなのか。
一方、保護者たちはチャットなどで情報交換をし、保護者会が開かれる時点ではクーン側からの情報と子どもたちからの情報により、はなからカーラに対してのバイアスがある。保護者には保護者の言い分もあるだろうが、そこには偏った情報の拡散や監視社会といった問題がある。
そもそもの発端として、リベラルであるとされるこの学校が生徒に対して抜き打ち検査をすること自体がどうなのか。学校側は生徒たちに潔白であれば問題ないはずだとして、「生徒の自主性を重んじている」かのように振る舞い検査を強いた。それは権威主義的であり、カーラ、保護者らと同じく学校こそが率先して監視社会を実践しているようにも思える。そしてカーラはそれに異論を唱える人物だったはずなのに、保護者から見れば「対学校」という図式になってしまう。
教師として正しく、誠実であろうとした結果、カーラが招いた混乱。それは、そのまま私たちの身の回りで起こる可能性のある、あるいは現在そこかしこで火種がくすぶっていることを思わせる。本作で描かれているのは、ありふれた日常であり、社会の映し鏡なのである。

私たちは善悪の境界が曖昧である社会に生きている。そのことをより一層自覚的である必要性を、本作はカーラの物語を通して観客に伝えている。
『ありふれた教室』5月17日(金)、新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座、シネ・リーブル池袋ほか全国公開
監督・脚本:イルケル・チャタク
出演:シオニー・ベネシュ、レオナルト・シュテットニッシュ、エーファ・レーバウ、ミヒャエル・クラマー、ラファエル・シュタホヴィアクほか
配給:アルバトロス・フィルム
ⓒ if...Productions/ZDF/arte MMXXII ⓒ ifProductions_JudithKaufmann ⓒ BorisLaewen ⓒ Judith Kaufmann, Alamode Film
取材・文/今 祥枝