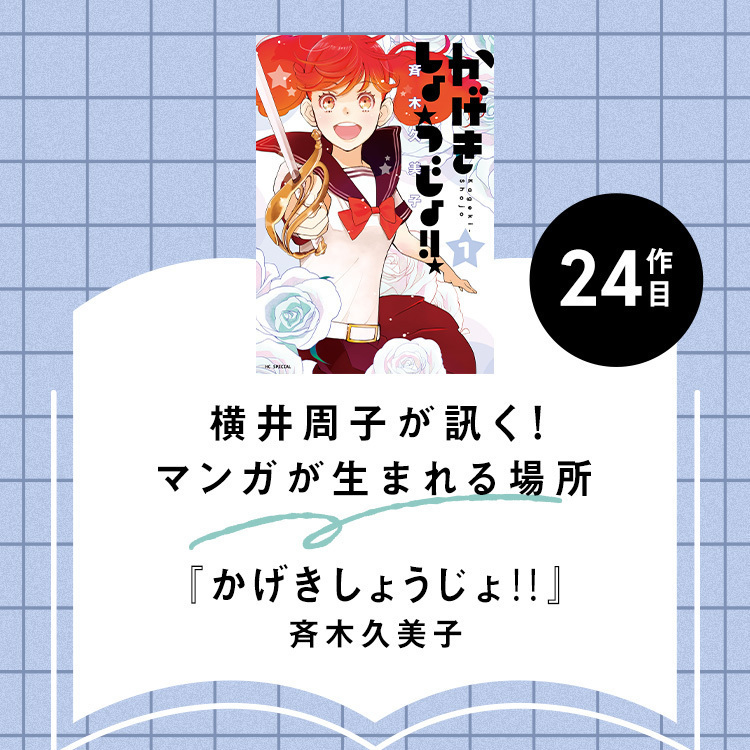体内時計のリズムに着目し、食べるタイミングでその栄養素の効果を最大限活用することを目指す「時間栄養学」。その効果を最大化するには、腸内環境を整える食物繊維の摂取においても、体内時計のリズムを考慮するのがポイントです。そこで今回は、時間栄養学を研究する管理栄養士の古谷彰子さんに朝食時の食物繊維について期待できる効果や、おすすめ食材を教えてもらいました。

理学博士・管理栄養士
愛国学園短期大学准教授。「chronomanage」代表。早稲田大学規範科学総合研究所ナノ・ライフ創新研究機構招聘研究員。「時間」という観点から、医学・栄養学・調理学の領域にアプローチする時間栄養学を専門とし、科学的根拠をもとにした栄養指導や講演活動のほか、企業との商品開発など多岐にわたり活躍。
時間栄養学とは…?
「何をどのくらい」だけではなく、「いつ」食べるかということを考慮した栄養学。栄養素によって体内時計(細胞・器官に備わっている地球の自転に合わせた約24時間周期のリズム)を整えたり、体内時計に合わせて栄養素をとることでより効率的に代謝や合成を進めることができる。
時間栄養学では、朝食によって毎朝、体内時計をリセットし、1日の生理現象のリズムを整えることを重要視していて、それにより睡眠の質向上、自律神経、ホルモン調整、ボディメイクなどさまざまなメリットがあることがわかっている。
体内時計を整えるのに必要な栄養素は?
※本記事内で、食物繊維と記載しているときは、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の総称を指しています。
──朝食で体内時計をリセットすることで、健康や美容に関してさまざまなメリットがあることが時間栄養学ではわかっていますが、体内時計をリセットするためにとりたい栄養素にはどんなものがあるのでしょうか?
古谷彰子さん(以下、古谷):まず一番大切なのは糖質、そしてタンパク質です。体内時計をリセットするのはインスリンというホルモンで、糖質を摂取することでインスリンがしっかりと分泌されるので糖質はマスト。
タンパク質はインスリンに似た「インスリン様成長因子-1=IGF-1」の分泌を促すため、タンパク質と糖質をセットでとることは体内時計のリセットにおいて最も大切なことです。
さらに、プラスアルファでとりたいのが魚油と食物繊維。
魚油に含まれるDHA、EPAをとると、「グルカゴン様ペプチド-1=GLP1」と呼ばれる、インスリンの分泌を促すホルモンが出ます。
魚油というと、「朝から魚を焼くのは難しい…」と思ってしまう方もいると思いますが、ツナやサバ缶などの缶詰や、サプリメントを上手に活用することをおすすめしています。
また、体内でDHAやEPAに変換されるα-リノレン酸を含む、アマニ油やエゴマ油をお味噌汁やサラダにひと回し入れるというのもいいかもしれません。
食物繊維については、食物繊維の中でも水溶性食物繊維を食べることで腸内細菌の代謝物として「短鎖脂肪酸」という酸が作られ、マウスの実験では、体内時計のリセット効果があることがわかっています。

古谷:ヒトの実験ではまだ明らかになっていませんが、私が以前、行った実験で、朝に水溶性食物繊維を子どもたちにとってもらったところ、早起きになって調子がよくなったという結果が得られたので、ヒトでも体内時計をリセットする効果が期待できるかもしれません。
また、体内時計リセット以外にも、短鎖脂肪酸は健康、美容面においてさまざまなうれしい効果を発揮するので水溶性食物繊維は積極的にとることをおすすめしたいです。
健康的に体を引き締めたいなら、朝食時に水溶性食物繊維をとり、「短鎖脂肪酸」を増やす
──短鎖脂肪酸にはどのような効果があるのでしょうか?
古谷:短鎖脂肪酸は、酪酸や酢酸といった炭素が6個以下の鎖状の脂肪酸(脂質を構成する要素)の総称。
例えば酪酸は大腸のエネルギー源になり粘膜の保護・再生を促し、便秘や下痢の改善、免疫力改善、肥満予防、生活習慣病予防などの効果が期待できます。
最近では食欲抑制効果も期待できるかもしれないという報告もありました。
酢酸は、腸内のpHを下げ、酸性状態にすることで腸内細菌のうち、悪玉菌が増殖しにくく、善玉菌が働きやすい環境に整えてくれます。
ほかにも、「AMP活性化プロテインキナーゼ」という脂肪の合成を抑える酵素を活性化し、脂肪の蓄積を減らしたり、血糖値の上昇を抑えたりする効果も期待できるため、総じて健康的なボディメイクには、短鎖脂肪酸を増やすことはとても有効といえるでしょう。
──短鎖脂肪酸を増やすにはどうしたらいいのでしょうか?
古谷:まず、腸内細菌のエサとなる水溶性食物繊維を積極的にとることが大切。特に、短鎖脂肪酸の合成は朝が盛んなことがわかっているので、時間栄養学の視点では、朝食時に水溶性食物繊維をとることを推奨します。
──食物繊維には不溶性食物繊維もありますが、水溶性食物繊維は不溶性食物繊維とどう違うのでしょうか?
古谷:一番大きな違いは名前のとおり水に溶けるか溶けないか。水を加えたときにネバネバとするような食品は水溶性食物繊維を多く含みます。
機能面では、水溶性食物繊維は前述のとおり腸内細菌のエサとなるほか、胃の中でゲル状になり消化がゆっくりになり満腹感の持続を助けます。一方、不溶性食物繊維は便のかさを増すことで蠕動(ぜんどう)運動を促し、代謝を活性化します。
いずれも食べることでそれ以降の食事の血糖値の急上昇を抑えるセカンドミール効果が期待できるので、朝だけではなく、毎食とり入れることで、血糖値の乱高下が防げ、それが睡眠の質向上にもつながりますよ。
水溶性・不溶性の食物繊維がとれるおすすめ食材

本記事では、1.5g以上含む食品を「多く含む」と定義し、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を比較した際に、どちらかが顕著に多い場合に、水溶性、もしくは不溶性を多く含むものに分類しています。
──特におすすめの食品はありますか?
古谷:水溶性食物繊維がより多く含まれる食品の代表は海藻。わかめやひじき、昆布など和食では定番の食品はおすすめです。
特にわかめと昆布には、血中コレステロール値の低下や血圧調整、腸内環境改善に効果的な「アルギン酸」、免疫力向上、抗炎症作用、胃粘膜保護作用のある「フコダイン」、免疫調整作用や善玉菌を増やす「ラミナラン」など、健康へ導くさまざまな成分が含まれています。
きのこ類は不溶性食物繊維がより多く含まれていますが、血糖値上昇を抑制したり、血中コレステロール値を正常にする作用が期待できる水溶性食物繊維の「β-グルカン」も含んでいます。
加えて、しいたけには免疫力向上、まいたけやぶなしめじには整腸作用などきのこ類も多くのうれしい効果が。
他には、ビタミンCもとれるブロッコリー、マグネシウムもとれるバナナ、タンパク質もとれる大豆は食物繊維を多く含むおすすめ食材です。
イラスト/minomi 企画・構成・取材・文/長谷日向子