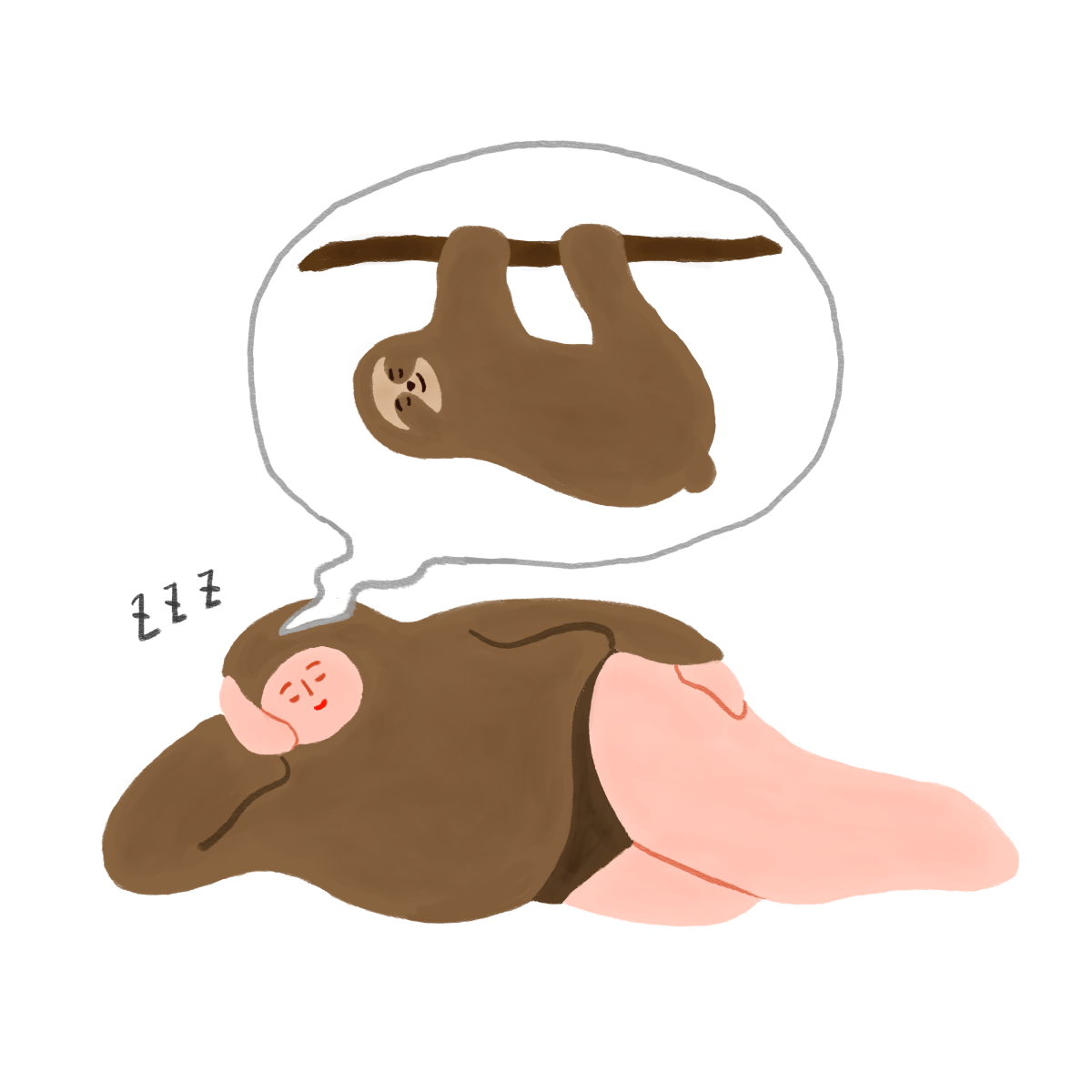仕事、家事、勉強……やるべきことはあるのに、先延ばししてしまう。そのお悩みは、脳のクセを知ることで少しラクに乗り越えられるようになります。今回は、脳神経外科医・菅原道仁さんに“先延ばしする脳”と上手につき合うための4つのヒントを伺いました!
脳神経外科医
脳神経外科医としてさまざまな病院での診療経験を重ねた後、2015年に「菅原脳神経外科クリニック」を開院。著書『すぐやる脳』『あの人を、脳から消す技術』(ともにサンマーク出版)など、脳科学に基づいたわかりやすい解説が支持を集めている。現場で多くの患者と向き合うなかで、現代人の「やる気が出ない問題」に着目。現在はメディア出演や講演活動でも幅広く活躍している。
先延ばしは、脳からの“優しいサイン”
——やらなければならないことを先延ばししてしまうのは、やっぱり“直すべき悪いクセ”なんでしょうか?
菅原 「また後回しにしちゃった」と落ち込む日、誰にでもありますよね。でも実は、先延ばしすること自体が悪いわけではありません。
特に、完璧主義の人ほど“すぐに動けない”傾向があります。「ちゃんとやらなきゃ」「失敗したくない」と思うほど、最初の一歩が重くなる。
これは、意志が弱いからではなく、脳が“守り”に入っている状態。あなたのメンタルを心配して脳がかけるブレーキ機能なんですよ。

——完璧主義と先延ばしは、関係があるんですね。
菅原 そうなんです。「完璧にやりたい」という気持ちは、素晴らしい意欲や向上心の表れです。でもその一方で、理想が高すぎると、少しのミスや失敗が大きなダメージに感じられてしまい、そもそも手をつけるのが怖くなってしまいます。
その「完璧にやろう」とする姿勢も、あなたの素敵な個性。だからこそ、ちょっとした工夫で脳の性質を味方につければ、「やらなきゃ」と思ったときのハードルがぐっと下がり、スムーズに作業に取りかかれるようになります。
ここからは、そんなときに役立つ、すぐに試せる4つのヒントをご紹介します。
脳のクセを味方に「先延ばしを減らす」4つのヒント
01. “自己暗示”で脳にスイッチを入れる
菅原 人間の思い込みには、よくも悪くも強い力があります。だからこそ、自分に向けてポジティブな思い込み=自己暗示をかけることが、とても大切なんです。
特に効果的なのが、言葉を声に出して自分の耳で聞くこと。聴覚からの刺激は脳にしっかり届きやすく、思い込みをより強く印象づけることができます。
「これは簡単にできる」「30分だけ集中してみよう」。そんなハードルの低い目標設定と前向きな言葉を、ぜひ声に出してみてください。
脳は怠け者なぶん、何度も優しく語りかけてあげることで、じわじわとその気になってくれる。自己暗示は、脳の“やる気のスイッチ”を入れる、シンプルで効果的な方法ですよ。

02. 目標は“小さく、具体的に”立てよう!
菅原 「やらなきゃいけないこと」が大きく感じられると、それだけで脳はお手上げ状態になってしまいます。
なぜなら、ゴールがぼんやりしているほど、“どうはじめたらいいかわからないという不安”が大きくなるから。だからこそおすすめなのが、大きな目標をできるだけ小さく、具体的に分けること。
「参考書の1ページだけ読む」「机の上だけ片づける」「3分だけタイマーをかけて作業する」。このように、“やれば終わる”感覚が持てるサイズ感の目標に変換してあげることで、脳は「これならできるかも」と思いやすくなります。
小さなステップをこなすたびに、「できた」という実感が積み重なり、脳には“成功体験”として記憶されていきます。この繰り返しが、気づけば「続けていける自分」を育ててくれるんです。
最初の一歩が小さければ小さいほど、動き出しは軽くなりますよ。
03. “発表会”でモチベーションを育てよう
菅原 目標に向かって頑張るとき、最初はやる気があっても途中でペースダウンしてしまうこと、ありますよね。そんなときにおすすめなのが、「誰かに見せる場=発表会」を自分でつくることです。
例えば、「月末に友人に進捗を話す」「SNSで成果を共有する」「作った資料を誰かに見せる予定を立てる」など。ちょっとしたお披露目の場を用意するだけで、承認欲求がやる気を後押ししてくれるんです。
ピアノの練習が続くのは発表会があるから、受験勉強が頑張れるのは試験日が決まっているから。それと同じように、“成果を披露する場”があることで、やる理由がぐっとリアルになり、脳が先延ばししにくくなりますよ。

04. あえて“キリの悪い”ところでやめる
菅原 つい「キリのいいところまでやってから終わろう」と思っていませんか?
それ自体は悪いことではありませんが、実は脳の仕組みから見ると、“キリの悪いところで終える”ほうが、次の行動につながりやすいんです。
その理由は、脳が「未完のタスクを覚えておこうとする性質」を持っているから。
連続ドラマが「いいところで終わる」と次回が待ち遠しくなるのと同じで、作業をあえて中途半端に終えることで、「続きをやりたい」という欲求が自然と生まれるもの。
例えば、「作業の仕上げは明日に残す」「今日は半分だけやって、明日また半分やる」など、“気になるポイント”を残しておくと、翌日のスタートがぐっと軽くなりますよ。
脳のクセを活用して、自分に合った方法を見つけていこう
菅原 「やらなきゃ」と思っていても、どうしても動けない日もありますよね。そんなときは、自分を責めずに、今回ご紹介した4つのコツのなかから、ひとつだけでも試してみてください。
「今日はここまでできた」と思えることがあれば、それだけで十分。完璧を目指さなくていいんです。あなたらしいペースで、少しずつ前に進めば、それだけで立派な一歩です。
先延ばしクセも、脳のクセも、すべてはあなたを脳が守ろうとしている反応。だからこそ、優しくつき合いながら、自分に合った方法を見つけていきましょう。

イラスト/NACCHIN 取材・文・企画・構成/高浦彩加