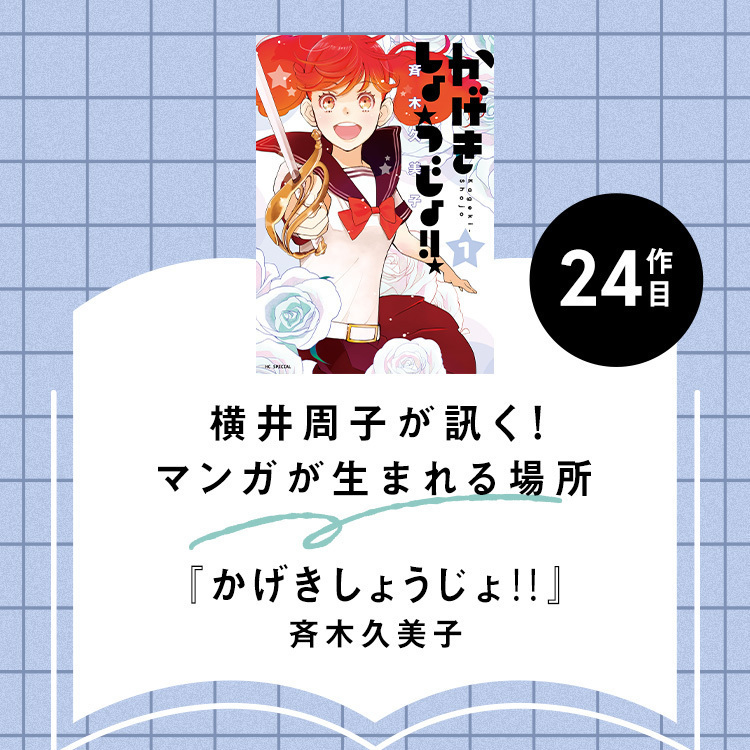ジェンダーについての記事や書籍に携わる編集者・ライターの福田フクスケさんが毎回ゲストをお迎えしてジェンダーの問題についてトークしていく連載「やわらかジェンダー塾」。Vol.11のゲストは、批評家の杉田俊介さん。二人が注目しているマンガや映画などのエンタメ作品から、ジェンダーのあれこれについて考えていきます。

一人で人生を楽しむ、ケアし合う…男性の生き方の可能性を提示した3作品

——杉田さんは、著書やSNSの中で、よくエンタメ作品を引用してジェンダーや社会問題について論じていますよね。最近、気になっている作品はありますか?
杉田さん:現在、週刊スピリッツで連載している『路傍のフジイ』(小学館)というマンガがありまして、これが面白いんです。
藤井という、40歳すぎの非正規社員の独身男性が主人公のマンガなんですが、彼は目立った才能があるわけでもなく、いわゆる世の中で必要とされるようなコミュニケーション能力もない。職場では、周囲の人から軽んじられている存在でした。でも、彼自身はすごく人生を楽しんでいる人なんです。

©鍋倉夫/小学館/ビッグコミックスピリッツ
杉田さん:彼は一人で絵画教室に行ってみたり、興味があれば音楽コンサートに行ってみたり。凡人ではあるのですが、非常に人生を楽しんでいて、他人に対しても“ありのままのその人”を受け入れる。そんな彼と交流することで、最初は藤井のことを低く見ていた人も、彼の生き方に感化されていく…という物語です。
仕事で成功するわけでもなく、あるいは趣味を生かして社会貢献しているわけでもなく、恋愛や人間関係が充実しているわけでもないけれど、ありのままの人生を受け止めて、日常を噛み締めるように生きている。そういった生き方が肯定される物語って、あまりないような気がするんです。
おじさんの日常を描く物語だと、どこかで若い女性が登場してちょっと親密な関係になったりとか、孤独な人生を送っている理由は過去にこういったことがあったからだ…という背景が匂わされたりとか、悪い意味で“おじさんが喜びそうな要素”が入ってきがちだったりする。でも、そういった要素って実は余計なんじゃないかと思っていて。
そんなものがなくても、おじさんたちは気高く堂々と生きていける。社会の片隅で、淡々と自分の人生を続けていく、そんな生き方だって可能なんだということを描いたこの作品は、小さな希望の灯になるんじゃないかと思います。
福田さん:テレビ東京のドラマ『孤独のグルメ』にも通ずるものがありますよね。主人公の井之頭五郎(松重豊)も、別に誰かからの承認を必要としているわけでもなく、自分の食べたいものを追求していく。仕事で何かを成し遂げるみたいな描写も薄いし、家庭を持っているような描写もない。ただ自分の食べたいものを食べて、日常を楽しんでいる。
どうしてこんな淡々とした描写のドラマがウケているんだろうと思ったこともあったのですが、そういうものが求められているのかもしれませんね。
杉田さん:韓国でもウケているそうですね。韓国では「食事は誰かと一緒に行くものだ」という価値観が強かったのもあって、一人でゆっくりと食事の時間を楽しみ、仕事の合間にリラックスするというのが新鮮だったのかもしれません。
福田さん:「男性と食」をテーマにしたドラマだと、最近やっていた『晩餐ブルース』も印象的でした。
福田さん:主人公はテレビ局の若手ディレクター・田窪優太(井之脇海)で、あまりに多忙で限界寸前の生活を送っていたのですが、ある日、もう一人の主人公である高校時代の同級生・佐藤耕助(金子大地)と再会します。元料理人で今はニート生活を送っている耕助がカレーライスを作ってくれたことで、優太は久しぶりに何かをじっくり味わいながら食べる時間を持つことができた。
男性同士がただ一緒に晩ごはんを食べる…ドラマの中では“晩活”と呼んでいたのですが、そんな“晩活”を通して、人間らしい心とか生活を取り戻していくみたいな話なんです。
今まで日本のドラマで男性同士がケアし合う世界みたいなものって描かれることが少なかった気がしますが、そういったテーマを扱った作品の代表になったのではと思います。
“多様性”を綺麗事のスローガンで終わらせないための表現

——男性が主人公の作品をいくつかご紹介いただきましたが、男性以外が主人公の作品ではどうでしょうか?
杉田さん:最近、久々に映画館で観た『サブスタンス』は面白かったですね。
杉田さん:デミ・ムーア演じる主人公は元トップ人気女優。ルッキズムやエイジズム、裏返ったミソジニーみたいなものも含めて、いろいろと内面化してしまっている女性です。そんな彼女が、若くて美しい体に憧れて、謎の若返り薬に手を伸ばすけれど、その先に待っているのは…?というお話です。
この映画は、今の世で、表立っては“社会化されない欲望”みたいなものを描いているところが面白いと思ったんですよね。最近は、リベラルかつソーシャルな正しさが重視されていて、もちろんそれは大切にすべきなんだけれど、人の欲望がリベラルでソーシャルなものに地ならしされすぎると、そこに違和感も出てくる。
もちろん、ルッキズムやエイジズム、ミソジニーには対抗していかなきゃいけないんだけど、それを綺麗事で終わらせるんじゃなくて「やっぱり人間の中には、こういう欲望の凄まじさがあるんだ」ということにも同時に向き合わなければいけない。PC(ポリティカル・コレクトネス:不快感や不利益を与えないように配慮された中立的な表現や行動)的な環境を整備しつつも、そこからはみ出てしまうものが人間の欲望や身体にはあるということを、物語と表現で見せてくれた。
男性を主人公にした作品で、ここまでたどり着いているものはあまりないんじゃないかな。女性たちの格闘のほうが、より先に進んでいると感じます。
福田さん:私も『サブスタンス』は面白く観ました。SNSではこの作品がフェミニズム映画か、それともミソジニー映画かという議論がありましたが、女性が内面化してしまっている「自己嫌悪としてのミソジニー」を女性監督が描いたという意味で、私はこれは紛れもないフェミニズム映画ではないかと思います。
終盤に訪れるとんでもない展開も、お行儀の良いエンパワメントや傷つきの慰撫、いたわり合いだけがフェミニズムではない、というメッセージのように感じました。社会からの強烈なルッキズムやエイジズムに対抗するには、もはやPCからはみ出してしまうような悪辣なやり方で抑圧から解放されるしかないんだ、と言われている気がして。
——今は、PC的な価値観を持ちつつも、それと同時に「若くありたい、美しくありたい」という欲望も抱えていて、ダブルスタンダードな価値観を持つ人は多いかもしれません。自分の持つ欲望の綺麗事じゃなさに向き合うことは、まさに今を生きる人が直面している問題ですね。
杉田さん:たぶん、二段階に分けて考えていかなきゃいけない問題なんですよね。
一段階目としては、社会的な価値観として「こういうものはダメだよね」という考えを、みんなで共有して、地盤を作っていくこと。それがPCだったり、多様性と呼ばれるものなわけです。でも、一段階目の正しさだけでは、どこかで「本当にそうなのかな?」「本心は違うよね」という思いが生まれてしまう。でも、みんなそれを口にできない、という状況になります。
それが悪化すると、「建前はもういいから、本音で話そう」「現実はそうじゃない」みたいな流れが本来あるべきではない方向にエスカレートしてしまう。まさに今、世界はそういった流れの中にあると感じています。
“ポリコレ”嫌いや、インセル(主にネット上で女性蔑視発言などをする、異性との交際や性的関係が長期間ない独身男性)やマノスフィア(男性がより“男らしく”なる方法や異性との交際に関するアドバイスを提供するオンラインコミュニティの総称。その内容には、女性を性的ステレオタイプとして見たり、男性の孤独や社会的挫折の原因がフェミニズムにあるとするなどの女性蔑視的な思想がしばしばみられる)のような、PCや多様性に対抗する新しいマッチョイズムに、人々が取り込まれようとしている。
——アメリカでは特にその流れが顕著だそうですが、日本でもそういった“揺り戻し”の動きはありますよね。
杉田さん:はい。だから、そういった揺り戻しに取り込まれないための戦略や努力が必要なわけです。
そのためには、一段階目を整えたうえで、二段階目として、個々が持つ欲望や身体というものを表現していかなきゃいけない。
正しいものは正しいんだっていうふうに欲望とか身体を抑圧して、個人の欲望に向き合うことをおろそかにしてしまうと、多様性という言葉もただのスローガンで終わってしまうんですよね。
福田さん:個々の中にあるPCからはみ出してしまうような欲望や身体の存在を認めることと、そこに開き直って揺り戻しに取り込まれてしまうこととは違う、ということですね。
観客と作り手、双方から育てていくエンタメの未来

杉田さん:#MeTooが話題になった頃、社会的な必要性もあって、「#MeToo時代のフェミニズム映画」と呼べるような作品がたくさん制作されました。女性たちは権力を持つ男性が作り上げた社会の犠牲者であって、犠牲者たちがシスターフッドを結ぶことで、ヴィランである男性を倒すという図式です。
海外の作品は、最近はそこから進んで、フェミニズムや女性たちの描き方が複雑化した作品が増えていますよね。例えば、『TAR/ター』『TITANE チタン』『落下の解剖学』『ANORA アノーラ』といった作品です。女性の中にもある加害性を描いたり、単純に「犠牲者だからかわいそう」という女性像だけにとどまらない表現が模索されている。
また、シスヘテロ(出生時の性別と性自認が一致し、異性愛者の人)男性を中心とした、マジョリティとされている人々が抱える不安をすくい取っている作品も出てきています。
福田さん:そういう意味では、日本のエンタメ作品はまだまだ「#MeToo時代のフェミニズム映画」の図式の作品が多いかもしれませんね。
ただ、もし今の日本で女性の加害性やマジョリティの苦悩を描いた作品が出てきても、先ほど杉田さんがお話ししていたような、PCや多様性に対抗する“揺り戻し”に利用されたり、解釈されかねないんじゃないかと思うんです。
杉田さん:それはきっとそうですね。もどかしいところです。
日本社会はまだまだ、ジェンダーにまつわる“ねじれ構造”を物語で描ける段階にはないと思います。もっと手前のところで、やっておかなければならないことがたくさんある。
——どうすれば、日本も先に進んでいけるのでしょうか?
福田さん:それはもう、多様な作品が作られていって、見る側の空気が追いついていくしかないんじゃないかな…と思っています。
杉田さん:今はSNSなどで、観客の影響力が高まっていますよね。観客がプレッシャーを与えることで、作り手側と受け手側が相互作用を起こして、高みへいけるんじゃないかなと。
理想論かもしれないですが、そういう方向に行ってほしい。少なくとも、今の観客は「PCやフェミニズムなんて」という人ばかりじゃない。PC的な価値観をインストールした観客がどんどん育ってきていると思うんです。
僕自身、市民であり消費者の一人として、極めて微力であっても、SNSで作品の批評を発信していくことで、世の中の空気を変えていくことにコミットしている部分はあると思っています。
福田さん:SNSの市井の人々の感想を見て、「こんな解釈や読み解き方があったのか!」と気づかされることも多いです。
杉田さん:集合知の力って侮れないと思うんです。たぶん、みんなの作品への理解がこれほど深まったことって、人類史上初めてのことなんじゃないかと。これまでは、一部の評論家が本とかを出して、それを多くの読者が読んで考えるという形が多かったですよね。でも今は、何か作品が公開されると、膨大な数の人たちが自分の知恵を持ち寄って解読していく。もちろんそれの悪いところもあるんだけれど、総合的にいうと、みんなの批評眼というのは確実に養われている。そこから出てくる面白い解釈も、どんどん増えている気がするんですよね。
少なくともそうすることで、みんなの意見が同じ方向に流されるみたいなことはなくなると思います。
福田さん:そうですね。そうやって、大衆の消費行動から変わっていくことに期待したいです。
イラスト/CONYA 画像デザイン/齋藤春香 企画・構成・取材・文/木村美紀(yoi)