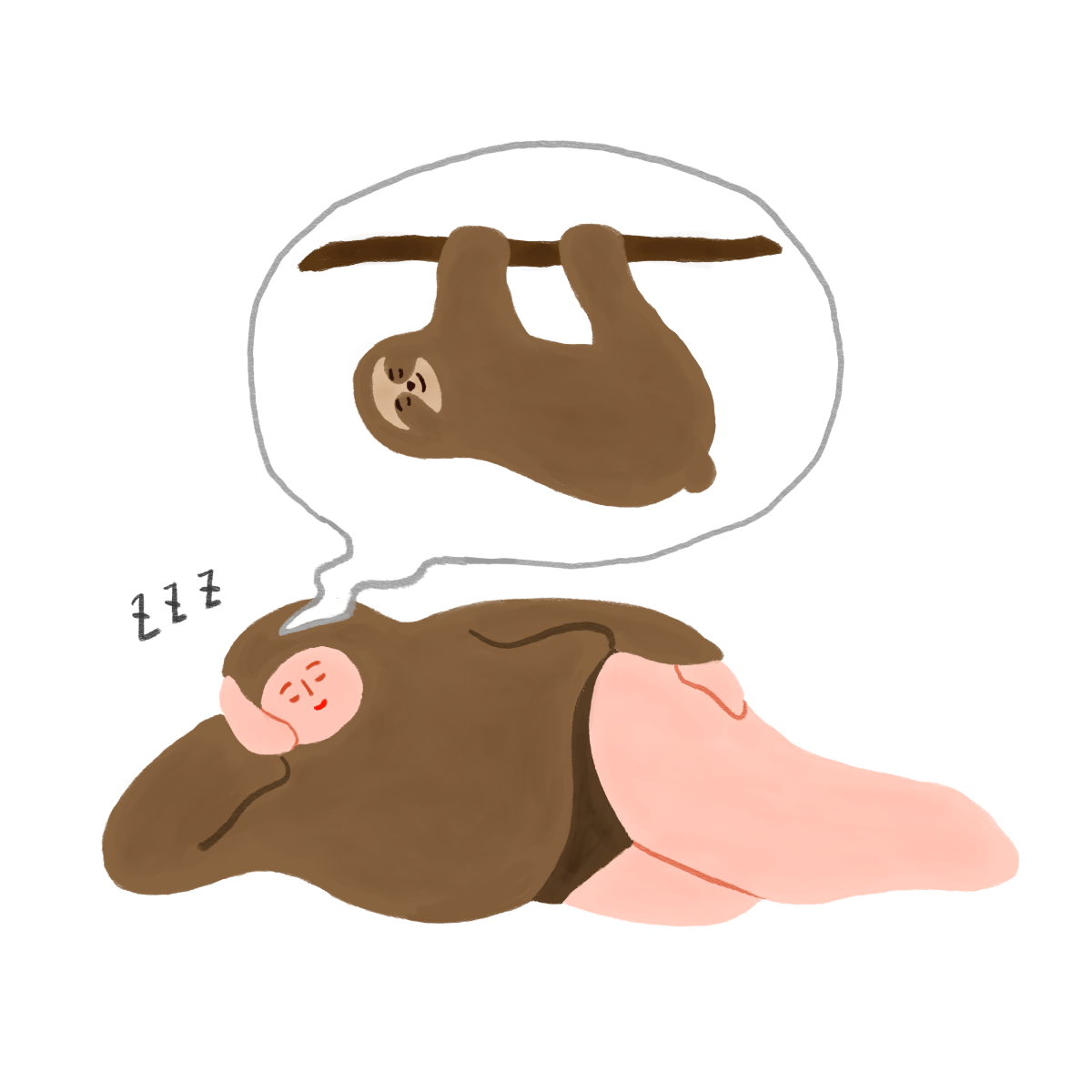生理についての理解が深まることは、女性にとっても男性にとっても、社会にとっても有益なこと。そんな思いで日々過ごす私たちにとって、うれしいお知らせがありました。それは「横浜国立大学で、学生による生理についての企画展『あなたにとっての“生理”って?』が行われる」というもの。共学である横浜国立大学での展示がなぜ実現したのか、学生たちがどういった思いを持っているのか、yoi編集部の木村と、ライターの堀越が取材に伺いました。
※展示は2025年4月14〜18日に開催されました。
横浜国立大学の企画展「あなたにとっての“生理”って?」

出迎えてくださったのは、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部で講師をされている髙野陽介先生。
髙野先生:実は2023年に横浜国立大学の憲章が20年ぶりに改訂されて、新たに“多様性”が加わりました。そして横浜国立大学と提携しているフェリス女学院大学で行なっていた「生理の歴史」展という展示を見たこともあり、本学でも何かできないかと考えて今回の企画展を実施することになりました。
企画展を主導したのは、5人の学生です。

(左から)川嶋美夢さん、頭島壮汰さん、井上歩美さん、小岩井優子さん、萩原蒼さん
髙野先生から「横浜国立大学でも何か生理に関する展示をしてみませんか」というアナウンスを受け、同じ授業を受けていたメンバーや、そのメンバーが声をかけた有志が集まったのがこの5人だったそう。

頭島さん:今回は5人で話し合いながら各々が気になるテーマをひとつ決めて、それについての展示を作成しています。フェリス女学院大学の展示も見ていたので、共学である本学でどんなことができるかを考えました。
男性である私たちは生理についての知識も少なかったと思います。展示を作る中で、女性間でも理解されない場合があることを知りました。男性の生理への無理解はもちろんですが、女性の無理解も解決しなければならない問題だと感じました。
萩原さん:私はパートナーから生理の話を聞いたことはあったのですが、それでも知らないことばかりです。今回の展示を通して、女性の中でも生理のつらさや痛みの感じ方がそれぞれに違うことを再認識しました。
生理周期やPMS、ピルについての展示

小岩井さんが作成したのは、生理周期についての展示です。
小岩井さん:展示を作るにあたって調べていく中で、男性は生理についてまったく違う理解をしていたり、自分でコントロールできるものだと思っている人がいるという話を耳にしました。男性の無理解を解消したい、基礎知識をつけてほしいという気持ちで、まず最初にこの展示を見ていただいています。
この展示は生理の周期についてカレンダー調にまとめています。生理周期というのは生理中の1週間だけの話ではなく、1カ月周期でずっと続いていて、その中でも色々な時期があり、それぞれ体に変化が起こることを知ってほしいと考えました。
体の状態にも個人差があるので、自分がどの時期にどのような体験をしているかを付箋に書いて貼ってもらうことで、みんなでこの展示を完成させたいと思っています。

井上さんは、生理中の悩みや困りごとをふきだしに書いて展示しました。
井上さん:この展示は、とにかく生理中に困ることの具体例を挙げたいという思いでつくりました。皆さんの実体験に即した困りごとや悩みなどリアルな声を聞き、共感性が高そうな実際にある場面を想定して、“つぶやき”のような形にしています。
付箋には“つぶやき”への共感はもちろん、反対意見を書いてもいいし、自分はこう感じる、という意見を交換するために使ってもらっています。

頭島さんは、PMSについての展示を担当されました。
頭島さん:PMSというワードはYouTubeでも「生理前爆食」といったコンテンツがあったりするので、男性でも耳にする機会が増えたと思います。
ただ単語を知っても、その情報は正しいのか、どうやって情報にアクセスすればいいのかわかりづらいと感じたので、PMSについて一歩踏み込んだ展示にしたいと考えました。だから身体・精神の不調に分けて、症状をまとめています。
右側には、今回協賛してくださった『ケアミー』さんが実施した、男性へのPMSについてのアンケート調査結果を載せています。男性でも女性でも、見た方にPMSに関する困りごとを付箋に書いてもらって、我々もさらに理解を深められるようにしました。

川嶋さんがテーマとして選んだのは、まだまだ誤解されることも多いという低用量ピルについて。
川嶋さん:今でもピルについての偏見があると感じています。私たちの親世代は「病気じゃないのに」「費用がかかるのに」「気合いで耐えられないのか」と思う人も多いそうです。
我々世代でも副作用が怖いという声もあり、知識がないことで抵抗感が生まれているかもしれません。だからピルについての知識をわかりやすく掲示することで、苦しむ人を減らせるのではと考えて作成しました。
私自身も低用量ピルを飲みはじめてかなり楽になったので、展示を見てくださる人たちにも「私はこうだったよ、そのつらさを軽減できるかもよ」と声をかけてあげられるような展示にしました。
無料でできる生理痛体験も!

萩原さんが案内してくれたのは、「生理のトリセツ」というカード。
萩原さん:伊藤忠商事さんが実施されていたイベント「生理と社会の交差展」で、実際に配布していたものです。今回伊藤忠商事さんにお願いして、このイベントでも無料で配布させていただいています。
自分の生理について当てはまる項目にチェックを入れて、家族やパートナーに渡しておくことで、理解が深まると考えています。
展示の奥には大きなテントがあり、そこではなんと生理痛体験ができました。


yoi編集部のエディター木村(左)と、ライター堀越(右)も体験
萩原さん:EMSを使った生理痛体験デバイスを使って、生理痛体験ができます。男性が生理について体感できる機会として、また女性でもご自身が普段感じている痛みと比較することで個人差を認識できる機会として実施しました。本イベントの目玉とも言えるコンテンツです。本学の学長にも体験してもらいました。
エディター木村とライター堀越も体験させていただきました。
木村:私は生理痛が軽いほうだと思いますが、それでも、これよりはもっと痛いですね。でも、お腹の奥のほうがギュッと掴まれる感じはかなり生理痛っぽいです!
堀越:この装置は筋肉量の多い人のほうが痛みを強く感じるそうですよ。だから、男性のほうが比較的痛く感じやすいとか。私はあまり筋肉がないので痛みは強く感じませんでしたが、痛みの“質”はリアルに再現できていると思います!

誰でも参加できる座談会の時間も設けられ、この日は他大学の学生が参加していました。彼女はイタリア旅行でロストバゲージに遭い、異国の地で生理用品を買うことになって戸惑った経験から、「生理用品によって女性の生活は大きく変わる」ということに気づき、日本の生理用品の歴史をテーマに卒論を書いているそう。学生たちがランチしながら生理の話をする姿は、なんだか頼もしいですね。
男性も女性も、お互いへの理解を深める一歩に
「生理痛体験してみませんか」という5人の声かけに対して、通りかかる学生たちは興味ありげに目を向けたり、ちらっと見て通り過ぎたり、「やりたいです!」と答えたり、反応もさまざま。
髙野先生:本学では今まで生理に対するこういった取り組みはなかったですし、通りかかる学生の反応を見ていただければわかると思うのですが、見て見ぬ振りをしたり、恐る恐る入ってくる人も多いです。
今回企画展を主導してくれた5人も最初は意見を出しづらかったようで、企画の内容もなかなか進まなかったのですが、少しずつ積極的に変わっていく姿を見ることができました。この企画展も多くの学生に見てもらえたら、学内全体の空気も変わるのではと期待しています。
撮影/細谷悠美 取材・文・構成/堀越美香子 企画/木村美紀(yoi)