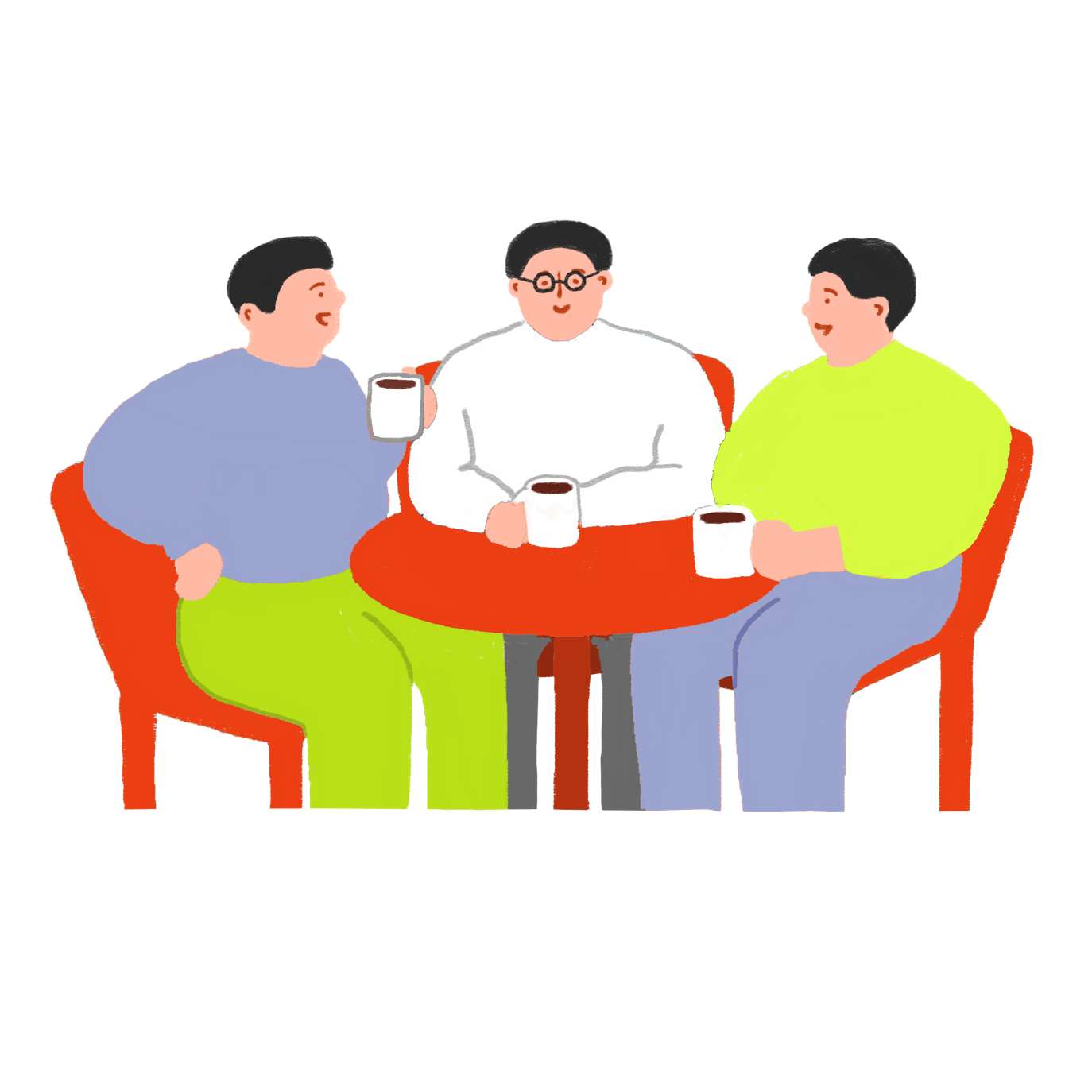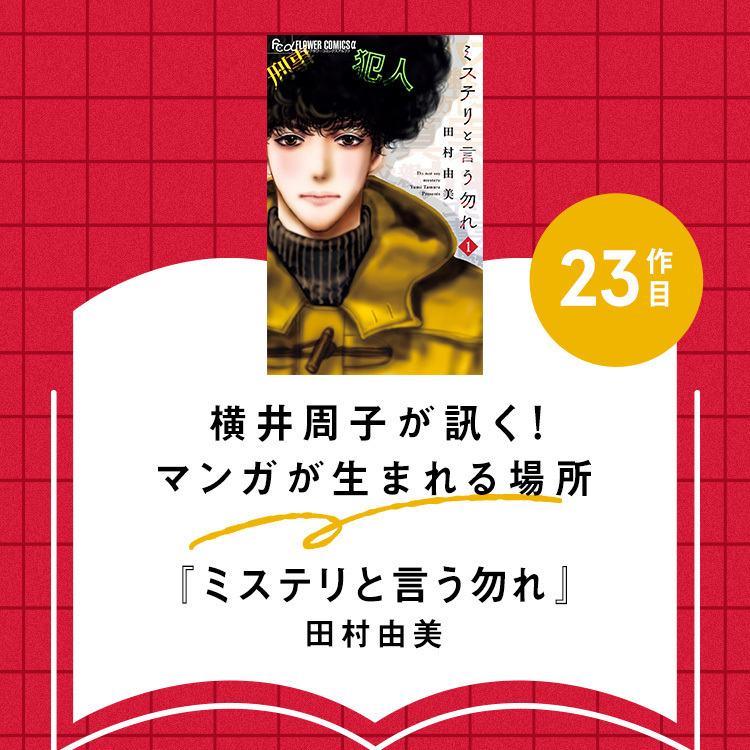食べ物の刹那的な魅力を、唯一無二の表現で綴るフードエッセイストの平野紗季子さん。「自分が自分でいるためには、ごはんを食べて感じる時間が必要不可欠」と語る平野さんを支える味とは。
ごはんを食べる行為が自分を自分たらしめる

——小学生の頃から、どこでなにを食べたのか食日記を綴っていらっしゃるそうですね。今にいたるまで20年近く続けるモチベーションの源はどこにありますか。
平野さん:食体験について感じたことを記録することは、もう自然なルーティンになっているので、特別に続けようとは意識していないんです。食日記に対してモチベーティブでいる必要がないというか。
今はすべてスマホのメモに書き留めていますが、始めた頃は自由帳に書いていました。その後は文房具屋さんで見つけた「食べものノート」みたいなやつに。食日記のいちばん古い記憶は、たしか給食に出た「タラのクリームグラタン」。あまりにおいしかったんでしょうね(笑)。食べものは、どんなものでも食べたら消えてしまうから、何らかの形で残しておきたいという気持ちはずっと変わっていません。

——大学生時代に発信していたブログをもとにした初の著書『生まれた時からアルデンテ』が話題になりフードエッセイストとしてのキャリアをスタートさせます。それから約10年経ちましたが、心境の変化はありましたか。
平野さん:『生まれた時からアルデンテ』を刊行したときは、まだ大学を卒業したばかりでしたし、ただただ食の眩しさに心を奪われていたというか、どこが前なのか後ろなのかわからないくらいに、乱反射の中に身を置いていたっていう感覚なんです。時を重ねていくうえでだんだんと一面的な光だけでなく、影の部分というか暗がりにある食の世界も見えてくるようになったように思います。
食体験を立体的にとらえることができるようになってきたな、と感じることが増えてきたのがこの10年間。喜ばしいハレの食べものだけが日々口に入るわけではないし、それだけが価値のすべてではない、ということを身をもって知っていく期間でもあったと思います。
会社員時代にプレゼンの資料づくりが終わらなくて、夜中の2時になっても帰れない。必死で仕事をしているなか、誰かが買ってきてくれた吉野家の牛丼の味とか、発砲スチロールの容器からお米こそげとるカサカサという音とか、むしろそういったもののほうが記憶に残ってたりするんですよね。その渦中にいたときは、なんてしょっぱい日々なんだ、早く思い出になってほしいと願っていましたが、今はあのときの日々を愛おしく感じています。

やっぱり虚無にはごはんが効きますから
——個人の仕事と並行しながら会社での仕事も続けるのは、とても大変な日々でしたよね。激務をこなしてきた平野さんを支えてきたのもやはり「食」でしょうか。
平野さん:それは本当にそうですね。本にも書きましたが、やっぱり虚無にはごはんが効きますから。仕事で疲れ果ててしまって、自分が空っぽのように感じてしまうタイミングってありますよね。深夜にやっと会社を出られても、もう外には誰も歩いていないし、本当に空っぽ、自分の中になんにもない、みたいな感覚に……。
そんなときに、家の前の深夜までやっている食堂にすがるように入ってごはんをいただいたら「おいしい」のはもちろんそうなんですが、自分にもまだ「感じる力」が残っていたのか……と気がつくことができて、それが強く心に残ったんです。その経験から、私が私でいるためには、たとえちょっとやそっと人様に迷惑をかけてでも、食事をして何かを感じる時間を守らなきゃいけないんだと強く感じるようになりました。
「私って人の人生の一部なのかも」とか、「社会の歯車だな」って感じるときがあるじゃないですか。もちろんそう思えるからこそ寂しくなかったり、社会に貢献できてると感じたりできるから、その感覚も必要なんですけど、あまりにそればかりだと自分を失ってしまうような、むなしい気持ちにもなりますよね。
でも食べたいものを選んでそれに全力で向き合っている時間って、すごく自分の時間を生きている感じがするんです。そこで得られる感情も嘘偽りがないですし。「あ、私、今生きてるな」って実感を持てるのが、私の場合は食べものなんです。

——何が食べたいのかわからなくなってしまうくらい虚無の状態になってしまったらどうしていますか?
平野さん:「もうダメだ。スーパーに入ったのに何も買わずに出てきてしまった。食材が何も訴えかけてこない……」って日もありますよね。もうそれくらい虚無になってしまったら、私は、コンビニの冷凍鍋焼きうどんを食べるって決めています。夏でもちゃんと売っていますし。化石のように霜がかかっているときもありますけど(笑)。考えるのも負担になるので、決めておくと気持ちがラクになります。
Uberも信頼と実績の鬼リピ店がいくつかあります。とあるイタリアンはおひとりさまのお任せコースみたいなのがあってもはやメニューを選択する必要もない。もう色々限界だ!という時は、仕事の帰り道にそれを頼んで、家に着くなり料理を受け取り、YouTube観ながらだらだら食べるのもめっちゃ幸せです。
お菓子の、悲しみに寄り添う力はすごいです

平野さんが「供えらたい菓子」と評する、京都「kew」のカスタードドーナツ。「セーターに散らばった砂糖のきらきらまでもが愛おしい」。
平野さん:悲しいときは、やっぱり甘いものに支えられていますね。お菓子の悲しみに寄り添う力はすごいです。家では、冷凍庫に好きなお菓子をたくさんストックしてあるので、つらいときに解凍してパクっと食べる。会社員時代は「ウエスト」のシュークリームに支えられていました。世知辛さ通さない外皮、心の隙間埋め守るカスタード……。生地がすごくやわらかくって、やさしいんです。
つらい経験、つまり、闇がお菓子をおいしくするんだ、と気づいたのは社会人になってからのことでした。学生時代からよく食べていた味も、仕事で大変な経験をしてから改めて食べてみると「前に食べてたときと全然違う!脳が輝くほどおいしい」と感じたこともありましたから。
撮影/中村力也 取材・文/高田真莉絵 構成/渋谷香菜子