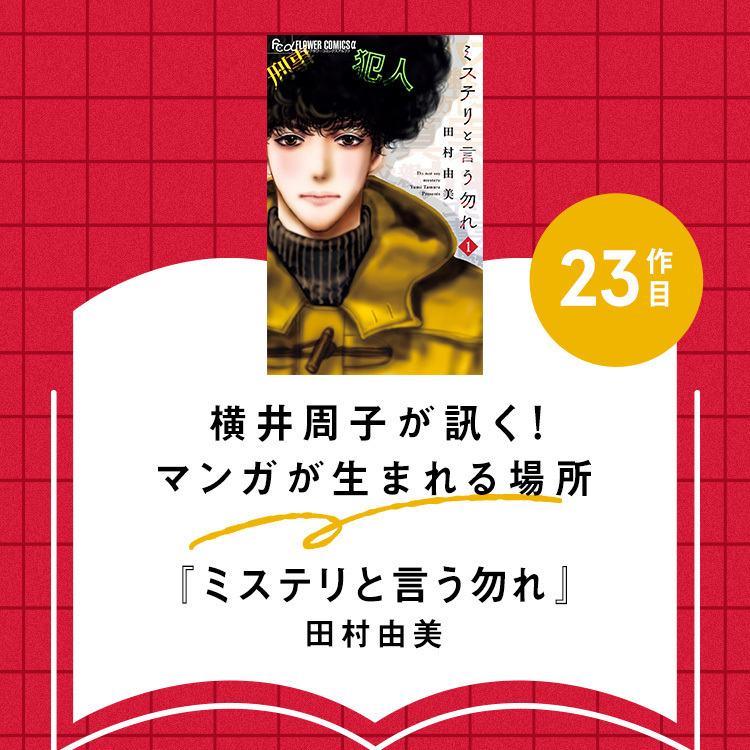人種と貧富がごちゃまぜの「元・底辺中学校」に通う息子の日常を描いた話題作『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』では、他者を考え、想うことの大切さを教えてくれたブレイディみかこさん。インタビュー後編では、行動に移す勇気を持つ大切さを教えてもらいます。
もやもやしているばかりじゃ始まらない!

——集英社の雑誌メディア「MORE」のウェブ&プリント版では20代女性の悩みを聞く連載をされています。読者が日々モヤモヤしていることを聞くことで気づいたことはありますか。
ブレイディさん:まず東京在住で大手企業に勤めている子と、地方在住で中小企業に勤めている子では、話す内容も、悩みも違う。日本では“階級化”が進んでしまっているな、と感じます。
私が若かった80年代は、今よりずっとマスメディアの力が強くて、雑誌も影響力を持っていたから、都心と地方で流行っているものにそこまで違いがなかったと思うんです。でも今は見ているコンテンツが階層ごとにまるで違うから、文化的なものを含めた階級が生まれてしまう。日本はそれこそ“縦の多様性”がめちゃくちゃあると思いますよ。
でも、大企業に勤めている子が得をしているかというと、そうでもない。上司からのセクハラやパワハラに悩まされている子もたくさんいるようです。いまだに、「結婚適齢期」というキーワードを発する子がいることにも驚きました。「25~30歳が適齢期だから、今から婚活して、結婚、妊活しなきゃ」とかって。
私はイギリスの国民保健サービス(NHS)を使って、無料でIVF(体外受精)治療を受けたんですが、当時は40歳までしかやってもらえなかったものが、最近改めて調べてみたら年齢制限が43歳に上がっていたんです。テクノロジーや医療技術の発達が、適齢期などを気にしている日本の子たちの意識を変える突破口になるんじゃないかなって。
——女性が抱える労働問題を解決するためには、どんな心構えでいたらいいのでしょうか。
ブレイディさん:どんな言葉をかけたらいいのだろうって、書き手として考え続けています。やっぱりみんな本当にもやもやしているから。
韓国の小説『82年生まれ、キム・ジヨン』が流行りましたよね。この本の担当編集者に聞いたところ、韓国では女性たちがあの小説を読んでみんな怒ったらしいんです。でも日本の読者は「泣きました」ってリアクションばかりだったと。泣いているばかりじゃ何も始まらないんですよね。韓国の人たちみたいに怒らないと、行動を起こすまでに至らない。
100年ほど前にイギリスで女性参政権運動をやっていたサフラジェットを知っていますか? 彼女たちは参政権を得るために、街に出て暴れたんですよ。当時、夫や子どもたちを優しく支えてくれる母性あふれる存在だとされていた女性たちが、暴力沙汰を起こすわけですから、男性たちはさぞ衝撃を受けたと思います。でも、激しい運動を通じて「女性だって社会に参加すべき人間なんだ」っていうのを、男性たちにしっかりと理解させたわけです。
——行動を起こすことが大切ですね。
ブレイディさん:日本はジェンダーランキングがめちゃくちゃ低いって話題になりますよね(2024年は146カ国中118位)。でも、15年連続1位になっているアイスランドだって、最初から男女平等の考え方が根付いていたわけではない。
1975年に女性たちが家事や育児、仕事をすべて放棄して街へ繰り出すストライキ運動を起こしたんです。「女性の休日」と呼ばれるこのストライキにアイスランド女性の9割が参加したそうです。9割ってすごくないですか。そういう行動があったからこそ、今がある。日本はもやもやしたり泣いたりしているだけで終わってしまって、まだ次の一歩に踏み出せない……。生きづらい、きつい、という感じは膨張していると思うんですけど。
「yoi」でも、ウェルビーイングを取り上げていますけれど、自分だけのウェルビーイングじゃなくて社会全体のウェルビーイングも考えていかなくちゃいけない。「私のウェルビーイングを突き詰めていきたいのに、制度とか社会からの邪魔が入るんだよね」って気づけたら、最初の一歩。自分のことだけ考えて動いても、必ず限界がおとずれます。社会全体が少しでも上向くようにしないと、自分の暮らしも向上しないわけです。

——社会全体のことを考える俯瞰的な視野を持たないと、自分だけ得をすればいい、自分が損をするのは嫌だ、という考えが広まってしまいますね。「弱い」女性でいたくないから、男性側につこうとする人も出てきてしまいそうです。
ブレイディさん:いわゆる名誉男性って言われる人たちですよね。でも、日本に女性の首相が出てこないということが、名誉男性なんてやっていても限界があるということの証拠なのでは? たとえ男性に好かれて引っ張ってもらったとしても、男性と同等に活躍することが約束されていないですから。人口の半分を占めている女性を活躍させないなんて、単純に国の損失だと思いますけどね。腹立たしいです。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の中で、意見の異なる相手を理解する知的能力である「エンパシー」という言葉を、「他者の靴を履く」と表現して紹介しました。たしかに権力を持っている人の靴は履き心地がいいし、得をすることももしかしたらあるかもしれない。
でも、自分が病気になったり、事故にあったりして権力者側にいられなくなる未来を想像することも大事です。今ここにいる自分とは違う境遇になるかもしれない自分へのエンパシーです。生活保護受給者をバッシングする動きもありますけど、自分だっていつ受給者になるかわからないのに。あまりにも想像力が欠如している人が多い気がします。
家族にばかり面倒をみさせて国は何もしない
——イギリスの若い世代の人は、どんなことに生きづらさを感じているのでしょうか。
ブレイディさん:階層によってまったく違ってくるとは思いますが、イギリスは貧困がとても広がっているから、貧しい層は本当にお金がないですよね。TikTokでは、一昔前なら自分たちが買ったものを紹介する動画が流行っていましたが、今は着回しを紹介する動画がよく見られます。みんな新しい服を買うお金がないから。「丈の長いシャツはこうすればボレロみたいにして着られますよ」みたいな。マーガレット・サッチャー時代に、貧困層が増えたときにもDIYって言葉がすごく流行ったんですよ。時代が戻ってきてしまっている感じがします。
——日本の若い世代では、親との関係性に悩んでいる方も多くいます。イギリスではどうですか。
ブレイディさん:普遍的な問題なので、もちろんイギリスでも悩んでいる人はいると思いますが、日本の家族観って独特ですよね。たとえば日本では、結婚は相手とするというより、“家”とする側面が強いように思います。
夫が先に他界した場合、死後離婚しておかないと義両親の介護をしないといけないとか、生活保護を受けるときは、親族や兄弟に「あなたが扶養できないんですか」って連絡がいきますよね。家族に面倒を見させて、国は責任を放棄する。欧州の人たちにこの話をすると「税金払っているのに国は何をしているの? そのための税金じゃないの」ってとても驚かれます。
日本では、将来何かあったら国じゃなくて子どもたちに面倒をみてもらわないといけないという考えがあるから、教育熱心にもなるし、子どもと親の距離が近くなりすぎてしまうのかもしれません。「困ったら家族でなんとかしよう」から、「社会全体で個人を支えよう」という方向に意識を変えていかないと。個人のために政治を行う国になってもらわないと困るから、社会に目を向けなければいけないし、そういった政治家を選ぶ必要がある。個人の生活とそれを支えるべき政治がきっぱり切り離されてしまうと、その間を補うものとして家族の関係性の圧が強くなりすぎるのかもしれません。

『転がる珠玉のように』ブレイディみかこ(中央公論新社)
イラスト/よしいちひろ 取材・文/高田真莉絵 構成/渋谷香菜子