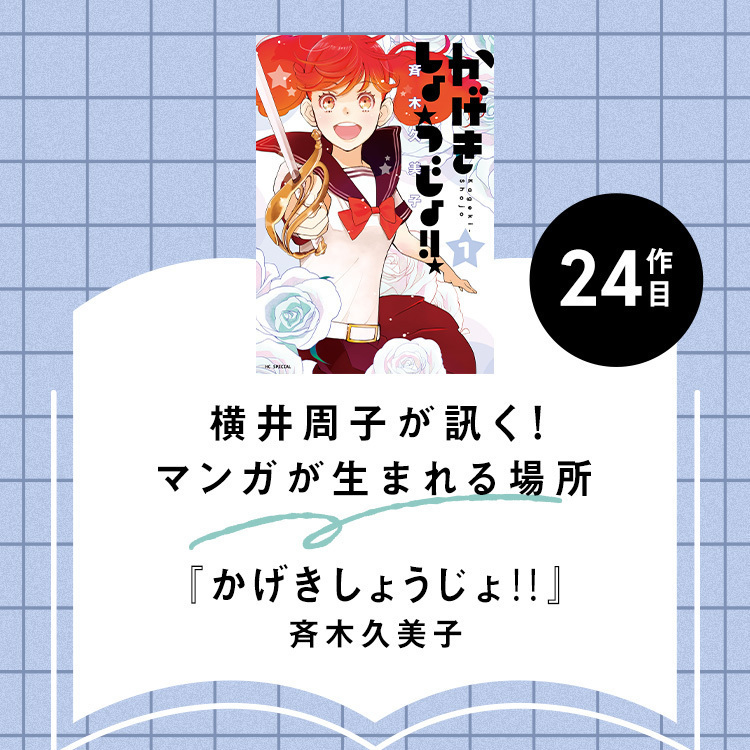ジェンダーの視点から広告観察・批評をしている小林美香さんに、不安を煽ってくる広告やSNSとの付き合い方を伺いました。広告は、何をしていても毎日目に入ってくる存在だからこそ、上手な距離の取り方を考えることが必要と小林さんは語ります。
実体のあるものを観察して「腑に落ちる」経験を

——インタビュー前編では、コンプレックスを煽るような広告の存在と若年層への影響についてお話していただきました。小林さんはご自身にもお子さんがいらっしゃいますが、どのように広告との付き合い方を教えていらっしゃるのでしょうか。
小林さん:スマホが普及して以降、SNSやYouTubeなどで、他人の顔写真をクローズアップで見る機会が増えましたよね。スマホがない時代にはあまりなかったことだと思います。
よくも悪くも、自分と他人の顔や容姿がはっきりと見えてしまうからこそ、他人と比べて劣等感が生まれてしまう。そこに「今のままでいいの?」「きれいになったほうが幸せになるよ」と圧をかけてくる広告があります。
自分の子どもだけではなく、私が教えている学校の生徒さんたちにも伝えているのは、「画面上だけでものを判断してはいけない」ということ。実際の相手の姿は見えない一方で、情報は過剰でアンバランスです。
でも、今の子たちはまるでスマホを握りしめているかのように過ごしていますよね。見えすぎてしまうこと、見すぎてしまうことによる疲労がたまってしまっているように感じます。
可能であれば実物をしっかりと観察し、「腑に落ちる」経験を積んでいってほしいと考えています。スマホで“なんでも見える”気になってしまうからこそ、画面から離れる時間を持つことも大切です。また、落ち着いてまわりの人たちと話す機会をもっと増やしてほしいです。
——おすすめの書籍などはありますか?
小林さん:なりたい自分を求めて、SNSに依存してしまう現代の人々を描いた『欲望の鏡』(リーヴ・ストロームクヴィスト/著) という本があります。美しさ、魅力、欲望はどこから来てどこに向かっているのかを論ずる内容になっていて、私たちがいかにSNSなどによって作られた魅力に翻弄されているかがよくわかります。
広告は消費者に評価されるもの。私たちの声は少しずつでも届くはず

——広告においては、ルッキズムの価値観が根強く残っているように感じます。日本に限らず、ルッキズムをめぐる現状については、どう思われますか?
小林さん:日本と比べて、欧米では女性差別やルッキズムの問題に「NO」を表明する人たちは多いかもしれませんが、セレブリティの多くはルックスの変化を逐一チェックされ、常に話題にされています。誰々が整形した、豊胸した、なんて情報であふれていますよね。彼女たちが誰の視線と欲望を反映し、体現しているのかをきちんと考える必要があります。
——最近見た(取材時は2024年12月)広告の中で、違和感を感じたものはありますか?
小林さん:東京五輪のときにも感じたことですが、アスリート選手を神格化しすぎているのも気がかりです。著名なアスリートを起用した広告は、商品よりも人物の写真を大きく使用しているのが印象的です。 嫉妬すら感じさせないほどの能力を持っているからこそかもしれませんが、神格化するかのような広告表現は危ういと感じます。
スポーツは能力が評価されるものなので、アスリートをあがめ続けている広告表現が増えると、この社会がどんどん能力主義になっていくことにもつながります。
その一方で、さまざまな企業の広告で、ジェンダー・ステレオタイプを解消するためのさまざまな取り組みが行われているものもありますね。飲料や酒類の広告で、水着のような肌の露出の多い女性像を使って、女性を性的に客体化する表現は以前に比べると減ってきたように感じます。
違和感を感じる広告を減らしていくには、よいと思ったCMを評価することも大切だと思います。広告はよくも悪くも消費者に評価される。私たちの声は少しずつでも届くはずです。
イラスト/Saki Morinaga 取材・文/高田茉莉絵