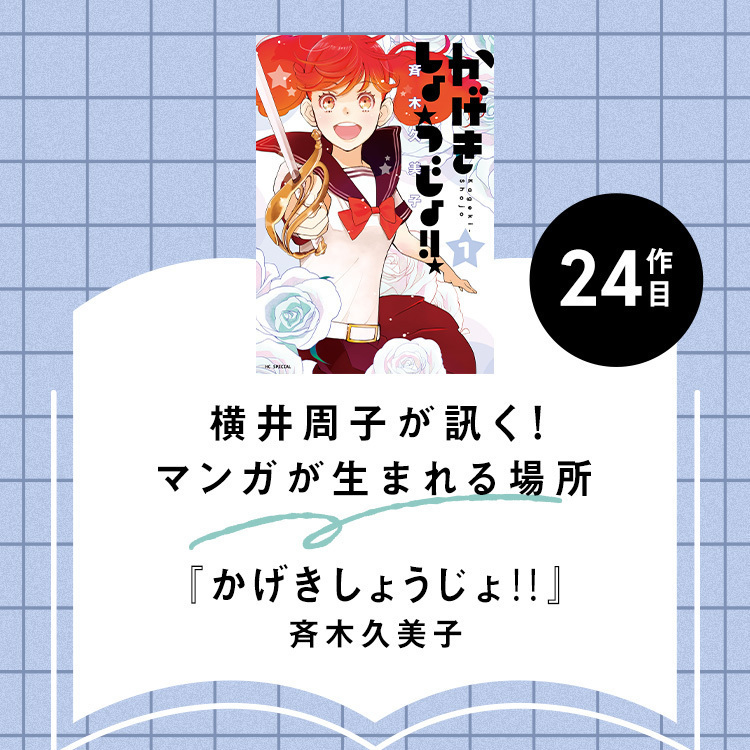『yoi』の人気連載「桃山商事・清田のBOOKセラピー」を手掛ける文筆家・清田隆之さんが、昨年、新著『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』を発表。2020年に大反響を呼んだ『さよなら、俺たち』から5年が経った今、男性たちの意識や在り方は変化しているのでしょうか。清田さんが感じた変化から、男性読者からの反響、今作に取り組む中で感じた葛藤まで、じっくり語ってもらいました。


文筆家
1980年生まれ、早稲田大学第一文学部卒。文筆家、『桃山商事』代表。ジェンダーの問題を中心に、恋愛、結婚、子育て、カルチャー、悩み相談などさまざまなテーマで書籍やコラムを執筆。著書に、『おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門―暮らしとメディアのモヤモヤ「言語化」通信』(朝日出版社)など。最新刊『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』(太田出版)も好評発売中。桃山商事としての著書に、『どうして男は恋人より男友達を優先しがちなのか』(イースト・プレス)などがある。Podcast番組『桃山商事』もSpotifyなどで配信中。
#MeTooムーブメントの影響で、前作は多くの男性から反響が

——2024年12月、男性性にまつわるエッセイをまとめた著書『戻れないけど、生きるのだ』が出版されました。本作の執筆に至った経緯を教えてください。
清田さん:2020年に同じような作りの『さよなら、俺たち』を出しまして、その当時から、同じ編集者さんとまた数年後に続編を出そうと話していたんです。前作は2016年から2020年までのエッセイをまとめたもので、『戻れないけど、生きるのだ』には、主に2020年から2024年にかけて書いたエッセイをまとめています。
エッセイはそれぞれ異なる媒体に掲載されたもの。1冊の本にするために書いたわけではないけれど、振り返ってみると、そこには連続した問題意識が流れていたように思います。
——前作『さよなら、俺たち』は大きな反響があったとか。読者からは、どのような言葉が届きましたか?
清田さん:前作に掲載したエッセイの多くは、2017年に始まった#Me Tooムーブメントが広がっていく中で執筆したもの。ちょうど社会的にも、男性の加害性とか暴力性、特権性、男性優位な社会構造があらためて浮き彫りになり、“いくら女性側が異議申し立てをしても、男性がそれを受け止めて見つめ直さないと変化しないよね?”と問われているような時代背景がありました。そういう状況の中で、マジョリティの男が当事者として内省していく内容が珍しいものとして映ったのだと思います。
男性向けに書いたものではあったものの、実際に読んでもらうのはなかなか難しいかも……と思っていたのですが、想像を超える反響がありました。「当事者の一人として、なぜこのような価値観が自分たちの中に根付いてしまったのか、深く考えさせられました」「身につまされる思いです」「読んでいてお腹が痛くなりました」といった言葉を特に多くいただき、とても驚きました。
5年が経ち、男性間の「意識の差」はますます広がった

——今作に集約されたエッセイを読み直す過程で、前作と比べて社会の変化は感じられましたか?
清田さん:変化している部分と変わっていない部分、どちらもあると思います。まず、男らしさをめぐる議論が進み、男性の立場や目線からジェンダーの問題を考えること自体は珍しいものではなくなりました。男性たちだって複雑な傷つきやトラウマを抱えていて、それは社会構造が生み出している部分も大きく、個人の反省だけを強調してしまうのも問題ではないか……という認識も広まってきた。内省や反省だけでなく、もっと問題を細分化し、丁寧に解きほぐしていこうというのが男性性をめぐる議論の現在地だと思いますが、一方それが一般社会にまで広がっているかというと、そうでもないというのが現状で。
つまり、ジェンダーの問題に関心ある人たちの中では普通のことになっているけれど、まだまだ社会全体としては認知されていない。そのような状況の中で、どういうスタンスの本にして、誰に届けるのか、すごく悩みました。前作で「さよなら」と言ってしまったけれど、そんなに簡単には抜け出せないし、かといって同じところに留まっているわけにもいかないし……そんな葛藤がタイトルにも現れている気がします。
ハラスメント意識が広がっている中で反動的な意見も増加
——世間の関心度や問題意識にバラつきがあるなかで、誰にどう届けるべきか、と。
清田さん:そこはとても悩みました。たとえばシンプルに、「男は反省しましょう」「アップデートしていきましょう」みたいな内容にすれば、よりわかりやすい本になるとは思うんですが、マジョリティの男性を悪魔化して叩いていれば議論が進むかというと、決してそうではない。とはいえ男性は悪くないよね、社会のせいだよね、っていうのも違うし……。そこが本当に難しいところでした。
——社会が変化していると感じたのは、具体的にどの部分ですか?
清田さん:たとえばこの数年、芸能界の大御所たちが性加害で告発され、一線を退くという事態が続いていますよね。#MeTooムーブメントという文脈の中で言えば、社会においてかなり力のある立場の人であっても、告発されれば、立場を失うような状況にはなってきた。何かが劇的に変わったというよりは、もともとあった#MeTooムーブメントの流れがより顕著になってきたということかもしれません。
セクハラやルッキズム、コンプライアンスといった言葉がメディアで普通に使われるくらいには意識が広がっている一方で、反動的な意見も増えている。「コンプラコンプラうるせえ」「今は女の方が優遇されてるだろ」「息苦しい時代になった」などの声が上がったり、フェミニストが悪魔的な扱いを受けたり。実際にバラエティ番組などでも反コンプライアンス的な企画が増えてきている印象ですが、そういった禍々しい感情がより強まっているように感じています。

「自分は言わない」だけじゃ問題解決にはならない
——今作にも書かれていましたが、“言っちゃいけないから言わない”雰囲気も漂っていると感じます。“納得はしていないけど、叩かれるから仕方ない”というスタンスの人が少なくないような…。
清田さん:わかります。ジェンダーやルッキズムに関する問題意識が浸透し、軽率な言動がしづらくなっていること自体は悪いじゃないと思うんです。ただ、そうやって“損するから気をつけよう”とか、あるいは言う相手を選んだりとか、テクニカルに対応することだけが上手くなっている印象もある。そういう人の中には、今の状況を息苦しく感じて、「本当だったらもっと面白いことを言えるのに……」と不満を抱えている人が少なくないはずです。
一方で、Z世代くらいになると、“人の外見について言わないのは当たり前でしょ?”という感覚を普通に持っていたりする。そちら側からすると、むしろ昔の人の感覚の方が逆に理解できないわけですよね。実際に今作にも、20〜30代の男性たちから、「自分の周りには、こんなやばいジェンダー観を持った人いない」「男をひとまとめに悪者扱いして、イメージを下げないでほしい」といったフィードバックもありました。
——ジェンダーを学んで育った世代ですね。
清田さん:性差別的なことは言わない、それが当然という意識が広がっていることは本当に素晴らしいなって思います。世代間の差異に関してはずっと課題意識があるので、いろんな世代の男性に話を聞きながら学びを深めていきたいところです。
一方で、我々男性には男性優位な社会構造から恩恵を受けている部分が少なからずあり、世代に関係なく、「男性」という括りで考えてみないことには見えてこない問題もあると思います。
例えば、社会に出ると産休・育休の制度が充実してきているとはいえ、家事育児の負担が男性より女性に偏ってしまっている現実がまだまだありますよね。賃金格差もあるし、妊娠や出産によってキャリアの中断を経験するのはほとんどが女性です。このように、「気づかないで済む」とか「考えなくて済む」といった形で享受しているのが男性特権というものではないかと思います。
学びや心がけによって個人が変化していくことは大事だけど、同時に社会のシステムや構造を変えていくことも考えねばならないわけで、まだまだ課題は山積みのはず。そのためには、より広い層に言葉を届け、社会全体の関心度を引き上げていくことが大事だと考えていて、この本が、一つのきっかけになったらいいなと考えています。
『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』
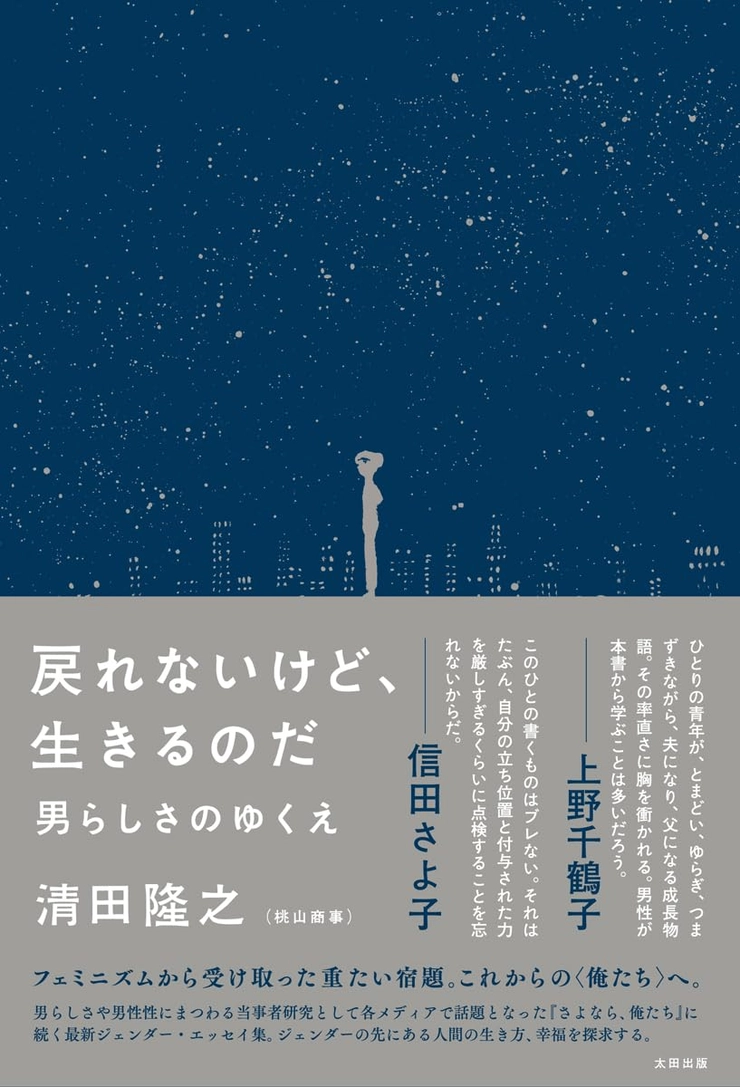
¥2090/太田出版
イラスト/NACCHIN 構成・取材・文/中西 彩乃