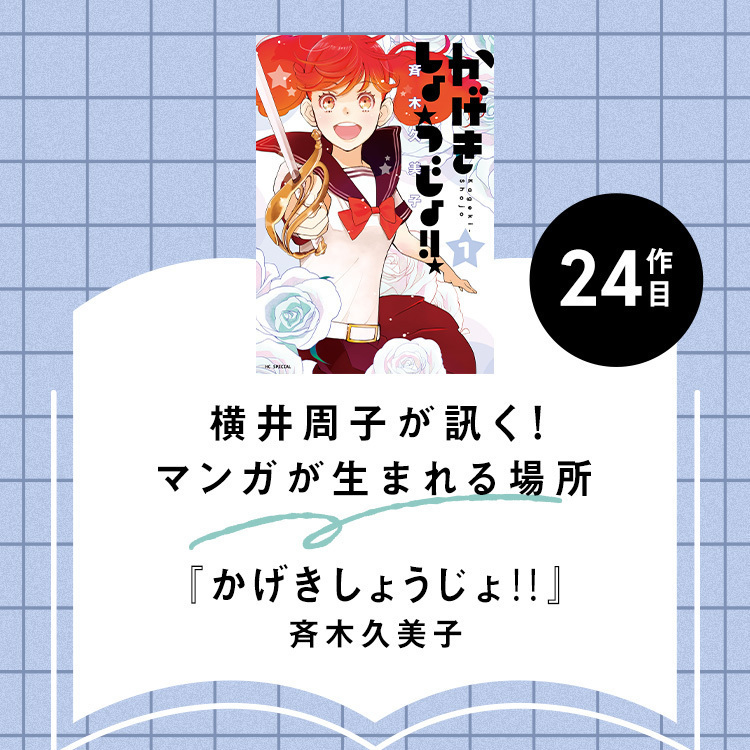文筆家として恋愛やジェンダーに関する書籍・コラムを多数執筆している『桃山商事』代表の清田隆之さんによるBOOK連載。毎回、yoi読者の悩みに合わせた“セラピー本”を紹介していただきます。忙しい日々の中、私たちには頭を真っ白にして“虚無”る時間も必要。でも、一度虚無った後には、ちょっと読書を楽しんでみませんか? 今抱えている、モヤモヤやイライラも、ちょっと軽くなるかもしれません! 最終回は産休・育休から復帰した同僚に寄り添える本についてご紹介します。
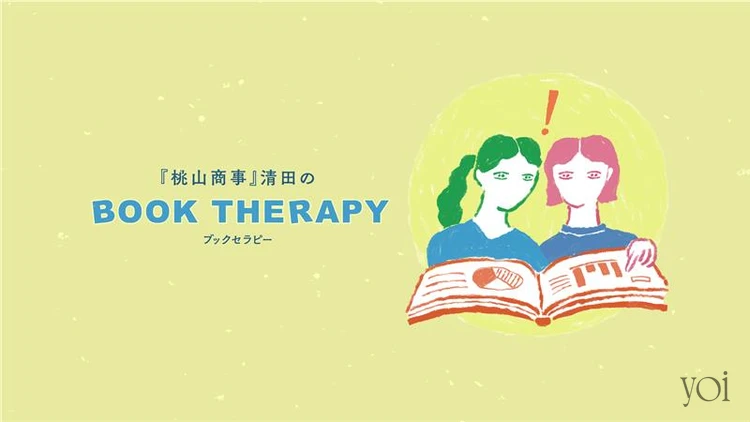

文筆家
1980年生まれ、早稲田大学第一文学部卒。文筆家、『桃山商事』代表。ジェンダーの問題を中心に、恋愛、結婚、子育て、カルチャー、悩み相談などさまざまなテーマで書籍やコラムを執筆。著書に、『おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門―暮らしとメディアのモヤモヤ「言語化」通信』(朝日出版社)など。最新刊『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』(太田出版)も好評発売中。桃山商事としての著書に、『どうして男は恋人より男友達を優先しがちなのか』(イースト・プレス)などがある。Podcast番組『桃山商事』もSpotifyなどで配信中。
『桃山商事・清田のBOOKセラピー』担当エディター&ライターは……
エディターH:1994年生まれ。ジャンルを問わず読書はするものの、積読をしすぎていることに悩み中。好きな書店は神保町・書泉グランデ、池袋・ジュンク堂書店、西荻窪・今野書店。
ライターF:1979年生まれ。小説&マンガ好きだが、育児で読書の時間が激減。子連れで図書館に行くのがささやかな楽しみ。一人時間には、テレビドラマを見てパワーチャージ。
産休・育休から復帰した同僚に寄り添える&自分も一緒に読んで頑張れるような本は?

今月の“虚無っちゃった”読者のお悩み…
産休・育休を取り、復帰した同僚がいます。時代が変わって、休暇が取りやすく、時短勤務もしやすくなってはいるものの、仕事に全振りできない生活にモヤモヤしている同僚を見ていて、自分に何かできることはないものかと思う日々です。また、その同僚は最短ルートで復帰しているのですが、「子どもより仕事を優先させるなんてかわいそう〜」というような嫌味や、「早くフルで働けるようになるといいね!(本音:早くもっと働いてほしいな)」というような応援に見せかけたプレッシャーも、上司からうっすらかけられており……。ルール通り産休・育休を取っているのに、心地いい環境とは言えないよな〜と、自分も虚無ってしまいます。こんな同僚に寄り添える&同僚と一緒に読んで頑張れるような本はありますか?
ライターF:今回は、産休・育休を取り、復帰した同僚を持つ相談者さんからお便りをいただきました。「同僚に寄り添い、自分も一緒に読んで頑張れるような本はありますか?」とのこと……優しいですよね。
清田さん:なるほど……自分のタイムラインには、最近バキバキの自己責任論をまき散らすインフルエンサーのショート動画がめちゃくちゃ流れてくるようになり、どんどんその人について詳しくなっていっている自分に虚無っております。
それはさておき、大前提として、産休・育休というのは正当な権利ですよね。出産した女性が、自身の回復や子どもの世話のために一定期間仕事を休むのは当然のことだし、大きな枠組みで考えれば、そういう制度を整えないと子どもを持ちたいと望む人がどんどん少なくなっていって、少子化がますます進んでしまう。
制度を利用するのは当然の権利なのに、それを使ってバランスを取りながら仕事と育児を両立させている人に、変な圧力がかかるのは、基本的にはおかしなことだと思います。
エディターH:本当にその通りですね……!
清田さん:もしかしたら、嫌味やプレッシャーをかけてくる上司も、「産休・育休の取得で部署の人数が減っても、変わらず成果を出すように」と求められているのかもしれない。現場の業務量が変わらなければ、上司を含む周りの人の負担が増えることになり、そのモヤモヤは産休・育休を取った人に向けられてしまう……。
現場の人同士が対立させられてしまうのは理不尽なことだけれど、仕組みができていなければ不満は生じるに決まっていますよね。そして、その不満は、産休・育休を取りづらくする方向に働いてしまう。壮大な話になりますが、その結果が、出生数70万人割れという数字にも表れているような気がします。
ライターF:一体どうすればいいんでしょう……。
清田さん:まずは、こういった状況を引き起こしているのは、制度の不備や社会の構造だと認識することが大事なのではないでしょうか。
もちろん、相談者さんのように「なんとか身近な同僚に寄り添いたい」と考えるのは素晴らしいことだし、相手にとってもすごく心強いはず。ただ一方で、これは個人で解決できる問題ではないので、仮に現状が変わらなかったとしても、無力感に苛まれないでほしいな、と思うんです。それに、個人の努力でなんとかなってしまうと、制度は改善されないま温存されていくという理不尽な構造もありますしね。
正直、「個人的にできることをどんどんしてあげましょう」というメッセージも送りづらいし、かと言って「何もしないほうがいい」とも思えない。そこで今回は、問題を解決できるかどうかはわからないけれど、ひとまず同僚や自分が置かれている状況をより具体的に知ることができれば、という視点で2冊を選んでみました。
セラピー本① 女性が置かれている労働環境やその問題点を解き明かす本
清田さん:最初におすすめするのは、『働きたいのに働けない私たち』 です。
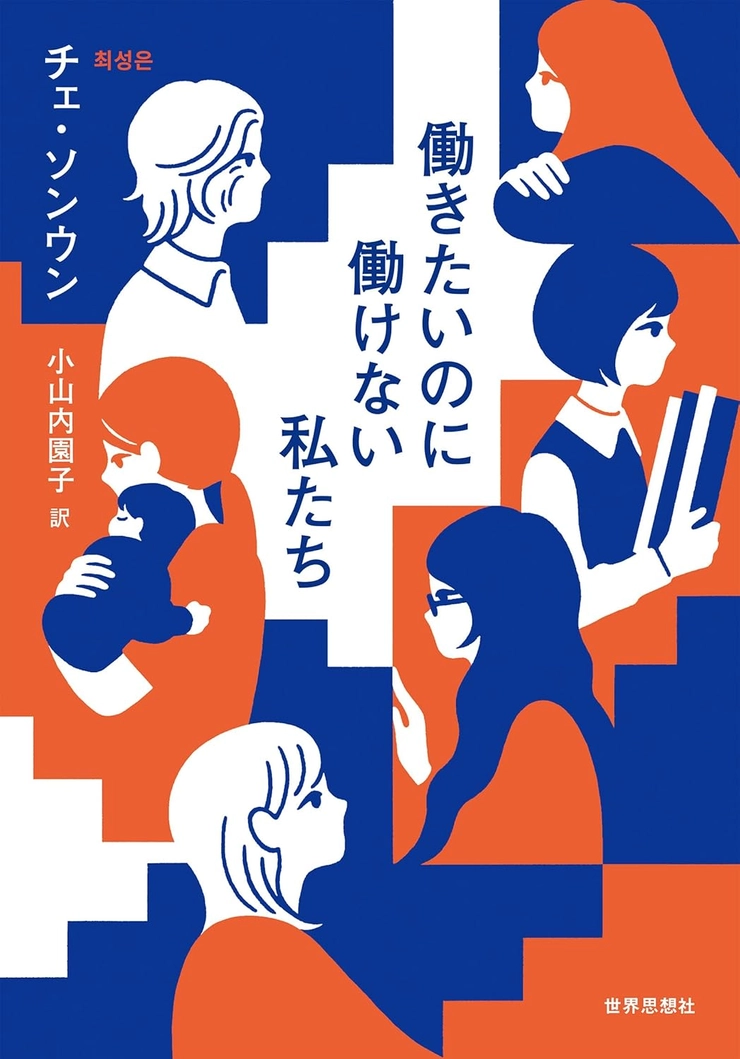
チェ・ソンウン・著
『働きたいのに働けない私たち』
(世界思想社)
清田さん:これは、韓国で女性、子ども、少子化政策の課題を研究している著者が、女性が置かれている労働環境やその問題点を解き明かす本。
エディターH:清田さんも帯の言葉を書かれているんですね!
清田さん:そうなんです。この本のすごさは、“働きたいのに働けない”という悩みが生じてしまう社会構造の問題や、その多くがジェンダー格差として女性にのしかかっている不均衡な状況を、データとエビデンスを揃えて可視化していくところ。
これを読むと、今ある制度を俯瞰することができ、国家的な意図や経済上の狙いにまで目を向けられるようになると思うんです。
ライターF:著者自身にも、苦労して出産、育児、学業、仕事を並行させたり、そのことで周りから「欲深い」「図太い」と言われたり、といった経験があったんですね……。
清田さん:眠っている夫と子どもを起こさないようにホテルのトイレで作業をした、といった実体験も書かれていましたよね。そこまで努力しても、周りからは心ない言葉をかけられ、男性たちには悠々とステップアップしていく様を見せつけられる。当事者としてかみしめてきた、怒りや悔しさが原動力となっているのも伝わってきて。韓国の話ではあるけれど、遠いところで起きたことではなく自分事のように感じられるはず。
相談者さんのような立場の方が読むと、同僚が嫌味や圧力をかけられてしまうこと、それによって自分がモヤモヤさせられることの原因が、会社や社会にあることがよくわかると思います。
ライターF:育休・産休から復帰した方も、今は「上司にこんなことを言われた」「同僚に迷惑をかけてしまった」と落ち込んでいるかもしれないけれど、もう少し状況を客観的にとらえられるようになるかもしれませんね。
清田さん:そう、近視眼的になっていると、つい隣にいる誰かに憎悪を向けてしまいがち。でもそれはあまりよくないことなので……。いったん高いところから状況を見下ろすことで、「この構造、おかしくない⁉」と気づけたら、気がラクになるんじゃないかな、と。
社会構造に苦しめられているという点では、みんなで連帯することも可能なはずなので、本当は嫌味やプレッシャーにも「そうですよね!」「私もフルで働ける社会になってほしいです!」なんて返したい(笑)。現実には難しくても、それくらいの気持ちで構えられるといいですよね。
セラピー本② 職場の問題をケーススタディ的に考えていく1冊
清田さん:続いてご紹介するのはこちら、『職場で傷つく』です。
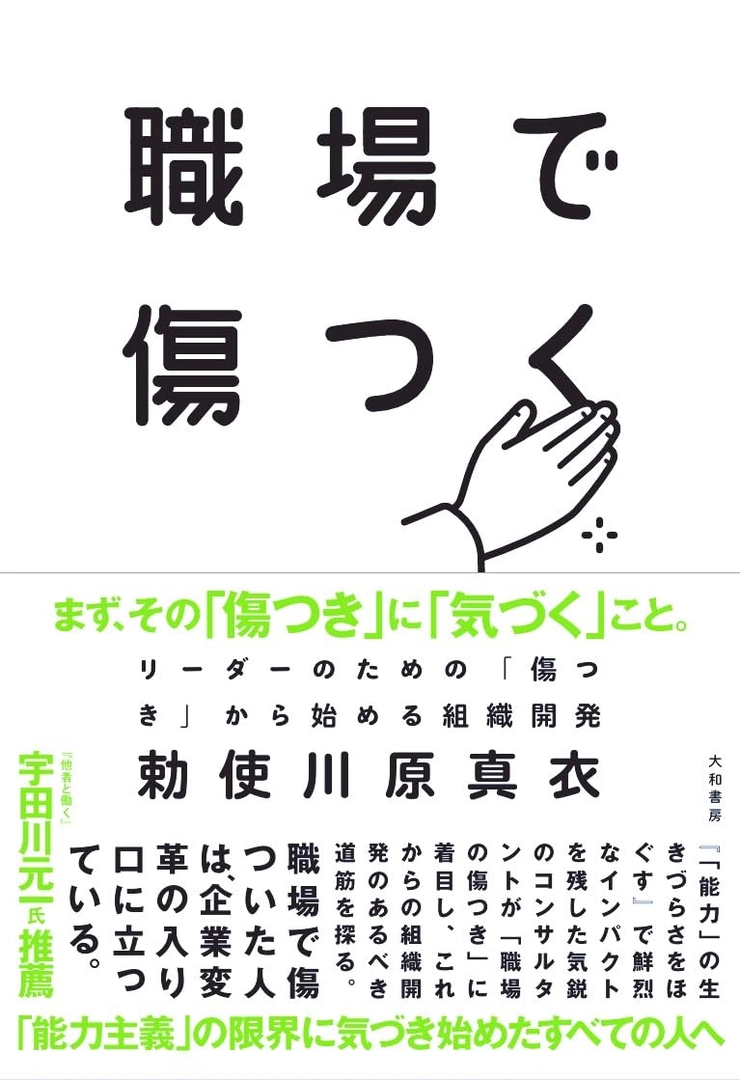
勅使川原真衣・著
『職場で傷つく』
(大和書房)
清田さん:著者は、組織開発専門家で、『「能力」の生きづらさをほぐす』という本でも注目を集めた、勅使川原真衣さん。現代社会における能力主義の問題を研究している方なんです。
能力主義というのは、スキルや資格、コミュニケーション能力や情報処理能力、体力や精神力など……あらゆる個人の能力をもとに、資源の分配を行い、社会を統治するための原理原則だそう。
自分自身も、「あれもこれもできなきゃいけないんじゃないか」「まだまだ自分には身につけなければいけないことがあるんじゃないか」という呪いにかかっているので、能力主義の問題にはとても興味があるんです。
エディターH:確かに、この社会で生活していると、そんな風に考えてしまいますよね。
清田さん:「評価や収入を上げたいなら頑張れ」とみんなのモチベーションを上げること自体は悪いことではないけれど、行き過ぎると、社会で起きている問題はすべて個人の努力が足りないからだ、という自己責任論に結びついてしまう。さらには、いろいろな能力商品が開発されていくことにもつながりますよね。
この本は、職場のいろいろな問題について、「それは個人の能力のせいではなく、構造や全体の組み合わせの問題ではないですか?」という視点で、ケーススタディ的に考えていくところが素晴らしい!
ライターF:“職場で傷つく”というタイトルや、“まず、その「傷つき」に「気づく」こと。”というキャッチコピーにもハッとさせられました。
清田さん:産休・育休の問題について直接触れられてはいないけれど、職場にはいろいろな傷つきの要素があって、そこで働く人はみんな傷ついている可能性がある。そう考えれば、横の連帯感が生まれやすくなると思うんですよね。
このお悩みの原因が、実は個人の問題ではなく、社会の問題にあると気づかせてくれる、という点は、1冊目も2冊目も共通なんです。前者が空の上から見下ろしているとするなら、こちらは職場の天井のカメラから定点観測している、という感じ。より内容が身近に感じられるかもしれません。
この本を読むと、決して無理をしてもっと働けばいいわけではなく、かけられる時間や体力が変わっていく中で、どうやって課題を乗り越えていくかが大事、ということが分かるように。そこから発展して、「そもそも職場とは? 仕事とは?」ということまで考えさせてもらえるはずなので、ぜひ読んでみてほしいな、と思います。
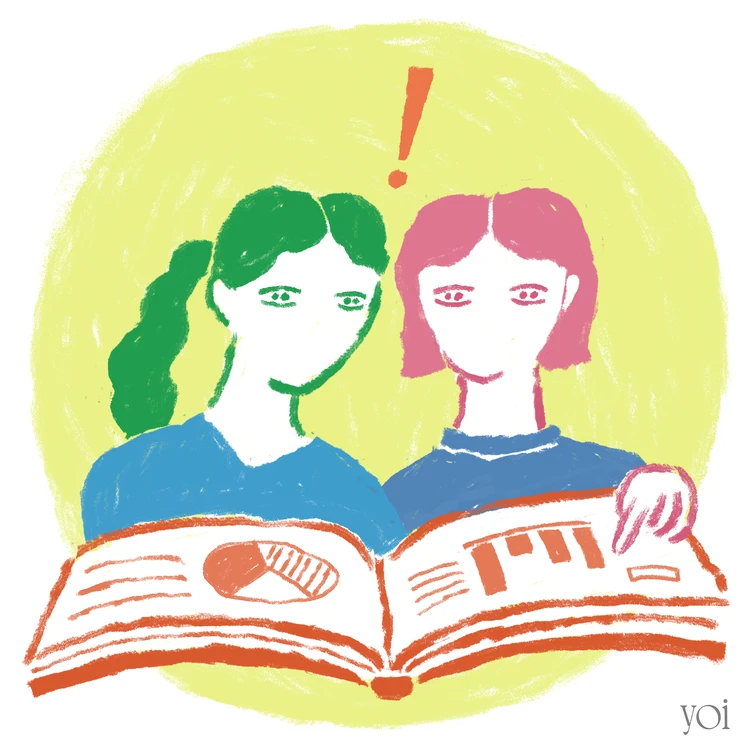
今回は、お悩みの原因が、個人の問題ではなく、社会の問題にあると気づかせてくれる2冊をおすすめいただきました。職場での圧力がつらい時、そんな同僚が近くにいる時に読むと、新しい視点を持てて心が軽くなりそうです!
〈清田さんから一言〉
この連載が始まったのが2023年10月なので、約2年間、読者のみなさんからさまざまなお悩みをうかがい、自分なりのおすすめ本を紹介させていただきました。自分自身もショート動画の沼にハマっては虚無るということを相変わらず繰り返している日々で、お悩みは尽きませんが、心身をスローダウンさせてくれる本は、せわしない現代においてやっぱり必要なものだと思います。またどこかでお会いできたらうれしいです。どうもありがとうございました!
イラスト/藤原琴美 構成・取材・文/藤本幸授美