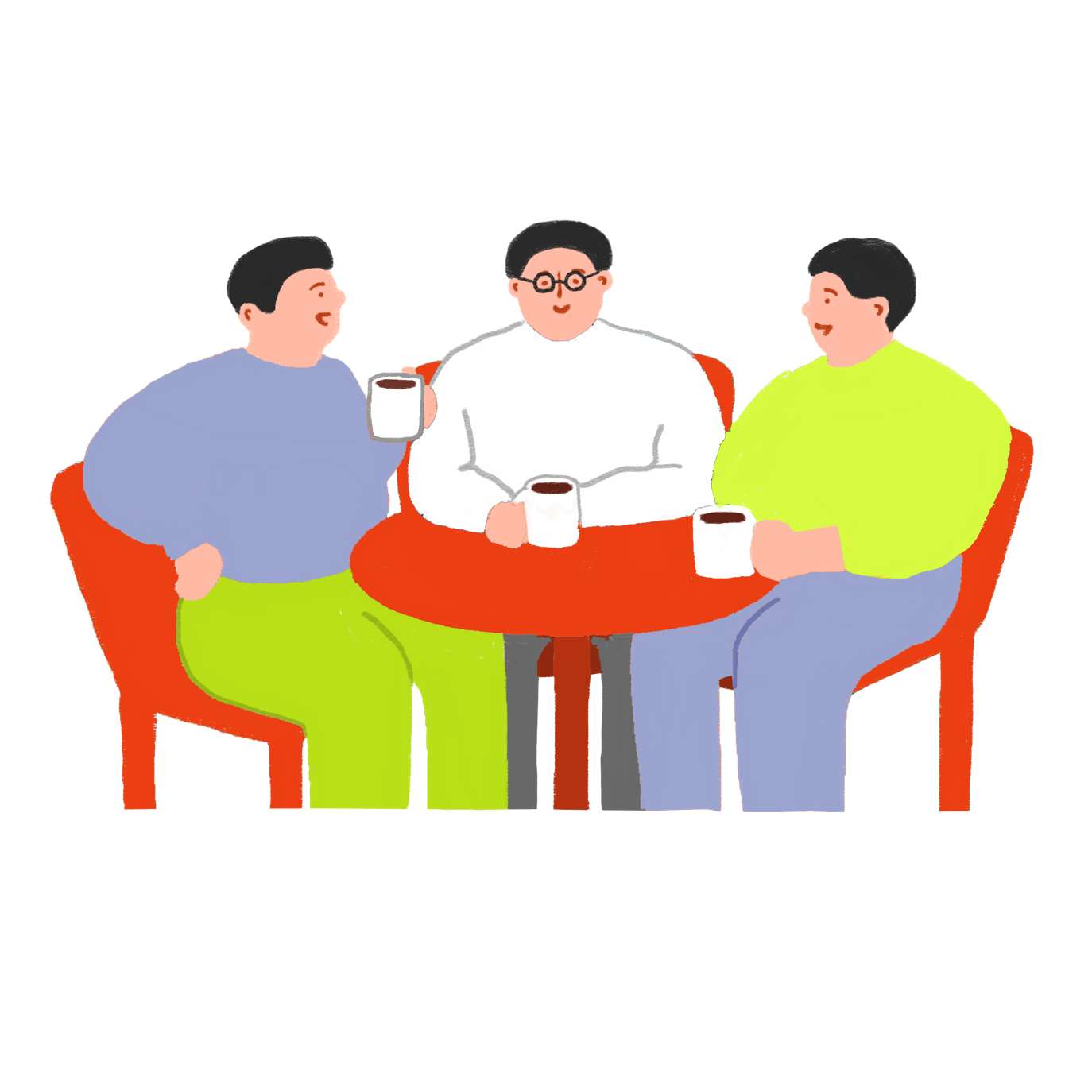『平場の月』朝倉かすみ ¥748/光文社文庫
“ちょうどよくしあわせ”なあり方を願い、求めた二人
ある日突然、誰かの支えなくしては日常生活さえままならない体になってしまったとしたら、私は誰に助けを求めるだろう。あるいはその逆。支える側に立ったとき、無条件に自分を差し出すことができるだろうか。躊躇いや不安なく、フラストレーションも抱かずに。
こういうときに強い力を発揮するのはきまって、家族だとか夫婦だとかきょうだいだとかの関係性だが、「身内」の効力が強固であるがゆえに生じる不都合もまた、あるのではないだろうか。朝倉かすみさんの『平場の月』は、相手を思うがゆえに「身内」にはならなかった男女の恋愛を綴った作品。
50歳。共に離婚歴があり、今は地元で一人暮らしをしている「青砥健将」と「須藤葉子」。中学の同級生だった二人は、病院の売店で再会したことをきっかけに、「互助会」と称して酒を飲む仲になる。かつて青砥が須藤に片思いをしていた過去はあるものの、すぐに恋心が再燃、とはならないところが、年齢分の経験を重ねた男女のリアルだ。
愛によって結ばれたとしても、結局人は一人で、自分の人生の責任は自分で取っていかなければならないことを二人はすでに知っていた。言葉や制度で関係性を定めてしまうことで生じる責任の重さや、煩わしさがあることも(げんに二人は親の介護問題や、いびつな家族関係を抱えていた)。
だからこそ、須藤に大腸がんが発覚したのち、支え合うのではなく共に立つように恋人同士になっていった彼らに理想を見たし、死を前に須藤が取った行動には、この選択をどう捉えるかと試されているような気持ちになった。
抗がん剤治療、ストーマケア、経済的支援…。誰かの助けが必要な状況であることを理解しつつも、誰にどんな助けを求めるかは最後まで自分で決めたかった須藤。そんな彼女が、青砥との会話の中で漏らした言葉が印象的だ。
〈『身内』ってそんながんばんなきゃならないものかね。〉
彼女を病ごと引き受けたいと願い、のちに求婚する彼への牽制のようにも聞こえるが、これほどまでに、青砥の人生を敬いたいという姿勢の表れもない。最愛の人を頑張らせなければ生きられない現実は、須藤にとって生きる意欲を削がれてしまうほどのものだったのだろう。
「なるべくずーっと、なんとかやってるって思わせたいじゃん」
そう言って青砥から離れ、一人人生をまっとうした須藤に、言葉や制度に甘えない愛のかたちを、自分を生き抜く強さを見た。

1980年生まれ。中央大学大学院にて太宰治を研究。10代から雑誌の読者モデルとして活躍、2005年よりタレント活動開始。文筆業のほか、ブックディレクション、イベントプランナーとして数々のプロジェクトを手がける。2021年8月より「COTOGOTOBOOKS(コトゴトブックス)」をスタート。
文/木村綾子 編集/国分美由紀