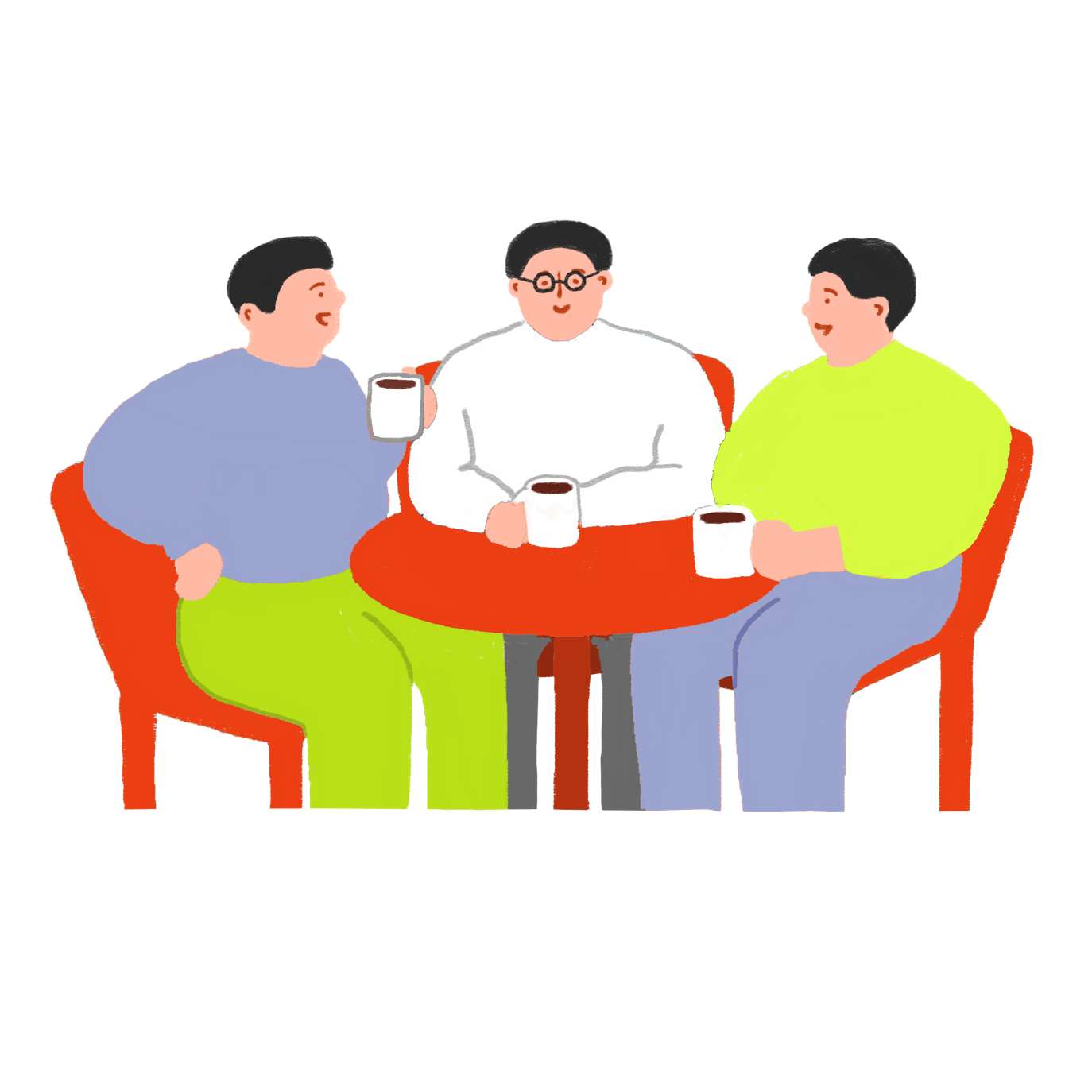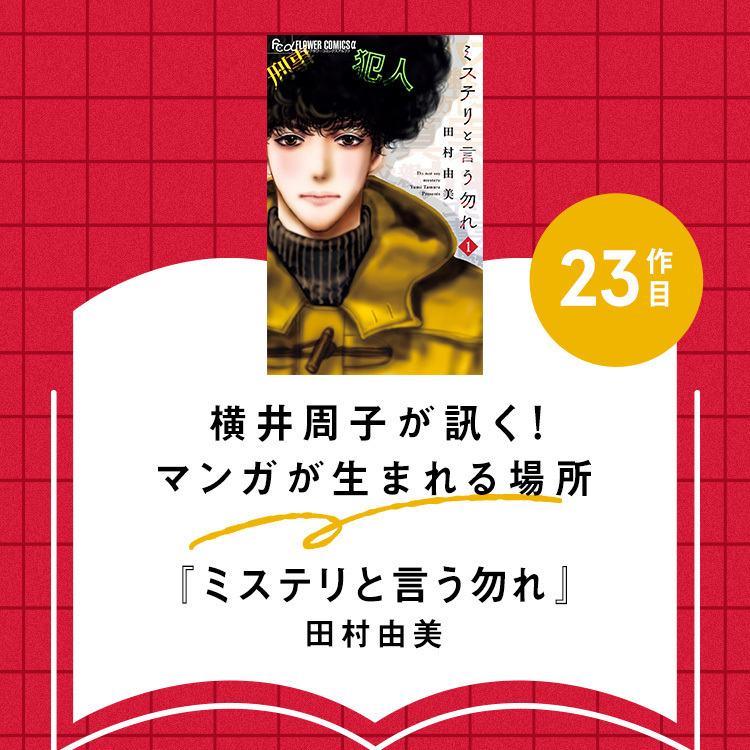『娘たちへの手紙』
マヤ・アンジェロウ 著・白浦 灯 訳 ¥1980/海と月社
マヤ・アンジェロウが遺した『娘たちへの手紙』から受け取る28通の知恵と励まし
自分はいつから大人になったのだろうか。車の運転や、お酒が飲めるようになったとき、あるいは就職や結婚、出産といったライフステージが変化したときだろうか。それとも波風を立てないようにまわりに合わせて世慣れた態度でそつなく事を進められるようになった頃だろうか。
本書の著者マヤ・アンジェロウは、そうしたことはすべて「歳をとった」だけのことで「ほとんどの人は大人にならない」のだと語る。そして「本当の自分はたいてい子どものままで、いまでもマグノリアの花のように無垢ではにかみ屋」なのだと言う。取り繕った「大人」であることをやめて、小さな子どもに戻ったような心持ちで気ままにページを開いてほしいのが、この本だ。
マヤ・アンジェロウはアメリカの作家。詩人で人権活動家でもある。本書は彼女が家族や友人、知人たちと交わした会話やエピソードと、そこで学んだいくつかの知恵を私たち、つまり「娘たち」に宛てた28通の手紙である。一通ごとに温かい彼女の人柄があふれ出ていて、どこにも気取ったところがない。
その中には、10代で思いがけず妊娠したのち無事に我が子を迎えたときのこと、恋人であるマークに壮絶な暴力を受けて監禁されるも、必死の祈りが届いたのか奇跡的に母が助けに来てくれたことなど、壮絶な経験も淡々と語られる。
また、モロッコの旅先で出会った老人たちから振る舞われたコーヒーに、あるものが入っていたときの驚きのエピソードや、客として招かれた際に勘違いで失礼な態度をとってしまったことなど、失敗談も披露される。どう感じ、いかに受け止めるのかは、読者一人一人の心のうちにゆだねられていて、読み返すたびに違った言葉が響いてくる不思議な本だ。
11通目はこんな話だ。幼い息子をサンフランシスコの母と叔母に預け、ミュージカルのダンサーとしてヨーロッパ巡業をしていたとき、働きづめで精神的に追いつめられてしまったアンジェロウ。長旅を経てようやく会いに戻ってきたものの、息子とともに窓から飛び降りたくなる衝動にかられる。黒人を取り巻く社会状況への不安や、育児を人に任せきりでいる罪悪感から、おかしくなってしまいそうになったのだ。精神科クリニックに飛び込んだがうまく伝えられず、本音を話せるボイストレーニングの先生のもとに駆けこんだ。彼は、その様子を見てすぐにひと眠りをすることを促し、目覚めてから「おかしくなりそうだ」と伝える彼女に、自分の恵まれている点を書き出すよう促した。自己を見つめ、恵まれていることに感謝しながら、それをひとつずつ書いていくうちに彼女は落ち着きを取り戻していった。
「書く」ことで自己を治癒し、当たり前にあることの有り難さに気づきを得た彼女は、嵐の日も晴れの日もすばらしい夜も寂しい夜も、感謝の気持ちを持ち続けたいと語る。
〈悲観的になろうとしても、明日はかならずやってくるのですから〉
嵐の中にいる人も、そうでない人にも、本書の中には自分と世界をつなぎとめる一文がきっと見つかるはずだ。お守りのようなこの本を開く人はみんな、誰でも小さな、無垢な子どもなのだから。
代官山 蔦屋書店 人文コンシェルジュ
代官山 蔦屋書店で哲学思想、心理、社会など人文書の選書展開、代官山 人文カフェやトークイベント企画などを行う。毎週水曜20:00にポッドキャスト「代官山ブックトラック」を配信中。
文/宮台由美子 編集/国分美由紀