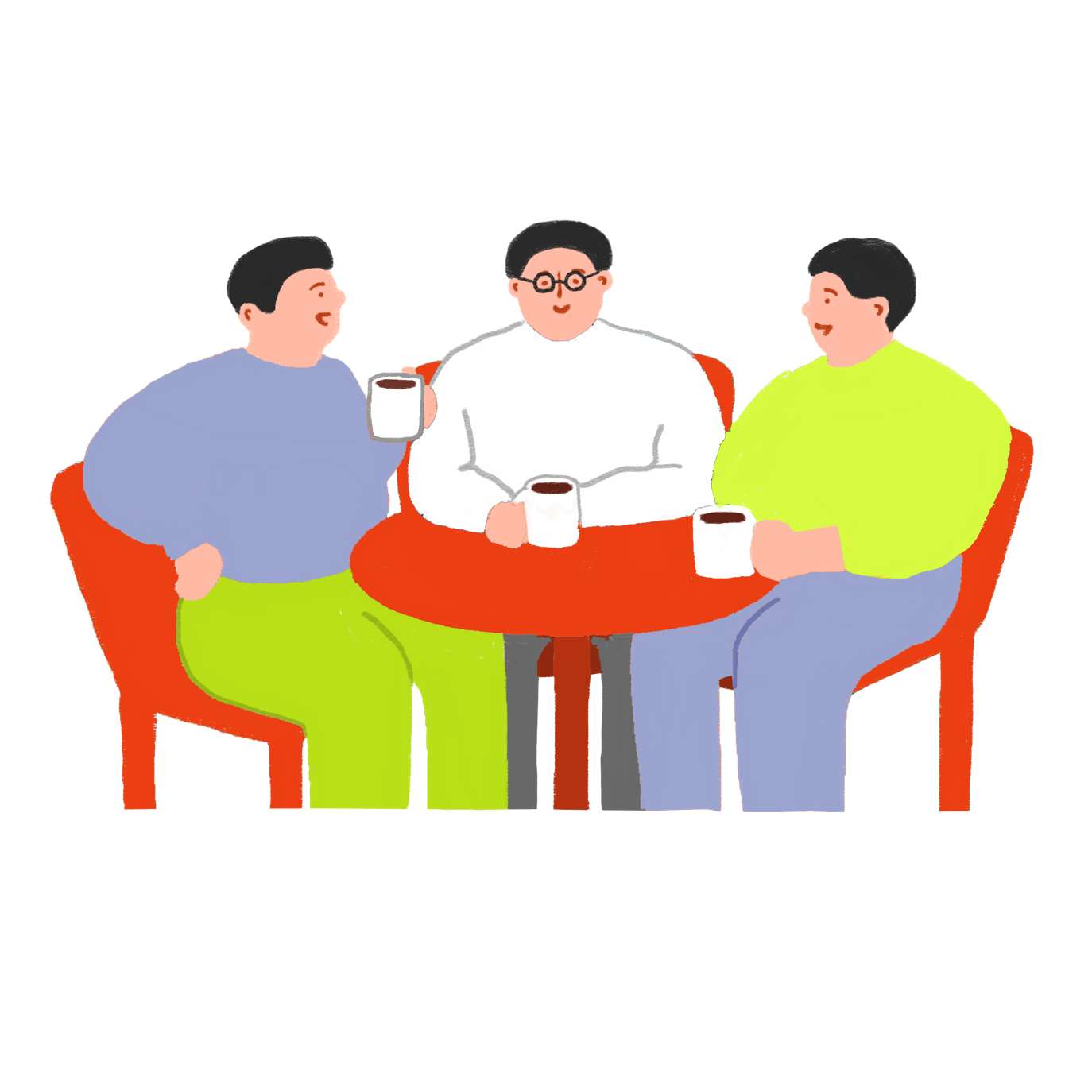「BAILA」「クーリエ・ジャポン」ほか数々のメディアで執筆するライターの今祥枝さん。yoiの連載「映画というグレー」では、正解や不正解では語れない、多様な考えが込められた映画を読み解きます。第3回は、ジェンダー・アイデンティティに悩む8歳の子どもと、その家族の関係を描いたこちら。
ジェンダー・アイデンティティに悩む8歳の子どもの心の変遷

日々の生活の中で違和感を覚えながらも、それが何なのかを言葉にできず、心を閉ざしてしまうアイトール。演じるソフィア・オテロは、第73回ベルリン国際映画祭コンペティション部門で史上最年少の主演俳優賞を受賞した。同映画祭は2020 年に男優賞・女優賞の廃止を発表、翌年から性的区別のない主演俳優賞、助演俳優賞が新設された。
夏のバカンスで、母アネと3人の子どもたちは仕事がある父親をフランスに残し、スペイン・バスク州にやって来る。美しく豊かな自然に囲まれたこの地で、アネの母親リタと叔母ルルデスが彼らを迎える。
子どもたちは洗礼を受けることになっているが、末っ子の8歳のアイトールは心を閉ざしている。自分の名前を呼ばれるのがいやで、可愛いものが好き。泳ぎに行きたくないし、同年代の男の子たちになじめない。アイトールはジェンダー・アイデンティティ(性自認)に悩んでおり、トランスジェンダーだと考えられるが、日々苦痛を感じる自分の違和感を言葉にできない。だから、どんどん内側に閉じこもってしまう。
そんなアイトールが、異国の地の美しく豊かな自然と触れ合い、家族との関係が変化していく中で、心がほぐれ、自分自身と向き合いジェンダー・アイデンティティを探求していく。その過程が、やわらかい光に満ちた美しい映像とともに繊細なタッチでつづられる。
監督・脚本は、スペイン出身のエスティバリス・ウレソラ・ソラグレン。非当事者として、自らの経験からジェンダー・アイデンティティというテーマが気になっていたという。本作の脚本には、組織を介して3歳から9歳までのトランスジェンダーの子どもを持つ家族 20 世帯と会い、共有した体験談が反映されている。
多くは語らないが、心の揺らぎや言葉にできないもどかしさを繊細に伝えて、観る者を引きつけてやまないアイトールを演じるのはソフィア・オテロ。第73回ベルリン国際映画祭コンペティション部門では、当時9歳で史上最年少の主演俳優賞を受賞した。

アイトールの母アネ(パトリシア・ロペス・アルナイス)は現代的な考え方を持っているが、うまくコミュニケーションを取ることができない。アネの父は著名な彫刻家で、アネは美術学校の教鞭をとるための審査用に自分の作品を生み出そうとしている。そんな彼女もまた、保守的な母親との間に溝があった。
家族それぞれの、ジェンダー・アイデンティティに対する考え方の違い

叔母ルルデスの存在と豊かな自然との触れ合いが、アイトールの心をほぐしていく。ルルデスを演じるのは、スペインのベテラン、アネ・ガバライン。監督・脚本は、スペイン出身のエスティバリス・ウレソラ・ソラグレン。
映画を通して、私たちはアイトールの視点で見た世界には、どんな困難があるのかを追体験する。日々の生活の中で、どんなことに心を痛め、どういったことから自分の居場所がないと感じ、自分に対して否定的な気持ちになってしまうのか。
一方、アイトールの母親アネと祖母リタ、叔母ルルデスら、世代の異なる人々の「出生時に割り当てられた性と性自認が異なる子ども」に対する考え方の違いも描かれる。子どもの自主性を尊重しようとする現代的な考えを持つアネ、保守的なリタ、最大の理解者となるルルデス、そして遅れてやってくる保守的な父親。それらの主張は、比較的わかりやすく類型化されたものと言っていいだろう。
リタは、アネに「アイトールを甘やかしすぎた結果、混乱させた」と批判する。"男の子らしく"髪の毛を短く切って、明確に自分が何者であるかを線引きしてあげることが、親の務めであると。一方、アネは子どもの自主性を尊重して、自由に育てたといい、真っ向から対立する。二人の口論からは、保守的な考えを持つ両親のもとに育ったからこそ、アネが今のような考えになったのだろうかと想像できる。
しかし、そのアネもまた、アイトールとうまくコミュニケーションが取れない。さらに遅れてやって来たアイトールの父親が、妻からアイトールのことを相談されると、リタと同じように「自覚するには早すぎる。甘やかしすぎだ」という。
そんな中、実に自然にアイトールとの距離を縮めていくのが、山麓で養蜂場を営むルルデスだ。このルルデスとの出会いが、いかにアイトールにとって大きく何ものにも代え難いものであるか。それはルルデスが、進歩的な考え方を持ちながらも社会通念やその枠組みの中でものを考えてしまい、一歩踏み込むことができないアネに向かって、「子どもが自分を恥じるのは間違っている」と言い放つシーンからもよくわかる。みんながアイトールを愛していることは確かだろうが、最もアイトールのことを理解しているのが両親であるとは限らないというのもまた、珍しいことではないのだと思う。
ジェンダー・アイデンティティをいつ自覚するのかについては、多くの異なるケースがある。当事者の年齢によって、それを受け止める家族にもまた、さまざまな意見や考えがあって当然だろう。しかし、両親の口論などを聞いてしまったアイトールが、劇中で「死んだら生まれ変わって、女の子になれるのかな?」とルルデスに問いかけるシーンには、思わずはっとした。何があっても、このような考えを子どもに抱かせることは、絶対に避けなければならないはずだから。
多様な個でありながら、大きな集団=社会の一員であること

「女の子になりたい」という思いを胸にドレスを着るアイトールと、その思いに寄り添おうとする母アネ。しかし、遅れてやって来た保守的な父親の言葉が、アイトールの心を傷つけてしまい……。
もうひとつ、周囲の理解と同時に必要なことはアイトールが自分を解放することである。その鍵となる要素のひとつが、“ミツバチ”だ。
本作の原題は、『20.000 especies de abejas(2万種のハチ)』。巣の中にいるハチはそれぞれに明確な役割を担う個であるが、全体としてはひとつの巣として機能している。アイトールはミツバチの世話を手伝いながら、ひとつの集団に見えたミツバチの個を認識していく。
本作は、社会の最小単位である家族の重要性を伝える一方で、アイトールは一緒に暮らす家族だけでなく、その外の社会とも関わりながら生きていく必要があることにも言及がある。養蜂は、そうした人間が生きる社会のメタファーといえる。
アイトールが異国の地に来ること、そして叔母ルルデスと会うことも大事な社会経験だ。孫を愛しているが、多様な性のあり方に関しては批判的な祖母リタとの関わりの中にも、アイトールは重要な啓示を得る。また、友達がいなかったアイトールは、この地で女の子と仲良くなる。日々生きているだけで傷つくことはたくさんあるが、そこから新しい発見をし、自分自身を見つめ、自らを信じると決意するアイトールの姿は、頼もしくもあり、こちらが励まされるものもある。そんなアイトールの個性を包み込むような、この土地の人々の大らかさもスクリーンからよく伝わってくる。
多様な個でありながら、大きな集団=社会の一員であるとは、どういうことなのか。翻って、多様な個にとって生きやすい社会とは、どうあるべきなのか。言うまでもなく、本作で問われているのは当事者とその家族だけの問題ではないのである。

地元の人々と自然が、アイトールとその家族に大きな変化をもたらす。舞台となるスペイン・バスク地方は、古い歴史があり、美食とアートの街として知られる。また、ミツバチは昔から神聖な生き物として尊重されており、バスク文化の一部だという。