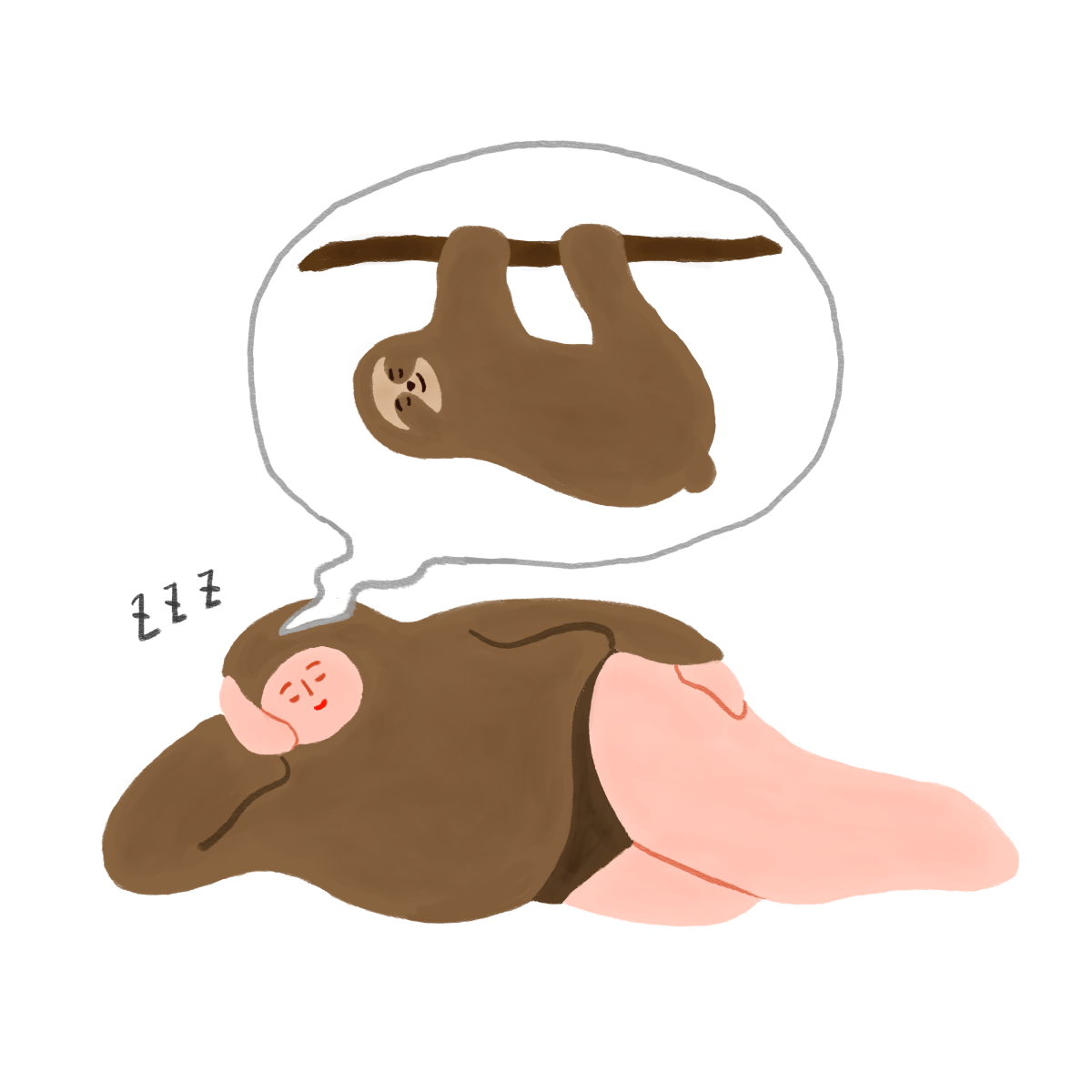日々、当たり前のように行なっている「睡眠」。実は、私たちが健康に過ごすうえで欠かせない重要な役割を担っています。その仕組みや役割はもちろん、睡眠不足のデメリットから“質のいい眠り”を手に入れるためのアドバイスまで、医学博士の西野精治先生に教えていただきました。今回は、「睡眠時間の長さ」と「寝具」について。

GoodStudio/Shutterstock.com
Q10.睡眠時間は長いほどいいですか? マットレスや枕の選び方も知りたい!
医学博士
スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学睡眠生体リズム研究所所長。日本睡眠学会専門医。ブレインスリープの創業者兼最高研究顧問。著書に『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版)、『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社)など。
A10. 睡眠は「量」ではなく、「質」のほうが重要です
睡眠不足によって睡眠負債が蓄積されると、がんや生活習慣病の発症リスクを高めたり、仕事や生活のパフォーマンスを低下させたりすることは、さまざまな研究によって明らかになっています。また、私たちの実験では、休日の寝だめでは日ごろの睡眠負債を完全に解消することも、睡眠預金もできないことがわかりました。
では、9時間や10時間など、平均より多く寝ている場合はどうなのでしょう? 実は、睡眠時間が長すぎても健康に支障をきたすという研究報告も出ています。
2002年にサンディエゴ大学のダニエル・F・クリプケ氏らが実施した100万人規模の調査によると、アメリカ人の平均的な睡眠時間は7.5時間でした。この調査の6年後、同じ100万人を追跡調査したところ、病気で亡くなった人がもっとも少なかったのは、平均値の7.5時間睡眠の人たちで、短時間睡眠(3〜4時間)の人だけでなく長時間睡眠(9〜10時間)の人も、平均値の人と比べて死亡率がおよそ1.3倍も高かったのです。
長く寝すぎると体内時計のリズムが乱れ、かえって疲れやすさや頭痛といった不調を引き起こしてしまいます。特に、一晩に9時間以上寝る人は、活動量の低下を招き、結果として肥満や脳卒中、心臓病などのリスクが高まることがわかっています。
ほかにも、中国の調査では、睡眠時間が9時間以上の人は、7〜8時間睡眠の人に比べて脳卒中のリスクが23%高く、昼寝の時間が90分以上の人は30分未満の人に比べて脳卒中のリスクが25%高いという結果が出ています。睡眠は長さよりも、質を高めていくことが大切です。
マットレスや枕は「通気性」で選ぶのがおすすめ
眠っても疲れがとれない場合は、寝具が体に合っていないのかもしれません。寝具でまず重要なのは敷布団です。就寝中の体を支え、寝床の温度や湿度を快適に保ってくれる存在です。最近は、低反発や高反発のマットレスが注目されていますが、それぞれに特徴があります。
新素材の高反発マットレスについて、ある寝具会社に依頼されて調べたところ、通気性のよい高反発マットレスでは、入眠直後から深部体温がスムーズに下がり、その状態が4時間持続したうえ、眠り始めに深いノンレム睡眠が多く出現していることもわかりました。
一方、低反発のウレタンマットレスでは深部体温の低下は1時間も続かず、睡眠中にいったん上がっていました。これは、体とマットが密着して鬱熱(体温調節がうまくできず体の中に熱がこもってしまう状態)が起こり、熱が逃げにくいためと考えられます。
この結果から、体に密着しすぎず通気性のいい高反発マットレスのほうが、スムーズな熱放散により深部体温が下がりやすいので、質のよい睡眠をもたらすと立証されました。
通気性の重要さは敷布団だけでなく、ほかの寝具にもあてはまります。例えば、脳の温度は脳が活動的なときに上昇していますが、深部体温と同じく睡眠中に下がるので、快適な入眠を促すには「頭寒足熱」の言葉通り通気性のいい枕で効率よく冷やしましょう。むしろ脳が冷えることで、よい睡眠がおとずれるといっても過言ではありません。
構成・取材・文/国分美由紀
出典/『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社)