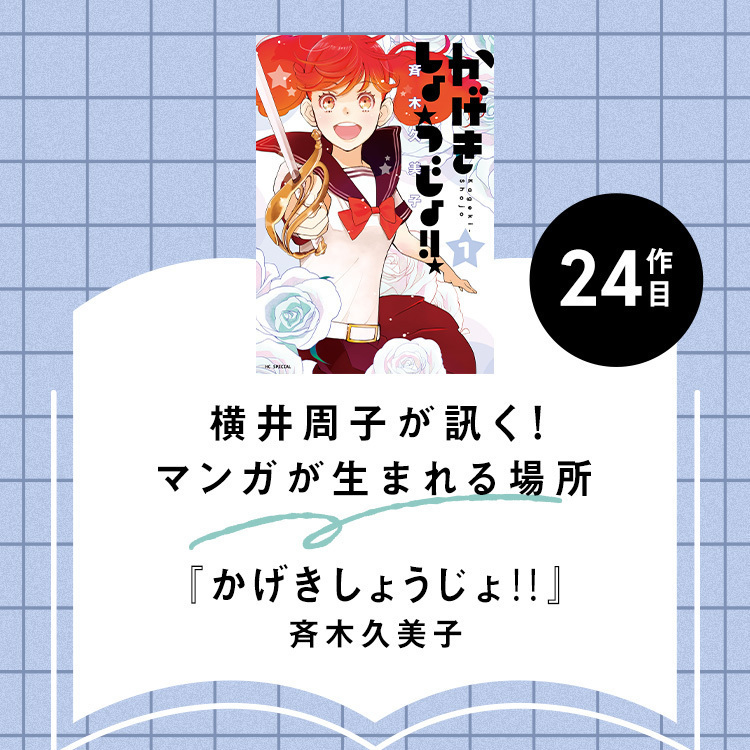増税に物価高、円安…さまざまな事情が重なり、お金の悩みを抱えている人が増えています。内閣府の調査では、20〜40代の働き盛りの世代の約半数が「現在の収入や資産に関する悩みがある」と回答しています。人に相談しづらく、抱え込んでしまいがちなお金の悩みは、メンタルヘルスとどう関係し、心理面にどのような影響を及ぼすのか? ファイナンシャル・セラピーを行う臨床心理士・公認心理師の岸原麻衣さんにお話を聞いてみました。
お話を聞いたのはこの方

ファイナンシャル・セラピスト/臨床心理士・公認心理士
金融機関勤務を経て、お茶の水女子大学大学院 博士前期課程を修了後、臨床心理士と公認心理師を取得。2017年からプロフェッショナル・サイコセラピー研究所〈IPP〉に在籍。ファイナシャル・セラピストとして女性のウェルビーイングを支えている。
ファイナンシャル・セラピストとは?
お金にまつわる心理的な苦痛をサポートする「ファイナンシャル・セラピー(金融療法)」を行うのが、ファイナンシャル・セラピストです。日本ではまだ専門資格がないものの、金融にまつわる専門的な知識、そして心理学的な観点から、お金にまつわる悩みを抱える人々をサポートしています。
お金の問題は、メンタルヘルスに関係する?

──内閣府の調査では、現役世代の約半数がお金の悩みを抱えているそうです。岸原さんにお金の悩みを相談したいという方は増えていますか?
岸原さん:増加傾向にあります。私は女性限定でご相談を受けているのですが、30〜50代の方が多い印象です。年代問わず将来への不安や、日々のお金のやりくりがうまくいかない、運用をどうしたらいいかわからない、やらなきゃいけないのはわかるけどできない、というご相談が多いですね。会社勤めの方からフリーランスの方まで幅広くいらっしゃいます。
私のクライアントの場合は、「自らが抱えるお金の悩みを、お金を支払うカウンセリングで解決したい」と考える方なので、収入的には、平均より高めの方が多いかもしれません。しかしながら、カウンセリングに通っていない方でも、お金で悩んでいる方は増えているのではないかなと感じます。
最近は「自分にお金のトラウマがあるから向き合いたい」という方も増えてきました。 例えば、「過去に親が借金で苦しんでいるのを見ていて、自分もいつか借金に苦しむのではないかという不安がある」、「過去の経験が自分のお金の価値観に関係しているのではないか」と悩まれているパターンもあります。
──現状のお金の問題に直結していないことでも、相談に来られる方がいるんですね。では岸原さんから見て、お金とメンタルヘルスは相関関係にあると思いますか?
岸原さん:お金が多いとメンタルの状況がよくなる、少ないと悪くなる、というわけではないですよね。お金を持っていても「自分は不幸せだ、満たされない」と感じられる人がいるのも事実です。もちろん、生活が苦しくなるほどお金がないことはメンタルヘルスに悪い影響を与えると思います。その一方、裕福な暮らしをしていても、いつもお金の不安を抱えていたり、健康的なお金の使い方ができない人もいます。
だからお金とメンタルヘルスには密接な関係がありますが、必ずしも相関関係ではないと考えています。
人間にとって“安定していない”ことはストレスになるもの

──実際にお金の悩みがメンタルに与える影響というのは、どういったものがあるのでしょうか。
岸原さん:不安や焦燥感を抱く、抑うつ状態になる、ストレスを感じるといった、心理的な負荷を感じられる方が多い印象です。私たち人間にとって、“安定していないこと”はとてもストレスになるんです。
例えばフリーランスで収入が不安定であると感じられる方は多いですが、そのせいで気分が落ち込む可能性はおおいにありますし、それはごく自然なこと。でも自らの仕事が収入に直結してくる分、自分を責めてしまいがちなんです。そうすると自分を責めることに労力を使ってしまい、ほかのことに目を向けられなくなったり、収入が安定している人と比べて「自分はダメだ」と落ち込む、という負のループにハマってしまうことも。
──最近では、SNSで「働いても働いても税金で取られて、給料が上がらない」と嘆き、無気力になってしまっている人をよく見かけます。そうした、努力と得られる収入が見合わない状況が続くと、メンタルヘルスに影響はあると思いますか?
岸原さん:もちろんあると思います。心理学的には「学習性無力感」と言うのですが、努力し続けてもそれに見合うリターンがないとき、人は希望を持てなくなり、努力することをあきらめるようになってしまいます。どのくらいの期間リターンがないことで無気力になってしまうかは人にもよりますが、現在のような状況が続くことは、多くの人のメンタルヘルスに影響を与えると思います。
また、リターンは必ずしもお金だけではなく、人からの感謝や世のためになっているという実感などもあると思います。ただ、そういったものに頼りすぎて“やりがい搾取”のような状況が生まれてしまうことは、懸念しなければなりませんよね。
あなたの幸せのバランスは? 自分の価値観を測るための「3種類の幸せ」
──では、“お金を使って贅沢をする”ことは、メンタルヘルスにとっていいことなのでしょうか?
岸原さん:自分にとっての適切な範囲の中で、お金を使って“好きなこと”をするのはいいことだと思います。ただ、お金を使って“贅沢”をするというのはまた別ではないでしょうか。また、昔は当たり前だったことが今は贅沢になっているようなこともあるように、“贅沢”という価値観は社会の移り変わりや周囲と比べている場合が多くあります。そのため、まずは自分にとっての幸せが何なのかを考えるのがおすすめです。
心理学的な観点から言うと、幸せというのは3つに分類できます。
おいしいものを食べる、旅行する、映画を観る、音楽を聴くなど、一時的な感情としての幸せ。
・ユーダイモニア(充足感)
自分の価値観や目標に沿って生きている、社会に貢献する、自己投資をする、クリエイティビティを発揮するなど、持続的な満足感を得られる幸せ。
・ウェルビーイング(自分がよくある状態)
上記2つをバランスよく含んでいて、長く続く幸せの状態。
この3つのうち、自分にとっての「幸せ」とは、何にどのくらいの割合で取り組み、お金を使うことなのかを考えてみてください。ヘドニアのためにたくさんのお金を使っても、ウェルビーイングの一部でしかありません。かといってユーダイモニアだけというのも違う。そのバランスを見直すことで、お金の悩みにも解決の糸口が見つかることがあります。
お金に支配されるのではなく、自分がお金を使う

──自分の幸せの見直し方も、その3点を軸にしたら考えやすそうです。では、お金とうまくつき合っていくには、どのような考え方をしたらいいのでしょうか?
岸原さん:軸にあるのは自分であり、お金はその外側にあるもの。お金を使うのは自分である、という観点を持ってみてください。お金はあくまでも自分のための道具であり、支配されたり脅かされたりするものではありません。
意外と、それに気づかず苦しんでいる人も多いんですよね。お金こそが自分の価値だと思い込んだり、自分が不幸せなのはお金がないからだと感じたり、お金がないと何もできないと思ったり…。
人それぞれのお金の価値観・お金に対するマインドセットをマネースクリプトと呼ぶのですが、自分のマネースクリプトを知っておくとお金とのつき合い方がうまくいきやすい傾向にあります。お金は道具だと思うのか、お金こそが自分の価値だと考えているのか、お金なんてただの紙切れだと感じるのか…自分にとってお金がどういう存在になっているのかを考えて、その偏りに気づくだけでも、大きなきっかけになるかもしれません。
ただ、自分のマネースクリプトを知るには一人では難しい場合もあり、カウンセリングの中で少しずつ見えてくることも多いもの。まずは自分で一度考えてみて、それでも問題が解決しないようなら、ファイナンシャル・セラピストに相談することもひとつの方法です。
イラスト/MIYO 取材・文/堀越美香子 企画・構成/木村美紀(yoi)