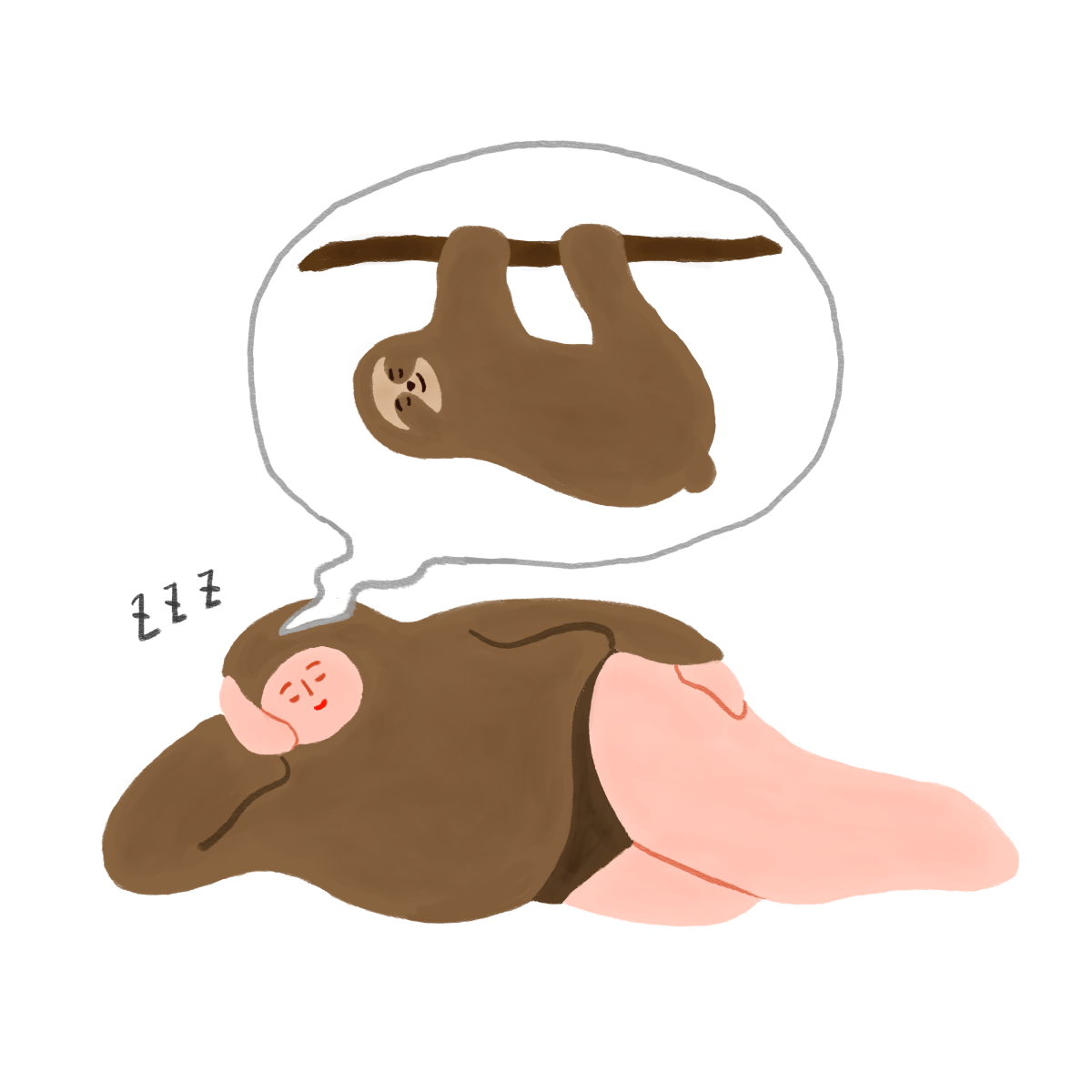「家事を分担しているのに、何故かわたしばかり…」そんなふうに感じたことはありませんか? 収入や労働時間を理由に、つい家事を抱え込み、手放すことに罪悪感を覚える人も多いはず。今回は、作家・生活史研究家の阿古真理さんに、家事の“フェアなシェア”について伺いました。
作家・生活史研究家
食や暮らし、ジェンダーをテーマに執筆し、家事や食文化の変遷について独自の視点で分析を行う。著書に『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』(幻冬舎)、『家事は大変って気づきましたか?』(亜紀書房)などがあり、幅広い世代の共感を集める。メディア出演や講演活動も積極的に行い、現代の家事負担やジェンダーの課題について発信を続けている。
“平等”にこだわるのではなく、“納得できる形”を見つける
——不満なく家事シェアをするために、必要な工夫はありますか?
阿古 家事を“フェアにシェア”するために、まず大切なのは「お互いの価値観をすり合わせる」ことですね。何「どこまでやれば十分か」など理想の家事レベルは、人それぞれ違うからです。
例えば、洗濯もの一つとっても、きれいにたたんで引き出しに収納したい人もいれば、クローゼットに吊るすだけで十分だと考える人もいます。たたみ方についても、縦にたたむ派・横にたたむ派など、細かいこだわりが意外と違っていたりするものです。
この感覚のズレを埋めずに家事をシェアすると、「わたしはこんなにやっているのに!」「それじゃやったことにならない!」と、不満がたまりやすくなってしまいます。
——確かに、価値観が違うままの家事シェアは負担軽減に感じないかもしれないですね。
阿古 そうなんです。だからこそ大切なのは、「どうすればお互いが納得できる形になるか」をきちんと話し合うことだと思います。例えば、家事のやり方の違いに気づいたときや、家事をめぐってケンカになってしまったとき。そのタイミングですり合わせの時間を持てるといいですね。
必要であれば「家事リスト」を作って、お互いがどんなことを負担に感じているのか、どこまでやれば十分だと思っているのかを“見える化”するのもひとつの方法です。それによって、「どこまでやるか」「何が負担なのか」という感覚のズレが明確になり、家事の優先順位や「毎日やる」「週1回で十分」「余裕があるときにやる」などのルールも決めやすくなります。

また、それぞれの得意・不得意を共有することもポイントです。「掃除は苦手だけど料理は好き」など、それぞれがやりやすい家事を担当すれば、無理なく続けやすくなります。
そして何より意識したいのは、“平等”にこだわるのではなく、“お互いが納得できる形”を見つけること。どちらかが我慢し続けるのではなく、お互いにとって心地よいバランスを探ることが大切です。そのためにも、暮らしの中で柔軟に、そして継続的に話し合っていくことが、家事シェアを続けるカギになるのではないでしょうか。
“誰がどれだけ稼いでいるか”と「家事の負担」を切り離す
——家事を手放すことに罪悪感がある場合は、どんな考え方を持つと気持ちがラクになりますか?
阿古 家事は女性がやらなきゃ…と感じる方は「自分のほうが収入が少ない」「労働時間が短い」といった理由で、“自分が家事を多めにやるべき”と感じてしまっていることもあると思うんですよね。
でも、家事と労働環境はイコールではありません。家事は「生活をスムーズに回すための協力」なので、本来は誰がどれだけ稼いでいるかとは、できる限り切り離して考えたいもの。意識的にその感覚から少し距離をとって、パートナーと「時間的・肉体的に無理のない範囲でシェアしよう」と心がけることが大切です。
また、「家事を手放す=サボる」ではありません。例えば、掃除や料理の代行会社を利用することで、心身の負担が軽くなり、その分ほかの時間を充実させることができます。「手放すことも、家族のため」と思えたら、罪悪感を抱いていたとしても気持ちがラクになるのではないでしょうか。

家事のシェアはライフステージに合わせてアップデートする
——妊娠や出産などのライフイベントがあると、家事の内容も変わりますよね。
阿古 家事のシェアは、パートナーとの関係性やライフステージに応じて柔軟に変えることが大切です。二人暮らしの頃は自然に役割分担できても、子どもの誕生や働き方の変化によって、従来のやり方が合わなくなることもあります。
例えば、共働きであれば、忙しい時期は「どちらがどの家事をやるか」を細かく決めすぎないほうがいいと思います。そのつどできるほうがやる“シェア”の意識を持つことが大切です。
一方、育児中は家事そのものの負荷が一気に高くなるため、「完璧にやる」よりも「できる範囲でやる」と割り切ることも重要になります。子どもがある程度成長すれば、お手伝いを習慣化することで家事を家族全体でシェアすることも視野に入れるのがおすすめです。
また、仕事を退職し、ライフスタイルが変化するシニア世代では、家事のやり方を見直すことで、どちらか一方の負担が偏ることを防ぐことができます。
家事のシェアは一度決めたら終わりではなく、暮らしの変化に合わせて調整していくもの。定期的に話し合い、お互いが納得できる形を模索することが、無理なく家事をシェアしていくコツだと思います。
阿古さん流「家事の負担を減らす」3つのコツ
阿古 家事をシェアするためのコミュニケーションに加えて、家事そのものの負担を軽くする工夫も、実はいろいろあります。「家事はこうしなければ」と決めつけず、それぞれの家庭に合った、無理なく続けられるやり方を見つけることが大切だと思います。例えば、こんな方法もありますよ。
01. 作り置き&料理のレパートリーを減らす
阿古 毎日の献立を考えるのって、本当に大変ですよね。そんなときは、「その日食べ切る量」ではなく、2〜3回分をまとめて作っておくのもひとつの方法です。温め直す前提で多めに用意しておけば、忙しい日の負担がぐっと軽くなります。
とはいえ、同じメニューが続くのはちょっと…という方もいるかもしれません。そこでおすすめなのが、「固定メニュー制」。たとえば、「月曜日はカレー」「金曜日はパスタ」と、曜日ごとに献立のルールを決めておけば、「今日は何を作ろう?」と毎日悩む必要がなくなります。献立を考える手間が減るだけで、日々の食事作りが少しラクになりますよ。
02. 家電を活用する
阿古 「家事の手間を減らせるアイテムを取り入れる」のも、負担を軽くするひとつの方法だと思います。例えば、掃除機を軽くて扱いやすいスティック型にアップデートし、スイッチひとつでゴミが捨てられるなど、使い勝手のいいものを選ぶこともおすすめ。
また、ご家庭の間取りや生活スタイルによっては、ロボット掃除機や乾燥機つき洗濯機などを取り入れることもいいと思います。
「家事は手間をかけるもの」という考えにとらわれず、自分たちの暮らしに合った、無理のない方法や道具を取り入れることも、家事の負担を減らすための大切な工夫です。

03. 家事代行サービスを活用する
阿古 掃除や洗濯など、「自分の負担が大きいな」と感じる家事は、家事代行サービスを活用するのもひとつの手。特に、仕事や育児、介護などで毎日忙しく過ごしている方にとっては、プロの手を借りることで、心にも時間にも余裕が生まれることがあります。
家事代行サービスは、週に1回、月に1回、必要なときだけなど、ライフスタイルに合わせて柔軟に取り入れられるのが魅力です。サービス内容にもよりますが、1回数千円から利用できる場合もあり、自分たちの生活スタイルや予算に合わせて選びやすいのもポイント。
そして、家事の負担が軽くなり、仕事に集中できるようになれば、キャリアアップにつながり、かかった費用も将来的には十分取り戻せるかもしれません。
すべての家事を自分たちだけで抱え込まず、ときには「外の手」を借りる。そんな選択肢を持つことも、家事負担を減らし、生活をスムーズに回すために大切な考え方ではないでしょうか。

イラスト/jami 構成・取材・文/高浦彩加