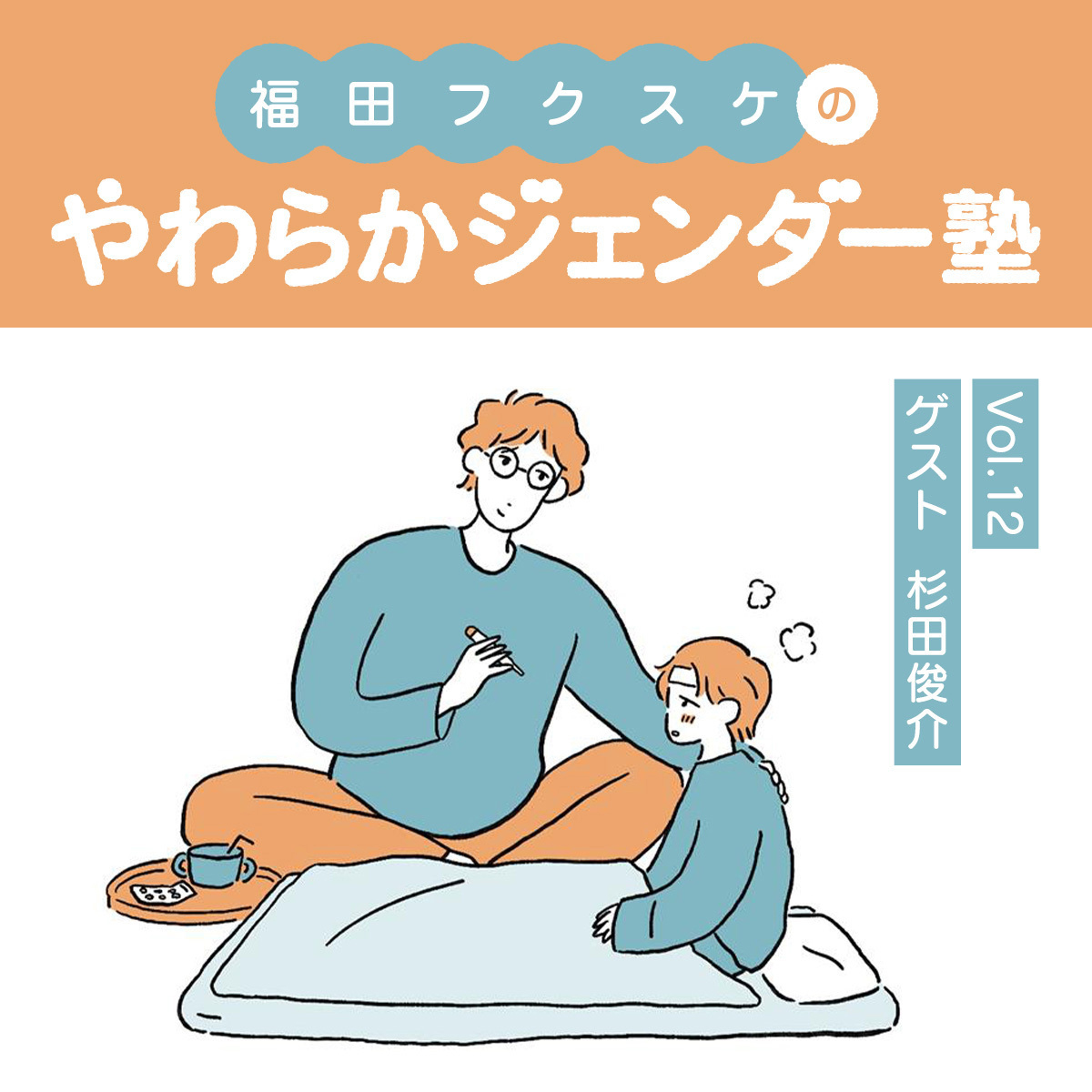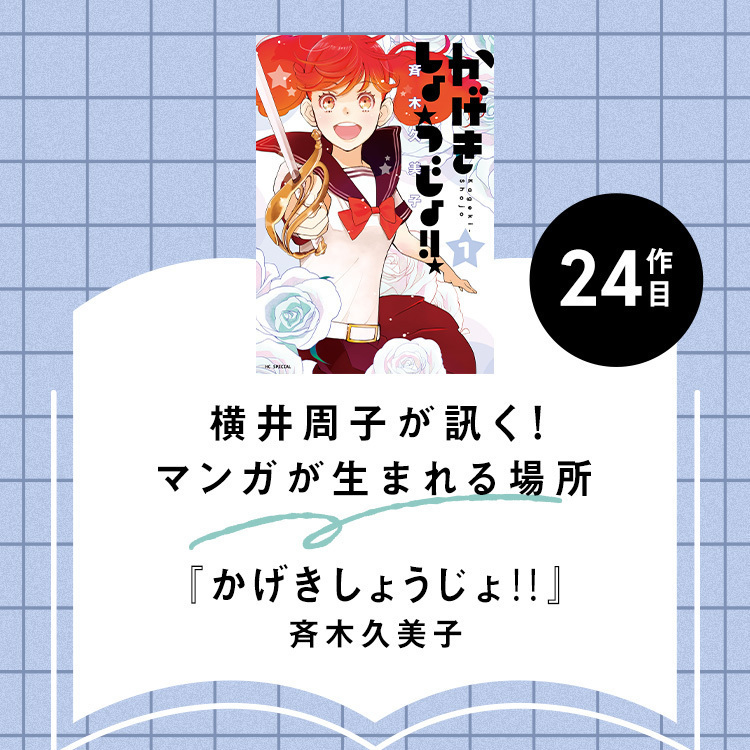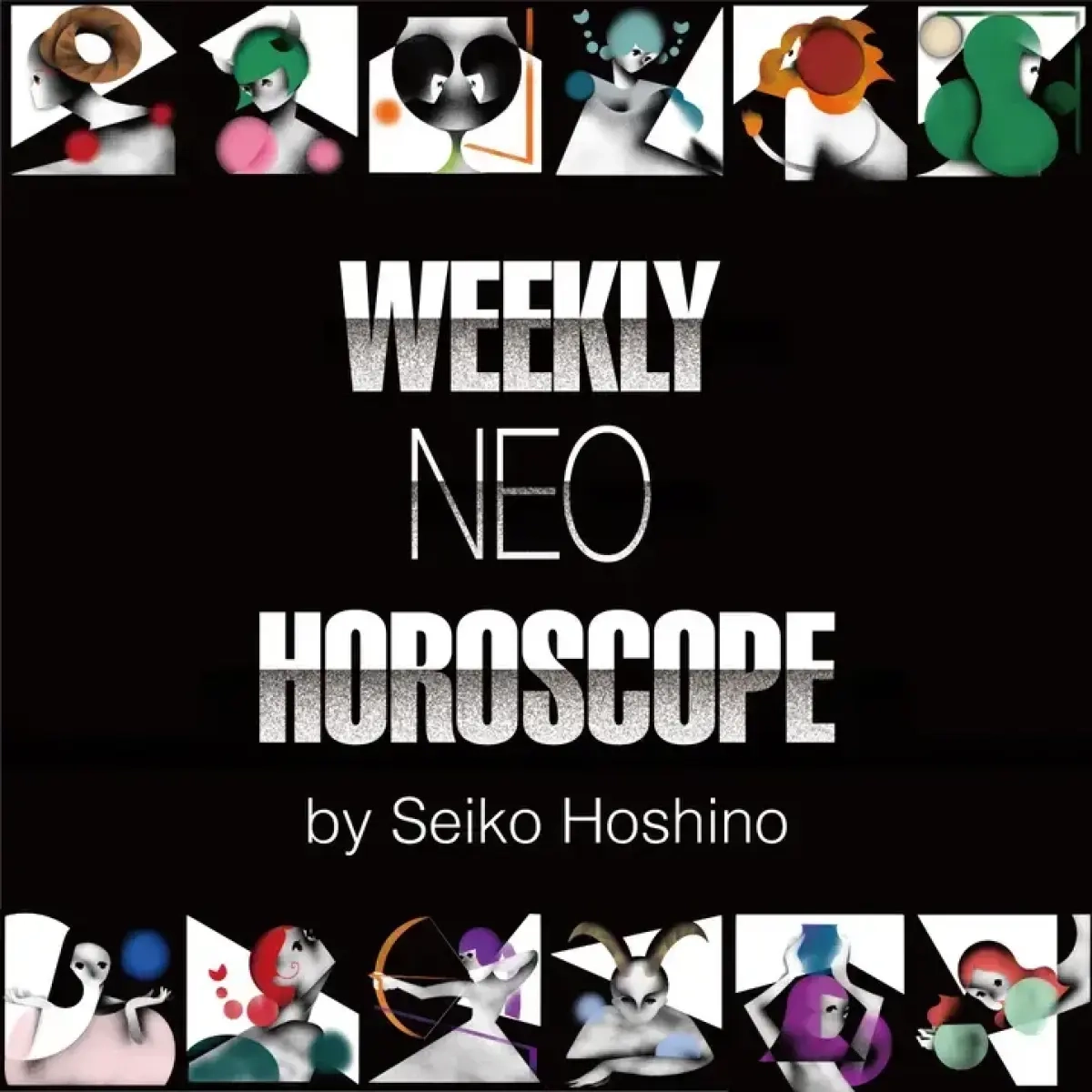これまでに3900を超える温泉に入浴し、ひとりで温泉を楽しみ、温泉地でのワーケーションを好む温泉ライター・高橋一喜さん。今回はひとリートにもぴったりの、1泊2日で訪れたい関東近郊のおすすめ温泉5選を教えていただきました!
※宿泊の金額は取材時のものです。
「ひとリート」とは…
半日~日帰り・1泊2日程度の「一人で楽しむリトリート体験や旅」を表す造語。yoi発の、心と体のセルフケアに役立つ時間の使い方です。
【栃木】板室温泉『大黒屋』

板室温泉ならではの入浴法「綱湯」(『大黒屋』には設置されていません)
板室温泉の温泉街は1000年もの歴史を誇り、湯治の里としての雰囲気を今に残しています。その効能から「下野の薬湯」として愛されてきました。古くから綱につかまり立ったまま温泉に入る独特の入浴法が伝わり、現在も一部の入浴施設で体験できます。

アート展示が行われるサロン

「松の館」シングルルーム
『大黒屋』は保養とアートの宿。サロンでは毎月さまざまなアーティストの展示が行われています。客室は全室南向き、床暖房完備の“陽室”になっており、「松の館」にはシングルルームもあり。

源泉かけ流し「ひのきの湯」

季節の野菜をたっぷり使った朝食
温泉は40℃前後の源泉かけ流し。ぬるめのお湯にゆっくりつかることで、身体を芯から温めます。お料理は地のものと季節の食材を満喫できつつ、胡豆昆(ごずこん・ごま、まめ、こんぶ)を使ったきれいと健康をつくるものばかり。ひとり客にもうれしい部屋食です。
高橋さん的おすすめポイント
板室温泉は昔の湯治場のような、ひなびた温泉地。環境自体も静かで過ごしやすいのですが、中でも『大黒屋』さんはアートも楽しめる珍しいお宿です。アートが好きな方にはぜひおすすめしたい。部屋もおしゃれですし、展示会を開いていたりもするので、いつ訪れても新しい発見や刺激を得られるのではないでしょうか。
ひとり用の部屋もあるので、ソロ温泉好きにはありがたいですね。温泉もゆっくりと入浴できる、ぬるめでやさしい泉質の源泉がかけ流しですし、お料理もヘルシーで、すごくおいしかったことを覚えています。体の外からも内からも健康的になれる温泉宿です。
板室温泉 大黒屋
◆栃木県那須塩原市板室856
一泊¥24000〜
http://www.itamuro-daikokuya.com/
【新潟】越後湯沢温泉『雪国の宿高半』

卵の湯を楽しめる露天風呂
新潟の越後湯沢といえば、冬にはスキーヤー、夏には花火や音楽フェスを楽しむ人に愛される温泉地。900年以上前に、高橋半六翁が関東へ行く途中に偶然天然湧出の温泉を発見したことが始まりと言われています。
そんな高橋半六翁が始めたお宿が『雪国の宿 高半』です。自然湧出のかけ流し100%の温泉は、とき卵を入れたような湯花が咲くことから“卵の湯”として親しまれています。

眺望フロアからの景色は越後湯沢温泉随一

畳とベッドでくつろげる客室
実はこの『高半』は、川端康成が愛したことでも知られる宿。「雪国」を執筆したとされる「かすみの間」は当時の部屋をそのまま保存してあり、宿泊者は誰でも見学することができます。昔ながらの釜で炊く南魚沼産のコシヒカリと、地元の食材を使った白いごはんに合うお料理も自慢です。

魚沼産コシヒカリによく合うお料理
高橋さん的おすすめポイント

川端康成が『雪国』を執筆した「かすみの間」 画像提供/高橋一喜
東京近郊ではありませんが、東京駅から新幹線で1時間少々の距離! 越後湯沢駅を中心に温泉街が広がっているので、車もいらず、関東の山の中へ行くよりも簡単にアクセスできるんです。スキーリゾートなので、ソロ温泉なら冬以外の季節に行くのがおすすめです。『高半』は老舗旅館で、かの川端康成も愛した宿。執筆した部屋が残されていたり、蔵書がたくさんあったり、本好きの方はより一層楽しめそう。読書に明け暮れるのもいいですね。
また、昔から女性の浴室のみ露天風呂があるのも強調したいポイント(昨年末には男性用露天風呂もできました)。一般に、高度成長期からバブル時代にかけて温泉地は男の遊興場という側面もあったので、古い宿ほど男性の浴室の方が広くて立派なケースが多いのですが、こちらは女性に優しく作られていると思います。お湯の質もいい! ゆで卵のような匂いがする本格的なお湯を、源泉かけ流しでたっぷりと楽しめます。
雪国の宿 高半
◆新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢923
一泊二食付 ¥17500〜
http://www.takahan.co.jp/
【神奈川】湯河原温泉『アルベルゴ 湯楽』

貸切できる露天風呂は大人気
“忘れられない時間 心に残る一皿”をコンセプトに掲げ、食事をメインとした宿泊施設「アルベルゴ湯楽」。イタリアンと和食を融合させたフルコースを楽しむことができます。さらに温泉は、自家源泉かけ流し。毎分70リットル、毎日100トンもの豊富な湯量があるため、露天風呂、石風呂、内風呂、大浴場のすべてが源泉かけ流しという贅沢なお湯使いが叶っています。

シェフ渾身の和とイタリアンを融合させたコース料理

朝食は小鉢がたくさん
お食事は、シェフである松村氏の手によって作られる和とイタリアンを融合させたフルコース。相模湾から水揚げされた魚介類や、地元伊豆山の有機野菜や果物など、箱根近隣各所から集まる豊富な旬の食材を楽しめます。
高橋さん的おすすめポイント

檜風呂 画像提供/高橋一喜

一人でも食べに行きたいお料理 画像提供/高橋一喜
一番の魅力は、やはりお料理です! 都内の人気レストランで出されるような、見た目も美しく、レベルの高いコース料理をいただけます。私も5〜6回泊まらせてもらっていますが、女性のひとり客もよく見かけますよ。ひとりでもわざわざ食べに行く価値のあるお食事です。朝食も一般的な旅館料理とは一線を画していて、白いごはんのお供になるような小鉢がたくさんついてきます。夕食と同じくらい満足できますよ。もちろん源泉掛け流しでお湯にもこだわりを持っていますし、写真の檜風呂も木のぬくもりがやさしくて最高にリラックスできました!
アルベルゴ湯楽
◆神奈川県足柄下郡湯河原町宮上528
ひとり泊 ¥20800〜
https://www.yurac.jp/
【群馬】四万温泉『中生館』

川べりにつくられた「かじかの湯」
群馬県の温泉地といえば草津を思い浮かべがちですが、ソロ温泉なら近くのエリアにある四万温泉はいかがでしょうか。もともと温泉療養を目的とした湯治客で賑わっていた温泉地で、まず草津温泉の酸性湯で患部に刺激を与え、四万温泉の中性湯で刺激を和らげるといったように過ごしていたそう。そのため四万温泉は“草津の上がり湯”として親しまれてきました。
そんな四万温泉にあるお宿『中生館』の初代館主が石を集めて作り上げたという「かじかの湯」は、なんと川べりにある野趣あふれる露天風呂。5月中旬〜10月中旬まで入浴が可能となっています。水着やバスタオルを着用してもOKなので、女性でも安心ですね。

カプセルルーム「森の部屋」

お庭をのぞめる「庭の部屋」

シンプルだけど栄養たっぷりの朝食を
湯治客がメインだったこともあり、一人用の客室が多いのも『中生館』の大きな魅力。窓から森の緑をのぞめるカプセルルーム「森の部屋」をはじめ、レトロな和室「川の部屋」「庭の部屋」など、自然の中にいることを感じられるお部屋ばかりです。シンプルで栄養のあるお料理も、暮らすように過ごすソロ温泉にぴったり。
高橋さん的おすすめポイント

レトロな雰囲気が残る外観 画像提供/高橋一喜
四万温泉は昔ながらの湯治場の雰囲気が温泉街に残っていて、一人でも行きやすい温泉地のひとつです。なかでも『中生館』はおひとり様の利用をメインにした宿で、ひとり客向けのプランも積極的に打ち出しているので、周りの目を気にせず過ごせるはず。
ひとり用の客室「森の部屋」はデスクもあって、ワーケーションもはかどります。四万温泉自体、どこへ行ってもお湯の質が高いのもうれしい! 『中生館』は清流沿いの湯船が名物で、川のせせらぎや森林浴を楽しみながら入浴できます。
中生館
◆群馬県吾妻郡中之条町大字四万乙4374
ひとり泊 ¥7000〜
https://chusei-kan.jp/
【群馬】湯宿温泉『ゆじゅく金田屋』

「文殊の湯」

純和風の客室
開湯1200年の歴史を誇る湯宿温泉は、塩分を含んでおり体がとても温まるのが特徴のお湯です。入浴後には肌がスベスベになることから、美人の湯としても愛されてきました。
そんなお湯をかけ流しで楽しめるお宿が『ゆじゅく 金田屋』。「文殊の湯」は、床は石畳、お風呂の木枠と天井は木曽桧で作られています。日差しが差し込む明るい浴場で、四季折々の表情を見せる坪庭を眺めながらの入浴を楽しむことができます。

炊き立ての酵素玄米

酵素玄米と合う素朴な田舎料理
宿泊したらぜひ味わってほしいのが、酵素玄米を取り入れた朝食。地元新治産の野菜を中心とした素朴な田舎料理で、季節ごとの旬な食材を使っています。初めて訪れた人でも、懐かしい気持ちでホッと一息つけそう。
高橋さん的おすすめポイント

雰囲気たっぷりな湯宿温泉の街並み
湯宿温泉はいい意味でひなびていて、団体やグループ客が少なく静かな温泉地です。『金田屋』はひとり客を歓迎していることでも有名。SNSで発信された「当館におけるひとり旅の割合は全体の8割を超えております!」というポストが反響を呼んで、温泉好きの間では“ひとり旅といえば金田屋”と広く知られています。お湯もいいですし、酵素玄米を使ったお食事をいただきながら、じっくり自分の時間を過ごせるはず。
ゆじゅく 金田屋
◆群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉608
ひとり泊 ¥8680〜
http://www.yujuku-kanetaya.com/
取材・文・構成/堀越美香子 企画/木村美紀(yoi)