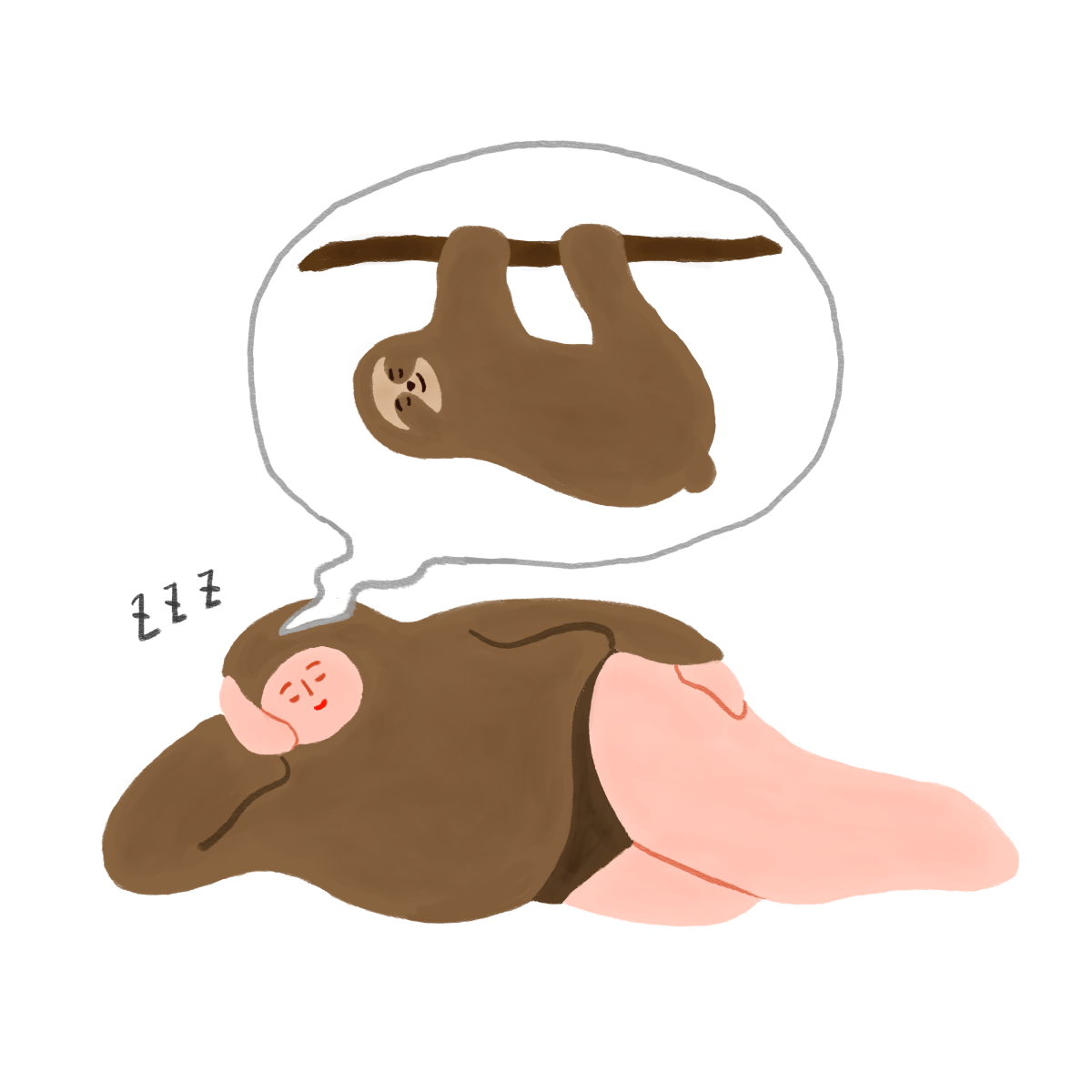恋愛・セックス・パートナーシップを「わかったつもり」で済ませないために──。国際的な知見をもつジャーナリスト池田和加が、映画・書籍・専門家の理論をもとに丁寧に向き合う連載です。第2回は最新の話題作と往年の名作を引き合わせ、「曖昧な関係」に健康的な境界線を引く方法を考えます。

「曖昧な関係」に境界線を引くことの大切さ
“友達以上・恋人未満”や“グレーな関係”といった曖昧なつながりは、現代の恋愛や人間関係において大きなテーマとなっている。マッチングアプリの普及や、「セフレ」といった関係性の浸透も相まって、「はっきりしない関係」に悩む声は後を絶たない。
そうした複雑な関係性において、最も重要なのが「境界線(バウンダリー)」――つまり、感情的・身体的・性的な領域において、どこまでを許容し、どこからを線引きするかという問題だ。心理学における境界線とは、「自分と他者とを分ける線」を指し、自分の好みや嫌悪感、限界を把握し、健全な距離感を保つために欠かせないものとされている。
境界線が曖昧なままでは、過剰に自分を犠牲にしたり、共依存に陥ったりするリスクがある。境界線をはっきりすることで、自己肯定感や自信が高まり、相手と対等で前向きな関係を築くことができるのだ。
なぜ境界線が必要なのか
アメリカの性科学者エイヴァ・カデル博士によると、境界線を明確にするとは、自分の「NO」を知り、それを伝えることだという。
自分のニーズや欲求を自覚し、明確に言語化して相手に伝えることは、相手を大切にすることにもつながる。例えば、自分の気持ちを伝えず「察してほしい」と相手に期待すると、期待が裏切られた場合に相手に対して怒りの感情をぶつけてしまう。相手を攻撃しないためにも境界線を知り、それを共有しておこう。
そして、境界線は相手に懇願されても、妥協しないようにしよう。なぜなら、自分の境界線を破って相手に合わせていくと、「自分が何者で何を欲しているか」がわからなくなってしまうからだ。すると、自己肯定感も低くなり、それをさとった相手に余計に軽んじられて、関係は悪循環になっていく。
とはいえ、日本では我慢が美徳とされ、個人の自己主張をよしとしない文化がある。「和を乱さない」「相手の気持ちを察する」ことが重視され、はっきりとNOを言うことが「わがまま」や「協調性がない」ととらえられがちだ。また、関係性を重視する文化では、境界線を引くことが拒絶と捉えられ「境界線を引く=関係を壊す」という誤解も生まれやすい。
しかし、だからこそ日本人にとって境界線を引くことは重要なのだ。相手への配慮を示しながらも自分の気持ちを伝える方法を身につけることで、互いを尊重する関係を築くことができる。境界線とは、実は「相手のことを大切に思っているからこそ、互いが心地よくいられる距離感を見つけたい」という愛情の表現でもある。
具体的に境界線を引くために。映画で描かれる「3つの境界線」
それでは、映画のシーンを通して、具体的な3つの境界線の在り方を考察してみよう。
1. 感情的境界線――『We Live In Time この時を生きて』
ただいま公開中の『We Live In Time この時を生きて』は、トビアス(アンドリュー・ガーフィールド)とアルムート(フローレンス・ピュー)の10年にわたる関係を、偶然の出会いと恋の始まりから、家庭を築き試練が降りかかる過程まで、時系列ではなく過去から現在の断片的なシーンをちりばめて見せるロマンチック・ドラマだ。
アルムートは、トビアスが「家族を持ちたい」と告白したタイミングで、「結婚も子どもも望んでいない」「(子どもを将来作るという)約束はできない」「子どもは好きじゃない」とはっきり拒絶する。それが一時的に二人の間に溝を生むことになるが、アルムートは自分の境界線を明確に示す。自分の人生設計や価値観を曲げることなく、相手に迎合することなく、率直に自分の気持ちを伝えるのだ。
しかし、のちにアルムートの境界線は変化していく。仕事に対する情熱、トビアスに対して深まる愛情、そして人生のさまざまな経験を通じて、彼女は自分自身の変化を受け入れる。境界線は大切にしなければいけないが、自分のために境界線の変化を受け入れることはアリなのだ。
2. 身体的境界線――『バービー』
映画『バービー』は、マーゴット・ロビー演じるバービーとライアン・ゴズリング演じるケンが、完璧なバービーランドでの日々から、突然の異変をきっかけに現実世界へ旅立ち、自分自身の存在や社会の多様性について向き合っていく物語である。
作中、バービーがケンに対して「お泊まりはしない」「あなたは私のボーイフレンドではない」と明言し、物理的な距離や接触の境界を明確に示す。ケンがロマンチックな関係や身体的な親密さを求めても、バービーは毅然と「NO」を伝え、自分の望む距離感を守る。
特に興味深いのは、ケンがバービーの車に同乗しようとした際、バービーは「乗らないで」と最初は断るが、最終的に「後部座席ならOK」と譲歩するシーンだ。これは、「ここまでは許容できるが、それ以上はNG」という物理的な距離の線引きの具体例だ。
本作で見るように、身体的な境界線は「どこまで近づいてほしいか」「どんなスキンシップが心地いいか」など、自分の体やパーソナルスペースを守るためのものだ。身体的境界線が曖昧だと、不快な触れ方や距離感を受け入れてしまい、ストレスを感じてしまう。自分のニーズを率直に伝えることが、自分の尊厳を守り、自分と相手を信頼することにもつなる。
3. 性的境界線――『ピアノ・レッスン』
『ピアノ・レッスン』は、エイダ(ホリー・ハンター)、ベインズ(ハーヴェイ・カイテル)、スチュアート(サム・ニール)、フロラ(アンナ・パキン)らが出演し、19世紀半ばのニュージーランドを舞台に、口のきけない女性エイダが娘とともに見知らぬ地に嫁ぎ、夫や現地の男性ベインズとの愛と葛藤、そして自立を描く物語である。
映画では、エイダが愛するピアノを夫スチュアートに売り払われてしまい、それを買い取ったベインズから、鍵盤を一つずつとり戻していくという設定がある。ベインズはエイダに魅力を感じており、鍵盤を返す条件として徐々に性的な要求を提示する。
エイダは最初は拒否するものの、ピアノへの愛情とベインズへの複雑な感情の間で揺れ動きながら、最終的に自分自身の意志で選択していく。ベインズは欲求の内容をその都度エイダに伝え、エイダが許したときだけ性的関係を深めることができるのだ。
この「どこまで許容するか」「どこから先は拒否するか」という交渉は、まさに性的な境界線をめぐるやりとりだ。面白いことにエイダは夫には自分から触れるが、夫には触らせないなど、相手ごとに明確な線引きをしている。妻が夫の所有物のように扱われていた時代の物語ながら「自分の欲望や限界を自分で決める」ことの大切さをも描いている。
性的境界は「どんな行為がOKか」「どんなタイミングなら大丈夫か」「どんな相手とならOKか」など、細かく設定すること。性的同意とは「積極的なYES」であり、「しぶしぶのYES」や「あきらめのYES」ではないということもこの映画は教えてくれる。
境界線を伝える実践的なアプローチ
よいコミュニケーションとは、双方の自己肯定感を大切にするもの。境界線を伝える際も、相手を攻撃することなく、かつ自分を卑下することなく伝える「アサーティブコミュニケーション」が重要だ。
基本の3ステップ
1. まず「ありがとう」から始める(相手への敬意を示す)
2. 「私は~と感じる」と<私メッセージ>を使う(攻撃的表現を避ける)
3. 具体的な提案をして相手の意見を聞く(建設的な解決策を探る)
性的な境界を伝える場合
「私のことを大切に思ってくれてありがとう。ただ、私はもう少しお互いを知ってから身体的な関係に進みたいと感じている。もっとゆっくり話す時間を今度作りたい。どう思う?」など。
境界線は「橋」を架けるもの
境界線を守ることは自己肯定感を高め、自分軸をもつ土台となる。“グレーな関係”の中で悩むときこそ、自分の境界を見つめ直し、相手と話し合うことが、ヘルシーな関係への第一歩だ。
境界線は相手を拒絶するための壁ではなく、より深い信頼と安心を育むための「橋」なのだ。
『We Live in Time この時を生きて』
新進気鋭の一流シェフであるアルムートと、離婚して失意のどん底にいたトビアス。何の接点もなかった二人が、あり得ない出会いを果たして恋におちる。自由奔放なアルムートと慎重派のトビアスは何度も危機を迎えながらも、一緒に暮らし娘が生まれ家族になる。そんな中、アルムートの余命がわずかだと知った二人が選んだ型破りな挑戦とは──。
監督:ジョン・クローリー(『ブルックリン』)
出演:フローレンス・ピュー、アンドリュー・ガーフィールド
配給:キノフィルムズ
提供:木下グループ
© 2024 STUDIOCANAL SAS – CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION
取材・文/池田和加 構成/長谷川直子