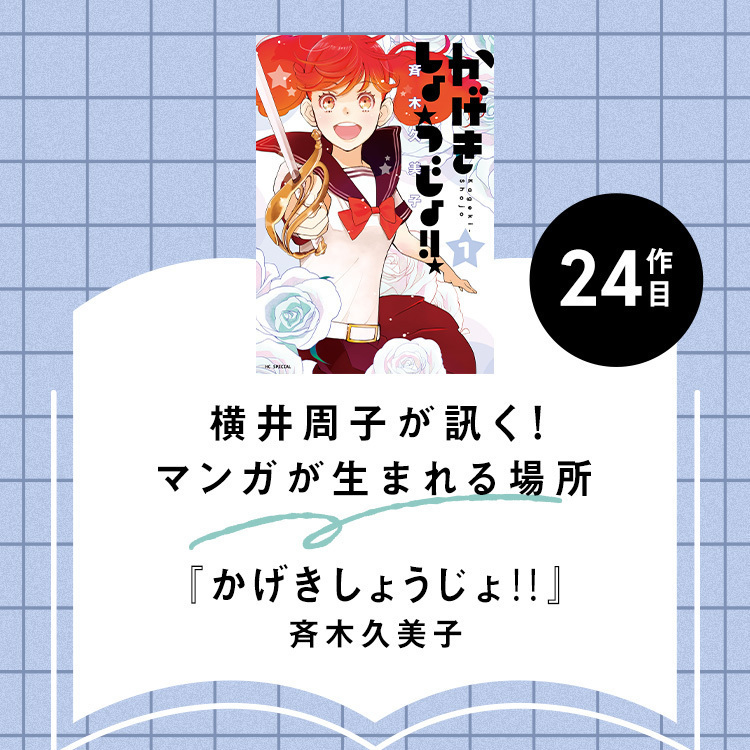竹田ダニエルさん連載「New"Word", New"World"」をまとめた書籍『ニューワード ニューワールド 言葉をアップデートし、世界を再定義する』に収録している対談を、WEBでも特別公開!
若者の政治参加を促進しようと活動している団体『NO YOUTH NO JAPAN』代表理事である能條桃子さんとの対談後編では、さまざまな問題に取り組む上で重要な情報の集め方、人と議論を発展させるために必要なことなどを語り合いました。

何を信じて、どこを情報源にする?

——お二人は環境、政治、人権などのトピックを扱っていますが、日頃どのように情報を集めているのでしょうか? 信用できる情報を集めるために、意識していることがあればぜひ教えていただきたいです。
ダニエルさん 自分の場合は、いろんなジャーナリストのアカウントをフォローしたり、インデペンデントメディアが配信しているメルマガやポッドキャストをチェックしてる。『FOXニュース』をはじめとしたメインストリームのニュースや、最近だと『ニューヨーク・タイムズ』でさえも、特にパレスチナ問題に関しては政治性が偏っていたりバイアスがかかった報道も多いから、距離を取りはじめているZ世代も多いと思う。
アメリカは情報源もメディアの数も多様な分、どこから情報を収集しているのかが自分のアイデンティティに結びつきやすいと感じる。「私はこういう考えだから、このメディアを読んでいる」というように。ただ、最近はメディアの閉鎖やジャーナリストのレイオフも起きていて、そもそもニュースの信憑性やジャーナリズムの質の低下も大きな社会問題になっています。
能條さん 私は友達との意見交換で情報を収集することが多いです。環境NGO団体の友達やクィアコミュニティの友達、難民・移民サポートをしている人、大学生、弁護士、介護士、保育士といったいろんな環境・立場の人たちと話しながら、それぞれが抱えている問題意識を聞いて、社会運動に役立つ情報を得てる。
人に話を聞くと、いろんな問題の根本が政治の構造の中にあるんだと再認識できるし、横のつながりを作っておけばいざというときに連帯できる。情報収集しながらコミュニティを作っていっている感じかも。
——日本では『LINE NEWS』で情報を得るという人も少なくないと思うのですが、アメリカではどうでしょうか? TikTokで情報を得ている人も多そうですが。
ダニエルさん TikTokで流れる情報の中には、ジャーナリストが書いた記事を要約して正確に説明しているものもあるんですよ。要は記事を動画にして転載しているような感じ。
能條さん ソース元があるのはいいよね。日本は著作権が厳しいから、記事そのままの転載はSNSだとBANされちゃう。その規制がゆるくなれば、日本でもニュースとのかかわり方が変わりそうな気がするけど、メディア経営の問題も別であるからね。
ダニエルさん アメリカでは、メディアがTikTokを使って自ら拡散しているところもあるし、読者層が広がるなら基本的に転載してかまわない、というスタンスをとっている企業も多い印象。
例えば『ニューヨーク・タイムズ』をはじめとしたいわゆる「レガシーメディア」の中でも、公式のTikTokアカウントを作って「ショートフォーム動画」を投稿しているし。そのコメント欄も参考になるんですよ。Instagramでの投稿だったら、「この記事のこういうところがよくない」みたいなコメントがついてバズったり。 Xだと、ジャーナリスト自身の考えや発信にも注目できるのが面白いんだよね。Xのプラットフォームのいろいろな使いづらさによって投稿をやめてしまっているジャーナリストも増えているけど。
「難しい問題だよね」で片づけない。間違えることを恐れないで

ダニエルさん 自分で発信をしたりSNSを見ていて感じるのは、アメリカでは自分に不利・不都合なルールは変えてほしいと声を上げる人が比較的多い印象があって、それによって実際にルールが変わることがあるということ。
実感としても、アメリカでマイノリティとして生きていると、自分にとって不利・不都合なルールがありすぎるんですよね。なぜなら、そういうルールが作られた当時は白人男性にとって都合がいいことが優先されていたから、多様な人が生きる現代にはフィットしない場合が多い。だから、それを変えていこうという動きが当たり前のこととして受け取られているんだと感じるんですよ。日本ではそういうことを感じたりする?
能條さん なるほどね。日本では逆に、すでにあるルールを変えることがすごく難しいと感じる。例えば最近も、都知事・県知事選に立候補できる年齢(2024年9月現在は30歳以上)を若年齢化できるように活動しているんだけど、やっぱりルールの問題が立ちはだかるんですよ。
国に意見を聞いてもらえるように、あえて25歳で立候補届を出して、不受理になった上でそれに対する申し立てとして裁判をしているんです。そのやり方でないと、制度的に訴えが認められないから。でも、そういう背景を知らない方から「ルールもわかんない人が知事になれるわけないでしょ」とか、「あなたが30歳で立候補して国会議員になってからルールを変えればいい」という意見がくる。
つまり、「とにかくルールは絶対に守らなきゃいけない」という“圧”なんです。私が思っていた以上に、すでにある決まりを変えることに心理的な抵抗がある人が多いんだなって。
——ルールに対する考え方にも、大きな違いがありそうですね。
能條さん 日本の社会や文化では、誰かと意見交換をするときに、「人格」と「意見」を切り離すことが難しいというのもある気がする。意見が食い違ったときに、「人格まで攻撃された」と勘違いして、冷静な議論に発展しないとか。でも本当は、意見が違うのは当たり前なわけで、その前提を忘れてはいけないなと感じます。
ダニエルさん 自分の意思表明で終わるのではなく、全体を俯瞰して意見することが大事ですよね。
——最近、お二人が注目している課題や社会問題についてのトピックはありますか?
ダニエルさん 今、自分が気になっているのは、情報が閉鎖的になっていることです。プラットフォームの変化によって得られる情報が限られてきて、デジタルネイティブのZ世代でもアクセスする情報が偏ることで考えが先鋭化したり、視野が狭くなっている傾向があります。ソーシャルメディア上でAI生成画像が拡散されて誤った情報に流されてしまうことも結構危険ですよね。
能條さん あまり大切なことではないニュースに埋もれて、重要な海外の情報がきちんと届かなくなってしまうこともあるよね。
ダニエルさん インターネットって本来は世界とつながれるツールのはずなのにな。 それから、特に最近のメディアを見ていて感じるのは、なんでも「難しい問題」という言葉でまとめて、思考停止してしまうこと。「難しい」で片づけず、一人一人自分で考えていくことが大切だと思うんだよね。
能條さん 「難しいからわからない」とか、「学校で習ってこなかったから」という言葉も聞くけど、すべてを学校で教えてもらえるものでもない。知識は誰かが教えてくれるものだというスタンスを変えていくことが、権威主義から抜け出すことにつながると思う。間違えることは悪いことじゃないから。間違えたら、次から正せばいい!
私たちには“感情のリハビリ”が必要だ

——一人一人が自分で考えていくためにはどうしたらよいと思いますか?
能條さん 新聞の記事を読んだり、『NHKニュース』などテレビ局のアカウントをフォローしておくことは大事だと思う。一部、偏向報道もあるけど、基本はきちんとした取材に基づいた情報だから、それを読んで自分はどう思うかを客観的に把握すればいい。
その過程で、“感情のリハビリ”が必要なこともあるかもしれないですよね。一部では、ニュートラルかつクールでいることがいいとされ、「これは間違ってる」とか「これは許せない!」と怒って声を上げる人はダサい、うるさいととらえられることもあるけれど、その考えを見つめ直していく必要がある気がする。
自分の感情が動くものからでいいから、生きてる中で「これはおかしい」「これはどうにかなんないのか」みたいな感情を呼び起こされる情報を摂取して、表現していくといいのかもしれません。
ダニエルさん “感情のリハビリ”か。いい言葉だね。
能條さん リハビリをはじめるには、まず友達や信頼できる人と話すことだと思う。その中で、「共感する」とか「私はそう思わない」みたいな会話をしながら慣れていくものなんじゃないかな。一人で考えてると鬱々としかしないからね。だから、私は話せる場を作りたいと思って活動している、というところにつながるかも。
ダニエルさん なるほど。自分たちの手で生活を変えていくためには、まずは間違っていると思ったら間違っていると言っていい、と思うことからはじめる。人権や環境を守っていくには、そういうことをひとつずつ重ねながらよりよくしていくしかないと思うな。
単行本「ニューワード ニューワールド 言葉をアップデートし、世界を再定義する」発売中!
本対談も収録している書籍が好評発売中。書籍でしか読めない、書き下ろしトピックスも!

画像デザイン/前原悠花 構成・取材・文/浦本真梨子 企画/木村美紀・種谷美波(yoi)