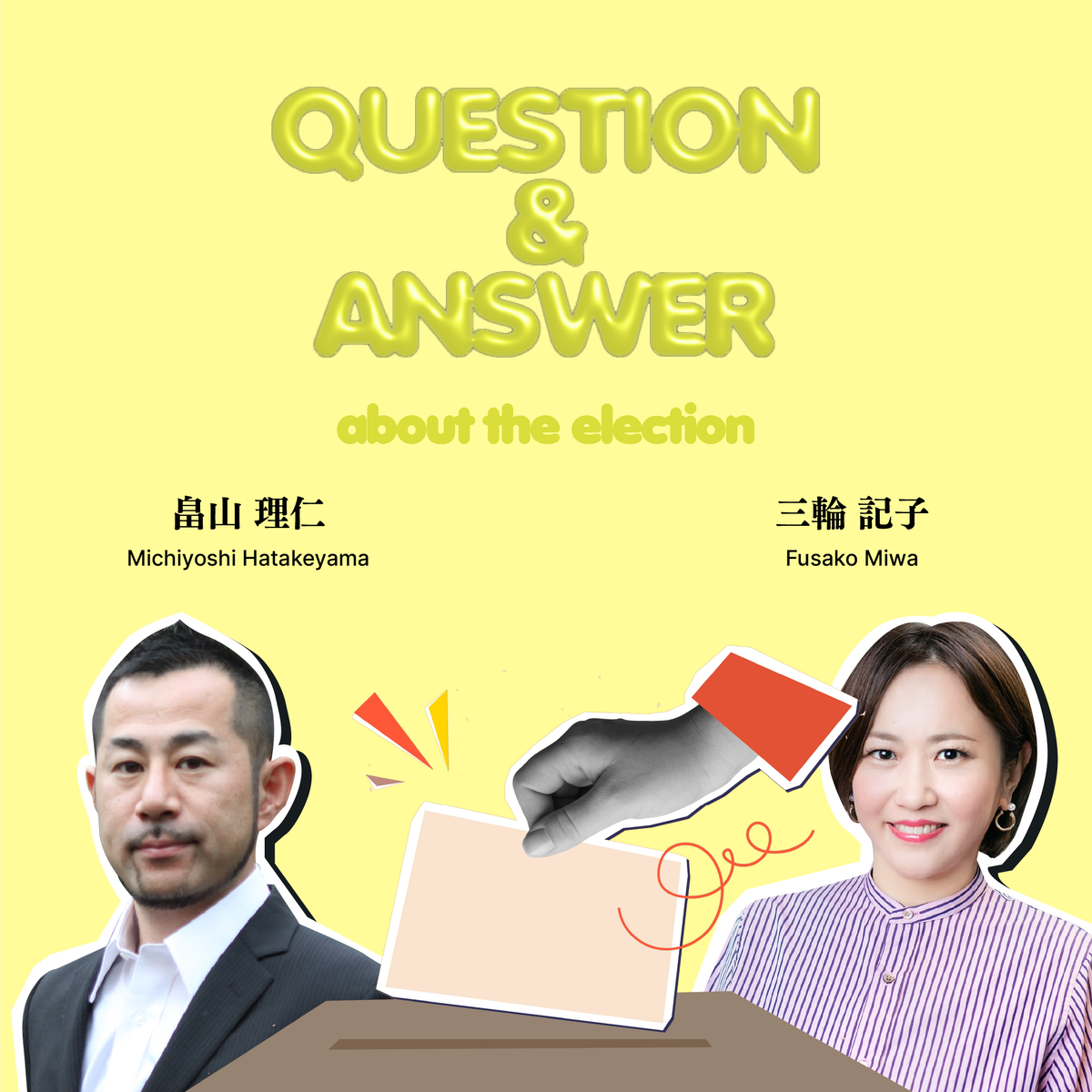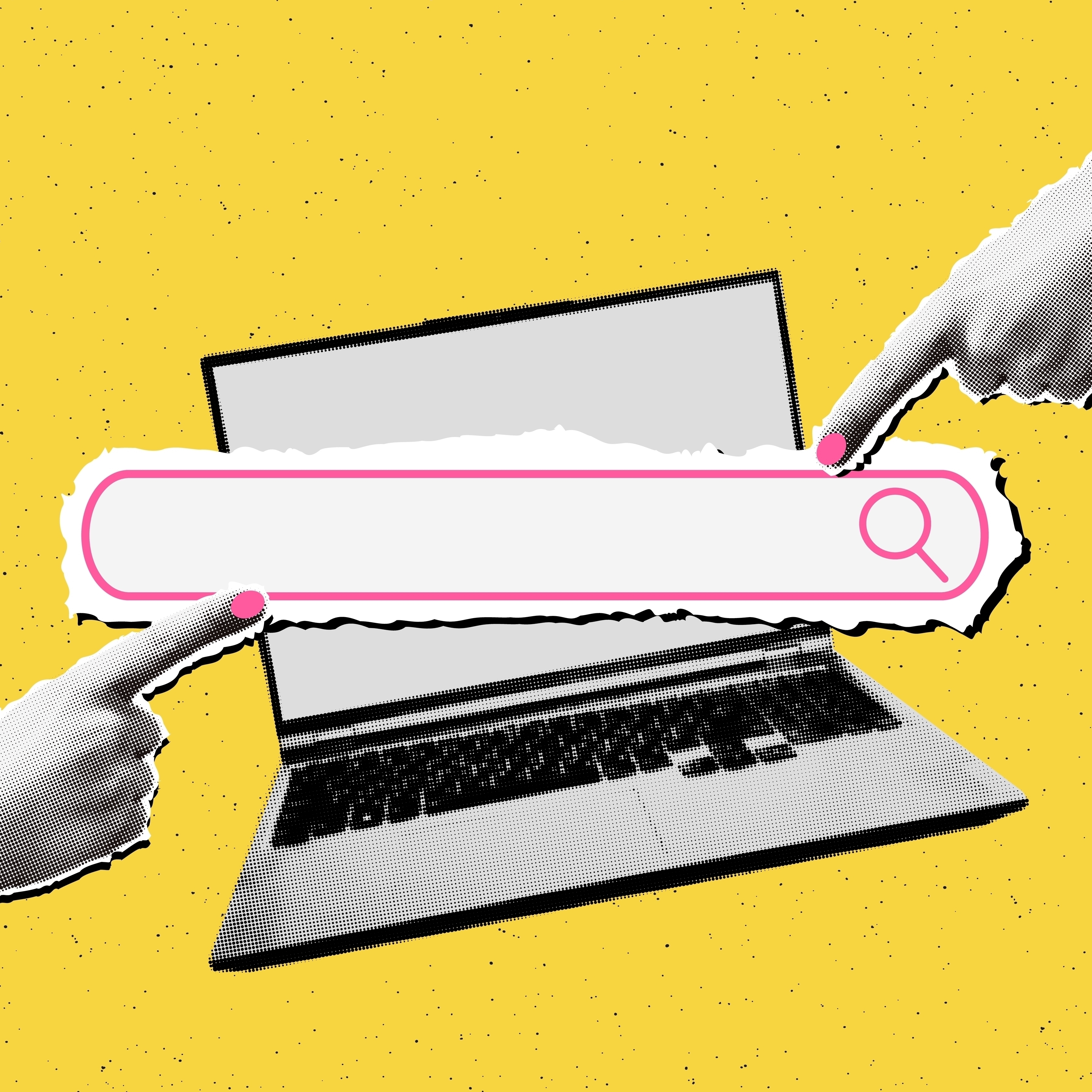YouTube番組「ヒルカラナンデス(仮)」から派生したロードムービー『劇場版 センキョナンデス』と『シン・ちむどんどん』を手がけたダースレイダーさんとプチ鹿島さん、そして『映画 ○月○日、区長になる女。』で2022年の杉並区長選挙を記録したペヤンヌマキさん。「選挙」をテーマに映画を制作した3人に、選挙を“自分ごと”として味わう秘訣をたっぷり語っていただきました。

ラッパー
パリ生まれ、幼少期をロンドンで過ごす。全国東大模試6位の実力で東京大学に入学するも、浪人の時期に目覚めたラップ活動に傾倒し中退。2000年にMICADELICのメンバーとして本格デビュー。日本のヒップホップでは初となるアーティスト主導のインディーズ・レーベルDa.Me.Recordsの設立など若手ラッパーの育成にも尽力。2010年6月、イベントのMCの間に脳梗塞で倒れ、合併症で左目を失明するも眼帯をトレードマークに復帰。現在はThe Bassonsのボーカルのほか、司会業や執筆業とさまざまな活動を積極的に続ける根っからのエンターテイナーとして活躍。2020年4月よりプチ鹿島氏とYouTube番組「ヒルカラナンデス(仮)」を毎週金曜に配信中。

時事芸人
新聞14紙を読み比べ、スポーツ、文化、政治と幅広いジャンルからニュースを読み解く。2019年に「ニュース時事能力検定」1級に合格。コラム連載は月間17本で「読売中高生新聞」など10代向けも多数。著書に『半信半疑のリテラシー』(扶桑社)、『お笑い公文書2025 裏ガネ地獄変』(文藝春秋)など。

劇作家・演出家/演劇ユニット「ブス会*」主宰
早稲田大学卒業後の2010年、演劇ユニット「ブス会*」を立ち上げ「自分ごと」を起点に現代を生きる女性たちに焦点を当てた作品を発表してきた。2014年『男たらし』、2015年『お母さんが一緒』が岸田國士戯曲賞最終候補作品に選出。近年は地域の問題を「自分ごと」とし、ドキュメンタリー『映画 ○月○日、区長になる女。』を監督(2024年公開)。また脚本家としてテレビドラマなども手がける。

“非日常”だから、ふとした瞬間にむきだしの素顔が現れる
──選挙を「祭り」として楽しみながら各地の選挙現場を漫遊するダースレイダーさんとプチ鹿島さん、杉並区民として選挙が突然“自分ごと”になったペヤンヌマキさん。まずは、皆さんが思う「選挙の見どころ」を教えてください。
ダースレイダー(以下、ダース) 選挙って限られた期間の中でみんなが必死に動いているから、ふとした瞬間にむきだしの素顔が見えることがあるんですよね。だから僕らは街宣(街頭宣伝)に行くことを心がけていて。候補者の演説はもちろん、スタッフに対する態度とか、スタッフの人たちが「この人のために頑張ろう!」という空気で動いているかとか、街頭演説を聞きに来ている人の雰囲気とか。
プチ鹿島 街頭演説にも選挙事務所にも背広を着たおじさんばかりで女性がいないぞ、とかね。
ダース そうそう。選挙事務所をのぞいてみると、なんとなくジェンダーバランスが見えるし、いまだに「女性はお茶くみ」みたいな事務所もあったりします。そういうところを見ていくと、候補者の人となりが結構浮かび上がってくる。
実はこれって社会を生きていくうえで必要な、人を見る目を養うトレーニングにもなると思うんです。それに、選挙中の様子を見ておくと、「こんなに人って変わるの?」みたいな選挙後の変節も見えやすくなりますから。
プチ鹿島 現場を見ていない人にかぎって「政治家は口がうまいんだから、選挙現場なんか行っても丸め込まれるに決まってる」なんて言うけれど、近くで見たり話したりしてみると、いいことを言っているように見えても「中身がふわっとしているな」「スタッフには偉そうだな」ってわかるものなんですよ。
ペヤンヌマキ(以下、ペヤンヌ) 以前、若くてすごく感じがいい候補者の街宣を見ていたとき、すぐ近くで高齢の女性スタッフがチラシを配っていたんです。そうしたら候補者がその女性に対して「チラシ!」とあごで使うような態度で言っていて…見え方が少し変わりましたね。
プチ鹿島 選挙って非日常だから、ちょっとした一瞬に本音が出ちゃうんですよね。
選挙は「祭り」。そこにあるのは喜怒哀楽と熱がぶつかり合う真剣勝負

──ペヤンヌさんの『映画 ○月○日、区長になる女。』には、「選挙は続くよどこまでも」というフレーズが登場します。プチ鹿島さんとダースさんは国政選挙や知事選挙などの規模が大きい選挙を中心に取材されていますが、ペヤンヌさんは国政選挙をどんなふうにみていたのでしょう?
ペヤンヌ 逆に私は国政が遠かったんですよね。私の中では、政治家って「悪いことをしている人たち」という印象が強くて身近に感じられないから興味も持てなかった。本当はちゃんと勉強しなきゃいけないんだろうなと思いつつ、時間だけが過ぎていく。
でも、お二人が映画(『劇場版 センキョナンデス』と『シン・ちむどんどん』)で選挙を「祭り」として追いかける姿は、一緒に旅をしているような感覚で楽しめるし、いろんな政治家の、普段いいところしか見せない姿とは違う一面が垣間見えるのがすごくいいなと思ったんです。そこから「この人って本当はどうなんだろう?」って興味を持てるじゃないですか。その入り口をつくってくださっている気がして。
プチ鹿島 いやぁ、うれしい。もくろみ通りですね(笑)。「選挙は祭りだ」って言うと、たまに「選挙はエンタメじゃない」なんて怒る人もいるんですよ。でも、人間がこれほど喜怒哀楽や熱をぶつけ合う機会ってほかにはない。それはイコール真剣勝負だから。僕は真剣勝負だからこそ「祭り」になると思っています。
ペヤンヌさんがおっしゃったように「政治を勉強しないといけないんじゃないか」「政策をまるごとわかったうえで投票しなくちゃいけないんじゃないか」って完璧を求める真面目な人も多いですよね。すごく偉いと思うけれど、それはいったん置いて、「これだけ真剣勝負でみんなが激突し合っている場を見なくちゃもったいないですよ!」という思いもあるんです。
ダース 僕らが師と仰ぐフリーライターの畠山理仁さんは、選挙権がない地域の選挙現場を観戦しながらその土地の名物を楽しむ「選挙漫遊」を提唱していますが、選挙ってそこに暮らす人たちが参加してつくっていく地元の祭りでもあるから、各地の祭りを見に行くような楽しさもある。それに実際の祭りだって、運営したり参加したりしている人たちは超真剣ですからね。
『シン・ちむどんどん』
Prime Video、DMM TV、Hulu、YouTube、U-NEXTほかで配信中。
配給:ネツゲン ©「シン・ちむどんどん」製作委員会
5年近く選挙現場を旅してきたからこそ言いたい。「その祭り、本物ですか?」
プチ鹿島 祭りが面白いのは、ルールを守ったうえでの真剣勝負だから。ただ最近でいうと、兵庫県知事選の“二馬力選挙”での熱狂については、少なくとも相手に対する敬意がないし、人間の負の感情を徹底的に煽ってきたなと感じました。そこに対しては「違う」と言いたいですね。
──兵庫県知事選に限らず、「さすがにこれは誰もやらないだろう」と思われていたこと、例えば別の候補者の演説を妨害する、根拠不明なデマを流す、ポスター掲示場の枠を候補者以外に事実上販売するといった行為が、法律の抜け穴を利用して公然と行われました。
プチ鹿島 そうそう。僕らは5年近く「選挙は祭りだ」と言いながら日本中を旅してきたからこそ、お祭り感が変に利用されるとこうなるんだなという危険性を身をもって感じるし、「違う」と言える資格はあるのかなと思うんですよね。「ちょっと待って。それ祭りじゃないですよ!」みたいなポスターつくろうかな。
ダース 「その祭り、本物ですか?」ってね。本来はルールを守ったうえでとことん主張をぶつけ合う真剣勝負のはずが、いまは脱法的にチート技を使うことで盛り上がるみたいなおかしな空気がある。
プチ鹿島 僕らが選挙を好きな理由って、そこに「可笑しみ」があるからなんですよ。人間って真剣であればあるほど、まわりからすると、とんちんかんなことをやったりするじゃないですか。そうやって自然に発生する可笑しみは、最初からウケをねらうのとは別物。真剣さと可笑しみって絶対セットなのに、いまは全然違うものが「面白い」「エンタメ」みたいになっているから「それは違うよ」と言いたい。
ペヤンヌ お二人が言う「祭り」とか「可笑しみ」とは定義が違っていますよね。私は「自分の生活を守りたい」という気持ちで選挙に密着取材しましたが、鹿島さんが「可笑しみ」とおっしゃったとおり、選挙は人間の欲望がもろに出てくるというか。
候補者の隣にいると、毎日何かしらの要求や要望をぶつけてくる人に出会うんです。選挙って立候補する人だけじゃなく、そのまわりも含めた人間模様のドラマが面白い。
プチ鹿島 そうなんです。熱量のある人たちがおかしな状態になっちゃうのが選挙という非日常。それってまさに祭りじゃないですか。
投票してから「間違えた!」と思っても、そこで終わりじゃない

──ちなみに、皆さんは自分の選挙区で投票するとき、どんなことを判断材料にしていますか?
ペヤンヌ 映画を撮るまでは、選挙公報にざっと目を通すくらいしかしていませんでした。今は、地方選挙なら自分が住む街の区政をウォッチしながら、その候補がどれだけ地域の課題を自分ごととしてとらえているか、住民の声を議会に届ける姿勢があるかどうか、自己実現のためではなく住民の生活をよくすることを第一に考えているかどうかを見ています。
私がいちばん気になるのは、その人がなぜ政治家になりたいと思ったのかという動機なんですよね。もちろん変節していく人もいるでしょうけれど、やっぱり権利欲とか権力欲じゃなくて、よりよい社会を目指している人や人権意識がある人を選びたい。ただ、それを見極めるにはやっぱり複数の情報源が必要なんじゃないかなと思いますね。ダースさんはいかがですか?
ダース 僕はそもそも「自分は間違える」ということを前提にしていて。なぜ3年とか4年の任期ごとに選挙が行われるかというと、もし投票先を間違えたとしても次の選挙で選び直す機会がきちんと担保されているからなんですよ。だから「うわ、間違えた!」と思っても、そこで終わりじゃない。
判断材料としては、自分の経験を次に生かすことを心がけています。例えば、ポスターの格好よさとか名前の読みやすさだけを見て投票した結果、えらいことになった…みたいな苦い経験が、次に選択するときの判断材料になるわけです。しかもその材料は、選挙にかかわる年数や経験を重ねるほどに増えていく。僕の場合は、そのつど自分がどう考えて、誰に投票したのかを日記のように記録しています。
それから、自分を含めた有権者からの要望に対してどんな対応をする議員なのかを見ていくことも大事。たとえ自分の考えとは違っても「そういう意見もあるなら話を聞いてみよう」となる人もいるし、全然聞かない人もいる。逆に選挙期間中は「◯◯をやります!」と宣言していたのに、いざ議員になったらまったくやらない人もいる。そうした振る舞いが見えてくるのは選挙後なので、そこを踏まえて次の選挙で判断していく。その繰り返しですね。
完璧な候補者はいない。だから次の選挙までウォッチすることが大事

プチ鹿島 人間って間違える生きものだから、自分が投票した人や、新たに議員になった人が次の選挙まで何をしているかをウォッチしていくことは本当に大事だと思います。
それから、みんな「せっかくの一票だから無駄にできない」って完璧な人を求めるけれど、完璧な人ってなかなかいない。だからダースさんが言ったように、自分が投票した理由や選挙後の状況からそのつど振り返っていくと、自分の中で点と点がつながっていくと思うんですよね。
あえて名前は出しませんが、どこかの知事選では選挙後に「あんなデマにのってしまった」「間違えた」と思っている人がいるかもしれないし、いないかもしれない。でも、そんなふうに「間違えたかも」と思える自分がいるなら、次に生かせばいい。選挙に限らず、生きていればいろんな失敗とか苦い経験ってあるじゃないですか。それと同じですよ。
ペヤンヌ 実は私も2018年の区長選挙で間違えちゃったんです。当時は、映画のきっかけになった道路の拡張問題なんて知らなかったし、特に杉並区政に不満を感じたこともなかったので、「じゃあ現職の人でいいんだろう」とたぶん当時の現職区長に投票しました。「たぶん」って言っちゃうぐらい記憶にないんですよ。
その反省もあって今にいたるわけですが、知らないでいることってすごく危険だなと思って。お二人がおっしゃるとおり、「選挙と選挙の間」をチェックしていくことも本当に大切ですよね。
ダース こと選挙の場合、「当選」「落選」という言葉の印象から、当選した議員に入れたら“勝ち”で、落選した議員に入れたら“負け”みたいなことを言う人もいますが、選挙は勝ち負けの勝負ではないということも理解しておいたほうがいいと思います。
ペヤンヌ それはすごく思います。そもそも選挙って“勝ち馬に乗る”ためのものではないし、そうではない楽しみ方やかかわり方がたくさんあるはずなので。
プチ鹿島 そうそう。勝馬に乗る必要なんてないんですよ。だって、投票は自分自身の選択なんだから。
『劇場版 センキョナンデス』
Prime Video、DMM TV、Hulu、YouTube、U-NEXTほかで配信中。
配給協力:ポレポレ東中野 配給:ネツゲン ©「劇場版 センキョナンデス」製作委員会
撮影/安川結子 画像デザイン/前原悠花 構成・取材・文/国分美由紀