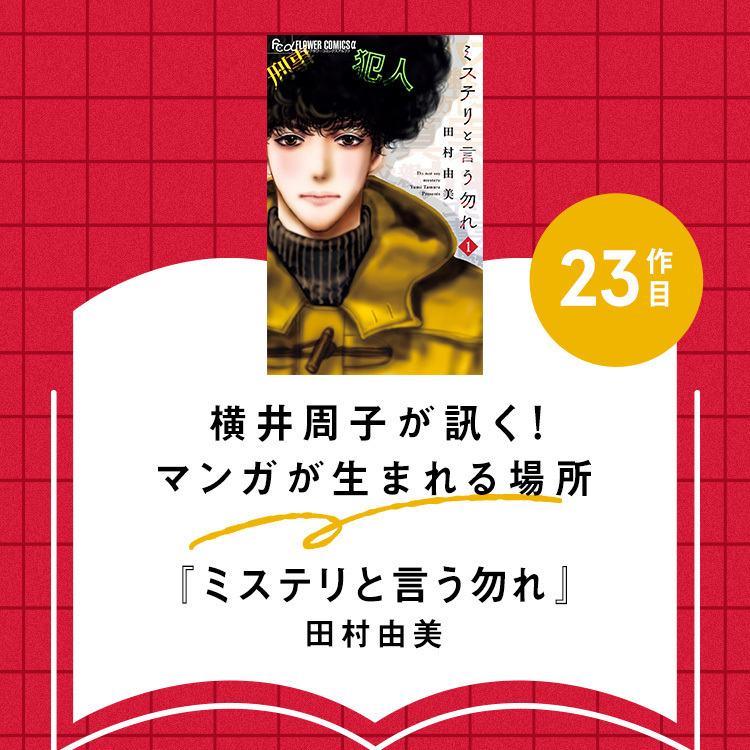独特の言語感覚とグルーヴ感で、若者の連帯と社会への抵抗を鮮やかに描く小説『みどりいせき』。その著者であり、同作で第47回「すばる文学賞」、第37回三島由紀夫賞を受賞した大田ステファニー歓人さんは、ラップで披露した授賞式のスピーチやその後のインタビューなどでも注目を集めました。今回は大田さんに、小説家になるまでの葛藤や、日々のセルフケアなどについて伺いました。


『みどりいせき』大田ステファニー歓人(集英社)
学校になじめず不登校ぎみの高校2年生の「僕」は小学校時代にバッテリーを組んでいたピッチャーの 春と再会し、知らないうちに怪しいビジネスの手伝いをすることに。隠語と煙で充満する隠れ家でグミ氏やラメちたちとつるみ、不健全で抗いがたい、鮮烈な青春にまみれていく——。
小説なんてなんでもアリ。自分も“いろんなやつ”の一部になっていいでしょ
——最初に、大田さんが小説を書き始めたきっかけについて教えていただけますでしょうか。
大田さん 明確なきっかけよりも、何かを作りたいという気持ちがずっとありました。学生時代は友達と音楽をやったり、映画を作ったりしていたんですけど、集団作業が自分的に厳しいことがわかってきて。映画専門の大学に進んで日常的にレポートや論文を書く機会が増えたあたりから、一人で没頭して書くことの楽しさにのめり込みました。
「書く」という行為が自分にとってはセルフケアになっていたというか。心の底から思っていることを書かないとつまんないから、その過程で必然的に自分を知ることになって面白かったんですよね。
大学3年生くらいのときにいろんな人から「将来どうするの?」と聞かれるようになって、正直鬱陶しかったから適当に「小説家っすかねー」って答えてたんですけど、言ったからにはなんかやってみようと。それで書き始めた感じっす。
——そんなノリで始まったんですね。すぐに書きたいテーマは決まりましたか?
大田さん テーマというよりはスタイルですね。「何を書こう」よりも「どう書こう」ということにずっと意識が向いていました。いろんな小説の文体やスタイルを見て「あ、こういう書き方するんだ。おもろ!」と思いながら読んでいましたね。
——影響を受けた作品はあるのでしょうか?
大田さん 音楽でいうと「ザ・ブルーハーツ」と「ザ・ハイロウズ」。特に中学時代は彼らの歌詞が刺さりまくってました。小説は丁寧にきれいな文章で書かれたものより、書いてる人のエキスやセンスがそのまま出てる作品が好きっすね。
川上未映子さんとか町田康さんのクセ強文章とか。あと「こういうふうな思考で小説書く人もいるんだ」って知ったのは保坂和志さんの本を読んでから。いろんな人の作品を読むうちに、「小説なんてなんでもアリ。自分も“いろんなやつ”の一部になっていいでしょ」って思えた。その発見が書くときの支えになりました。

——大田さんの作品を読むと、自分の中からにじみ出てくるものをストレートに書こうという意識を感じます。
大田さん 自分より先に伸び伸びと小説を書いたり、映画を作ったり、音楽をやってる人の作品を見て育ったから、自分もそうありたいって思えたのかも。信念を持って今の文体を書いているというよりも自然とたどり着いた気がします。誰かと比べてどう書くかということは意識しないっすね。さすがに後から自分で読んで意味がわかんないものは消しますけど(笑)。
嘘の自分で人に好かれてもしょうもない。適当に生きてくのが苦しくなったから、変わっていった

——作品だけでなく大田さんご自身も、自分に対して正直でいらっしゃる印象を受けます。そういった態度は以前から意識せずともできていましたか?
大田さん どうだろう…。今より若い頃は、いつも嘘ばっかついてたんですよ。人を笑わせるのが好きだったから、面白いことが優先で事実はねじ曲げてもいいって思ってたっすね。呼ばれた飲み会では、その場が盛り上がるようなテキトーな話をずっとしてた。
でも、たまに飲んでないときに真面目な話をすると、「急にどうした?」みたいに言われて、「いやいや、これが本当の自分なんだけど」みたいに、だんだんと本当の自分を誰も知らないことに、虚しさを感じるようになって。その頃から嘘の自分で人に好かれてもしょうもないって思い始めた。適当に生きてくのが苦しくなったから、変わりたくなったって感じですかね。
あと、自分を包み隠さず表現をしてる人の作品が刺さり続けてきたっていうのもあると思います。音楽は虚勢を張った歌詞よりも、自分の弱さとか自分にとってのダサさと向き合って葛藤していることを隠さず書かれた詞に勇気をもらう。『みどりいせき』を書いてるときに心の支えになっていたのは、HIPHOPグループの「SCARS」。メンバーそれぞれのリリックが、自分の内面と向き合ったことをそのまま書いてるのがすごい伝わってくるんですよね。
瞑想してなかったら、もっと感情に任せて泣き叫んだり、キレ散らかしてるかもしんないっす(笑)

——「朝起きたら現世にチューニングするために瞑想をする」と過去のインタビューでおっしゃっていました。どんなきっかけで瞑想を始めたんでしょうか?
大田さん お酒を止めようと思ったときに、瞑想が助けになるかなと思って始めました。今も毎朝30分くらいの瞑想を習慣にしています。お酒を止めようと思ったのは、自分を変えたかったから。酔うと自分の気持ちが大きくなって適当なことを言っちゃうし、体に悪いし、時間もお金ももったいない。
瞑想をすると今の状況を俯瞰できて冷静になったり、心も沈められる気がします。自分、普段から悲しいことがあったらめっちゃ泣くし、イラついたら態度に出るし、あんまりコントロールできないタイプ。というか押し殺す気もない。だから瞑想してなかったらもっと感情に任せて泣き叫んだり、キレ散らかしてるかもしんないっす(笑)。
ゴミの収集はめっちゃ社会貢献だし、公共性マックスみたいな
——普段はゴミ清掃員の仕事を終えてから小説を書いているそうですが、この仕事を選んだ理由は何でしたか?
大田さん 今は子どもが生まれて、一旦休業中なんですけど。ゴミ清掃員の仕事を始めたきっかけは、朝早いけど終業が15時前後と決まってたからっすね。小説を書くことが優先だったから、正直お金もらえるんだったら仕事は何でもいいやって最初は思ってて、空き時間多いしめっちゃ小説書けるじゃんと思って決めました。
その前にも色々仕事してた中で、営業職をしていたことあるんですが、社会にどう貢献してるのかわからなくなって辞めちゃったっす。必要のない需要を無理やり生み出して人に営業をかけてもの売って、何になるんだろうって。
でも、ゴミの収集はめっちゃ社会貢献だし、公共性マックスみたいな(笑)。やり始めたらやりがい感じました。肉体労働でキツいし、適当にゴミ出してる人もいて、そういうのは嫌になるけど、時々ゴミ袋に「いつもありがとうございます」って付箋がついていたりして、そういう人の優しさに触れられるから続けられてるのかもしれないです。
あと、ごみ収集しながら人と関わることで、小説の風通しがよくなる部分もあるんです。体感ですが住民の半分は清掃員に高圧的な態度でムカつくけど、そういう人も家族に優しかったり、職場で頼りにされてるかもしれないなって想像する。嫌な他人の見えていない側面を想像しているうちに、小説を書くときもひとつの側面で人物を書かないようにしようって気持ちになりますね。
「いやいや、俺そんないいやつじゃないよ」と言いたくなる

——すばる文学賞を受賞してから変化したことはありますか?
大田さん 自分の表現で傷つく人がいるかもしれないと考えるようになったこと。今までは自分のためだけに書いてたけど、本を出してから傷つけたくない人も傷つけるかもしれないって思うようになったし、これまでの自分の人に対する振る舞いを振り返って、いろんな人を傷つけたなって病むことがあるっす。
あと、受賞後にインタビューが増えたことで、自分が人にどう見られているかが気になるようになりました。取材って基本的に聞かれたことに答えるじゃないですか。こちらが好き勝手に話してるわけじゃない。まじめな質問がきて、それに答えたら“いい人”っぽい感じに見えちゃうわけで。それに対して「さすがです」みたいなコメントが来ると、「いやいや、俺そんなやつじゃないよ! よくない自分を出してないだけ」って思ったりします。自分の発信したことが「そのまま自分」として受け取られるから、自分の中のイメージと社会で受け取られている自分のイメージに乖離があると苦しいっす。
ポジティブな変化としては、エッセイの依頼がくるようになって、ガザの惨状を訴えたり、日常のささいなことも面白く書けそうだなって思う瞬間が増えたことですね。妻のかおりんの話を聞いてても、友達と遊んでても、小説読んでてもいつもどんなことが書けるか考えています。
——現在は、二作目執筆中と伺いました。次回作はどんな作品なんでしょうか?
大田さん 今は、妻が妊娠した男の話を書いてます。この話を書こうと思ったのは、実際に自分の妻が妊娠したというのもあるんですけど、子どもを授かってからハマスとイスラエルの戦争に、より目が向くようになっていろんな憤りや悲しみが自分の中に渦巻いたからです。
虐殺を止められないこの世界へ、今まさに子どもを放り込もうとしている夫婦の話を描こうと思いました。逆境の妊婦が出てくる話なんで、書いてて結構つらいんですけどね(苦笑)。そのダルさに向き合うのが小説家です!
撮影/Saeka Shimada 取材・文/浦本真梨子 企画・構成/種谷美波(yoi)