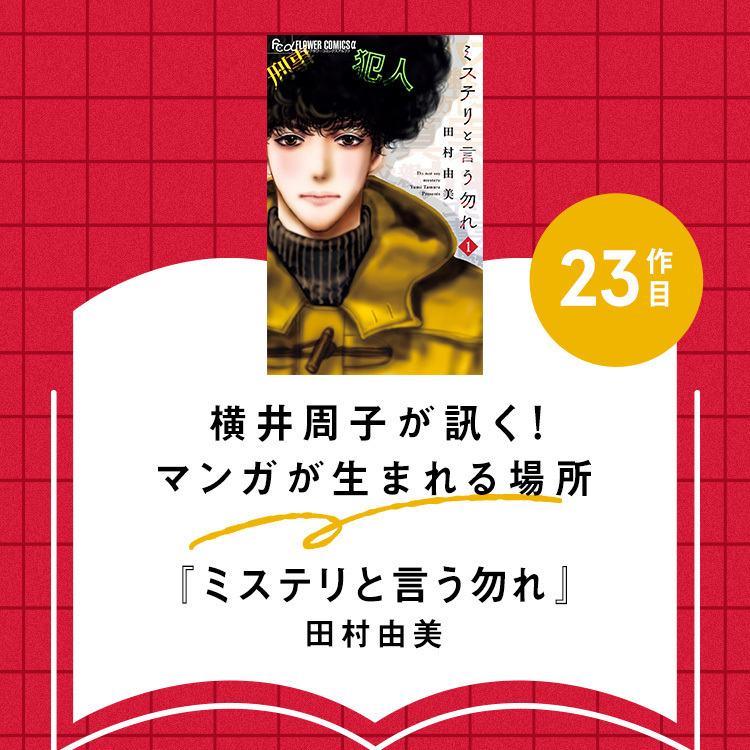Prime Videoで配信中のドラマ『1122 いいふうふ』で初めてタッグを組んだ今泉力哉さんとかおりさん夫妻。後編では、同じクリエイターとして、生活を共にするパートナーとして、3人の子育てをする戦友として、絶妙なコンビネーションを見せる二人の関係性を深掘り。

監督・脚本家
1981年生まれ、大分県出身。地元の看護大学卒業後、大阪で看護師として働くが、映画監督の夢を追い求め2007年に上京。ENBUゼミナールで映画制作を学ぶ。卒業制作の短編映画『ゆめの楽園、嘘のくに』が2008年度京都国際学生映画祭で準グランプリを受賞。初長編監督作『聴こえてる、ふりをしただけ』は、2012年ベルリン国際映画祭「ジェネレーションKプラス」部門で子ども審査員特別賞を受賞した。ドラマ『1122』では脚本を担当。
『1122 いいふうふ』STORY
フリーランスのウェブデザイナーとして働く一子(高畑充希)と、文具メーカーで働く二也(岡田将生)は、結婚して7年目を迎えた気の合う夫婦。何でも話せる親友でもあり、側から見れば羨ましいほど理想的なパートナーだが、実は性生活は2年もストップしている。彼らの結婚生活は“婚外恋愛許可制”の公認という、秘密の協定によって支えられていた…。2024年6月14日からPrime Videoにて世界独占配信。
変に気を遣うことなく、こだわりを話せたのも楽でした(力哉さん)

──仕事の現場と家庭、共に過ごす時間が長かったのではないかと想像しますが、お互いに気持ちよく過ごすためのルールや距離感などは意識されていたのでしょうか?
力哉さん 特にないですね。俺は基本的に喫茶店とか家とは違う場所じゃないと仕事ができないので、ずっと家で一緒に作業することもなかったし。あなたは作中の一子(いちこ)みたいに、リビングのテーブルで脚本を書いていたよね?
かおりさん そうだね。私は子どもたちが学校に行ってから帰ってくるまでの間を執筆時間と決めていたから。ただ、当時は夫が別の作品の撮影もしていたので、あまり家にいなくて。帰ってきたときに脚本を見せて相談する感じでした。
力哉さん 妻とは変に気を遣うことなく、こだわりを話せたのも楽でした。脚本に対して提案や相談をしたときに「監督に言われたから直します」じゃなくて、「ここは絶対に残したほうがいい」というやりとりができる。
もちろん、そういう人だと思うから依頼したし、自分の場合は普段一緒に仕事をする脚本家の方たちとも対等に話せますが、脚本家と監督の関係ってどうしても“監督が絶対”になってしまうケースもあると思うので。
脚本とでき上がった作品がガラリと違うものになるのは、やっぱり面白いですね(かおりさん)

──監督は普段から、かおりさんに作品について相談するとおっしゃっていましたね。
力哉さん 彼女はそんなに優しくないというか、“イエスマン”ではないので、意見を言われた瞬間は「何くそ!」と思うこともあるんですけど(笑)。指摘はいつも的確です。しかも基本、俺の作品を観ていないんです。そこがいいんです。いい意味で興味がない。
かおりさん 子どもがまだ小さかった頃は、なかなか映画を観る時間を確保できなくて(笑)。ただ、『街の上で』とか『窓辺にて』とかは観ています。
力哉さん 『窓辺にて』では、物語の終盤に稲垣吾郎さん演じる主人公が妻の浮気相手と会うシーンが出てくるんです。実はあのシーンは、「二人は会わなくていいの?」と妻に言われて追加したシーン。結果的に作品にとってプラスになったし、その場面を評価されたりもして。さすがだなと思いました。
──お互いのクリエイターとしての魅力を、どんなところに感じていますか?
力哉さん 妻が過去に撮った2本の映画がめちゃくちゃ面白いんですよ。自分はどちらかというと、“今までにないものを”って感覚でつくりたいタイプ。でも彼女は映画学校のシナリオの授業で学んだ基本に忠実に、物語の起承転結をしっかりつくるタイプですね。
かおりさん 彼の作品は“間”をすごく大事にするので、絶妙なタイミングで笑いを生み出したり、強弱をつけるのが上手いなと思います。私は脚本のストーリーがすごく好きだけど、彼はたぶん脚本よりも演出が好き。
『1122 いいふうふ』でいえば岡田将生さんが原作とは少し違う二也(おとや)を演じたように、彼は役者の持ち味を最大限生かしている気がするんです。自分がこうしたい、というこだわりよりも、俳優の魅力に合わせて演出している印象があります。脚本とでき上がった作品がガラリと違うものになるのは、やっぱり面白いですね。
力哉さん 俺は作品の中にいる人さえ生き生きしていればいいと思っています。だから、俺は自分を脚本家だと思ったことはなくて。自分で書いた脚本はあくまで設計図で、それをもとにいろんな人の力を借りて面白くできるのが、映画とかドラマのよさだから。
彼女は「脚本家」というより「監督」だなってことがわかったんです(力哉さん)

──『1122 いいふうふ』での共同作業を経て、今後、お二人でまたタッグを組む可能性は?
力哉さん それはちょっとわからないです(笑)。というか、やりたくないわけじゃなくて、一緒に仕事をしてみて、やっぱり彼女は「脚本家」というより「監督」だなってことがわかったんです。明確なビジョンも意見もありますし。
彼女が2012年に監督した『聴こえてる、ふりをしただけ』は、ベルリン国際映画祭で賞を受賞しています。当時、彼女が映画祭に行っている間、俺は家で自主映画の脚本を一生懸命書いていて。「俺は今、何をやってるんだろう」ってちょっと涙出ましたもん。なんだか悔しくて。嫉妬していました。
──同じ土俵に立つクリエイター同士の葛藤もありそうですね。
力哉さん でも、扱っているジャンルが違ったことは救いですね。同じジャンルで差異を見せつけられていたら、俺、たぶんやめていたかもしれない。
ただ、妻に対しては「この業界に戻ってきてほしい」「彼女が監督した作品を観たい」という思いがつねにあったので、ようやく自分が仕事で食べられるようになって、彼女がこの世界に戻ってきてくれたことが本当にうれしいです。
かおりさん 子育ても看護師の仕事も楽しかったんですけど、もともと映画の世界に行きたかったので、彼が作品をつくることで「まだ映画の世界とつながっている」という安心感がありました。そのことは救いでしたね。
彼は「いつも楽しく過ごしてほしい、幸せでいてほしい」と思う相手(かおりさん)

──いいバランスですね。改めて、お互いの存在を言葉にしていただけますか。
力哉さん 愛情はもちろんありますけど、尊敬できる人。他の人にはない視点だったり、俺に対するいい意味での興味のなさだったり、そういうことも含めて15年も一緒にいられるのかなと思います。
かおりさん 「いつも楽しく過ごしてほしい、幸せでいてほしい」と思う相手。自分が産んだ子どもはかわいいし、絶対に幸せになってほしいと願っていますが、彼に対しても同じように思います。それはやっぱり、家族だからなのかな。
力哉さん そうか…。やばいですね。ちょっと泣きそうです。仕事が全然なかった時期も、「映画やめたら?」とは一度も言われたことがないんですよ。そこはありがたかったですね。去年までしばらく撮影が続いていたので、今年は長期の仕事をしないで家でゆっくり過ごそうと決めているんです。でも、自分で休むと決めたはずなのに、いざ家に数日間いると、めっちゃ不安で。
かおりさん 休めない人になっちゃってるよね。
力哉さん 無趣味だからね(笑)。

撮影/天日恵美子 取材・文/松山梢 企画・構成/国分美由紀