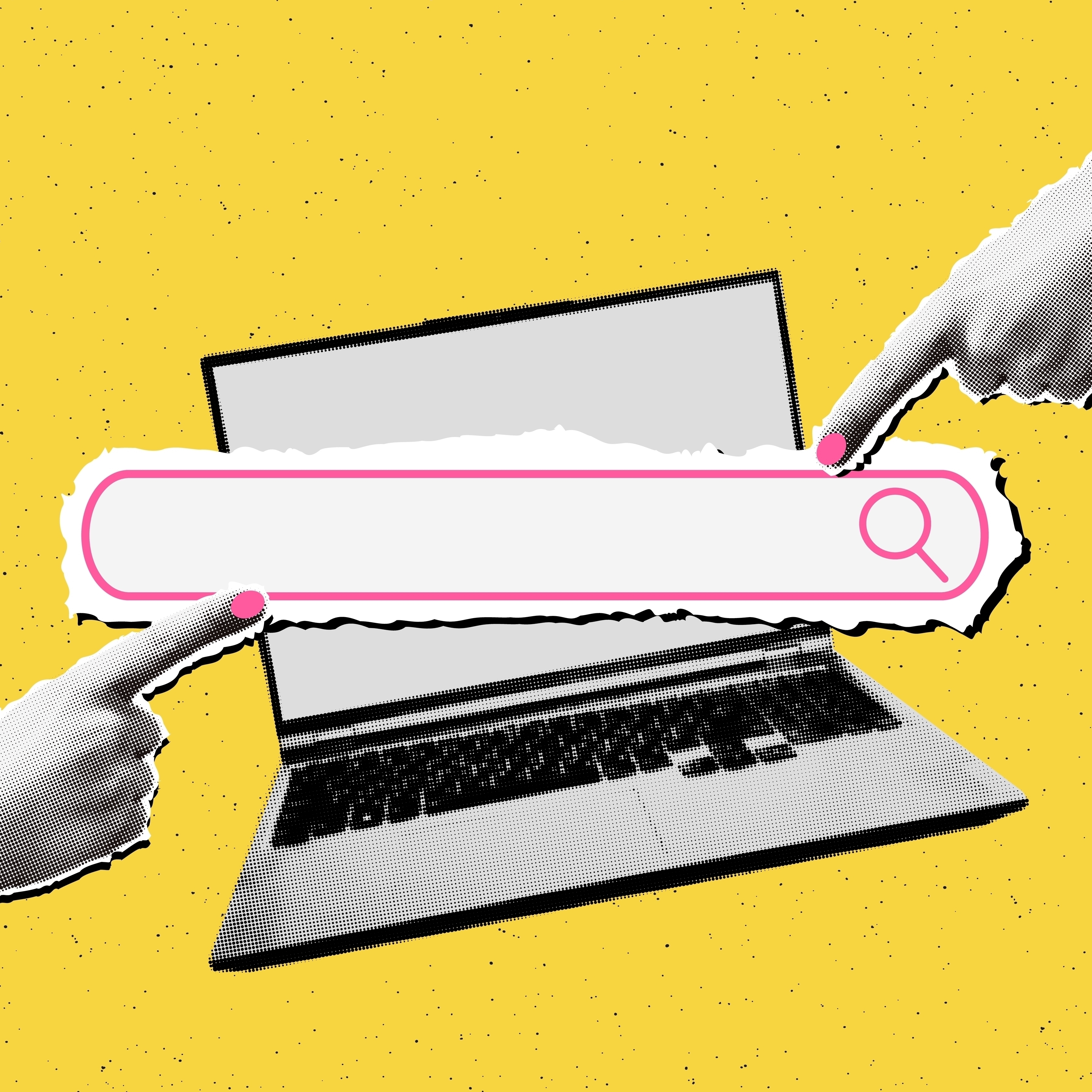「比例代表制」ってどういうこと? 一票の重さは誰でも同じ? そんな選挙にまつわる疑問について、25年以上にわたり選挙取材を続けるフリーランスライターの畠山理仁(みちよし)さんと、弁護士の三輪記子(ふさこ)さんに教えていただきました。
- Q1.「選挙権」と「被選挙権」は違うもの? なぜそれぞれの年齢が違うの?
- A1.「『選挙権』は自分たちの代表を選ぶ権利、『被選挙権』はみんなの代表に立候補できる権利です」(三輪記子さん)
- 〈被選挙権を行使できる年齢〉
- Q2.日本で暮らしている(納税している)のに投票権がない人もいると聞いたのですが…それって不公平では?
- A2.「自分たちの国の政治について決める権利なので、日本国籍を持つ人に限られています」(三輪記子さん)
- Q3.選挙でよく見かける「小選挙区制」と「比例代表制」にはどんな違いが?
- A3.「小選挙区制は『候補者』に、比例代表制は『政党または候補者』に投票する制度です」(三輪記子さん)
- ◆小選挙区制
- ◆比例代表制
- Q4.衆議院議員選挙だと、選挙区で落選したはずなのに「比例復活」する候補がいることにモヤッとします
- A4-1.「比例復活はより多くの民意を反映させるための制度。逆の立場になって考えてみてください」(三輪記子さん)
- A4-2.「疑問に思ったことは、選挙に出る候補者に伝えてみましょう」(畠山理仁さん)
- Q5.無所属の候補と政党に所属している候補の違いは? それぞれのメリット・デメリットも知りたいです
- A5.「無所属は自由度の高さ、政党への所属は傾向のつかみやすさがメリットです」(畠山理仁さん)
- ◆政党に所属している場合
- ◆無所属の場合
- Q6.一票の格差問題が気になります。どこでも、誰でも票の重さは同じといえるのでしょうか?
- A6.「残念ながら同じとはいえません。どうしたらいいのか、私たち有権者も考えていく必要があると思います」(三輪記子さん)
- Q7.政党は違うのに同姓同名の候補者がいる場合、投票用紙に書くのは名前だけで大丈夫?
- A7.「年齢や政党名を書くケースも。記載台にある一覧表をしっかり確認しましょう」(畠山理仁さん)
- Q8.「白票(白紙投票)も意思表示」という人もいるけれど、それって本当ですか?
- A8-1.「残念ながら、意思表示としてはどこにもカウントされません」(三輪記子さん)
- A8-2.「白票や棄権は、『選挙結果を無条件に後押しする』という強烈な政治行動。そして結果の責任は自分に重くのしかかります」(畠山理仁さん)
- Q9.いろいろなことがネット上で完結できる時代なのに、オンライン選挙はなぜ導入されないの?
- A9.「公平性が保たれ、一人一人の権利が大切に守られるのであれば、実現される可能性はあると思います」(畠山理仁さん)
- Q10.長期の出張や旅行はもちろん、住民票がある場所から離れていて投票に行けないとき、何か方法はありますか?
- A10.「あります! 期日前投票や不在者投票を利用しましょう」(畠山理仁さん)
- 【期日前投票制度】
- 【不在者投票制度】

フリーランスライター
1973年生まれ。『週刊プレイボーイ』(集英社)の連載「政治の現場すっとこどっこい」を担当したことをきっかけに選挙取材を始める。2017年に『黙殺 報じられない"無頼系独立候補"たちの戦い』(集英社)で第15回開高健ノンフィクション賞を受賞。2021年には『コロナ時代の選挙漫遊記』(集英社)で咢堂ブックオブザイヤー2021の選挙部門大賞。2023年にはその選挙取材に密着したドキュメンタリー映画『NO 選挙,NO LIFE』が公開され、話題となった。ニコニコ生放送「畠山理仁チャンネル」配信中。

弁護士
外交官志望から弁護士の道へ進み、離婚、遺産分割、犯罪被害者、セクハラ・パワハラなどにまつわる事件の弁護を多数手がける。2022年に「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」を開設。テレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。
Q1.「選挙権」と「被選挙権」は違うもの? なぜそれぞれの年齢が違うの?

Viktoriia_M/Shutterstock.com
A1.「『選挙権』は自分たちの代表を選ぶ権利、『被選挙権』はみんなの代表に立候補できる権利です」(三輪記子さん)
「選挙権」とは、日本国籍を持つ人が18歳になると与えられる、選挙で自分たちの代表を選ぶ権利のこと。2016年6月19日から18歳に引き下げられました。そして、「被選挙権」はみんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に立候補できる権利を指します。ただし、被選挙権の行使については、選挙の種類によって権利行使の最低年齢が異なるなど、選挙権とは違う制限があります。
〈被選挙権を行使できる年齢〉
・満25歳以上:衆議院議員、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員
・満30歳以上:参議院議員、都道府県知事
NO YOUTH NO JAPANと日本総研の共同プロジェクト「YOUTH THINKTANK」の「被選挙権年齢に関する調査」によると、明治時代に選挙制度を創設する際、当時の欧米各国では選挙権年齢を21~25歳以上、被選挙権年齢を25~30歳以上とするのが主流だったことから、それにならって選挙権を満25歳以上、被選挙権を満30歳とした経緯があるのだそう。
過去20年の間に被選挙権年齢を引き下げる国も増え、OECD加盟国では選挙権年齢と被選挙権年齢を「満18歳以上」で統一する国が過半数を占めています。
参考:総務省「なるほど!選挙」、YOUTH THINKTANK「被選挙権年齢に関する調査」
Q2.日本で暮らしている(納税している)のに投票権がない人もいると聞いたのですが…それって不公平では?
A2.「自分たちの国の政治について決める権利なので、日本国籍を持つ人に限られています」(三輪記子さん)
日本国憲法において、日本国籍を持つ国民には政治に参加する権利「参政権」が定められています。なぜ日本国籍を持つ人だけに参政権があるかというと、日本では国民が選んだ代表者によって国政が運営されるので、自分たちの国の政治について決める権利を、日本国籍を持たない人には与えられないという考え方です。
そのため、戦後の歴史的な経緯から日本国籍はないけれど在留資格がある「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人、台湾人)や10年以上日本に在留していて一定の要件を満たす「一般永住者」は、長く日本に暮らして納税していても参政権は認められません。
ただ、地方自治体によっては、条例で特別永住者や一般永住者に住民投票の資格を認めているケースもあります。このように、国政と地方自治とでは別に考える条例がすでに存在しており、国政と地方自治とで同じように考えなければならないわけではありません。
そして現在、日本に住んでいて日本国籍を有する人は、日本国籍を持たずに日本で暮らす人に対して「マジョリティ」の側になります。日本国籍を持たない人たちへの対応や規制に関する政治的な判断が自分たちの選択によって決められるということは忘れないほうがいいと思います。
日本において、外国人と日本人とを比較すると日本人は「マジョリティ」ですが、さまざまな政治的論点を検討するにあたっては、自分自身が「マイノリティ」に属することもあるので、自分が「マジョリティ」だからといって「マイノリティの権利を無視してもいい」ということにはならないのです。
Q3.選挙でよく見かける「小選挙区制」と「比例代表制」にはどんな違いが?
A3.「小選挙区制は『候補者』に、比例代表制は『政党または候補者』に投票する制度です」(三輪記子さん)
◆小選挙区制
「選挙区制」とは、有権者が応援したいと思う候補者の名前を投票用紙に書いて投票し、もっとも得票数の多い人が当選する制度。各選挙区につき一人が当選する仕組みを「小選挙区制」といい、衆議院議員選挙で採用されている。ひとつの選挙区から二人以上が当選する場合を「大選挙区制」といい、参議院選挙で採用されている。
◆比例代表制
政党ごとの得票率に比例して議席を分配する制度。衆議院議員選挙と参議院議員選挙で制度が異なる。
【衆議院議員選挙:拘束名簿式比例代表制】
・有権者は投票用紙に応援したい「政党の名前」を書いて投票する。
・各政党は事前に決めた候補者の名簿(当選順)を作成し、得票率に応じて獲得した議席の数だけ、名簿の上から順に当選者が決まっていく。
・選挙区は全国11のブロックに分けられる。
・選挙区に立候補した候補者でも比例代表に立候補できる「重複立候補」が認められているため、小選挙区で落選しても名簿に記載された順位と政党の得票数によっては比例代表制で復活当選(比例復活)できる場合もある。
【参議院議員選挙:非拘束名簿式代表制】
・有権者は投票用紙に応援したい「候補者の名前」または「政党名」を書いて投票する。
・各政党は事前に候補者の名簿(五十音順)を作成し、原則として得票数が多い候補者から順に当選する。そのため、応援している候補者がいる場合は、個人の名前を書いて投票しないと得票数に反映されない。
・比例代表の選挙区は日本全国。つまりどの選挙区でも候補者の顔ぶれは同じ。
・参議院議員選挙の場合、「選挙区」の候補者と「比例代表」の候補者は別なので、比例復活は不可能。
・2018年に改正された公職選挙法で「特定枠」が導入され、非拘束名簿とは別に、政党が優先的に当選させたい候補者の名簿を順位付きで提出できるようになった。
参考:総務省「第27回参議院議員通常選挙」
Q4.衆議院議員選挙だと、選挙区で落選したはずなのに「比例復活」する候補がいることにモヤッとします

SofART/Shutterstock.com
A4-1.「比例復活はより多くの民意を反映させるための制度。逆の立場になって考えてみてください」(三輪記子さん)
そもそも比例代表制が設けられた理由は、死票(落選した候補に投じた票など、当選には直接関係しない票)を減らして、多様な意見の代表者を議会の場に送るためです。
例えば、ある小選挙区に候補者が2人いて得票率が51:49で決まった場合、落選した候補に投票した49%の人たちの民意がないものにされかねませんよね。比例復活には、「より多くの民意が反映される」というメリットがあります。
なぜ自分がモヤっとするのか、それは制度に対してなのか、比例復活した候補者に対してなのか、その理由もぜひ考えてみてほしいと思います。もし逆の立場なら「比例復活があってよかった」と考える人もいるはずなので。
A4-2.「疑問に思ったことは、選挙に出る候補者に伝えてみましょう」(畠山理仁さん)
比例復活に違和感を覚える人は、そもそも少数意見の立場からも候補者を送り出せる制度であることを思い出してください。自分がどちらの立場になるかわからないからこそ、公平なシステムとして存在することを理解してほしいと思います。自分が勝つためだけのシステムを考えるのは不公平ですから。
もちろん、「制度を変えたほうがいい」という考えや提案を持つのは健全なことなので、疑問に思ったことは候補者に伝えていくことが大事。それが社会にとって必要であれば、「議論して形にしていこう」という流れにつながることもあります。
Q5.無所属の候補と政党に所属している候補の違いは? それぞれのメリット・デメリットも知りたいです
A5.「無所属は自由度の高さ、政党への所属は傾向のつかみやすさがメリットです」(畠山理仁さん)
両者のメリット・デメリットは、選挙戦や政策、議員活動などさまざまな観点から考えられますが、今回は政策的な観点からお話ししたいと思います。
◆政党に所属している場合
【メリット】
・政党は商品でいうとメーカーのようなもの。所属する候補者は政党からいわゆる“お墨つき(公認)”を得られた状態。公認を得るには、各政党の考え方にある程度沿っていることが前提なので、例えば「自民党ならこういう考え方の人だろう」と傾向をつかむことができる。
・法案などを決める議決の際、政党が「我々の党はこういう方針だから、議決には賛成(もしくは反対)しなさい」という党議拘束(党の方針に従うよう義務付けること)をかけることがある。党の政策を知ることで当選した後の行動がある程度予測できるので、投票先を選択するひとつの指標になる。
【デメリット】
・テーマによっては自分は党の考えや方針に反対であっても、党議拘束などの場面では自由に動くことができず、有権者の思いを背負って議員となった自分の意志を曲げなければならないこともある。
◆無所属の場合
【メリット】
・最大のメリットは自由度の高さ。党議拘束がないので、有権者からの声をビビッドに政策などに反映できる。
・候補者の基本的な考えとは違っていても、有権者からの要望が強い問題や政策は「社会のために、こういう判断をしたほうがいいだろう」と有権者の側に立った判断ができる可能性がある。
【デメリット】
・政策などの方針は本人が決めるため、政党に所属する人と比べると客観的な第三者の視点が少くなりやすい。そのため、意見のブラッシュアップがされにくく、多角的な視点を持ちづらいこともある。ただ専門分野があれば、その人にしか出せない政策もあるので悪いことばかりではない。
Q6.一票の格差問題が気になります。どこでも、誰でも票の重さは同じといえるのでしょうか?
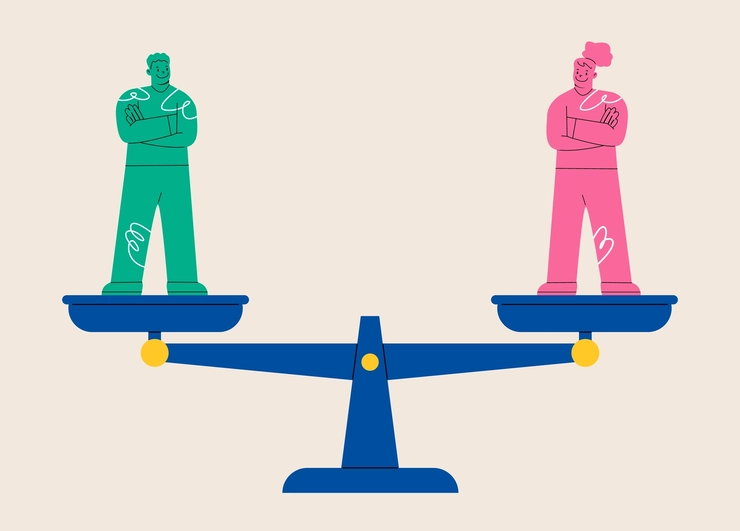
Stranger Man/Shutterstock.com
A6.「残念ながら同じとはいえません。どうしたらいいのか、私たち有権者も考えていく必要があると思います」(三輪記子さん)
一票の格差とは、「有権者が持つ一票の重みに地域差が出ること」。選挙区の人口によって、議員一人あたりの有権者数が異なることなどが原因です。現状の制度では、選挙区の人口が多い地域ほど一票の価値が軽くなっています。2024年の衆議院議員選挙では、選挙区によって最大で2.06倍の格差がありました。
一票の格差については、選挙のたびに「有権者の権利が不平等である」ということで必ず訴訟が起きていますし、私も「同じ」とはいえないと思います。ただ、いまある仕組みの中で単純に一票の重さを同じにしようとすると、人口の多い地域が「多数派」となり、構造に歪みが生じるという問題もあります。
一番の問題点は、平等を前提とした選挙制度において格差が生まれているということ。それを是正するには、今までとは違う制度の構築が必要だろうと思います。
選挙制度は、これまでも時代にあわせて変化してきました。選挙区の設定変更など、一票の格差を縮めるための研究をしている人もいます。制度設計には時間もかかりますが、一票の重さを近づけていくためにどうしたらいいのかを有権者も考えていく必要があると思います。
Q7.政党は違うのに同姓同名の候補者がいる場合、投票用紙に書くのは名前だけで大丈夫?
A7.「年齢や政党名を書くケースも。記載台にある一覧表をしっかり確認しましょう」(畠山理仁さん)
投票用紙を記入する記載台には毎回、候補者の一覧表が掲示されていますよね。もし同じ選挙区内に同姓同名の候補者がいた場合、選管(選挙管理委員会)が区別をつけるための表記を考えて、一覧表に記載します。
例えば、名前だけでなく政党名を書く、候補者の年齢を書くなど、違いがわかるような記載例が表記されているので、それを見て記入することが大切です。というのも、どちらの候補者に入れた票なのか判別できない書き方の投票用紙は「按分(あんぶん)」といって、確定した得票率に応じて分配されてしまいます。
自分が望んでいないほうの候補者に票が入ってしまうこともあるので、かならず一覧表と同じ書き方をしましょう。また、投票用紙に「頑張れ!」「絶対当選!」など候補者名以外のことを書くと無効票になってしまうので気をつけてください。
Q8.「白票(白紙投票)も意思表示」という人もいるけれど、それって本当ですか?
A8-1.「残念ながら、意思表示としてはどこにもカウントされません」(三輪記子さん)
白票を投じる人を全面的に否定する気にはなれないし、「選びたい人がいない」という気持ちもわかるけれど、白票を投じた人の意思はどこにもカウントされません。結果として、たとえ消極的であっても現状を支持することになってしまいます。
A8-2.「白票や棄権は、『選挙結果を無条件に後押しする』という強烈な政治行動。そして結果の責任は自分に重くのしかかります」(畠山理仁さん)
基本的に選挙権を使うも捨てるもご本人の意思なので、僕は尊重したいと思います。ただ、選挙権を捨てることによって何が起こるかはお伝えしておかないといけない。最近は、選挙運動をしたり、政治的思想を話したりすることを「思想強い」と揶揄する声もありますが、実は選挙に行かないことも強烈な政治行動です。
投票は、社会を自分のほうに引き寄せていくための意思表示ですから、白票や棄権によって意思表示を放棄することは、「選挙結果を無条件に後押しする」という強い意思表示。なおかつ選挙結果を見て、「今回の選挙は失敗だった」と思ったなら、その責任は意思表示をしなかった自分に重くのしかかってくる、ということも自覚してほしいと思います。
もちろん白票を投じる理由はいろいろあるはすです。ただ、そもそも「この人に入れたい!」と思える候補者に出会える確率ってものすごく低いんです。例えば、2022年の参議院議員選挙で立候補した人は、被選挙権を持つ有権者の約16万人に一人という計算になる。その人たちと自分の意見が完全に一致するなんて奇跡じゃないですか。
もしこれが買い物なら「欲しいものがないから買わない」という選択肢があるけれど、選挙の場合は候補者に所得の50%近い参加費(税金)を預けることが決まっている。つまり、白票は「お金は払ったけど商品が手元に届かない」状態。自分が預けるお金の使い道に意思表示をしなくていいんですか?と思いますね。
Q9.いろいろなことがネット上で完結できる時代なのに、オンライン選挙はなぜ導入されないの?

Mary Long/Shutterstock.com
A9.「公平性が保たれ、一人一人の権利が大切に守られるのであれば、実現される可能性はあると思います」(畠山理仁さん)
セキュリティ面でいうと、本人確認の問題があります。それから、どこでも投票できるのは便利な反面、例えば「この候補に入れるところを見るまで解放しない」とどこかに閉じ込められたり、会社で「今からみんなで順番に投票するぞ」と強制されたりする危険性がある、というのが導入に消極的な人たちによく見られる意見です。
エストニアなど、すでにオンライン投票を導入している国もありますが、日本より人口が少ないから実現できている面もあります。大事なのは、オンラインだけでなくリアルでも投票できることや、開票日前であれば投票し直すことができることなど、制度として本人の自由な投票が担保される仕組みづくり。
第三者が立ち会う投票所のように不正が行われにくい公平性が保たれ、一人一人の権利が大切に守られるのであれば、実現される可能性はあると思います。日本でもし導入されるとしたら、仕事や留学などで海外に暮らす方が海外にいながら国政選挙に投票できる「在外投票」からではないでしょうか。
現状の在外投票は、申請から投票までに手間も時間もお金もかかります。国内でも、外出が難しい方や入院されている方など、さまざまな事情で大切な権利を行使できない人がいます。そうした人たちの声を届けるためにも、有権者が政治家に対して働きかけていくことが必要です。ただ、一番の理由は「オンライン投票を導入しよう」と訴える政治家が当選していないことだと思います。
Q10.長期の出張や旅行はもちろん、住民票がある場所から離れていて投票に行けないとき、何か方法はありますか?
A10.「あります! 期日前投票や不在者投票を利用しましょう」(畠山理仁さん)
投票権は大切に保護された権利なので、投票できない事態が起こらないように法的にも制度的にも手立てが取られています。投票日に行けない人は「期日前投票」、住民票がある場所に行って投票するのが難しい人や選挙期間中に不在の人は「不在者投票」を利用しましょう。
【期日前投票制度】
投票日の前日まで、投票日と同じ方法で投票を行うことができる仕組み。住民票登録がある市区町村での投票が対象。
・投票期間
公示日または告示日の翌日から、投票日前日まで。
・投票場所
選挙区の役所や図書館など、各市区町村に1カ所以上設けられる「期日前投票所」。
・投票時間
8:30〜20:00。ただし、期日前投票所が複数設けられている場合、各投票所の投票期間や投票時間は異なることがあるので、事前に確認を。
【不在者投票制度】
選挙期間中に、住民票がある選挙区以外の場所に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票ができる仕組み。身体障害者手帳を持ち、対象となる障がいのある人または介護保険「要介護5」にあたる人は、郵便などを使って投票が可能。
また、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入院・入所している方などは施設内で不在者投票ができるほか、日本国外を航海する船舶に乗船する船員や、南極地域での調査業務を行う人が投票できる制度がある。
〈不在者投票の方法:選挙期間中に出張などで不在の場合〉
① 住民票がある市区町村の選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を提出
各自治体のWebサイトから「不在者投票宣誓書(兼請求書)」をダウンロードして記入し、住民票がある市区町村の選挙管理委員会に直接または郵送で提出する。自治体によってはオンラインでの請求も可能。
② 選挙管理委員会からの書類を受け取り、滞在先の選挙管理委員会へ
選挙管理委員会から郵送されてきた書類は、開封すると投票できなくなるので絶対に開封しないこと。その書類を持って、滞在先の最寄りの選挙管理委員会へ行き、指定された手順で投票する。選挙管理委員会の対応時間は事前に確認を。
不在者投票の場合、書類を提出してから投票用紙などが交付されるまでに時間がかかる場合があり、タイミングによっては投票期間に間に合わない…ということも起きかねません。選挙があるとわかった時点で、住民票がある選挙管理委員会に連絡しましょう。
また、投票所入場券がなくても手ぶらで投票できるので、ぜひ投票の機会を逃さないでほしいと思います。投票所によっては運転免許証などの身分証明書を求められることもありますが、それは相手の認識が間違っているだけ。もちろん持参していれば本人確認はスムーズにできますが、法的には証明書がなくても大丈夫。「そんなはずはないので確認してください」と言えば、本人確認に少し時間がかかるかもしれませんが投票はできます。
それから、選挙のお知らせは基本的に世帯主に送られるので、パートナーのDVから避難しているなど、さまざまな事情で世帯主と離れている場合、投票所入場券は手元に届きませんが、不在者投票などで投票できるようになっているはずです。できるだけ早めに滞在地域の選挙管理委員会に問い合わせてみてください。
参考:総務省「なるほど!選挙」
画像デザイン/前原悠花 構成・取材・文/国分美由紀