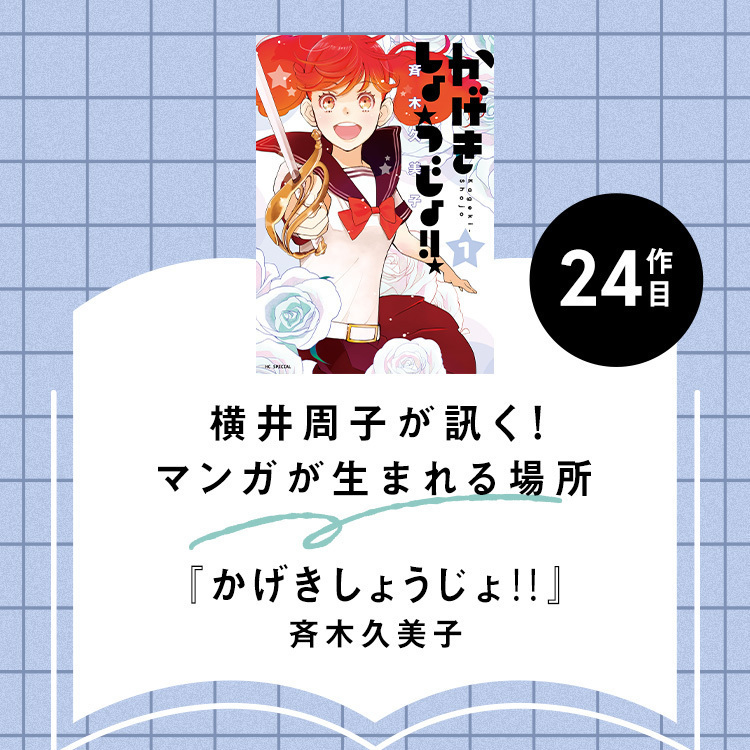「プロギング」という言葉を聞いたことはありますか? ジョギングとごみ拾いを組み合わせたスウェーデン発祥のフィットネスで、今や世界100カ国以上で親しまれているそう。3月30日の「ごみゼロ国際デー」に合わせて、エディターの長谷がプロギングを実際に体験し、その魅力をレポートします。
プロギングジャパン会長
幼い頃から自然の中で遊びながら育ち、大学4年生時には、2年間の休学をし、登山やクライミングに没頭。友人の紹介でプロギングを知り、実践していく中でプロギングに可能性を感じるように。2019年にプロギングジャパンを設立、翌20年には、一般社団法人化。「ポジティブな力で足もとから世界を変える」をモットーに、さまざまな自治体や企業、個人との協業により、社会課題を解決しながら街も人も元気にする新たな価値を生み出している。

ジョギング+ごみ拾い。世界中で楽しまれているプロギングとは?
毎年3月30日は、2022年の国連総会にて制定された「ごみゼロ国際デー」。この日をきっかけに、ごみ削減に向けた意識づくりや具体的なアクションをそれぞれが実践していくことが期待されています。
環境問題対策の重要性は頭では理解できていても、いざ、自分ごととしてアクションを起こし、継続するには、自分自身にとっての心地よさも大切なポイント。
そこで、今回紹介するのが「プロギング」です。プロギングは、ジョギングしながらゴミを拾うスウェーデン発の新しいフィットネスで、スウェーデン語の「plocka upp(拾う)」と英語の「jogging(走る)」を組み合わせた造語。
2016年にスウェーデン人アスリートのエリック・アルストロム氏によってはじまり、瞬く間に世界中に広がり、現在では100カ国以上で楽しまれているそう。
今回は、全国各地でプロギングのイベントをはじめ、日本での普及活動を行っている「プロギングジャパン」主催のイベントに参加し、会長の常田英一朗さんにその魅力を教えてもらいました。
“社会貢献しよう”ではなく、楽しむことを何よりも大切にする
──プロギングならではの魅力を教えてください。
常田英一朗さん(以下、常田):プロギングのコンセプトは「社会貢献と言わない社会貢献」で、参加のハードルを下げるため、参加する方にとっての心地よさを何よりも大切にしています。

プロギングジャパン会長の常田英一朗さん。
常田:自分自身、学生の頃から世界中でクライミングや滝登りをしていて、本当に自然が好き。そこで、何か恩返しをしたいという思いがあったのですが、デモなど環境活動に参加するのは正直、ハードルが高いなと感じてしまったんです。
そんなとき、スウェーデンに行った友人からプロギングの存在を教えてもらい、見様見真似でやってみたら結構面白くて! これなら環境活動をしながら、誰でも気負わずに集まってくれるんじゃないかと思いました。
ごみ拾いのいいところは誰でもできて、誰がやっても世界規模の効果があること。例えば、目の前のごみを拾わなかったら、それがいつか海に流れて、海洋汚染問題になり別の国の人が困るかもしれませんよね。
さらに、次々にノルマを課せられるということがないので、純粋にそのときの成果を喜ぶことができます。仕事だと、ひとつの目標を達成したら次はより高い目標の達成が求められますが、ごみ拾いなら「今日は3個なら次は10個」なんて言われたりしません。
だからこそ、ジョギングにごみ拾いをかけ合わせることで、運動効果やリフレッシュ効果はもちろん、達成感や自己肯定感も得られるし、さまざまな世代、バックグラウンドを持つ人との出会う機会が生まれます。
どうしてもネガティブな情報発信が多くなりがちな環境問題ですが、楽しさや心地よさといったポジティブな力が集まって、結果として地球環境改善につながっていくというのが、プロギングならではの魅力かなと思います。
エディターが体験!思わず笑顔になるプロギングの魅力
今回はエディターの長谷が実際にプロギングに参加。今回の参加者は20名弱でしたが、イベントによっては100名を超えることもあるそうです。
参加者は呼ばれたい名前と、お題に合わせたひと言コメント(今回は今年の目標)を名札に書き、輪になって準備体操からスタート! 基本のストレッチだけではなく、手足をバラバラに動かすような、少し頭を使う体操も入り、苦戦する参加者たちは思わず笑みがこぼれ、空気がやわらぎます。

続いて、ジョギングしながらごみをスマートに拾う方法を常田さんが伝授。
「横に回って、片足を前に出して腰を落とすと、詰まることなくスムーズに拾えます」(常田さん)。

心も体もほぐれたところで、自己紹介タイム。今回は、下は小学生、上は70代と幅広い世代の方が参加。 ご夫婦で参加している方もいれば、単身赴任でコミュニティを求めて参加した方もいて、バックグラウンドも職業も、ジョギング歴もバラバラな人が集い、互いの言葉に真剣に耳を傾け合います。

自己紹介のあとは、いよいよプロギングに出発する準備へ。軍手をつけ、ごみの種類ごとに決められた色のごみ袋を数人が持ちます。
「ごみを拾った人がごみ袋に入れるタイミングでまわりの人は『ナイス』と言いましょう!」と常田さん。 ごみ袋を人数に対して少なめにしているのは、コミュニケーションを増やすための工夫なんだそう。

今回はある程度のスピード感で走るチームと、まったり走るチームの2つに分かれて街中へ。一見、きれいに見えても、意識して見ていると、意外とあちこちにごみが落ちていることに気がつきます。

プロギングでは、拾いたいごみだけ拾うのがルール。触るのをためらうようなごみは無理して拾わなくてOK。そうすることで義務感なく楽しめると常田さんは言います。
ごみを拾うたびに「ナイス」という言葉が飛びかい、みんな笑顔に。ごみの種類によって袋の色が違うので自然といろんな人とコミュニケーションを取ることができました。

今回のコースは川沿いで、ジョギングするのにも快適な道。開放的な景色を見ながら体を動かすと同時に、街もどんどんきれいになり、気分も爽快でした!

1時間弱ゆっくりと街を巡ったら、スタート地点へバック。最後はみんなでハイタッチをして、互いを褒めたたえ合います。

2チームそれぞれが拾ったごみの重量を量り、みんなでごみをひとつにまとめていきます。拾ったごみからまた話に花が咲き、最初から最後まで、参加者の皆さんが笑顔なのがとても印象的でした。


ごみがまとまったら「ありがとうございました、よい一日を」と言って拍手で今回のプロギングは終了。
「『お疲れ様』だとボランティアになってしまうと思い、あくまでも楽しいイベントにしたいので、『ありがとうございました、よい一日を』で終えるようにしています」(常田さん)と、最後までプロギングならではの世界観を守るための工夫が散りばめられていました。
最終目標はプロギングをツールとして明るい社会を造ること
実際に体験してみると、コンセプトの通り、社会貢献をしようと意気込むのではなく、純粋にプロギングそのものを楽しむことができました。
新しいコミュニティに参加すること自体も刺激的で、ごみ拾いを介して、自然とコミュニケーションが生まれるのもプロギングの力ならではだなと実感。
「私たちの最終目標は社会を明るくすること。今の日本には、漠然とした不安感や先が見えない印象があると感じています。だけど、プロギングをひとつのツールとして、互いに褒め合って、『私もいいし、あなたも最高だよね』みたいな循環が生まれる明るい社会にできたらいいなと思っています」と常田さん。
その思いの通り、参加者はとても楽しそうで、互いを肯定し合う優しい空気感が心地よかったです。
イベントによっては、オフィス街で実施したり、観光地を巡ったり、ヨガや筋トレと組み合わせたり、アレンジがしやすいのもプロギングならでは。プロギング・ジャパンのHPでは、イベント情報を発信しているので、興味があるイベントに参加してみてはいかがでしょうか?
撮影/井手勇貴 取材・文/長谷日向子