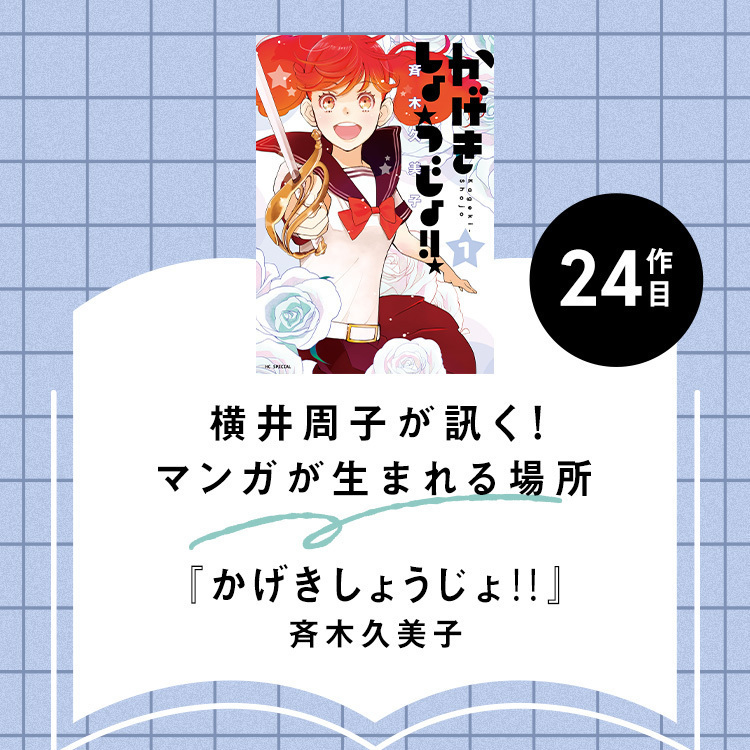スマホやPC操作、情報過多でストレスフルな環境、ヒールの高い靴…。実はこれらすべて過剰な「噛み締め」を引き起こす要因の一部。噛み締めによるあごの緊張は顔の歪みにつながり、悪化すると顎関節症や全身の不調を引き起こすリスクも。今回は「あごストレッチ」を考案した歯科衛生士の長守雅恵さんに、あごの緊張が引き起こす不調や、緩める重要性を教えてもらいました。
歯科衛生士
長守式顎関節ストレッチトレーナー。日本口腔リハビリテーション学会会員。歯科医院に10年間勤務した後、口腔ケアを専門とする「ティース・アイ富山本店」に勤務。2019年に独立し、「口腔整体療法による顎関節症の改善の取り組み」を学会にて発表。現在は「顎関節専門サロン Grace」の代表を務め、著書に『1分神あごストレッチ』(自由国民社 )。

顎関節症にもつながるあごの緊張のリスク
──あごまわりの筋肉をほぐす「あごストレッチ」を考案した長守さん。歯科衛生士でありながらあごに注目しているのはなぜでしょうか?
長守:多くの方は、口まわりだと歯並びや歯ぎしり、虫歯、歯周病など、歯にまつわることで悩み、歯科治療を検討されると思います。私自身も歯科医院で働いていた当時は、歯にばかり注目して改善をしようとしていました。
しかし、歯科衛生士で介護向けの口腔ケアに取り組んでいる精田紀代美氏に弟子入りをしたとき、舌や口腔周囲の筋肉をケアすることで高齢の患者さんの口腔内環境が整い、口まわりの悩みが改善されていくのを目の当たりにしたんです。
その経験から、舌や口腔周囲の筋肉と関係が深い「あごの重要性」に着目するようになりました。 実際、歯や歯茎などの悩みを抱えている方にあごの調子を尋ねると、10代くらいからの長年の不調を訴える方がほとんど。
にもかかわらず、皆さん慢性化していて不調の状態が当たり前になっています。
また、歯を矯正して見た目はきれいになっていても、本来のあごの動きができていないため、しっかり噛めている感じがしなかったり、体の不調は改善しないというケースも多いです。
──本来のあごの動きとはどういうものでしょうか?
長守:あごの動きはカチカチとした上下の開閉だけだと思いがちですが、実は360度全方向に動くんです。いろんな方向に動かすことができなければ、あごに「問題あり」のサインです。

あごは本来、さまざまな方向に動かすことができる。
長守:歯ぎしりで悩む人は多いですが、歯ぎしりが問題なのは過剰な力が入ってしまっているから。あご本来の動きができる状態で、歯の表面をなでるような滑らかな歯ぎしりができていれば問題ではありません(※)。
※強い歯ぎしりにより歯がたくさん削れたり、割れる、しみる、痛みが出るなどの場合は歯科受診をおすすめします。
噛むという行為自体は、幸福感が得られ、ストレス発散になり、歯ぎしりによってβエンドルフィンという快楽物質がでることがわかっています。
睡眠中の歯ぎしりは無意識ですが、日中も緊張する場面が多かったり、スマホやPCの使用で長時間猫背姿勢のままだと、歯と歯をぐっと噛むことがクセになりやすく、力の抜き方がわからなくなってしまうんです。
すると、咀嚼に関わる頭や顔の筋肉に加え、首や肩の筋肉もこり固まるほか、顎関節の血流やリンパの流れが滞り、全身の不調につながります。そして、そういった緊張状態が長年続くと、顎関節症になってしまうリスクがあります。
──顎関節症とはどういった状態でしょうか?
長守:下あごは、頭蓋骨の下に筋肉でぶら下がっている構造です。
その下あごと頭蓋骨の間には、関節円板というクッションがあり、本来は下あごの骨と一緒に動くのですが、長年の緊張状態などで、あごに負担がかかると、下あごと関節円板がずれてしまい、頭蓋骨と下あごの骨があたり、音がなったりします。
このように関節円板と下あごがうまく連動していないのが顎関節症の状態です。

あごの緊張が引き起こす、全身の不調の数々
──あごの緊張が慢性化したり、顎関節症になったりしてしまうと、どんな不調が起こりうるのでしょうか?
長守:あごの緊張が抜けず、寝ている間中強く噛み締めていると、思考をつかさどる脳の前頭葉に刺激が入りすぎて、眠りが浅くなります。
また、長年強い歯ぎしりを続け、歯がアンバランスに削れたり、上の歯が下の歯に覆いかぶさった状態になったりすると、歯ぎしりもできなくなり、結果としてグーッと同じ場所で強く噛み続けるということが起こります。
すると、咀嚼筋のひとつである側頭筋が緊張し、片頭痛の原因になるほか、頭、顔、首、肩まわりをはじめ、全身のコリや疲労感につながります。
また、あごが本来の動きができないと、咀嚼が上手にできないため、消化不良や便秘を引き起こしている可能性も。
さらに顎関節は耳の近くにあるため、耳鳴りやめまいもあごの緊張の影響を大きく受けます。もちろん、口が動きにくい状態だと唾液がでにくいので、虫歯や歯周病にもなりやすくなります。
ほかにも、二重あごやたるみ、顔の歪みといった見た目も左右するので、美容面でも顎あごの緊張をリリースするのはとても効果的です。
【あごの緊張によって起こる不調の例】
・不眠
・片頭痛
・コリ、疲労感
・胃腸の不調
・耳鳴り、めまい
・虫歯、歯周病
あごを緩めるために必要なこととは?
──あごを緩めるためには何をしたらいいでしょうか?
長守:まずはあごの筋肉を動かすこと。現代は柔らかい食べ物が増え、咀嚼の回数も減っています。たまに大きく口を開いたり、硬い食べ物を噛んだりしたら、あごが痛くなってしまったという経験はないでしょうか?
それはいわば、筋肉痛と同じ。普段使えていない筋肉が急に収縮することで、痛みにつながるのです。
逆に、噛み締めで普段から痛みを感じるところは、あごの筋肉をバランスよく使えるようになり、本来の動きを取り戻せば緩和していくはず。
顎関節症は改善が難しいのですが、あごを使うことで、関節円板につながっている外側翼突筋もほぐれ、結果として関節円板の動きもスムーズになり改善に向かう可能性があります。
そして、兎にも角にも、重要なのはストレスをためない工夫をすること。
ストレスが強いほど、それを発散しようと歯ぎしりは強くなります。思考のクセの影響はとても大きく、私の施術を受けにいらっしゃるのは、生真面目で、自分で反省会をしてしまうような方ばかり。
リラックスできる習慣を見つけて、セルフケアの時間を大切にすることもあごの緊張改善には必須なんです。
もちろん、矯正やマウスピースもいいのですが、いくら歯を変えても土台となるあごが整っていなければ根本改善には至りません。
目には見えませんが、生活習慣次第で案外、歯並びは簡単に動いてしまうんです。
歯は一度削ったら再生しません。まずはあごの緊張をリリースして土台を整えることにトライしてみてください。
イラスト/Rei Kuriyagawa 取材・文/長谷日向子