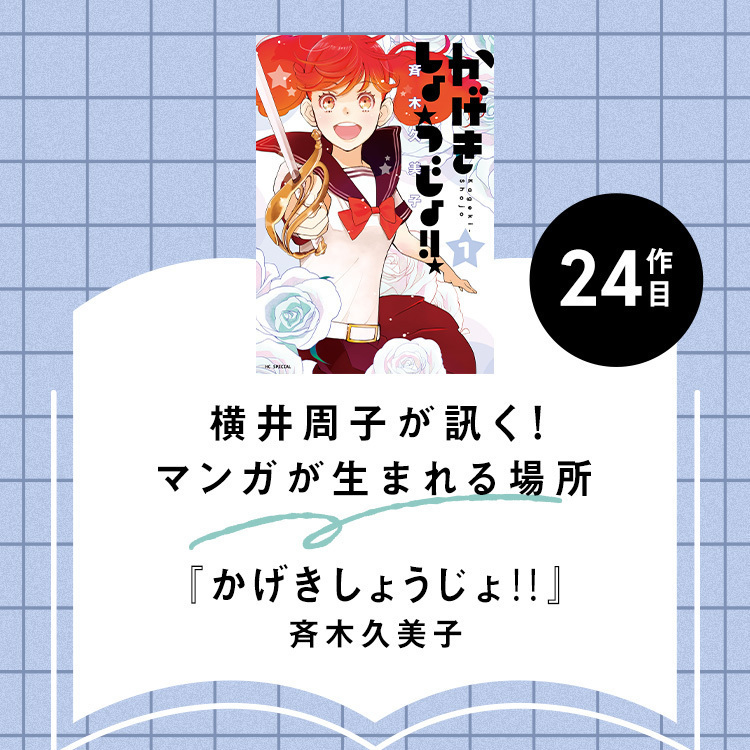ジェンダーについての記事や書籍に携わる編集者・ライターの福田フクスケさんが毎回ゲストをお迎えしてジェンダーの問題についてトークしていく連載「やわらかジェンダー塾」。Vol.12のゲストは前回に続き、批評家の杉田俊介さん。「男性とケア」をめぐる問題について、語っていきます。

男性の心身は「雑に扱っていいもの」なのか?

——今回は、福田さんが杉田さんと話してみたかったというテーマ「男性とケア」についてお話していきます。
福田さん:男性は「セルフケア」や「セルフメンテナンス」が総じて苦手な傾向にある…と思っているんですけれども、もし本当にそうなら、それは男性に特有の問題が含まれているのではないかなと。確かに、一人暮らし男性の生活ってセルフネグレクトのようになってしまうことが多い気がしています。体調管理ができなかったり、生活環境が悪化しがちだったり…。
杉田さん:確かにそうですね。その背景には「男らしさの呪縛」があるのではないかと思います。
僕は2013年末にうつ病でダウンした経験があるのですが、危機的状況にあるのにもかかわらず「男らしく早く回復しなくちゃ」と能力主義的なことを考えてしまったんですよね。一般的にも、メンタルヘルスを病んだときに、男性のほうが病院にかかりにくいといわれます。
また、ある人から聞いた話なんですが、リハビリ施設でリハビリをしている高齢男性たちが「どちらが早く回復するか」みたいな競争をするんだそうです。ケアされるべき状態に陥ったところでも、「男らしく能力を高く持たなければならない」という呪縛から逃れられない。
福田さん:自分の中の「弱さ」を認められない、あるいは認めたくないという心理ですね。「ウィークネス・フォビア(弱者嫌悪)」と呼ばれるものでしょうか。
杉田さん:男性たちは、「男は強くあらねばならない」そして、「自分の心身を雑に扱ってこそ、男は男らしい」とも思ってしまっている部分があると思います。会社のために滅私奉公するとか「組織のために自分をいかに雑に扱えるか」が男らしさの証明になる、という考えがある気がするんです。
福田さん:あくまで感覚的な話ですが、いわゆる「社畜」と呼ばれるような過重労働の内面化や、搾取への過剰適応をしてしまうのは、男性の方に多い気がします。組織に同化して生きていくためには、個人の感情なんて繊細なものは邪魔だから麻痺させたほうがいい、という考えがどこかにある。
杉田さん:また、男性を雑に扱ってきたのは、男性自身だけではありません。外からも雑に扱われてきたんです。これは保育とジェンダーの関係を研究している天野諭さんが語っていたのですが、保育園や幼稚園で、女の子の着替えは外から見られないように配慮するのに、男の子の着替えはその辺で適当に済ませてしまったり。「女の子に比べて、ちょっとぐらい雑に扱われてもしょうがないよね」という傾向があると思います。
そういった経験から、みんな「男性の身体というのは雑に扱われるものなんだ」と学んでしまったり、男性自身も「それを恥ずかしいと思っちゃいけない」と思ってしまう。
福田さん:男性自身が「男性の心身は雑に扱っていいものだ」という価値観を内面化することで、自身の心身への感受性というか解像度のようなものが下がってしまっているのかもしれませんね。だから、不調に気づいたりケアをすることが難しい。
一般に、女性より男性のほうが家事スキルや衛生観念が低かったり、病院嫌いが多かったりするのも、男性は社会からセルフケアの能力をスポイル(だめにする)されていると言っていいのかもしれません。
ケアを個人の能力としてとらえてしまうと、能力主義に取り込まれる

杉田さん:先ほどお話ししたような「男らしさの呪縛」から解放されるべきといったような話は最近よく言われるようになりましたが、そこから脱した先の「新しい男性性」とはなんなのかというのは、まだ十分に問われていないんですよね。
最近気になっているのは、ポリティカル・コレクトネス(不快感や不利益を与えないように配慮された中立的な表現や行動)的な正しさを身につけたり、自分の弱さをシェアできたり、他人の言葉を傾聴しケアできるという「男性性」が、エンタメの中だったりいろんなところで持ち上げられていること。
それ自体が、リベラルエリートのさらなる卓越化というか、マウンティングの材料になってしまっているのではないかなと。「資本主義の中の新しい男性性」として、リベラルエリートが他人と差をつけるために使われてしまっている。そこには、資本主義的な階級問題がかかわっていますよね。
福田さん:すごくわかります。「育休を取得しない男は遅れている」とか「ケア能力のない男はモテない」みたいな言い方で、リベラル的に進んでいることが新しい「男らしさ」の階級を生み出していますよね。極端な話、「俺のほうが弱音を吐けるぜ」ということでマウンティングする男が出てきてしまう。
杉田さん:ただ、そこを踏まえたうえでも「ケアする男性性」の可能性については積極的に言っていっていいんじゃないかと思っています。
ケアって「能力」だと思われることが多いと思うんですけど、僕はケアとは「関係」だと思うんですよね。ケアする能力が個人の中にあると考えてしまうと、「ケアする能力を競う」とか「誰が一番ケアできるか」という話になってしまう。
子どもが生まれた頃、うちは共働きだったんですが、僕は家で働ける環境にあったので、子育てをある程度受け持ちながら物書きをしていたんです。そうしたら、子どもがちょっと病弱だったのもあり、わりとあっさり育児ノイローゼになってしまったんです。
僕は介護の仕事をしていたことがあったので、自分はケアする能力が高いと思っていたんです。だけど、子育てを通して、そうではないことを知りました。
熱を出して寝込んでいても頑張って生きていこうとする子どもの姿を見ながら、「ケアすることとケアされること」の見分け難さにも気づいたり。ケアって主体的でも客体的でもなく「中動態的」なんだと思うんです。私であることとあなたであることが、分かち難くなっていく。
そういった経験を積み重ねて言語化していくことで、新しい男性性やあるべき男性の姿が見えてくるんじゃないかと思います。
福田さん:確かに、「ケアする能力」と言ってしまうと、スキルの優劣の話になってしまってまた新たな競争や階級を生みますが、ケアとはあくまでも「関係性」の中で築くものだと。
杉田さん:気をつけていかないと、簡単に資本主義や能力主義的な「競争」の中に取り込まれてしまう。そうすると、“男らしさ”をまた別の形で強化したり補完することになりかねない。そうならない形での、「ケアする男性像」が色々あっていいんじゃないかと思います。
男性同士の「ゆるいつながり」が自身の助けになる
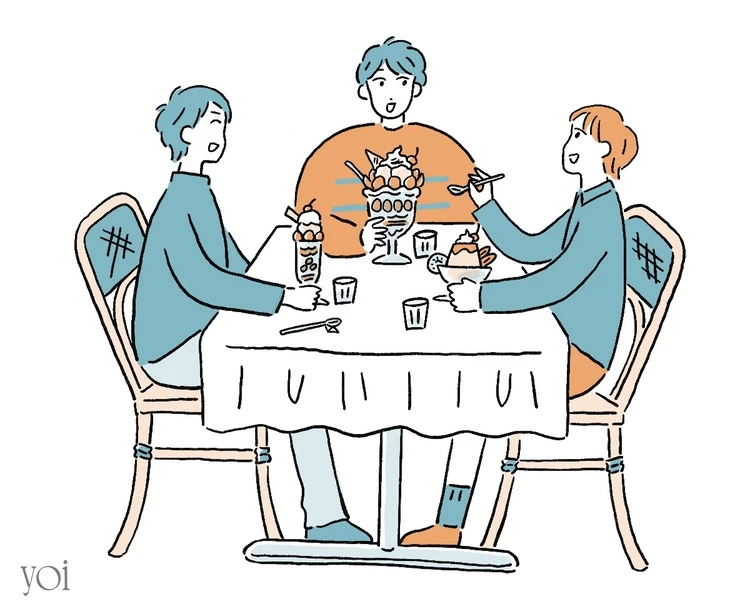
福田さん:自分の心身の不調や、周囲の環境の変化に気づいて、メンテナンスしたりセルフケアしたりするのは、現状だとやはり女性のほうが得意なように感じるんですよね。男性はそもそもそれに気づかないように感情や感覚を麻痺させてしまったり、現状に適応する方を選ぶというか…。
杉田さん:セルフケアについては、注意して考えなければならない部分もあると思います。「自助」「共助」「公助」という言葉がありますが、自分でセルフモニタリングして自分で頑張ってくれ、という考え方は「共助」「公助」から切り離される材料にもなってしまいがちです。
セルフケアが礼賛されてしまうと、社会性が失われてしまう部分もあるので、そのあたりも含めて男性たちは考えていかないといけないと思うんですが…。それも踏まえて、僕が男性のケアとして勧めたいのは男性同士での喫茶店でのおしゃべりのようなことです。
僕は『1日外出録ハンチョウ』(福本伸行作/講談社)という漫画が好きなのですが、これは中年のおじさんたちがいろんなごはんを食べに行ったり、遊園地に行ったり、猫カフェに行ったりして楽しむっていう漫画なんです。
かっこよくもないし、エリートでもない、その辺にいそうなおじさんたちが、男性だけで、“男らしさ”のプレッシャーみたいなところから解放されて楽しむ。「ホモソーシャル」って批判的に言われることが多いですが、善良なホモソーシャルというのはあると思うんですよね。
ブラザーフッドやブロマンスほど強い絆とまではいかない程度の、ゆるくつながる男性たちの善良なコミュニケーション空間がもっとあっていいんじゃないかって。
福田さん:男性同士が集まると、ついお酒を飲みに行ってしまい、仕事自慢や家庭の愚痴になってしまうことが多いですが、そうではないフラットでまったりとしたつながりや、いたわり合いのコミュニケーションが必要だと。
杉田さん:自慢や愚痴でつながるのでは、悪い意味でのホモソーシャルな一体感を高めることになってしまいますよね。趣味だったり共通の何かだったり、ある種どうでもいいことでつながるような、そういう関係性がいくつかあることが、自分の助けになると思います。
人とのつながりは「共助」ですが、それをすることが「自助」にもなる。男性に必要なのは、そういった形でのセルフケアなのではないでしょうか。
イラスト/CONYA 画像デザイン/齋藤春香 企画・構成・取材・文/木村美紀(yoi)