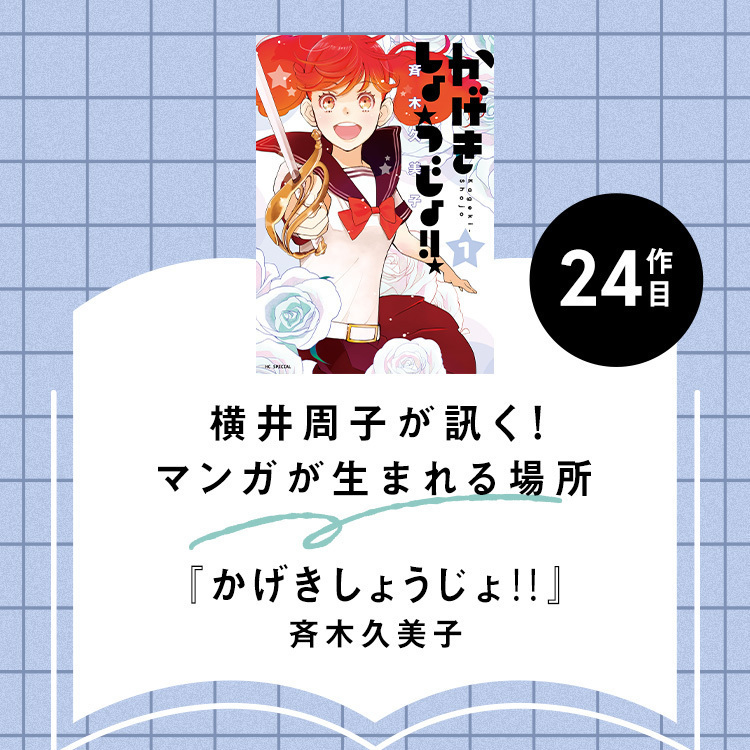セクソロジーとは、科学的根拠に基づいた性の研究のこと。「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」(ユネスコ他編著)に基づいて作られた、スマホで読める性の教科書「SEXSOLOGY - 性を学ぶセクソロジー」の開発に携わったひとり、福田和子さんのインタビューを通じて、日本ではまだあまり認知がされていないセクソロジーの現在地と未来を伝えます。

スウェーデン留学をきっかけに、性と生殖に関する健康と権利(SRHR)の実現を目指す『#なんでないのプロジェクト』を開始。国連機関勤務等を経て、『#緊急避妊薬を薬局でプロジェクト』、W7Japan共同代表等として政策提言等を展開。共訳に「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」(2020、明石書店)。女性の権利のための国際的ムーブメントWomen Deliver、She DecidesよりSRHRアクティビスト世界の25人、 Women Deliver Young Leade r2020に選出。「東大で性教育を学ぶゼミ」講師。WebFRaU×現代ビジネス等で連載中。2023年5月より東京大学多様性包摂共創センター特任研究員。

日本で知らなかった世界の当たり前——セクソロジーという性の「科学」
——SEXOLOGY(セクソロジー)は、日本語に翻訳すると「性科学」。人間の性に関わるあらゆる事柄について、医学、生物学、社会学、心理学、教育学といった側面から研究する学問です。まだ日本では聞きなれない人が多い言葉ですね。
福田さん:私自身も、2016年、スウェーデンでの留学中に初めてこの言葉に出会いました。現地で知り合った当時20歳の友人が、セクソロジストを目指していると教えてくれたのです。
スウェーデンのマルメ大学にはセクソロジーに関するコース(修士号、博士号)があり、セクソロジストが将来の進路として具体的に存在します。ただし、セクソロジストとして北欧臨床セクソロジー 協会(Nordic Association for Clinical Sexology,通称NACS)で認められるのは、かなりの難関。彼女の場合、まずはソーシャルワーカーとしての学位を得て、実務経験を経てはじめて修士号に進めます。その後複数回の論文発表などを経て、はじめてセクソロジストとして認められます。
以前に参加したセクソロジストの国際研究者組織「性の健康世界学会(WAS)」では、セクソロジーのさまざまな研究発表がされていました。テーマは、教師のセクソロジストによる「性教育の実践」や、生物学的バックグラウンドを持つセクソロジストによる「オーガズムの仕組み」、ほかにもポルノやセックスワークについての社会学的・法律学的アプローチなど……どの発表も、医療従事者や教員、また生物学、社会学、心理学などの専門分野を持つセクソロジストによるものでした。

アジア・オセアニア性科学学会(AOFS)での発表の様子
日本における、セクソロジーとセクソロジスト
——セクソロジーは、非常にアカデミックで専門性の高い分野なのですね。日本でセクソロジストの資格を取るのは難しく、また、職業としても認知されていないように思います。
福田さん:日本にはセクソロジーの専門的教育機関が存在していないのが現状で、私自身も、WASの「ユースイニチアチブ」という若手研究者の会のメンバーに属していますが、セクソロジストの資格は有していません。
このような現状の中で時に、セックスに経験値を持つ人こそが性の専門家のように扱われる場合もあるように思います。もちろん個人的な経験を基にした発言も貴重ですが、同時に、個人の経験だけが基になってしまうと、やはり取りこぼしてしまうファクトや視点もあると思います。
誰もが声を上げられる環境を作りながら、同時に、科学的根拠に基づき安心して頼れる、性についての包括的な情報を提供する場も必要です。セクソロジーはそういう意味で、あらゆる人が「安心して頼れる性知識」にアクセスするための知でもあり、そのためにも、学術的な知見の蓄積が必要なのだと思います。

セクソロジストの国際研究者組織「性の健康世界学会(WAS)」に参加する福田さん
すべての人に開かれたセクソロジー
——そうしたセクソロジーの認知の低さがある中で、福田さんは「スマホで読める性の教科書 SEXSOLOGY - 性を学ぶセクソロジー」の開発に関わられました。どんな思いで携わっているのでしょうか?
福田さん:日本にいて、性について知ろうとすると、なんとなく靄がかかっていて「普通のテンションで見られる性の情報」が少ないという現状を感じていました。義務教育で保健の授業を受けて以降、頼れる性の知識に触れる機会があるという方は少ないのではないでしょうか。
例えば「ピルの仕組み」ひとつとっても、検索するとさまざまなクリニックのサイトにヒットし、それぞれの情報に差異や過不足があります。クリニックのサイトだけでは、性教育的な側面や避妊の権利などの情報にアクセスするのは難しい。検索ワードによってはアダルトサイトやポルノのほうが真っ先にヒットするようなこともあります。
自分や相手の健康を守るために、性について知ろうとしても、正しい知識にたどり着くまでが大変。この問題を解決するために、さまざまな専門家の視点から、科学的根拠に基づいた情報の集積場所が必要だとずっと思っていました。そんな時にお声掛けいただいたのが、このプロジェクトです。
サイトは、ユネスコなどの国連機関が発表した最新の「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づいて作っています。国際的に性教育のスタンダードになりつつある「包括的性教育」の指針になっている文書です。そこでのキーワードを20項目に分け、性に関する情報を発信しています。包括的性教育の特徴のひとつは、科学的根拠に基づいていること。ここでも活躍するのがセクソロジーなのです。
セクソロジーの未来を考える。正しい知識を得られる社会に
——セクソロジーに触れる人が増え、認知が深まることで、どのような未来を描いていますか?
福田さん:偏見や差別を受けることなく、誰もがフラットに頼れる性知識にアクセスしやすい社会が訪れてほしいです。それには日本の性教育の不足の解消はもちろんですが、性を知ろうとする人に対する偏見、スティグマも解消されてほしいと思っています。
というのも、これまで避妊や性病の知識を得ようとすると、それだけでからかわれたり、やましい気持ちを抱かされることが少なくありませんでした。そういった視線は女性に対してより強く向けられていて、女性たちはネガティブな評価をされないために、「私は性に対する知識が必要になるような、はしたない女ではない」と振る舞うよう、社会に規定されてきたように思います。結果として、性について知ることができないまま、困ったり、傷ついたりしてきた事実は、今もなくなっていないように思います。
性教育とは、シンプルに自分の健康と権利について知るべきもので、性の知識を得ることを特別視する必要はありません。性を科学として探求していく、セクソロジーという知にアクセスしやすくなることで、誰もが自分を守るために、そして自分らしくハッピーに生きやすくなるためにも、性についての頼れる知識を得られる社会になっていくことを望んでいます。
取材・文/久保田梓美 構成/渋谷香菜子