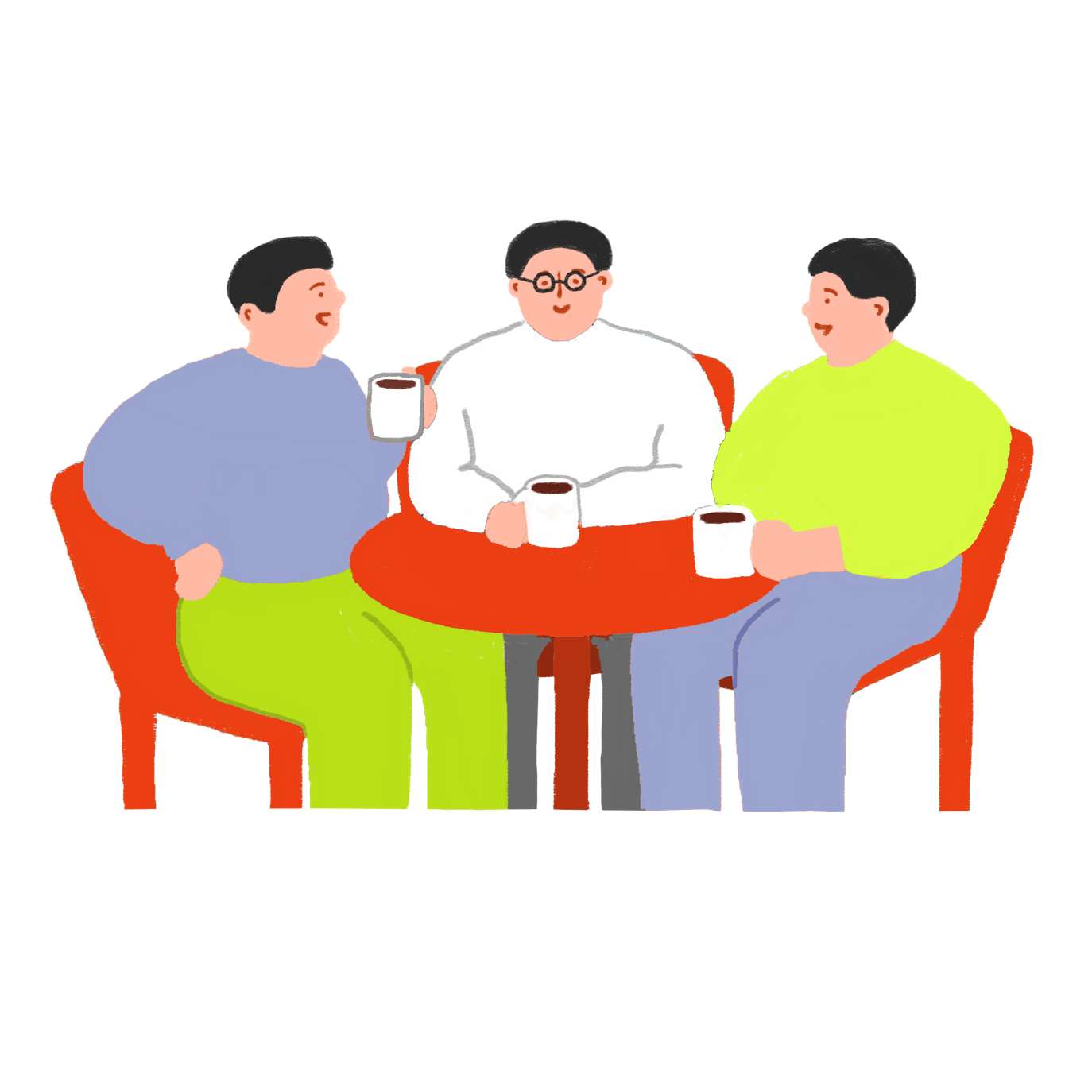美大在学中に写真家としてデビュー。以来、作品を通して男性中心的な価値観への問題提起を続けてきた長島有里枝さん。アーチストであり、大学生の子どもを持つ親でもある彼女が、40歳から10年間の日々を綴った連載をまとめた書籍『こんな大人になりました』が、今年3月に発売されました。著書の中では、自身の身心の変化とともに、生活、仕事、家族に向き合う様子が正直な言葉で綴られています。
今回は、長田杏奈さんが当著の書評を執筆したことをきっかけに、お二人の対談が実現しました。撮影には、「現在夢中になっている」という“ドラァグ・メイク”で登場した長島さん。幼少期から学生時代の話、写真を撮りはじめたきっかけや妊娠・出産についてなど、“こんな大人”になるまでの話を伺いました。

“男性の性的消費のためではない裸”を表現したかった

長田:長島さんのドラァグ・メイク、すごく素敵です! ご自身でメイクされたんですか?
長島:そうなんです。3月に名古屋で開催した『ケアの学校』という展覧会のワークショップで、ドラァグ・クーンのモチェ・レ・サンドリヨンさんに教えてもらったんです。今日のメイクも自分でやりました。
長田:実は私も、いつか華やかなメイクや衣装で舞台に立つ、“ショーガール体験”をしたいと思っているんです。長島さんのドラァグ・メイクを見て、その気持ちが強まりました。
――まずは長島さんのこれまでのご活動から伺いたいと思います。長島さんは1993年、大学在学中にご家族とのヌード写真を撮影したシリーズ『Self-Portrait』でデビューされました。2020年に発行された写真集『Self-Portraits』のインタビューでは当時を振り返り、「動機が何であれ、男の目的のために女が消費されるなんてありえない、という気持ちで作品を作り始めた」と答えていらっしゃいます。そのような意識はどこから生まれたのでしょうか?
長島:1990年代の初め、日本に“ヘアヌード写真”というジャンルが生まれました。わたしはちょうど美大に入るか入らないかぐらい。ヘアヌード写真とは、被写体がアンダーヘアを露わにしたヌード写真のことです。写真家は男性でモデルは女性、女優やタレントなども次々とヘアヌード写真集を出しました。彼女たちの多くは当時18歳だった自分と同年代か、少し年上の人たちです。版元や編集者もたいていは男性で、「ヘアヌードは芸術」だという言説をメディアを通じて構築していた。でも、実際の「ヘアヌード」写真は、ヘテロセクシュアル男性の性的な視線に晒されることがほとんどでした。美術の道を志す人間として、一人の若い女性として、「芸術」という言葉を利用して女性をお金儲けの道具にするこのブームが気持ち悪かったし、許せなかった。そこで、対抗するような写真としてヌードのセルフポートレイトを撮影しはじめたわけです。

Self-Portraits/Dashwood books
長田:今でも女性の体、特に「裸」は商品になるから、「ステップアップのため」とか「売れたいならこれくらいやらなきゃ」とタレントやモデルを説得して、“大人たち”が裸にさせようとするという話も聞きます。
長島:だとすると、状況は90年代からほとんど変わっていないわけですね。当時、記者会見やインタビューで本人がコメントすることもあったんですが、商業的な受け答えしかされなかったように思います。雑誌やテレビは、被写体の体つきや性的魅力の有無、美醜や年齢について、無神経に語ったりもしました。制作側は、内容なんてどうでも話題になれば「売れる」からいいんだろうけど、被写体は身体や人間性に対する批判に晒され、傷ついてしまいます。わたしの作品も、当初はヘアヌードの文脈で語られたんですよ。

Self-Portraits/Dashwood books
長田:作品が、制作者の意図と違う受け取られ方をされてしまうこともあったということですね。
長島:はい。でも、ヘアヌードブームに対抗的な作品なんだということは、ずっと伝えてきたつもりです。『Self-Portraits』の半年前に上梓した『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』という本では、25年越しの反論を展開してもいます。ただ、ヌードをヘテロセクシュアル男性のための表現だとみなす風潮がある限り、どのような文脈に置かれた裸であっても、彼らの言説で語られることを回避するのは難しいと思うんです。

「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ 長島有里枝(著)/大福書林
長田:そんななかで、ご家族と全裸で日常生活のワンシーンを演じたデビュー作『Self-Portrait』シリーズは、時代に一石を投じる表現だったと思います。
長島:インセストタブー(近親相姦のタブー)など、いくつかの社会規範を逆手に取って、裸を脱構築しようとした作品でした。モノクロで撮影したのは、大学の暗室を使って自分でプリントできるメリットがあったから。
あのときも、“長島さんちって裸族なんですか?”と質問されたりして、おもしろおかしく消費しようとする人たちはいましたね。フェミニズム的なヌード、という枠組みが当時の日本ではそれほど知られていなかったから、最初の写真集も美術系の出版社ではなく、ヘアヌード写真集の出版社が版元でした。インタビューの依頼も殺到したけれど、作品の話を深く聞いてくれる人は少なかったです。
でも、セルフポートレイトがきっかけになって、海外では『Purple Prose』で取り上げられたり、デンマークのルイジアナ美術館で開かれたフェミニズム展に呼ばれたりもしました。美術とフェミニズムの知識を背景として、私や写真家のヒロミックスの作品が世に出たことで、セルフポートレイトを撮って発表する女性がたくさん続いたんです。自分だけじゃなく、多くの女性が怒っていたんだな、と感じました。
保育園時代、すでに一人でボイコット運動をしていた
――ご著書『こんな大人になりました』の中で、『「女の子写真*」の言説に反論するため、大学院で勉強したいと思った』と書いていらっしゃいました。
*1990年代、女性写真家たちを中心に生まれた大きな写真の潮流は、おもに男性の写真家から、「技術的につたない」などの言葉とともに「女の子写真」と揶揄的に呼ばれた。
長島:修士号はふたつ持っています。アートを学んだカリフォルニア芸術学校の大学院では、第2波フェミニズム運動を担ったアーチストや、社会問題を主題にした作品で知られる写真家が教えていました。その頃はどちらかというと、ジェンダースタディーズのほうが身近だったかもしれません。フェミニズムがより自分ごとになったのは、帰国して子どもを持ってからです。写真界における女性蔑視だけじゃなく、社会のそこかしこで女性の立場が当たり前のように低いことにも戦慄しました。それが武蔵大学の前期修士課程で、フェミニズムを学んだ理由です。
長田:エッセイを読むと、今でこそ多くの人が関心を持っているフェミニズムの言葉を、長島さんはずっと前から自分のものにしていたのだな、と思いました。

長島:よく「いつからフェミニズムを勉強しているんですか?」と聞かれますが、自分でもはっきり「いつ」と言えないんです。19歳でボーヴォワールの著書『第二の性』を読んで大きな影響を受けましたが、それ以前からフェミニズム的な問題と戦っていたと思います。幼少期から「嫌なものは嫌」というパンク精神みたいなのはずっと変わっていないですね。保育園時代、すでに謎のボイコット運動を一人でしていましたから(笑)。
長田:保育園のときから…! それはどうしてですか?
長島:いちばんは、眠くないのに昼寝をさせられるのが嫌だったんじゃないかな。とにかく、すごく嫌な先生がいて、泣いて何もしないでいると放っておいてもらえるので、泣きつづけてたんだと思う。結局、ストレスでわたしが体調をくずし、ドクターストップで保育園はやめました。そのあと通った幼稚園はすごく楽しくて、先生も優しかった。昼寝もなかった(笑)。
わたしは“生きること”に、あまり向いていないのかもしれない
――子どもの頃から、ご自身の意思を表現することに迷いがない、という印象を受けました。「なんか違うな」と思っても、人に嫌われるのを恐れてはっきり言えない、などということはないのでしょうか。
長島:基本的には、笑って受け流したり、面白いことを言って場が和むほうがいいな、と思ってますよ。
長田:『こんな大人になりました』の第1章でも、「本当の気持ちなんてどうせ伝わらないのだし、面白いことを言って、その場が和むほうがいい」 と書いていましたよね。少し意外でした。
長島:誠実じゃないとか、楽しくできるのにやらないとか、そういうのは嫌ですね。普通に生きてて嫌だと思うことが、人より多い気はします。生きることにあまり向いていないのかもしれないです。子どもの頃から、他の子がすんなりできることができない、とにかくつまずくんです。
嫌われることに関しても、早くからあきらめがあったんです。幼少期からよく仲間はずれにされていましたし、小5のとき転校先でクラスの女子全員に一学期まるまる無視されたり、日替わりでハブられたりしました。当時は「不登校」なんていう言葉もなかったから、毎日学校に行かされてつらかったけど、よく観察するとわたし以外にも一人でいる子はいたんです。その子たちに話しかけて一緒に楽しく過ごしたり。そのうち、一人は寂しいけど楽かも、なんて思えるようになってきて、「人って嫌われても生きていけるもんだな」ってわかった。
長田:強いなあ。私も学生の頃は、クラスで一人でいる子が肩身の狭い思いをしたり、それが特別なことに見えないように、自分も一人でいる時間をつくったりしていた記憶があります。
人生は“起きた出来事に対処していくこと”
――長島さんは28歳でご出産をされました。過去のインタビューで当時のことを振り返り、写真家としてまさにこれからというとき、キャリアは出産育児によって中断された、と語ってらっしゃいました。そんななかで出産を選択されることについて、当時どのように考えていらっしゃったのでしょうか?
長島:今思うと怖いくらい、将来とか先のこととか、何も考えていなかったですね。「子どもができたから産もう!」、それだけでした。産んでみるとあまりに大変で、初めてそこで驚く、みたいな。妊娠中に読んだ育児雑誌には、「3カ月目くらいから楽になる」なんて書いてあって、「そのぐらいから働けるな」とぼんやり考えていました。当然そうならなかったので、不安になりましたね。長田さんはどうでしたか?
長田:私は妊娠がわかったとき週刊誌の編集部に在籍していて、かなり激務でした。このまま仕事は続けられないなと思って、そこからフリーランスになりました。
長島:そうだったんですね。ちゃんと考えてるなぁ。わたし、デビューと結婚が早かったから、「次は子どもとか欲しい」くらいの感じでした。ただ、まったくの想定外というわけでもなかったんです。子どもって、欲しいときに授かれるわけではないでしょう。そのときは「今なら!」と、直感的にですが思っていました。産んでからは、予定も期待も裏切られっぱなしでしたけれど。子育てのおかげで「起きたことに対処していく」力はつきましたよね。
長田:起きたことに対処していくこと、か。時々、「いくつまでに結婚して、出産して貯金はいくらあると安心で…」といった、 “ファイナンシャルプランナーのライフプラン”みたいな記事も見ますよね。計画的に人生を進めなければいけない、と思わされてしまうことが多い気がします。
自分の気持ちは我慢せずに伝える。それでうまくいかなかったことはない

――yoiでは、出産を経験することで、自分である前に“ママ”として扱われるようになったり、母親として完璧な姿を求められることに違和感を感じる、という読者からの声を聞くことが多くあります。この不安やモヤモヤを長島さんも感じたご経験はありますか?
長島:ありますよー。長田さんはどうですか?
長田:私は以前、「長田さんは、どうして“ママみ”を出さないんですか?」と聞かれたことがあってそれにモヤっとしたことがあります。
長島:“ママみ”ってなんですか?!
長田:“ママらしさ”というのかな。私自身が変わったわけではないから、あえて自分が“ママ”であることをアピールする必要ないと思っています。
長島:へぇ、そんな言い方があるんですね。ママだから普通にするとか、我慢するとかはわたしも苦手。言いたいことがあれば、最初は飲み込むけれど悶々としてしまうので、結局は伝えちゃいますし。「二度と会いたくない!」って思うほど我慢するより、話し合ってまた会えるほうがよくないですか。
――それはパートナーや友人、仕事相手など、どんな人に対してもでしょうか。
長島:家族ほど伝えますね。信頼しているし、一緒にいる時間が長い分、我慢しだしたら大変ですから。嫌なことも伝えるけれど、「大好き」っていう気持ちや素敵だと思うところも同じぐらい伝えるほうだと思います。パートナーの場合は別れることも念頭に置くけれど、わたしが問題を話し合おうとするのは一緒にいたいからだって、わかってくれていますね。自分の気持ちにどうこたえるのかは、相手が決めることだと思っています。正直に話したことが原因で別れたことはこれまでないですね。長田さんはどう?
長田:場合によるかな…。自分より上の立場にいる人に対しては、疑問を感じたら伝えるようにはしているけれど、明らかに自分のほうが年上だったり、社会的に力関係が上の場合は言いにくいかもしれないです。
長島:息子や自分の学生、仕事上の若い相手でも、必要だと思えば考えていることを伝えます。相手が誰であれ、どの程度の信頼関係がその時点で築けているのか考えながら、誠実に話すようにしていますね。
“見て感じ取って”だけではわかり合えないことがある
――『こんな大人になりました』だけでなく、これまでもさまざまな書籍を執筆していらっしゃいますが、長島さんにとって文章を書くことはどのような意味を持つのでしょうか?

踊るように闘い、祈るように働く——。気づけばティーンエージャーの息子、生活を共にするようになった恋人。自分だけのために作るナポリタン、国会中継へのやるせない憤り、20年ぶりにこじ開けた鼻ピアス。女性として、写真家として、シングルペアレントとして、生活者として。アラフォーからアラフィフの10年間を月々ありのままに記録した、伸びやかでパンクなレジスタンス・エッセイ! 長島 有里枝(著)/集英社
長島:「美術表現は言葉を必要としないジャンル」だと信じていたこともありますが、アメリカの大学院で学んでから考えは変わりました。同じヌードの表象でも、コンセプトや背景を理解したうえで作品を見ると、とらえ方が変わってきます。評論家や研究者であっても、作品の生まれた経緯として作者の属する社会や時代、階級、背景となる文化資本や地理的条件などを理解しなければ、その作品を深く理解することはできません。そのぐらい、わたしたちは言語の意味世界に支配されているわけです。
長田:“見て感じ取ってください”という姿勢だけではわからないこともある、ということですね。
長島:現代美術の作家は伝統的に、作品だけじゃなく「作品が引き起こす議論」も重要視してきたと思います。今日のドラァグ・メイクにしても、ただ見られるだけで終わりじゃないといいなと思う。「なんでわざわざそんなふうにするの?」と思う人と、コミュニケーションのきっかけを作りたいのかもしれない。
長田:メイクにも言葉や背景があることは大切でしょうか。
長島:あるほうが面白いですよね。
長田:美容業界では、以前は“モテ”とか“若見え”などの言葉が席巻していたけれど、最近は多様化してきている気がします。例えば“モテ”でも、“自分モテ”と言い方を変えたりして。
長島:「そもそも、なんでモテなの?」というところから考えたい気がします。
長田:女性が消費の対象になっているという、長島さんの最初のお話にもつながっていく気がしました。まだまだ女性が一人で生きていくのは大変で、そこから考えていかなくてはいけないと感じます。
――続く後編では、お二人にとって“年齢を重ねること”とは? 憧れていた大人の姿や、変化していく外見との向き合い方などについて伺います。
取材・文/浦本真梨子 撮影/上澤友香 企画・編集/種谷美波(yoi)