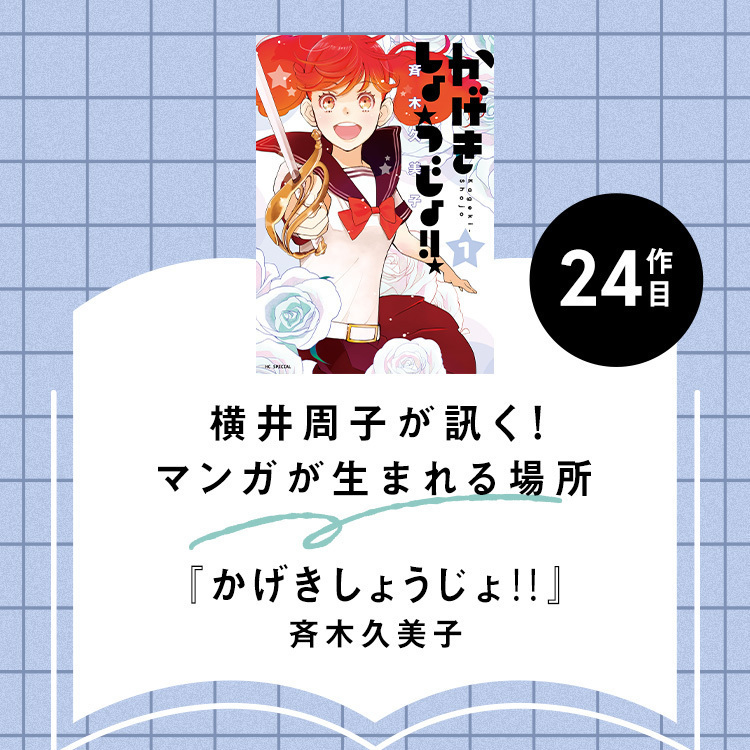清田隆之さんのインタビュー後編は、男性同士の関係を深掘り。バラエティ番組などで散見するイジり合いは、なぜなくならないのか。それについて当事者はどう感じているのか。傷つけ合うことが日常化している男性社会の構造について語っていただきました。


文筆家
1980年生まれ、早稲田大学第一文学部卒。文筆家、『桃山商事』代表。ジェンダーの問題を中心に、恋愛、結婚、子育て、カルチャー、悩み相談などさまざまなテーマで書籍やコラムを執筆。著書に、『おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門―暮らしとメディアのモヤモヤ「言語化」通信』(朝日出版社)など。最新刊『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』(太田出版)も好評発売中。桃山商事としての著書に、『どうして男は恋人より男友達を優先しがちなのか』(イースト・プレス)などがある。Podcast番組『桃山商事』もSpotifyなどで配信中。
加害として認識されない、男同士の傷つけ合い

——清田さんの新著『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』にまとめられているエッセイは全て、小説や映画、ドラマ、バラエティ番組といったエンタメ作品を切り口にしています。近年のバラエティ番組では、男性が女性をイジる場面は減ったように思いますが、男性同士のイジりは散見しますし、むしろ増えているような気も……!?
清田さん:人をイジったり、おとしめたりして笑いを取る文化は、まだまだ健在ですよね。でも、そこに女性を絡めると批判されやすい風潮になってきている。そういう制作サイドの都合もあるかもしれません。若手の男性芸人をターゲットにするドッキリ企画なんて、年々ひどくなっている印象ですし。
トラウマを植え付けるほど暴力的なことをしても、笑いというパッケージに包まれちゃうと、ガチでビビっている側が“芸人としてどうなの?”と思われてしまう。さらに、標的になった芸人は、そこで爪痕を残せばステップアップできるという建て付けになっているため、過剰適応せざるを得ない。ついつい面白く見てしまいますが、よく考えると恐ろしい構造ですよね……。
実は今、こういった男同士の関係で生じる傷つき体験をテーマにした本を書いています。かれこれ5年ほど体験談を集めているのですが、男同士の関係にはイジり合いや茶化し合いの体裁を纏った加害が本当に多いなと感じます。それらは一見、じゃれ合いのような顔をしているから、暴力として認識されにくい。
——今作でも触れられていましたが、読みながら、大学時代にこういう場面見たことある!と思いました。
清田さん:変なあだ名で呼び続けられるなどの言葉でのイジりから、身体的な暴力や集団的な村八分まで、日常にあふれていますよね。流れに乗らないとノリが悪いと言われて、劣位に置かれてしまう。だから自分もやる側になっちゃうし、やられる側にもなるし……そういった環境で自己形成や人間関係を構築していくカルチャーが、男社会には根強く残っています。
男性たちにインタビューを重ねる中で、男同士の関係に宿る“寄る辺なさ”をあらためて感じています。仲良くじゃれあっているのに、どこかで傷つけあってもいる。だから男は男に弱みを見せられないし、うっすら警戒もしている……。どんなに仲が良くても男同士では頼れず、女性にケアを求めてしまうのではないかと。あくまで仮説ですが、新しい本を書きながらそんなことを考えています。
男友達に相談しても、ケアを得られない

——私自身も含めて、男友達から相談を受ける女性は多い印象があります。自分よりもはるかに距離の近い同性の友達がたくさんいるのに、彼らには相談している様子はなくて、不思議に思っていました。
清田さん:弱みを見せる=恥という感覚がどこかにあるし、優しく受け止めてもらえるかどうかもわからない。悩みを相談しても、「大丈夫?」「それは辛いね」みたいなリアクションは期待できない。だからと冗談めかしてしか話せず、ケアし合う方向に話が進んでいかないという……。
映画やドラマでも、男同士でケアし合う描写は、ほとんど見ませんよね。くだらない会話で元気づけることはあっても、互いの内面には介入していかないというか。「どうしたの?」「何があったの?」っていう問いかけはない。男同士ってなんだか不思議な関係だなって思います。
——男性が女性にケアを求める心理は、新著で書かれている「射精責任」に関する章の内容とも関連しますね。男性が女性にコンドームなしのセックスを求める理由について、「受け入れられている感覚がある」「許してもらえたような安堵感がある」という内容に衝撃を受けました。
清田さん:恋人にコンドームの着用を頼まれただけなのに、うっすら拒絶されたような気持ちになる。女性側からすると意味がわからない話ですよね……。「彼女は無条件に、俺を受け入れてくれる!」っていう幻想を勝手に抱いている。だから「避妊して」という言葉が拒絶に感じる……って、どんだけナイーブなんだって話ですよね。
一方的に女性にケアを求めておいて、それが得られなかったら、今度は被害者感情を募らせる……。これもよくある話だと思います。こういった問題の背景にも、男同士で頼り合えないカルチャーが関係しているようにに思います。
自分自身の人生を振り返っても、男友達とケア的な関係を築けるようになったのは、30代半ばくらいになってからだと感じます。男友達とルームシェアをしたり、会社を立ち上げたりもしてきましたが、一緒に盛り上がることはできても、優しくいたわり合うような関係は築けていなかった。そういう関係性に違和感を覚え、少しずつ変えていくことができたのは、ジェンダーの問題に関心を持つようになってからでした。
自分の話したいことを話す、おしゃべり会のすすめ

——女友達とお茶を飲みながらおしゃべりして、そのセラピー的な効果に気づいたと書かれていましたね。それを機に男友達ともお茶をするようになり、関係性が変化したとか。
清田さん:そうなんです。それで本にも「お茶する」という行為の面白さについて書きました。男同士って、「昨日の大谷の試合すごかったな!」みたいな世間話をすることはあっても、自分の気持ちを話す機会ってあまりない気がするんですよね。また、ボケたりツッコミを入れたり、イジったり茶化したりというコミュニケーション様式が浸透してしまっているため、まとまらない話をまとまらないまま話す機会が持てないというのも大きいと思います。そういう点で、女性たちのおしゃべりはすごいですよね。話したいことを話す、自分の気持ちを言語化していく。こういうことの大切さを、自分は女子会やガールズトークの文化に学びました。
それを男同士の関係にも輸入したいということで、最近、男同士のおしゃべり会(「俺たちにはおしゃべりが必要だ〜男同士で語り合う夜のお茶会in蟹ブックス〜」・不定期開催中。今後の開催に関しては清田さんの公式Xをチェック)を開催しているんです。参加者は3人で1組になって、それぞれ7分間ずつ自分が話したいことを話す。ルールというか心構えとして、話す人は相手を笑わせようとしなくていいし、話がまとまっていなくてもいい。聞く側は、じっくり話を聞いてくださいと伝えています。
——参加者の方たちから、どんな感想が届いていますか?
清田さん:「今までにない体験でした!」とか「こんなに自分の気持ちを素直に話せたのは初めてです」とか、めちゃめちゃポジティブな感想が多くて。年齢は20代から50代まで幅広いですが、皆さん口を揃えて「男同士でじっくり会話をするのが新鮮だった」と言うんですよ。確かに照れ臭さや不慣れな部分もあるけれど、男同士のケアも不可能じゃないなって、希望のようなものを感じています。
——最後に、清田さんが今後、考えていきたいテーマがあれば教えてください。
清田さん:最近、男同士の関係性について考えたり、おしゃべり会を開催したりする中で、男性がジェンダーの問題に関心を持つとか、男性性について考えるとか、もちろんそれはとても大事なことなんだけど、そのもっと手前に「キャパシティの限界」という問題が立ちはだかっているんじゃないかと思い始めて。
みんな忙しいし、不安も多いし、キャパがパンパンの状態だから、何かについてじっくり考える余裕がそもそもない。そんな状況で「ジェンダーの問題と向き合おう!」とか言われても、なかなか難しいかもしれない。そのためには、人々から余裕を奪う社会の構造から考えていく必要があるのではないか。そんな発想を持ちつつ、ジェンダーの問題をジェンダーじゃない形で考えていくための手立てなんかも模索していけたらなと思っています。
『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』
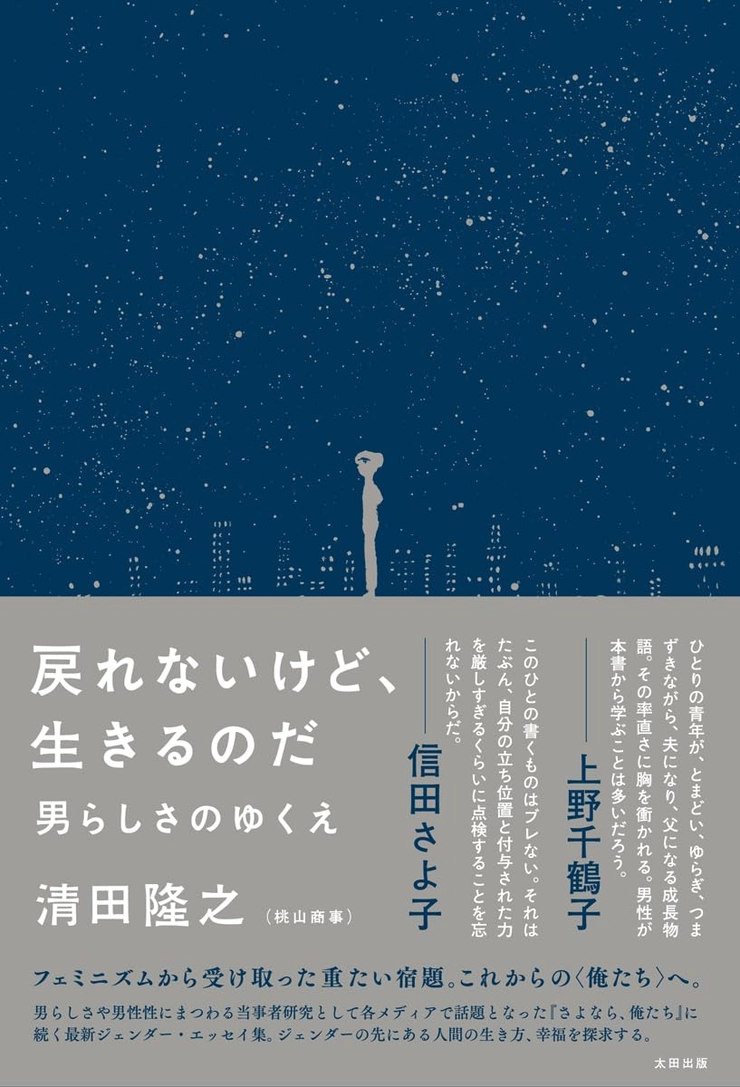
¥2090/太田出版
イラスト/NACCHIN 構成・取材・文/中西 彩乃