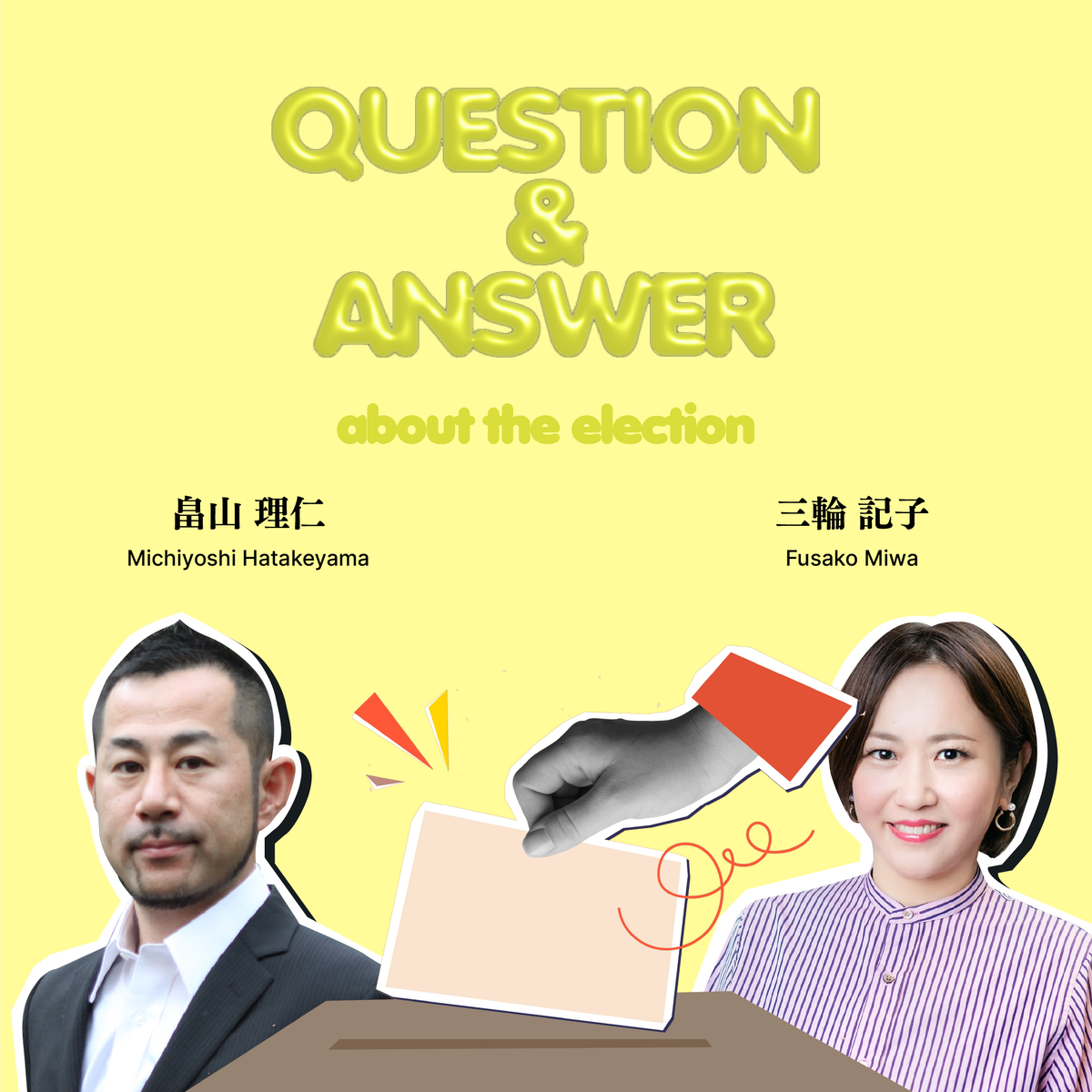25年以上にわたって選挙取材を続ける畠山理仁(みちよし)さん&弁護士の三輪記子(ふさこ)さんが選挙の疑問に答えるQ&Aの第2弾。政治家のメンバーチェンジがなかなか起こらない理由から選挙事務所訪問のコツまで、選挙中に実践したくなるトピックについて語っていただきました。
- Q1.選挙で政治家のメンバーチェンジがなかなか起きないのはなぜですか?
- A1.「詳しい人がノウハウを独占し、新規参入が難しくなっているから」(畠山理仁さん)
- Q2.日本では政治や選挙について話しづらいと感じます。身近な人たちと話すときのコツを教えてください。
- A2-1.「意見は違って当たり前だと理解し、説得しないことが大切」(三輪記子さん)
- A2-2.「政治は生活。世間話もすべて政治の話だと思えば、もっと気楽に話せるはず」(畠山理仁さん)
- Q3.いつも候補者選びに悩み、「しいていうならこの人かな…」ぐらいのスタンスで投票してしまいます。何を決め手にすればいいのでしょうか?
- A3-1.「消去法的な考え方もありだと思います」(三輪記子さん)
- A3-2.「もし自分が立候補するとしたら、どんなキャッチフレーズを訴えるか想像してみてください」(畠山理仁さん)
- Q4.候補者や政党の主義主張は、どこでチェックするのがおすすめですか? 政見放送は話題性目的のパフォーマンスや不快な表現も増えているので、見るのが怖いです…
- A4-1.「大手メディアの情報はSNSよりも確実で、比較検討しやすくなっています」(三輪記子さん)
- A4-2.「『不快』という体感は、消去法につながる最大の情報です」(畠山理仁さん)
- Q5.新聞をチェックする時間がなくて、ついSNS頼みになってしまいます。選挙中のSNSとの距離感はどんなふうに考えておけばいいですか?
- A5-1.「『世の中にはいろんな人がいるんだな』と確認するぐらいの距離感で」(三輪記子さん)
- A5-2.「まさにネット大航海時代。複数のソースにあたって吟味を」(畠山理仁さん)
- Q6.いわゆる「主要候補」は大々的に報じられるけれど、それ以外の候補者は扱いが小さく、最初からバイアスがかかっていると感じます。候補者全員の情報が同じように紹介されないのはなぜですか?
- A6.「メディアごとに方針が違うから。ただ、最近は変わりつつあります」(畠山理仁さん)
- Q7.せっかく投票しても、その人が落選しちゃったら意味がないですよね?
- A7-1.「『意味がない』なんてことは絶対にありません」(三輪記子さん)
- A7-2.「あなたの一票が、落選した候補者の政策を実現する後押しになります」(畠山理仁さん)
- Q8.SNSを含めたネットでの選挙運動って、有権者の場合は何がOKで何がNGなの?
- A8.「活動できるのは投票日前日の23時59分59秒まで。細かなルールは総務省や選挙管理委員会のWebサイトで確認を」(三輪記子さん)
- 【有権者がやってはいけないことの一例】
- Q9.応援したい候補者がいます。有権者としてできることはありますか?
- A9.「厳しい目を持って叱咤激励することが、一番の応援です」(畠山理仁さん)
- Q10.選挙事務所って誰でも入れるものですか?
- A10.「もちろん入れます。大歓迎されるのでぜひ行ってみてください」(畠山理仁さん)
- 【畠山さんおすすめの質問例】
- 「◯◯さん(候補者)ってどんな人ですか?」
- 「この選挙区では、どんな怪文書が出ていますか?」

フリーランスライター
1973年生まれ。『週刊プレイボーイ』(集英社)の連載「政治の現場すっとこどっこい」を担当したことをきっかけに選挙取材を始める。2017年に『黙殺 報じられない"無頼系独立候補"たちの戦い』(集英社)で第15回開高健ノンフィクション賞を受賞。2021年には『コロナ時代の選挙漫遊記』(集英社)で咢堂ブックオブザイヤー2021の選挙部門大賞。2023年にはその選挙取材に密着したドキュメンタリー映画『NO 選挙,NO LIFE』が公開され、話題となった。ニコニコ生放送「畠山理仁チャンネル」配信中。

弁護士
外交官志望から弁護士の道へ進み、離婚、遺産分割、犯罪被害者、セクハラ・パワハラなどにまつわる事件の弁護を多数手がける。2022年に「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」を開設。テレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。
Q1.選挙で政治家のメンバーチェンジがなかなか起きないのはなぜですか?

inspiring.team/Shutterstock.com
A1.「詳しい人がノウハウを独占し、新規参入が難しくなっているから」(畠山理仁さん)
選挙ってすごく特殊な世界で、経験を積んだ人が圧倒的に強い。しかも、そういう人たちはノウハウが外に漏れることを非常に嫌がるので、閉じた世界でノウハウを独占している人が勝ち続けてしまう。新規参入がすごく難しい世界になっているので、メンバーチェンジも起きにくいわけです。ただ、そんなふうに競争のない社会はいずれ衰退していくだろうとも思います。
そのあり方は、投票率が上がらないことにもつながっています。「詳しくない奴が政治を語るな」と言う人もいますが、それが選挙に行かない、あるいは選挙に興味を持たない人との間に壁をつくっていることを知ってほしい。僕が政治について話すときにあえて面白おかしく話すのも、興味がない人たちのハードルを下げたいから。
詳しい人ほど「選挙ってすごく面白い世界。かかわることで社会をいい方向に変えることもできるから、参加したほうがいいですよ」と伝えてほしいなと思います。
Q2.日本では政治や選挙について話しづらいと感じます。身近な人たちと話すときのコツを教えてください。
A2-1.「意見は違って当たり前だと理解し、説得しないことが大切」(三輪記子さん)
意見や考えは違うのが当たり前だと理解すること、説得しようとしないことが大切ではないでしょうか。自分とは違う意見も、政治に興味がある・ないも、支持している政党も、「相手の意見」として聞けばいいだけのことなんですよね。そこで意見の違う人を説得しようとしたり、勝ち負けで決めようとしたりすることが、話しづらさにつながっているのかなと。
「知識がないから馬鹿にされたらどうしよう」「自分とは違う考えだったらどうしよう」と不安になるかもしれませんが、意見表明は勝ち負けではないということをしっかり覚えておきましょう。ただし、差別発言やヘイト発言にはきちんとNOと言えるように、自分なりの考えや言葉を準備しておくことも大切だと思います。
逆に、「同じ考え方の人たちとわいわい話せるはず」と自分からハードルを上げてしまっている気もします。具体的な政党や政治家について話すよりは、日常で「これってどうなんだろう」と思っていることを話したり、その場で友達と一緒に調べたりすることから始めてみるのはどうでしょう。もし具体的な政党や政治家について話すのであれば、その政党や候補者のWebサイトやSNSを一緒に深掘りしてみるのもいいかもしれません。
A2-2.「政治は生活。世間話もすべて政治の話だと思えば、もっと気楽に話せるはず」(畠山理仁さん)
政治って生活なので、まずは生活で困っていることから話すのがいいと思います。例えば、「お米高いよね」「備蓄米を『小泉米』っていうけど、小泉大臣が個人的に備蓄した米じゃないよね」とか、もちろん自分の不満とか。
「他人は意見が違う」という前提を持ちつつ、自分の考えを表明したいならすればいいし、人の意見を聞きたいなら「どう思う?」と尋ねてみる。そうやって話していくうちに、「この人とは話が合いそうだな」と思ったら、きっと仲間になれるので。
世の中で起きていることにはすべて政治が関係しているのだから、世間話だって政治の話なんだと思えば、もっと気楽に話せる気がします。身近な人たちと話す中で一致する困りごとがあれば、「政治家の人に聞いてみようよ」とメールで質問を送るなどの行動をしてみるのもおすすめ。
「自分は有権者の代弁者だ」という意識を持つ政治家も多いので、有権者からの呼びかけにこたえたり、有権者が集まる場所へ出向いたりするケースも実は珍しくありません。
政治家に困りごとを伝えて意見を聞く機会を日常的に持つと、要求の実現に向けて動いてくれる人もいれば、そうではない人もいることがわかってきます。政治をやるのも人間だから、結局は人づき合いと一緒なんですよね。政治家とかかわって自分たちの代理人を育てていくのは、有権者の権利というか役割でもあります。
Q3.いつも候補者選びに悩み、「しいていうならこの人かな…」ぐらいのスタンスで投票してしまいます。何を決め手にすればいいのでしょうか?
A3-1.「消去法的な考え方もありだと思います」(三輪記子さん)
とりあえず学歴や外見、家柄などで選ぶのはやめたほうがいいと思います。それから、選挙=積極的に「いい人」を選ぶ行為だと考えるとハードルがすごく高くなるので、消去法的な考え方もありだと思うんですよね。
これは私が司法試験で実践していた方法ですが、例えば選択肢が10ある場合、まず「これは絶対ない」と思う選択肢を外す。残った選択肢に対して「これは◯寄りの△」「△だけど×に近い」「迷うからとりあえず△」と自分なりに検討し、×に近いものから外していく。
そうやって最終的に残った候補から選ぶほうが、選びやすいと思いませんか? それに、全部◯をつけられる人なんてまずいませんから。裏金問題や差別発言など、政党や候補者に関するネガティブな情報を忘れないことも大切。私たちはすぐに忘れてしまうし、政治家も「忘れるだろう」と思っている人が多いので。
裏金問題はそれほどフィーチャーされていないかもしれませんが、有権者にとって物価高や生活の厳しさが一番の関心事になっている昨今、裏金をつくっておきながら不十分な説明しかせず、しれっとしている政治家に、私たち一般市民の苦しさがわかるのでしょうか…。いいことばかりでなく、ネガティブなこともしっかりとらえていきたいものです。
A3-2.「もし自分が立候補するとしたら、どんなキャッチフレーズを訴えるか想像してみてください」(畠山理仁さん)
実は、最近発明した方法がありまして。それは、「自分がもし選挙に立候補するとしたら、どんなキャッチフレーズを訴えながら選挙を戦うか想像してみてください」ということ。そこで浮かんだことは、自分が社会に求めるテーマだと思うんです。そのフレーズと同じ、あるいは近い政策を掲げている人がいないかどうかをまず探してみる。もし見つけたら、投票の選択肢リストに入れていきましょう。
そして、可能であればそれぞれに会って「あなたは私が求めるテーマを訴えているけれど、私には解決策がわかりません。どうやって実現するつもりですか?」と聞いてみてください。候補者によって考え方や解決策が違うので、自分の考えと一致する人や「なるほど!」と納得させられた人を有力な選択肢と考えると、自分なりに納得のいく投票行動になるのではないかと思います。
Q4.候補者や政党の主義主張は、どこでチェックするのがおすすめですか? 政見放送は話題性目的のパフォーマンスや不快な表現も増えているので、見るのが怖いです…
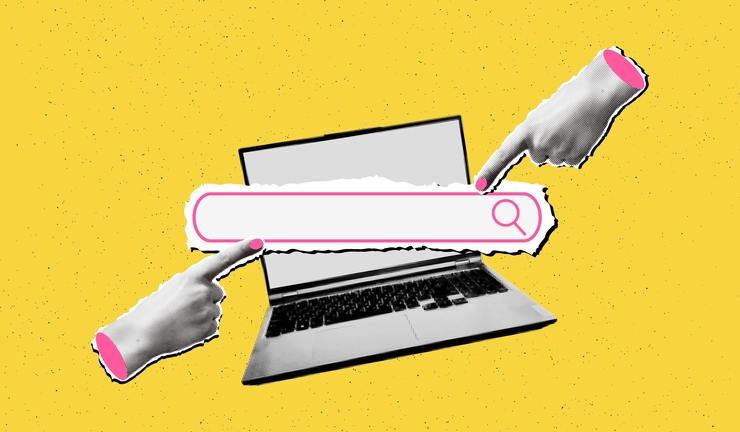
ugguggu/Shutterstock.com
A4-1.「大手メディアの情報はSNSよりも確実で、比較検討しやすくなっています」(三輪記子さん)
いまはSNSで情報収集する人が多いですが、確かな取材力できちんと物事の裏を取って報道する新聞など大手メディアの情報はやっぱり確実だと思います。
もちろん候補者本人のSNSアカウントをチェックするのもいいけれど、その人のことしかわかりませんよね。その点、メディアの候補者アンケートなどは、さまざまなテーマに対して誰が何と回答したかが一覧で見られるので、比較検討しやすくなっています。
A4-2.「『不快』という体感は、消去法につながる最大の情報です」(畠山理仁さん)
基本的に、候補者や支持者が発信する情報は、「自分が見せたいもの」だけ。特に切り抜き動画は手軽でインパクトがある分、宣伝のために使われているものだと考えたほうがいい。政見放送も選挙公報も、本人の主張をそのまま、第三者による事実確認をせずに届けているものだと意識したうえで触れてほしいと思います。
それから、過激なパフォーマンスに近い政見放送やヘイトスピーチのような街頭演説を最後まで見る必要は全然ありません。「不快」と感じたこと自体が最大の情報であり、選択肢の消去法につながりますから。もし不快だと感じたら、「あの候補者は、こんな言動をしていてひどかった」という情報を周囲の人に共有することも大切です。
あくまで自分の主観ではありますが、候補者を知らないがゆえの間違いを減らすためにも働きかけましょう。そういう意味では、嫌だなと思ったときに「いい情報に触れた。これで自信を持って『この人は絶対にない』と言える」ととらえると、「いろいろな候補者を見てみよう」と思えるのではないでしょうか。
Q5.新聞をチェックする時間がなくて、ついSNS頼みになってしまいます。選挙中のSNSとの距離感はどんなふうに考えておけばいいですか?
A5-1.「『世の中にはいろんな人がいるんだな』と確認するぐらいの距離感で」(三輪記子さん)
いまからSNSがない世界には戻れないし、よくも悪くもSNSで起きている現象は無視できないので、私は「世の中にはいろんな人がいるんだな」と確認するぐらいの距離感で見ています。
情報に触れなければ比較検討できないけれど、どこの誰が言っているのかわからないものを含めて何でも安易に信じてしまうのは危険です。たとえ推しの候補者がいても、その人の発言を全肯定してはいけないと思います。むしろ全肯定したい気持ちになっている自分がいたら、「ちょっと冷静になろうね」と自問自答するくらいでちょうどいい、というのが私の考えです。
A5-2.「まさにネット大航海時代。複数のソースにあたって吟味を」(畠山理仁さん)
現代は、有権者が候補者の情報を求めてSNSの海に漕ぎ出す「ネット大航海時代」。政治家を選ぶために情報を探すのはとてもいい傾向ですが、目に触れる回数が多い情報=正しいわけではありません。根拠が薄弱な情報でも刺激的なものは拡散されやすい。けれど、それは真実相当性の担保にはなりません。
一方的で刺激的な情報に引っ張られないためにも、自分が応援する人の発信だけでなく、それを批判的に見ている人たちが発信する情報にも触れたほうがいいと思います。両方を見たうえで冷静に比較検討して、最終的には自分で判断する。情報ソースが偏らないように、いくつもの情報をもとに冷静に候補者をとらえると、立体的な候補者像になっていくはずです。
政治家はキャンセルも返品もできない高い買い物のようなもの。参院選の場合、有権者一人につき約600万円の予算の行方を決める人なので、やっぱり現物を見て選びたいですよね。どうしても難しい場合は、せめていろいろな情報ソースにあたって吟味してほしいと思います。
Q6.いわゆる「主要候補」は大々的に報じられるけれど、それ以外の候補者は扱いが小さく、最初からバイアスがかかっていると感じます。候補者全員の情報が同じように紹介されないのはなぜですか?
A6.「メディアごとに方針が違うから。ただ、最近は変わりつつあります」(畠山理仁さん)
メディアには編集や論評の自由があるので、各候補の扱いや方針はメディアの判断によるものです。ただ、当初は“主要候補”でなかった人でも、現場を取材している記者を通じて「注目に値する」と判断すれば取り上げられることはあるし、「候補者全員を取材してほしい」という購読者の声も徐々に反映されるようになっています。
僕自身はすべてのメディアが全候補者を扱うべきだとは思っていなくて。もちろんやってくれたらありがたいけれど、それよりも、多様なメディアの記者が候補者を取材して独自に発信する情報が、誰でも触れやすい場所にあることが大事。
昨年の東京都知事選や兵庫県知事選などを経て、メディア自身も選挙中の情報発信が少ないことに対する危機感を持っているので、今までよりも有権者が信用のおける情報に触れられる機会は増えると思います。
Q7.せっかく投票しても、その人が落選しちゃったら意味がないですよね?

Marish/Shutterstock.com
A7-1.「『意味がない』なんてことは絶対にありません」(三輪記子さん)
選挙は「正解」を当てる試験ではないし、当選した人が「正解」というわけでもありません。「正解しなきゃいけない」という考えにとらわれる必要はないし、自分が応援した候補が落選したら「意味がない」とか「恥ずかしい」なんてことも絶対にありません。
そして人は変わっていくので、あのときベストだと思った選択も、いろんなことを知ったり経験したりするうちに、「こっちの選択のほうがベストだったかも」と考えるかもしれない。そうやって学びながら、毎回ベストを尽くすしかないと思います。
A7-2.「あなたの一票が、落選した候補者の政策を実現する後押しになります」(畠山理仁さん)
選挙は「誰が勝つか」を当てるゲームではなく、「どういう社会にしたいか」という自分の意思表示。「自分の一票を託した人が落選したら無意味じゃないか」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
支持した候補が落選しても、皆さんの一票がその政策を後押しする意思表示になるし、当選した人に対して「私たちが望むこの政策を実現してほしい」というプレッシャーにもなります。
実際、「自転車専用道路の整備」や「公立高校の女子トイレに生理用品を無償配置」「小中学校における1クラス30人の少人数学級」など、落選した人の政策が実現された例はいくつもあります。そういった意味でも、白票や棄権で一票を捨てるのは“愚かな賢さ”だと思います。
Q8.SNSを含めたネットでの選挙運動って、有権者の場合は何がOKで何がNGなの?
A8.「活動できるのは投票日前日の23時59分59秒まで。細かなルールは総務省や選挙管理委員会のWebサイトで確認を」(三輪記子さん)
有権者が選挙運動できる期間は、候補者が立候補届を提出する公示日・告示日から、投票日前日の23時59分59秒まで。個人のWebサイトやブログ、SNS、YouTubeなどの動画共有サービス、動画中継サイトなどを利用できますが、電子メールやスマホのSMSなどは利用禁止です。ただし、18歳未満の人は選挙運動に参加できません。
また、投票日当日は一切の選挙運動が禁止されています。SNSでのリプライやシェア、メッセージはもちろんNG。「投票(選挙)に行こう」という呼びかけや、特定の政党名や候補者名を出さずに「投票しました」という宣言のみOKです。細かいルールは総務省や選挙管理委員会のWebサイトなどで確認しましょう。
【有権者がやってはいけないことの一例】
・政党や候補者がネット上に公開した資料を印刷して配る。
・応援する候補者のパンフレットやポスターを勝手にコピーして使う。
・電子メールやSMS、メーリングリストやメルマガなどで応援や投票を呼びかける。※LINEやFacebook、Instagramなどのメッセージは投票日前日までOK
・候補者にまつわるネット広告を出す。
・他の候補者に関するデマや虚偽の情報を発信する。
参考:総務省「インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」
Q9.応援したい候補者がいます。有権者としてできることはありますか?
A9.「厳しい目を持って叱咤激励することが、一番の応援です」(畠山理仁さん)
応援する人であればあるほど、批判的に厳しく見ることです。候補者が何か間違えたときに、「応援しているから」と身内を守る感覚でかばってしまうのはダメ。
当選した政治家は社会全体の奉仕者なので、どこに出しても恥ずかしくない政治家に育ってもらうためにも、支援をしている人たちが厳しい目を持って「私たちのためにいい仕事をする政治家になってください」と叱咤激励をすることが、一番の応援になります。
特に応援したい候補がいなくても、当選する人は立候補者の中からしか選ばれないので、自分好みの候補者になってもらうための働きかけをしてみましょう。例えば、「自分はこういう社会にしてほしいと思っているけれど、あなたの政策には入っていません。それはなぜですか?」と聞く、あるいは「こういう政策をしてほしい」と伝える。
そこで政策に取り入れたり、「今後は取り組みます」と言ったりする候補者なら、「投票してもいいかな」と思える人に近づいていきますよね。そうした働きかけも有権者の大事な仕事のひとつです。
Q10.選挙事務所って誰でも入れるものですか?
A10.「もちろん入れます。大歓迎されるのでぜひ行ってみてください」(畠山理仁さん)
僕の「選挙漫遊講座」(選挙現場の歩き方・楽しみ方を伝える講座)でもおすすめしているのですが、選挙の世界は慢性的に人手不足なので、「ちょっと興味があって…」とか「お手伝いに来ました」と選挙事務所を訪ねると大歓迎されます。
もしお手伝いではなく野次馬的に行くときの定番は、「候補者の資料があったらください」と声をかけること。選挙権がない地域の選挙現場を見に行くときは、加えて「この近所においしいお店があったら教えてください」と聞くと、地元のおいしいものを教えてもらえます。
そうやってコミュニケーションをしていくと、今まで接触する機会がなかった政治の世界や選挙の世界に従事している人たちも自分たちと同じ人間なんだっていうことがすごくよくわかるので、楽しむ気持ちで最初の一歩を踏み出してもらえたら。講座でもお伝えしている質問の一例もご紹介しておきますね。
【畠山さんおすすめの質問例】
「◯◯さん(候補者)ってどんな人ですか?」
例えばAさんという候補者の事務所で資料をもらった後に「Aさんってどんな人ですか?」と質問して詳しく教えてもらったら、今度は「ライバルのBさんってどんな人ですか?」と他の候補者の名前を出すと、Bさんがオフィシャルには言っていない情報がAさんの側から聞けたりします。
それをAさん、Bさんそれぞれの事務所でやると、多面的に候補者その人を見ることができるし、それぞれの事務所の反応もわかって面白いですよ。
「この選挙区では、どんな怪文書が出ていますか?」
選挙中は怪文書(発信元や信憑性が不明な匿名の文書)が飛び交うので、選挙事務所にたくさん保存されています。「どんな怪文書出ていますか?」と聞くと、「ちょっと待ってね」と奥から持ってきてくれることも。読んでみると「これは本当なんじゃないか?」思うような内容もあったりして、候補者を多面的に見る意味でもすごくいい経験になりますよ。
構成・取材・文/国分美由紀