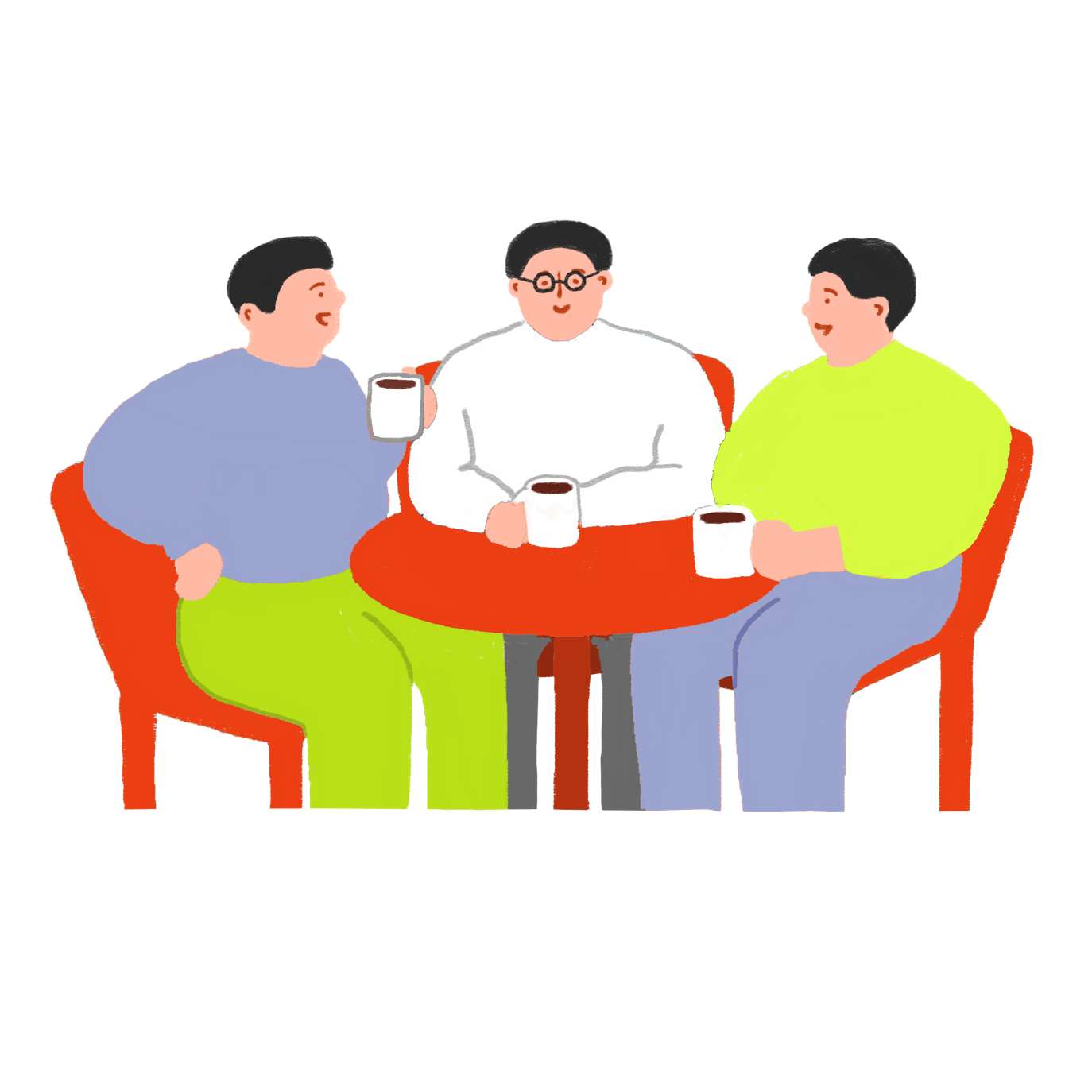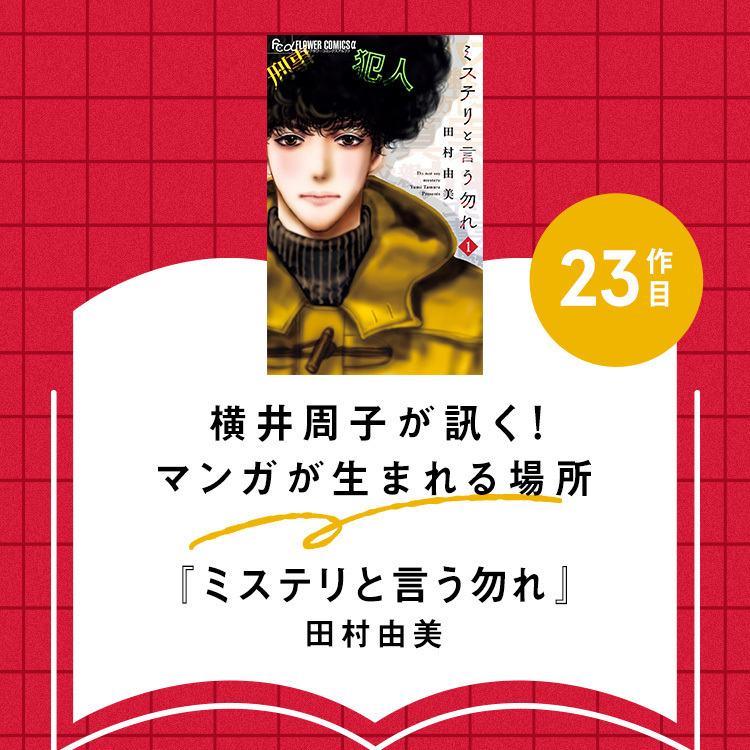“別れ”と感じるのは自分の主観。僕のなかでは、“別れ”はないんです

この辺で春一番の白い花。ポツンと。
冬から春へ。日差しに暖かさを感じる日が多くなると、わくわくする気持ちとは裏腹に、卒業だったり、仕事の異動や転職だったりで、“別れ”を意識することが増えます。生きていれば“別れ”があるのは当たり前ですが、それでもなんとなくセンチメンタルになりがちです。
「僕もこれまでの人生で、会わなくなった人、ご縁が切れた人など、いわゆる“お別れ”をいっぱい経験してきています。でもね、別れという感覚は主観的なものだと思うから、客観的な現実を悲しみとして自分の心にすり込みつづけなくても、って思っています。だから、僕のなかでは、誰とも別れていない。ちょっとわかりにくいですか?
“別れ”と聞いて、僕が真っ先に思うのは“死”のことかな。例えば、自分と近しい人がまだ若いのに亡くなってしまうというのは、自分自身どうしたらいいのかわからないくらいショックを受けるもの。すごく仲良くいつも一緒にいたときもあれば、いろんな事情であまり会えない時期もあり、それでも当たり前のように時々『元気かな』と思い出す。そんな人が亡くなったと聞いたら、心に大きな穴が空いてしまったような悲しみで落ち込んでしまいますよね。でもよく考えると、その友人と僕のそれまでの歴史は何も変わらず、生きているあいだも、亡くなってからも、やっぱり時々思い出しては心の中でその人と会話している。だから、友人と僕との関係は全然変わっていないってことにあるとき気づいたんです。つまり、僕の主観では別れていないんですよね」

きれいな水の流れだと思っていたら、そこには空が映っていました。
「あるいは、例えばリスペクトし合えないパートナーと別れたとします。もちろん、別れた直後は傷ついているし、イヤな思い出がフラッシュバックするかもしれない。でも、時間がたつうちに新しいことで気が紛れ、思い出す頻度が少なくなっていき、徐々に心の傷が癒えていきます。これも自分の主観。“忘れたい”という自分の意志が働くことで、思い出さなくなり、徐々に忘れていく。逆もしかり。『あのときに戻りたい』という気持ちや『悲しい思い出』を何度も脳内再生していたら、やっぱりその思いにとらわれたままだと思うんです。
この先も身近な人が亡くなったり、家族や友人と離れたり、失恋したり…本当にいろいろな“別れ”があります。でも僕のなかでは、自分が死なない限り、本当のお別れはないと思っているんです」
失恋を手放すことで、新たな人、コトに出合えることもある

前だけ見ていたけど、振り返ってみた。
『別れというのは自分の主観』という吉川さんの考えは、目からウロコでした。とはいえ、例えばフラれた、という形の失恋は、忘れようと思ってもなかなかそうはいかないもの。ましてや、同じ生活圏にいれば、相手の姿や情報が自然と目に入ってきてしまったり。
「近しいところにいて目に入ってきてしまうのなら、本当はその環境から離れるのがいいんですけれどね。人それぞれいろんな事情はありますが、見るも見ないも、最後は自分の意志ですから。失恋は傷と同じで、触りつづけるとなかなか治らないんです。触らなければ、治りも早い。そのためには、別の好きなコトを見つけるのがいいんじゃないかな。暇だと必要以上に傷を見直しちゃいますからね。
別れはとかくネガティブにとらえがちですが、別れがあることで、新しい出会いやチャンスがあると思うんです。それに、終わった恋愛には必ず理由があったわけで、どちらかがそれを無理につなぎ止めようとしたら、最後にはみんなが苦しくなってしまう。時には、つらくても手放すことが大切なこともある。失恋の相手にいつまでも固執するのは、ちょっとしたアディクト(依存・中毒)があるのかも。であれば、次にアディクトできるものを見つけられれば、そこから抜け出せると思います。失恋のアフターフォローは、いかにポジティブなアディクトをほかに見つけるか、にかかっているんじゃないでしょうか。
…と、僕の意見を述べてみましたが、若い人にはこれ、あまり響かないんですよね(苦笑)。失恋は、やっぱりつらくて、苦しくて、必死にもがくものですからね。でも、いつか忘れられるし、ひとつの恋が終わったからといって一生恋愛をしない、なんてことはありませんから。
ずっと同じ環境に居続けられる人はいません。別れを経験して、新しい環境、人との出会いがあったのなら、怖がらず、そこにどっぷりつからないと。新しいコトってジャンプインしないと手に入らないんですよ」
「この世の終わり」と思える別れを経験したとしても、人生はそれで終わりではありません。生きてさえいたら、時間がかかったとしても少しずつ、自分なりに受け入れられます。そうして、これまでとは違った何かに出合えるのも、また人生の醍醐味ですね。
取材・文/藤井優美(dis-moi) 撮影/Mikako Koyama 企画・編集/木下理恵(MAQUIA)