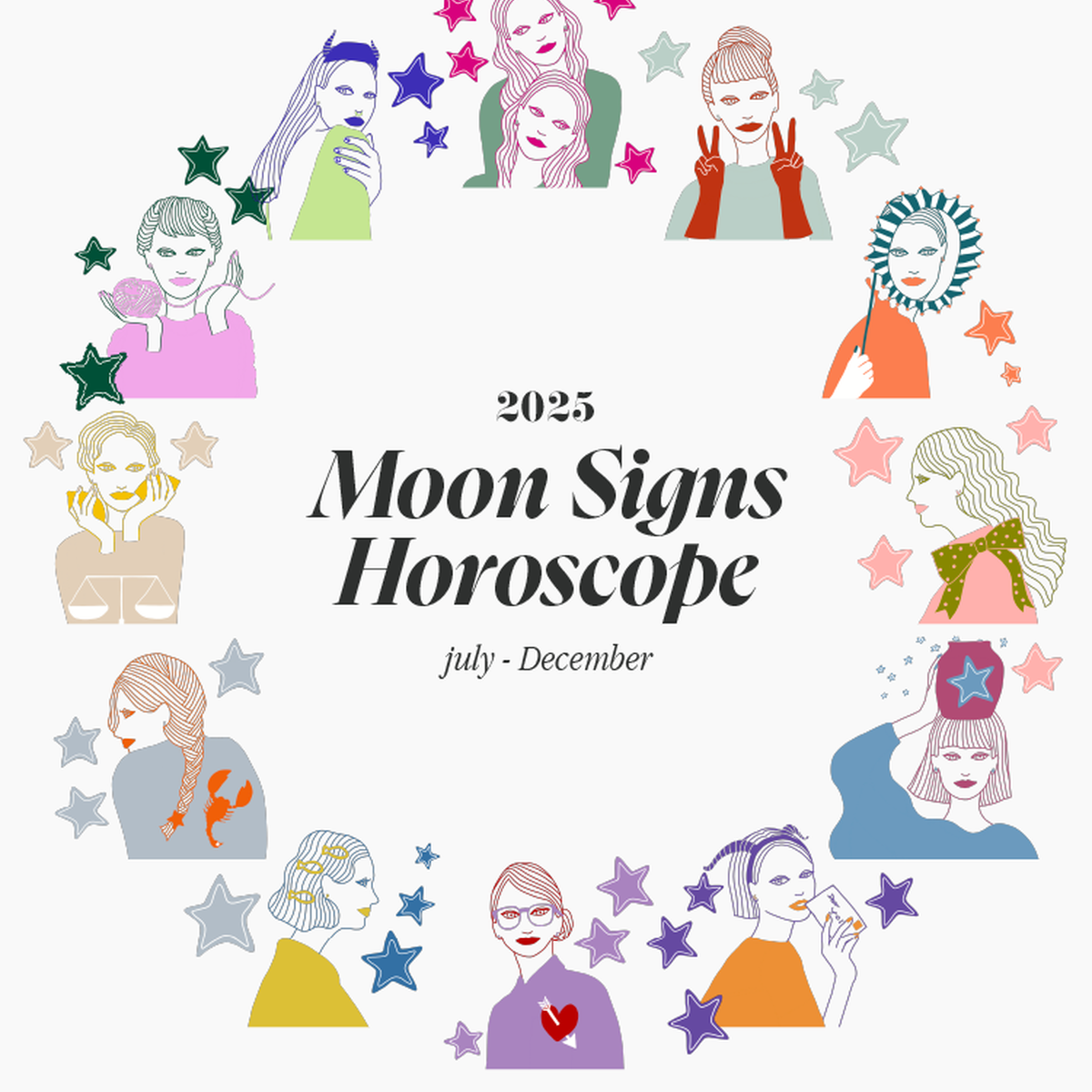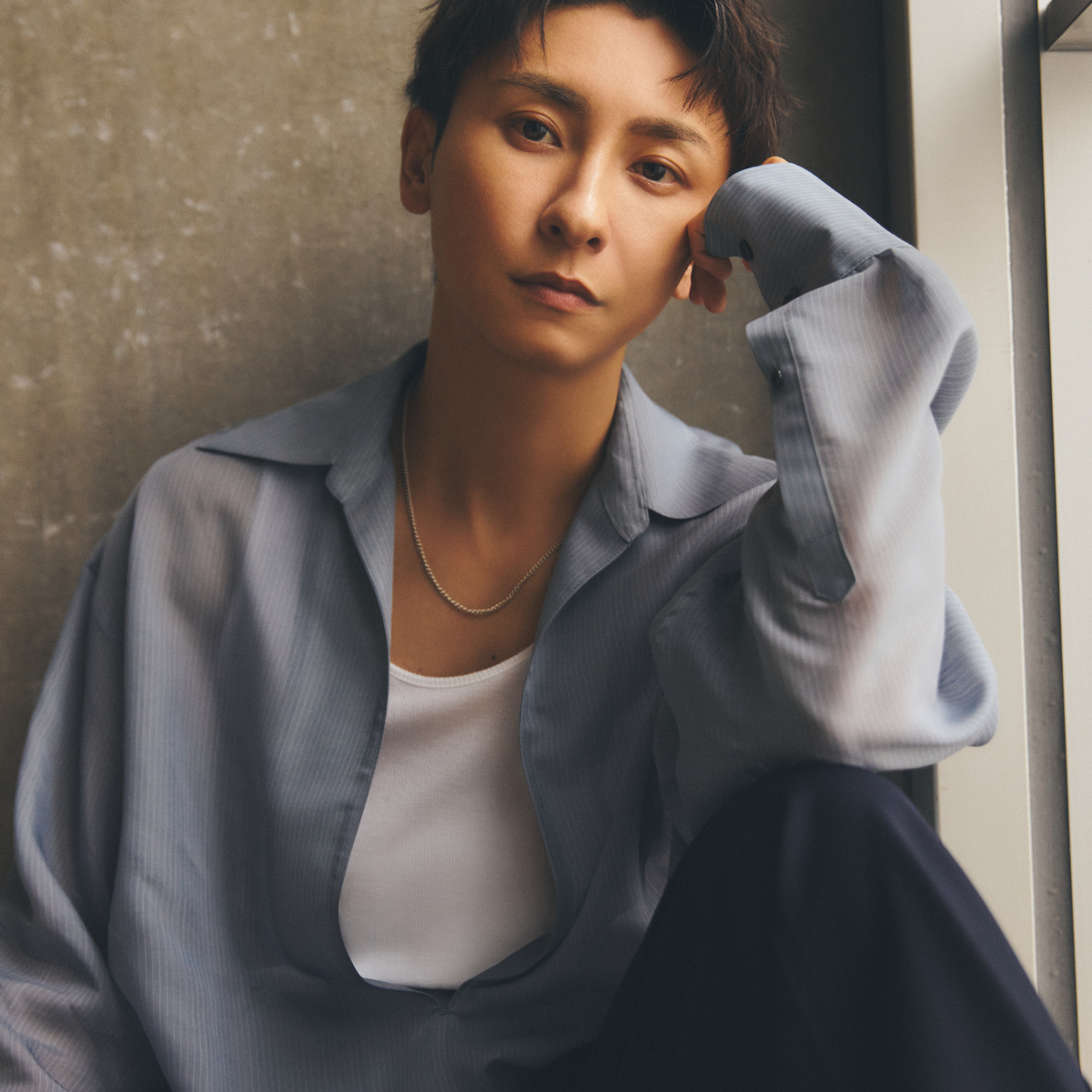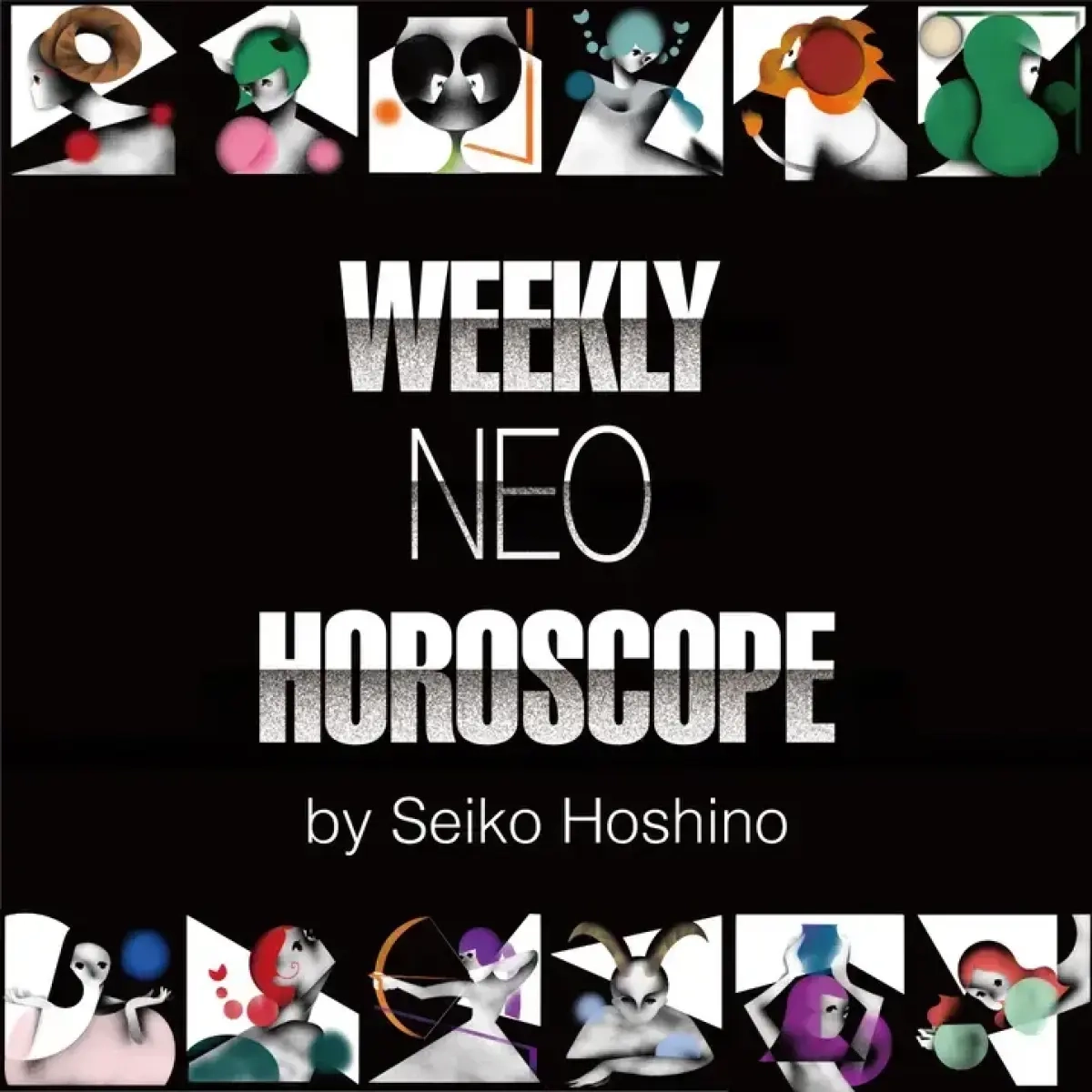2024年、yoiでご紹介したメンタルヘルス・人間関係記事の中でとくによく読まれた人気記事は? TOP5をまとめてご紹介します!
人気1位◆【パーソナリティ障害とは?】精神科医・藤野智哉先生が回答!日常の困りごととして現れる症状を解説
最も読まれた記事は人間関係が長続きしない、よくトラブルになるといった困りごとを抱えやすい「パーソナリティ障害」について。その定義や考えられる要因といった基礎知識から、病院を選ぶ際のポイントまで精神科医の藤野智哉先生に教えていただました!

Bibadash/Shutterstock.com
自分や他者が困りごとを抱えてしまう「パーソナリティ障害」
そもそもパーソナリティは個人差のあるものですが、平均からの著しい偏りをパーソナリティ異常と捉え、その異常性のために自分自身、あるいは他者や社会が困りごとを抱えている状態を「パーソナリティ障害」としています。パーソナリティ障害の割合は、人口の10〜20%ともいわれ、人間関係での問題を抱えやすい状況にあります。
最近は、パーソナリティ障害も含めた疾病にまつわる簡単なチェックリストがネット上に出ていますよね。自分の特性を知ることに興味を持つのは必ずしも悪いことではないけれど、安易に自分にレッテルを貼ってしまうのはよくないなと思います。自分で貼ってしまったレッテルって、剥がすのがすごく難しいので。
パーソナリティ障害には生育環境や家族との関係、社会要因など、さまざまな要因が影響するといわれています。また、研究によって、先天的な要因(遺伝性)もある程度関与していることがわかっています。
もし、「変わりたい」と思っているとしたら、しんどい状況の要因になっている考え方や、その考えの根底に目を向けていく必要があります。そのパーソナリティの存在自体を否定するのではなく、それがなぜ障害になっているのか、どうすれば影響を減らせるのか考えていくことが必要です。その場合は、心理学的カウンセリングや行動療法などを行います。
人気2位◆【『GIVE & TAKE』に学ぶ組織心理学まとめ】「テイカー」「ギバー」「マッチャー」、あなたの職場にいるのはどのタイプ?
人気第2位はこちら! 組織心理学者のアダム・グラントが執筆し、24カ国語以上で翻訳された大ベストセラー『GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代』(三笠書房)。この本を監訳した楠木建さんに、ギブ・アンド・テイクにまつわる3タイプの特徴や、それぞれの違い、コミュニケーションのポイントなどについてお話を伺いました。

natrot/Shutterstock.com
──楠木さんが監訳された『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代』では、他者とどのように「ギブ・アンド・テイク」をするかが仕事における成功を大きく左右すると書かれていましたが、その根底にある人間の思考と行動の3タイプを次のように表現していて、大変興味深かったです。
⚫︎テイカー(受け取る人)→「何をしてもらおうか」と考える。
⚫︎ギバー(与える人)→「何をしてあげようか」と考える。
⚫︎マッチャー(バランスを取る人) →「何かしてくれたら、私も何かしてあげる」と考える。
楠木さん 組織心理学者であるアダム・グラントは、人間の思考と行動をシンプルな3タイプに分けていますが、ギバーだからといって、「ひたすら他者に与えるだけ」ではなく、同様にテイカーも「人から受け取ろうとするだけ」ではありません。
どのタイプもギブ・アンド・テイクしながら仕事をしていますが、ギバーとテイカーとマッチャーでは、そこにいたる筋道がまるで異なるのです。
──道筋の違いについて、ぜひ詳しく伺えますか。
楠木さん 3タイプの本質的な違いを理解するには、それぞれの意図や行動を時間軸から見るとわかりやすくなります。ポイントは、「ギブ」と「テイク」のどちらが先に来るかということです。
⚫︎テイカーの目的:「テイク」すること
何でも自分中心に考え、自分の利益を得る手段としてのみ相手にギブする。裏を返せば、テイクという目的を達成する手段として有効だと考えれば、テイカーは実に積極的にギブすることもある。
⚫︎ギバーの目的:「ギブ」すること
思考と行動の順番がテイカーとは逆で、まずギブしようとする。相手のことを考え、見返りなど関係なくまず相手に与える。その際、目的としてのテイクがあるわけではない。その結果、はからずもどこかからお返しをもらえる。
⚫︎マッチャーの目的:「ギブ」と「テイク」の帳尻を合わせること
与えることと受け取ることのバランスを取ろうとするタイプなので、「これだけのことをしてもらったから、私も同じくらいお返ししよう」と考え、行動する。ギブが先行すればすぐにテイクして補完しようし、テイクを感じると意識的にギブをするので、ギブとテイクの間に時間的なズレがあまりない。
人気3位◆【令和の同調圧力まとめ】今、日本には圧を感じる“ずるい言葉”が蔓延。どう抵抗する?
第3位は令和の同調圧力について。価値観が大きく変化し続ける現代。多様性がキーワードになりつつあるものの、依然として「同調圧力」は存在しています。さまざまな価値観が混在する“今”だからこその同調圧力とは? 抵抗するには? 圧を感じる“ずるい言葉”への返し方まで、社会学者・貴戸理恵さんにお話を伺いました。

貴戸先生:現代では価値が多様化している一方で、根強い同調圧力があります。この「多様なのに同調を迫られる」という不思議な状況について考えるとき、3つの価値を腑分けしてみることがヒントになります。
まず「伝統的な価値」。戦後の高度経済成長期に広まった「日本型」の家族や企業、教育などに根差した価値を、そう呼ぶことができます。男は仕事・女は家庭という性別役割分業、痴漢やセクハラが当たり前の環境、滅私奉公の奨励、「仲間である」ことを認識するための非合理な慣行……。これらは差別や偏見を含んでいたり時代に合わなかったり、見直す必要があるものも多いです。
次に、多様性を肯定する「リベラルな価値」。これはマイノリティの権利の尊重や共生の思想などいろんなものを含んでいます。女性だからといって妻や母という役割に閉じ込められなくていい、LGBTを含む性的マイノリティの権利を尊重すべき、障害の有無や国籍の違いにかかわらず共に生きる社会をつくる、というものですね。
もうひとつは「市場的な価値」です。これは競争に勝つ、能力を高める、個性を生かして生産活動をする、消費を通じて承認を得る、などを重視する考え方です。
現代では、この「伝統的な価値」「リベラルな価値」「市場的な価値」が三つ巴のモザイク状になっています。そして、人々は属するコミュニティや状況により、これらの価値観それぞれから──特に「伝統的な価値」と「市場的な価値」から──「こうであれ」という同調圧力を受ける可能性があり、身動きが取りづらくなっていると考えられます。
人気4位◆【クオーターライフクライシスまとめ】アラサーが感じるキャリア、人生、妊娠や出産への不安。解決のヒントはここに!
「これまで築いてきたキャリアは間違いだった気がする」「大きな不満はないけれど、今の会社でスキルアップしていけるか不安」…。20代後半から30代半ばで感じる人生への漠然とした不安は、「クオーターライフクライシス」と呼ばれ、キャリアにおいてもこの壁にぶつかる方は少なくないようです。
どのようなアプローチをとればいいか、女性の働き方やキャリアに精通する『doda』副編集長の川嶋由美子さんに伺った記事が4位に!

──20代後半のyoi読者からは、「自分が思い描いていたキャリアとは違う方向に進んでいる気がする」「これまでやってきた仕事は間違いだったのではないかと思う」といった声を聞くことがよくあります。キャリアアドバイザー歴が長い川嶋さんのもとにも、そのような声が届くことはありますか?
川嶋さん 私の体感では、その世代の方の90%はキャリアに悩んでいるように思いますね。20代後半の方が感じるモヤモヤは「クオーターライフクライシス」とも呼ばれていますが、私たちキャリアアドバイザーから見ればむしろ、悩んでいるのが当たり前じゃないかなと。
──悩んでいるのが当たり前! 心強い言葉です。20代後半で仕事に対してそういった感情を抱いてしまう人が多いのは、なぜなのでしょうか?
川嶋さん 新卒の頃には見えていなかった、さまざまな“リアル”が見えてくるタイミングだからだと思います。新卒で入った会社にずっと勤めている方であれば、30代の先輩たちの姿から給与の上がり幅や昇進の条件などが見えてくる頃でしょうし、転勤を経験した方であれば、勤務地が変わることの大変さも実感されているでしょう。他社に勤めている友人と久しぶりに会ってみたら、結婚していたり家を購入した人がいたりして、自分との差を感じたという声も非常によく耳にします。
20代前半の頃は漠然としていた「10年後の自分」像にリアルな手ざわりを感じるようになり、このままでいいのだろうか…と悩む方が多いのだろうと思いますね。
人気5位◆なぜ私たちは「顔」に執着するのか?脳のメカニズムや社会的背景を読み解く!【中野珠実さんインタビューまとめ】
毎日、当たり前のように見つめている自分の「顔」。誰かと比べて落ち込んだり、SNSに載せる顔写真を加工したくなったり…そうした心の動きには、脳のメカニズムが深く関係しているといいます。私たちの心と顔の関係について、『顔に取り憑かれた脳』の著者である中野珠実さんにお話を伺いました。脳が自分の「顔」をVIP扱いする仕組みや「顔」への執着から自由になるためのヒントについても教えていただきました。

──2023年12月に上梓なさった『顔に取り憑かれた脳』に、「顔」は他者や自己を理解し、コミュニケーションするうえで重要な意味を持つと書かれていましたが、まずはそこから伺えますか。
中野 私たちは、現在やこれからの社会でよりよく生きていくために、どういう行動を選択するべきかという意思決定をつねにしています。より最適な選択をするために重要なのは、自分に関連する情報を集めて状況を正確に理解・評価することです。
自分の顔を見ることは心身の状態や快・不快などの感情を知ることにつながり、自分の顔が相手にどう見えているかを知ることは、相手や社会に与える印象を推測したうえでより適切な振る舞いや選択をすることにつながる大切な要素となります。
──「自分」というものを思い浮かべるとき、現代の私たちは自分の顔をイメージすることが多いと思いますが、鏡がなかった時代の人たちは「自分」をどんなふうにとらえていたのでしょう?
中野 権力の象徴であり、宝物であった鏡を庶民が持てるようになったのは、江戸時代以降だといわれています。多くの人が今ほど自分の顔をよく知りえなかった頃の「自分」は、もっと漠然としたものだったのではないかと思います。