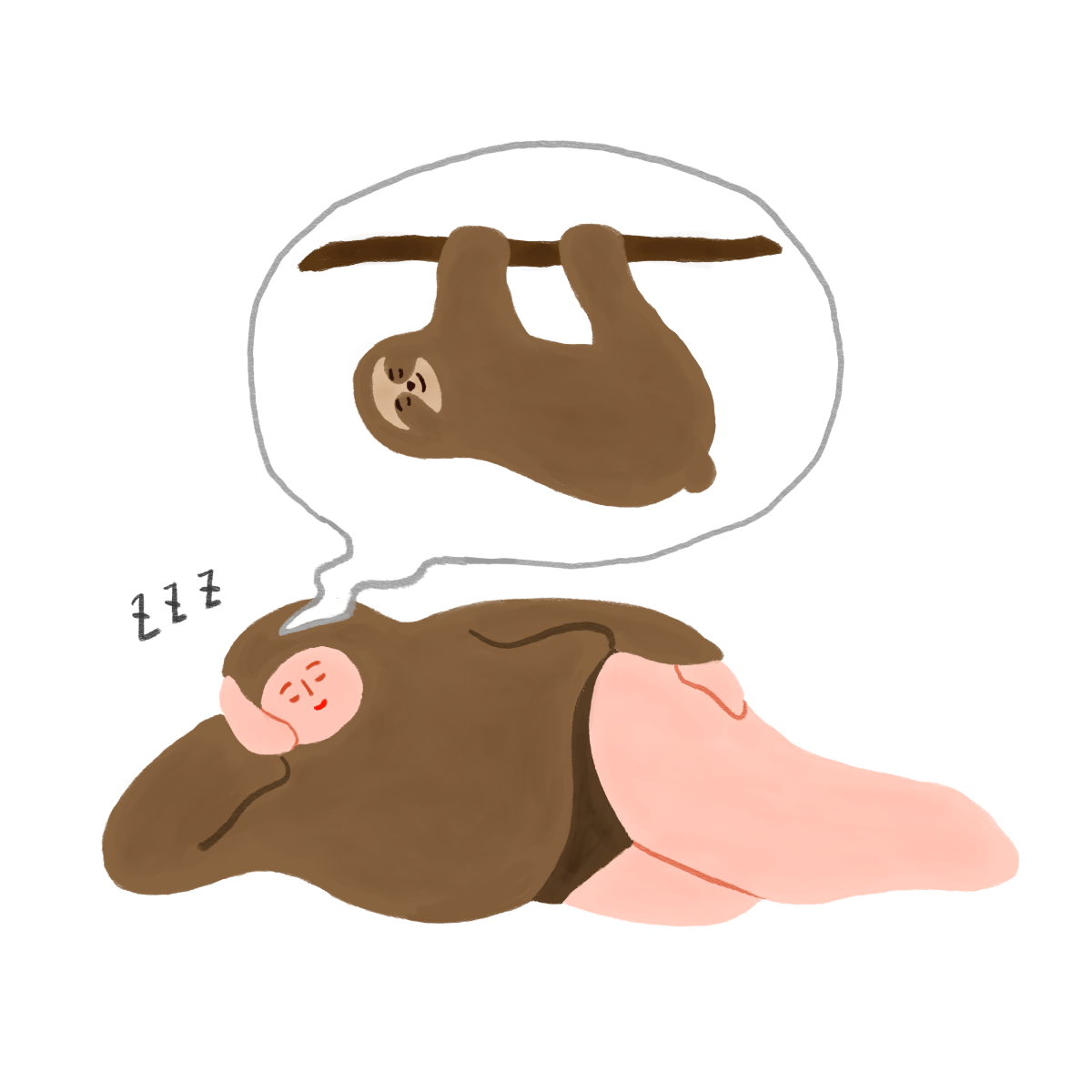2024年3月に『ノンバイナリースタイルブック』(柏書房)を刊行された漫画家の山内尚さん。「ノンバイナリー」かつ「ジェンダーフルイド」当事者として、揺れ動く性別の中で「装い」と向き合い、その時の気分にあったコーディネートをイラストで紹介しているスタイルブックは、当事者だけでなくさまざまな人からの反響があったそう。友人のひと言から、ご自身のアイデンティティについて考えるようになった中学時代、カミングアウトをせざるを得なくなった大学での“ある事件”についてなど、山内さんがこれまでどのように自分自身と向き合ってきたのかについて、伺いました。

『ノンバイナリースタイルブック』山内尚(柏書房)
男女二元論で説明しきれない性別を生きるノンバイナリー当事者として、ままならない「装い」の問題に、漫画、イラスト、文章で向き合う作品。
山内さんと、「ノンバイナリー」「ジェンダーフルイド」というアイデンティティとの出合い


——まず、「ノンバイナリー」そして「ジェンダーフルイド」とはどのようなものだと考えていらっしゃいますか?
山内さん 「ノンバイナリー」や「ジェンダーフルイド」の定義は、当事者の方の中でもそれぞれなんですよ。なので、私のとらえ方を説明するとしたら、「ノンバイナリー」とは、「性自認が男性だけでも、女性だけでもないこと」です。つまり「私は女である」「私は男である」以外の在り方、と思っています。どちらでもない場合もあれば、真ん中であることも、行き来していることも、その他あらゆる二元論に基づかない在り方が「ノンバイナリー」ではないかなと。そして「ジェンダーフルイド」は、「その人の在り方が変化、流動するもの」と私はイメージしています。
——では、山内さんがご自身の在り方について考えるようになったきっかけや、その過程をお伺いできますでしょうか。
山内さん 生まれたときに割り当てられた性別は女性でしたが、自分のことについて考えるようになったのは、中学生の頃です。最初のきっかけは、同級生の友達に「バイセクシャルなの?」と聞かれたこと。当時は男性とおつき合いすることもあったのですが、友達の発言を受けて、「女の子を好きになるという選択肢もあるんだ」と気がつきました。そこから、自分のことをバイセクシャルかもしれないと思うように。
高校生になってからは、自分の性自認にさらに真剣に向き合うようになり、「女性が好きだということは、つまり私は男性になりたいってことなのか?」と考えました。でもつきつめると、「私は男の人になりたいわけではない気がする」と思ったんです。
おそらく私はその頃からずっと、性自認がふわふわしていて、時期によって男性・女性どちら寄りかの度合いが違ったり、真ん中だったり、どちらでもなかったりしていたんですよね。それに応じて着たい服も変化していました。当時の私は、そんな自分を説明できる言葉が見つけられず、迷子状態だったんです。なので、大学生のときは自分のことを暫定的に「シスジェンダー(=体と心の性が一致している)の、レズビアン」「いろいろなジャンルの服を着るのが好きな人」としていました。
——そこから、ノンバイナリーでジェンダーフルイドである、と自認するようになったのですね。
山内さん 大学を卒業する頃には、「レズビアン」という言葉がしっくりこない自分に気づいたのですが、「じゃあ私は何者なのか」というところには答えが出ていなくて。
そんな中、ある日ネットで「ジェンダーフルイド」という言葉を見つけたんです。当時、英語圏のWeb上の辞書には、「男か女かその日で変わる」と書いてありました。私には「男か女かの二択」という感覚はなかったけれど、この単語との出合いは、かなり衝撃的だったのを覚えています。
自分の在り方をオープンにして何が悪い?

——セクシャルマイノリティの方は、ご自身の在り方を受け入れられるようになるまで時間がかかる方もいると聞きます。山内さんは、ご自身が「ノンバイナリーかつジェンダーフルイドである」ということを、すぐに受け入れることができたのでしょうか?
山内さん 私は自分を説明できる言葉をやっと見つけた…という思いでした。なので葛藤はなく、むしろすぐに納得しましたね。「この言葉、ナイスアイディア!」と言ったところでしょうか(笑)。私自身が何者かを説明するのにとてもぴったりな言葉だと感じたんです。今はもっとしっくりくる言葉がまた出てくるのかも?と思うこともありますが。
もちろんさまざまな事情で受け入れることが難しい方もたくさんいらっしゃると思います。私はその点についてはたまたま恵まれていたのかな、と。周囲にカミングアウトするタイミングも早かったと思います。
——まわりの方のご理解も早かった、ということなのでしょうか?
山内さん 実はそういうわけでもないんですよね。というのも、カミングアウトは自分で時期を決めたわけではなく、そうせざるを得なくなる事件がありまして…。大学時代は一部の友達にだけカミングアウトしている状態だったんですが、ある時、自分が伝えた覚えのない人から、「レズビアンなの?」と言われたんです。
それを聞いて、「このままウワサが広まったら、何か不本意な尾ひれがついてしまうかもしれない…」と怖くなり、「偏見やウワサではなく、私自身の口から言ったことで判断してほしい」という考えから、全部オープンにしようと決めました。もちろん傷つくこともありました。言ったところで伝わらないこともたくさんありましたし、「あなたなんて“本物のノンバイナリー”じゃない」と言われたりもしましたね。
【再放送のお知らせ】
漫画家の山内尚さんを取材した10分間のドキュメンタリー「それは偶然ひっついてきた乳房」
今月はなんと2回再放送あります!
BSではまもなく!!
NHKBS⁰4月13日(土)午前2:55 〜 午前3:05
⁰Eテレ
4月20日(土)午前3:49 〜 午前3:59https://t.co/Otd0t3WKZu
— つぶつぶ (@tsubutsubu_q_p) April 12, 2024
——傷つきも体験されているのですね。それでも山内さんはオープンにし続け、今ではご自身の在り方について発信し、著書も刊行されています。そのエネルギーはどこから来ると思いますか。
山内さん 私にあるのは「自分のアイデンティティについて話して何が悪い」という精神ですね。だって、「私の在り方はこうだよ」という説明をしているだけじゃないですか。悪いことを言ってるわけじゃない。SNSや漫画で発信しているのは、「みんなどう思う?」と聞いてフィードバックをもらうのが好きだから。もともと、自分の意見を言って人と議論するのが好きな性格なんです。議論といっても、友達と意見交換をするような気持ちでいるので、傷つけ合う言葉の応酬とは違うものだと思っているんですけど。
先ほどカミングアウトで傷ついた話をしましたが、逆にハッピーなこともたくさんあります。先日、トークイベントに来てくださった方が、私がX(旧Twitter)で発信した「ノンバイナリー」と「ジェンダーフルイド」についての漫画が、自分を説明する際にとても役に立っていると言ってくださったんです。こういうことがあると発信し続けていて本当によかった、と感じますね。
…といってもこれは私のケースです。人生にカミングアウトが必要ないとしたら、それはそれでいいことだと思いますし、カミングアウトをするにはその方を取り巻く環境がシビアな場合もあります。けれど、カミングアウトをすることで、心のつかえが取れたり、抑え込んでいたものが開放されて楽になるのならば、人を選びながら自分の在り方を伝えてみてもいいと思います。
もし周囲に話すことに抵抗があれば、ネットにいる似た環境の方や、信頼できるカウンセラーなどプロの方にお話しするだけでも、QOLは上がるのではないでしょうか。
取材・文/東美希 企画・構成/種谷美波(yoi)