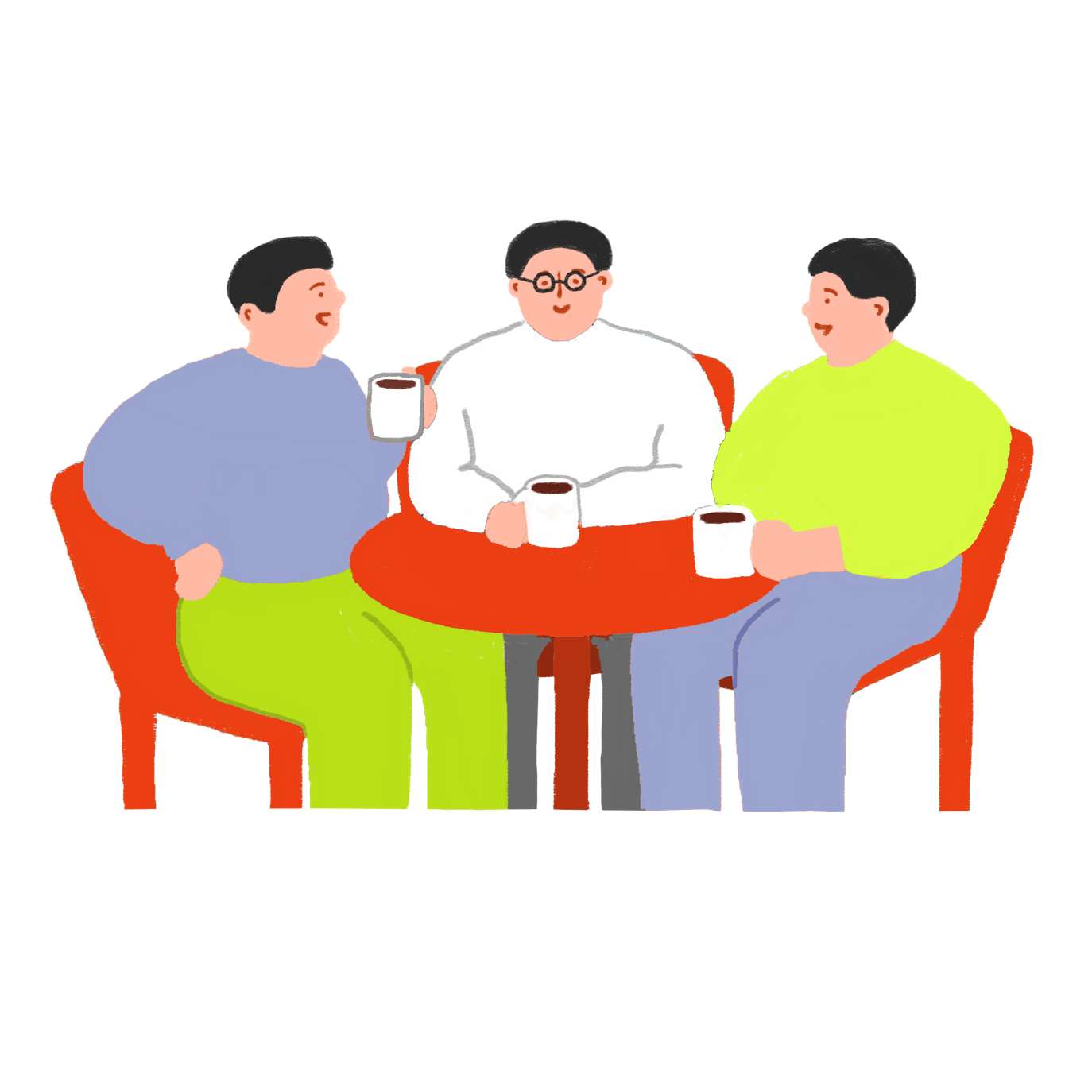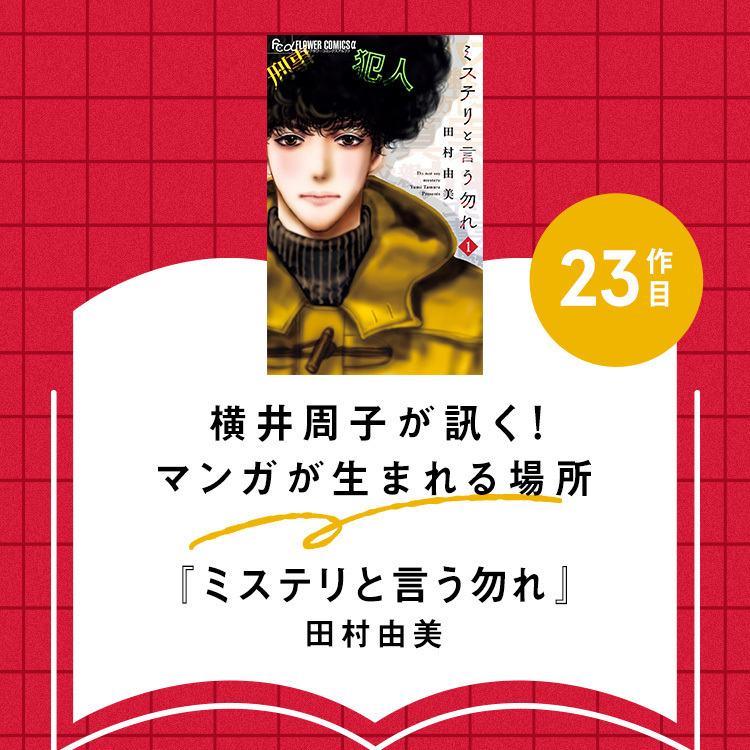“男性・男児の健康に目を向け、ジェンダー平等を促す”ことを目標とする「国際男性デー(11/9)」への認知が広まるなど、男性の生きづらさにも焦点が当たり始めている昨今。今を生きる男性から見る「ジェンダー」とは、どのようなものなのでしょうか。社会学者であり男性学を専門としている田中俊之さんと、フリーの編集者・ライターとしてジェンダーに関する記事や書籍に携わる福田フクスケさんにお話をお聞きました。
時代? 価値観? 男性であるふたりの「ジェンダー」意識

――おふたりが「ジェンダー」を意識したタイミングや、価値観が変わったきっかけを教えてください。
福田さん:男性と女性の役割は性別で分けられるものではないという価値観は、小さい頃からうっすら持っていたかもしれません。子どもの頃から引っ込み思案で、いわゆる“男性的”な気質があまりなかったですし、両親も父が働き母が専業主婦というモデルではありましたが、休みの日は父も家事をする姿を普通に見ていました。
また、高校では吹奏楽部でしたが、部長やパートリーダーは、男女関係なく楽器経験の長さや演奏能力で選ばれることが多く、それに違和感もありませんでした。だから、「価値観が変わった」とか「気づけた」のではなく、たまたま恵まれた環境で育っただけ、というベースはあると思います。
大人になってからは、いわゆる非モテ男子であるというコンプレックスがきっかけで、女性が本心ではどう思っているのかを知りたいと思うようになり、男女論やジェンダー論、やがてフェミニズム関連の言説について読むようになりました。モテるためにナンパスクールなどに行って、女性を抱いた数を競うような価値観にのめり込まずに済んだのは、これもたまたまインストールした価値観の順番のおかげで、紙一重の差だったのかもとも思います。
田中さん:時代もあるかもしれませんね。福田さんは僕より8歳年下ですよね。実は僕も吹奏楽部だったんですが、福田さんのようにはなりませんでした。なぜなら僕が部長だったからです。吹奏楽部自体は女性の方が圧倒的に多かったけれど、男の先輩から「女は感情的だから上に立つことに向いていない。お前がやれ」と指名されたんです。しかも当時の僕はそれを、「ふーん、そうなんだ」と受け入れてしまっていましたね。
――では田中さんはどうして「ジェンダー」に関する価値観が変化したのでしょうか。
田中さん:最近明確に自覚したのですが、僕はそもそも「人が2種類」というところに疑問を持っているんですよ。だから「男はこう」「女はこう」と、たった2つの強烈な枠組みがあることにも抵抗を感じる。性別が2個しかなく、その片方を勝手に割り振られて、「あなたはこの生き方しかありません」と言われてしまうことが嫌で嫌でしょうがないんです。
「あなたは男性で、絶対に就職しなければなりません。次に労働から開放されるのは定年後です」と言われ、それをみんなが固く信じていた時代、僕はかなり居心地が悪かったんです。
だからジェンダーの問題に関心を持ったのだろうなと今振り返ると思います。きっと僕が女性に生まれていても、抗っていたでしょう。
今でも多くの男性は「男は強い方がいい」と思っている?

――生来の性格や考え方、環境によって「ジェンダー格差」に疑問を持つようになった、ということですね。ではそうでない男性……例えば性別的役割分業がある中で教育を受けてきて、それを“固く信じていた”男性の価値観は今、変わりつつあるのでしょうか。
田中さん:大きな目で見れば変わって来ているとは思います。90年代の男性学の本を読むと、チェックリストに「洗濯物を外で干せますか?」なんて項目があるんです。つまり、今から30年くらい前だと、「男なのに洗濯物やらされてるよ」という感覚があったということです。ベビーカーを押したり抱っこ紐をつけていると珍しがられる、なんて記述もあります。
今はそんな感覚、全然ないですよね。そう考えると、30年前とは雲泥の差があると思います。
福田さん:そうですね。特に育児は自分事としてとらえる男性が増えたと思います。でもこれは世代というより、共働きが当たり前になり、「保育園に入れない」「パートナーの給料が減らされる」というようなことが、“男性自身の”困りごとになったからかもしれません。
その反面、「いつ産休に入るかわからない女性が就職で不利になるのは当然だ」と経営者目線で主張する男性も、世代問わず今でもたくさんいますが、経営者からすると、それが“自身の”困りごとだからでしょうね。
田中さん:同感です。変わっていない部分もたくさんある。福田さんが以前お書きになった現代ビジネスの記事で引用されていた、作家・白岩玄さんの「バカとエロの大縄跳び」という表現がとても良いなと思っていて。今でも男性の多数はこの大縄跳びを続けているんですよ。
先日、近所の小学校高学年くらいの子が「俺、女の子の着替え11回覗いたことあるぜ!」って友達に自慢しているのを見かけました。「すごいな!」と思いましたね。もちろん悪い意味で。どうしてこんなことが令和の小学生にまで継承されているんだろう。
そういう状況を見かけると、男と女がいて、男は女が好きで、男の方が強くて…みたいな感覚を疑っていない人はまだたくさんいると感じますね。
福田さん:そうですね。ジェンダーについて記事を書く僕のような界隈では、「変化している」「変化しなければいけない」という情報が飛び交っています。でも、「この感覚は世間とは乖離している」と意識しておかなければならないな、と感じることがあります。やはりまだ「男は強いほうがいいんだ」みたいな価値観が、全体では主流だなと僕も感じます。
田中さん:あと、男性には「性別が自分の生き方に影響を与えている」という視点がない人も多い気がしますね。企業研修で、「定年退職後にすることがなくて困る人が多い」という話をしたあと、「定年退職者としてどんな人を思い浮かべましたか?」と聞くと、みんなおじさんを思い浮かべていたりする。
でも、定年まで働くことを“男性だから”はっきりと思い描けている、という視点がない。
「定年まで働くことが当たり前だと思えるのは、男性だからですよ」と言われて初めて気づく。マジョリティの男性は違和感を抱きづらいから、気づきにくいんですよね。
男性は弱音を吐けない。吐いても受け皿がない

――でも、その「男性はこうあるべき」というマジョリティの“当たり前”に違和感を抱いたり、苦しんでいる男性も多いのではないか、とも思います。
福田さん:そうですね。特に男性特有の苦しみが生まれやすいのは「社会の歯車から降りるという選択肢が許されていないこと」「弱音を吐いても社会に受け皿がないこと」ではないかと思います。
以前、田中先生に取材させていただいたときにおっしゃっていたことなのですが、夫が働き、妻が専業主婦・またはパートでサポートするというケースの場合、男性が「精神的にしんどいから仕事をやめたい」と言っても、家庭が立ち行かなくなるので実行できない。だから妻は夫の弱音に対して「どうにかして頑張ろう」と励ますしかなくなってしまうんですよね。
これは女性が悪いのではなく、構造の問題だと思いますが、男性のつらい点だと思います。女性が稼ぎ、男性が家事をするというケースもありますが、まだまだ少数派ですし、偏見もありますよね。
田中さん:僕もまさにそこだと思います。僕は2016年に『男が働かない、いいじゃないか!』という本を出したんですね。編集さんが本のタイトルだけ持ってきて、こういう本を出しませんかと誘ってくださったんです。そのタイトルを見たとき、「これやばい、売れちゃう!」と思ったんですよ (笑)。男性が抱えている問題を端的に、キャッチーに表現したタイトルだと感じたからです。
福田さん:「男だって弱音を吐いていいよ」「仕事をしなくてもいいよ」と言われたとしても、その受け皿がない。弱音を受け止めてくれる仕組みがない。仕事をやめたら詰んでしまう。だから「男は弱音を吐かない」し「仕事をやめられない」。そこにしっかり切り込んだタイトルだと思います。
田中さん:でも、そんなには売れなかったんですよ(笑)。そのときに、社会ってそんな簡単には変わらないんだと思い知らされましたね。
その本を買っている人を書店で見かけたこともあるのですが、新書と新書のあいだに挟んで、隠しながら買っていました。息苦しさを感じている人でも、手に取って、買って読むことが恥ずかしいと感じてしまうということですよね。問題は根深いな、と感じます。
でも僕は、ここを崩さないと、女性の社会的位置の向上や、セクシュアルマイノリティの方が社会で認められることは難しいんじゃないか、とすら思うんです。だってそれを邪魔しているのは「異性愛者男性」というマジョリティで、そんな彼らを支えているのは「男は何十年も文句を言わずに働く」を始めとする、「社会は男性がメインである」が前提の考え方だと思うからです。
▶︎続く後編では「男性のセルフケア」についてトーク。「男性は自分のケアが苦手」といわれるのには、どのような理由があるのでしょうか。
イラスト/キムラカオル 取材・文/東美希 企画・構成/木村美紀(yoi)