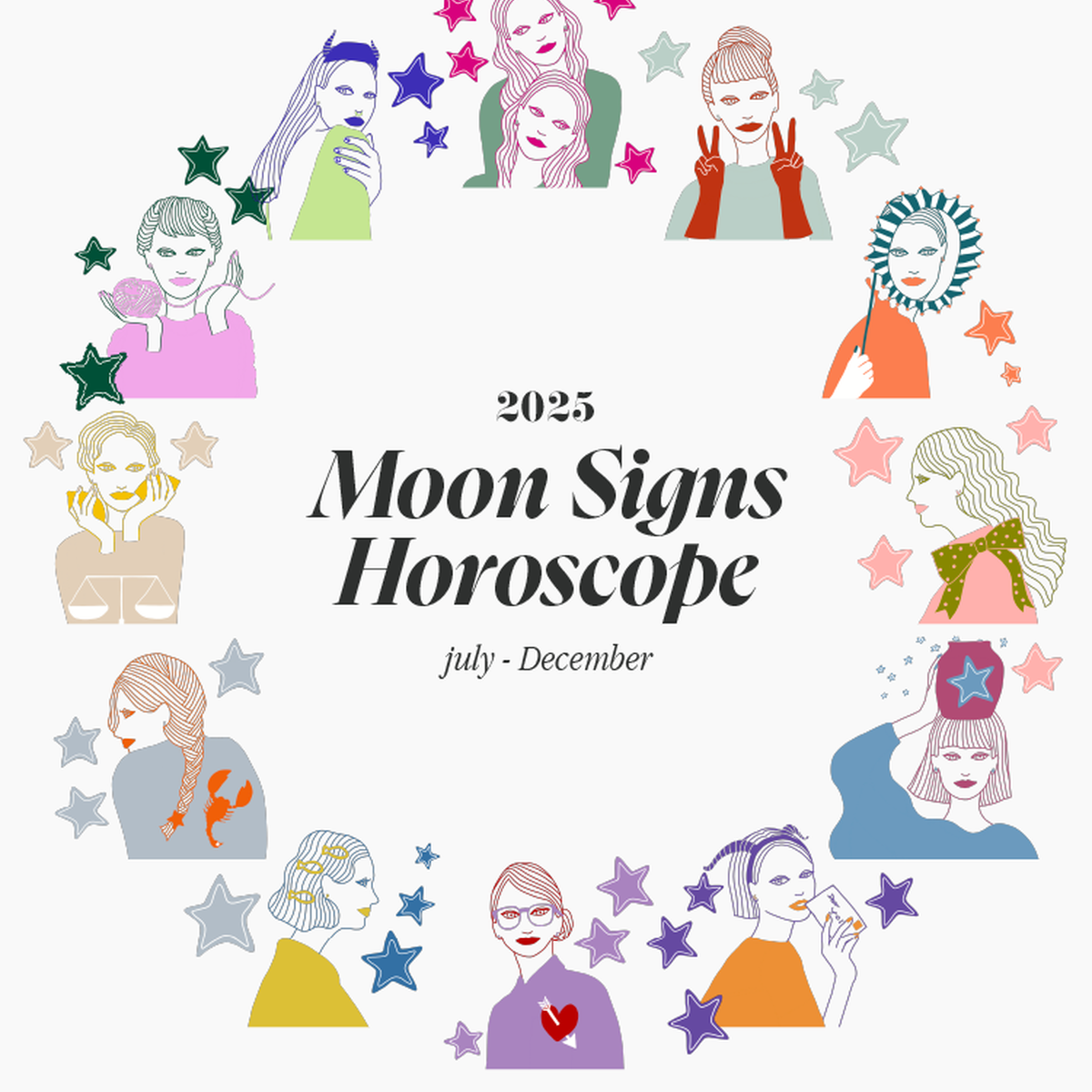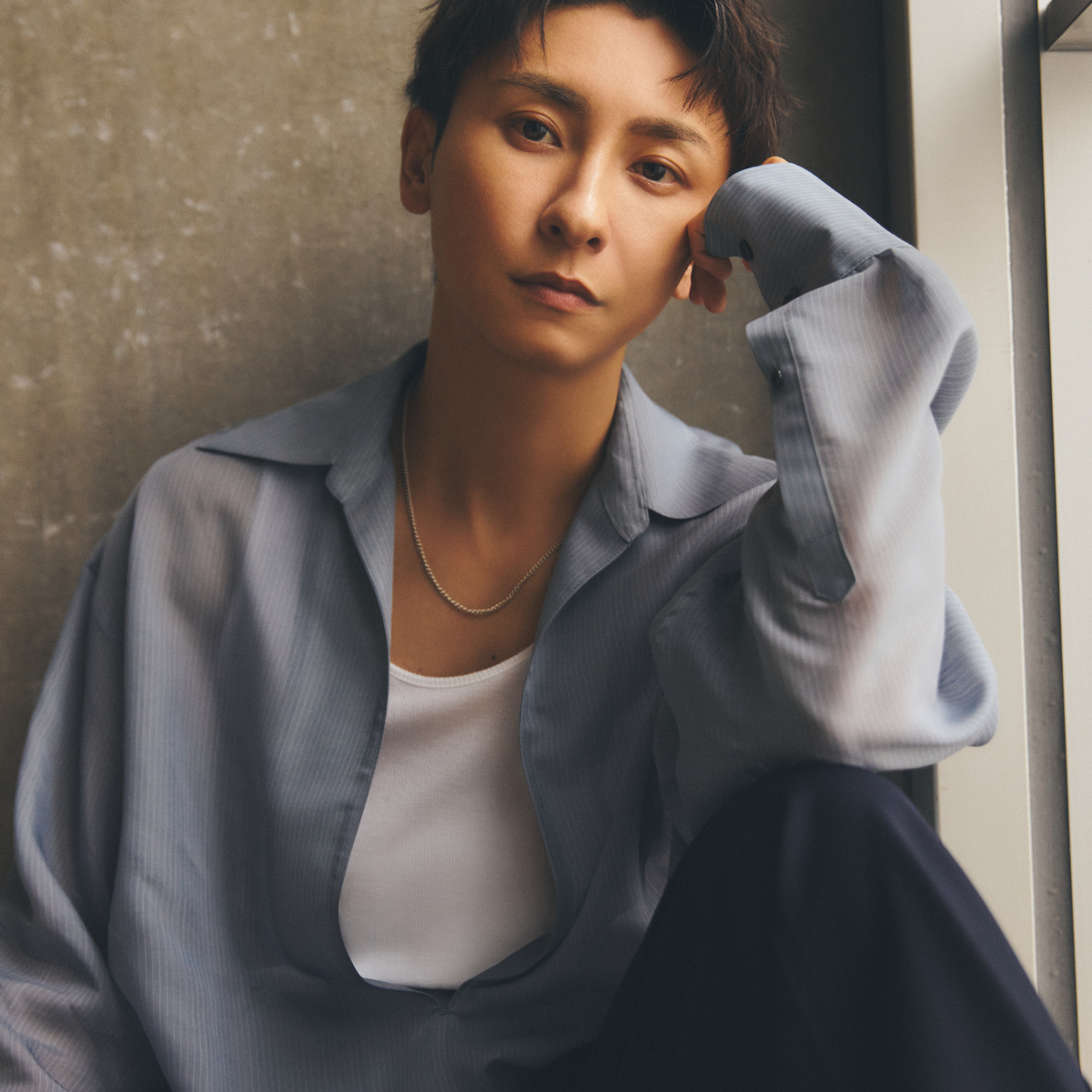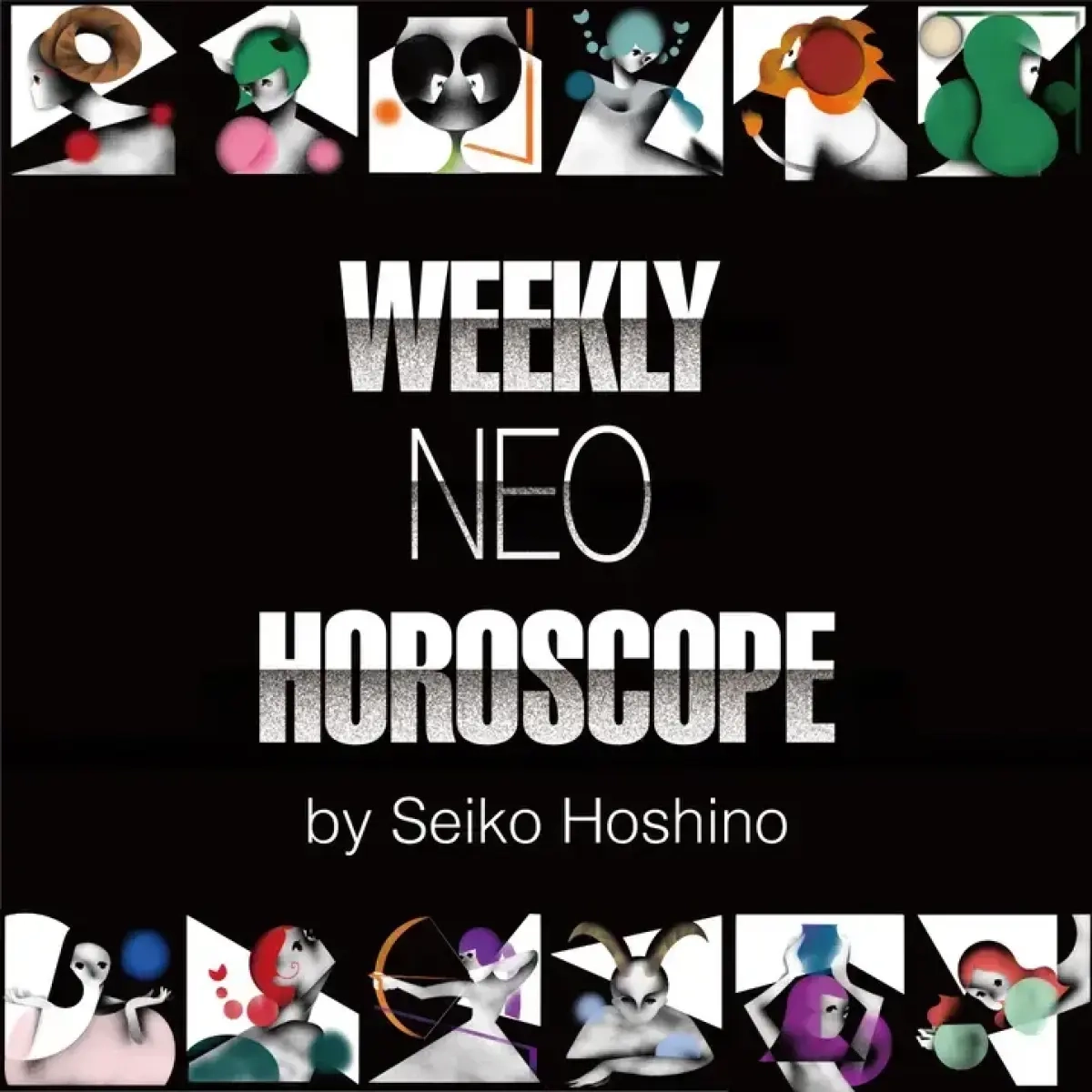メンタルヘルスの問題やジェンダーによる固定観念などに向き合う、フランス・パリ在住のアーティスト前田英里さん。私たちが抱える生きづらさの根源に気づかせてくれる陶芸作品を数多く生み出しています。昨年11月にはラフォーレ原宿にて、東京では自身初となる作品展「不適切な展示会」を開催。一時帰国していた彼女にインタビューを行いました。前編では、アーティストになったきっかけと、作品に込めた想いを伺います。
アーティスト
1989年生まれ。フランス・パリ在住。大学卒業後、グラフィックデザイナーとしてキャリアを積んだ後、2017年にセラミックアーティストへと転身。これまでにストックホルム、ミラノ、パリ、ロンドンなどで個展を開催。2024年11月には、東京では自身初となる作品展「不適切な展示会」をラフォーレ原宿にて開催し、大きな話題を呼んだ。
「可愛くなるためのチェックリスト」に悩まされた子ども時代

——まずは、前田さんがアーティストになろうと思ったきっかけを教えてください。
前田英里さん(以下、前田さん):子どもの頃、私の中での“可愛い”の基準は、雑誌のモデルやドラマの主人公たち。くっきりとした二重、小さな顔、スレンダーな体型——そういった容姿を持つ人こそが魅力的で、人気者になれると思い込んでいたんです。だから、「可愛くなるためのチェックリスト」を作って、それをひとつずつクリアするのに必死でした。
でも、17歳のときにアメリカへ留学して、授業で自分の意見を堂々と主張する同級生の姿を見て衝撃を受けたんです。それまで私は、「魅力的な人=容姿が美しい人」だと信じていたけれど、それは大きな勘違いで、実際には自分の考えをしっかりと持ち、話せる人こそが魅力的だと気づいたんです。それまで外見を磨くことだけに時間とエネルギーを注いできた自分が、すごく恥ずかしくなりました。それからは、どんなことにも「なぜ?」と問いかける意識を持ち、自分の考えや意見を大切にするようになって、自然とまわりの人との関係も深くなっていきましたね。そんなふうに留学生活を満喫していたら、体重を気にすることがなくなり、10kg太った状態で帰国。空港で母親からかけられた第一声が「太ったね」だったんです! 体重が増えたことは事実ですが、アメリカ留学で得た経験よりも体型の変化に注目されて、しかもそれがネガティブにとらえられる……。そのことがすごく悲しくて、またダイエットに励むことにしたんです。日本社会でサバイブしていくためには画一的な美の基準に従うほうが生きやすかったから。
ただ、以前と違って、私は「なぜ?」を考えられるようになっていたんです。「なぜ、私はこんなにも自分の体型を好きになれないんだろう?」「なぜ、可愛いの基準ってあるんだろう? 誰が作ってる?」と。その疑問に悶々と向き合い続けるうちに、「これはマーケティングだ!」と気づいたんです。例えば、「この色のアイシャドウが2025年のトレンド!」と言われると、時代に乗り遅れないためにも買わないといけないのでは?と焦りを感じてしまいますよね。
——確かに。電車の中や街で見る広告にも同じことを感じます。
前田さん:そう、それと同じで、私たちが無意識に感じている美の基準も、社会が作り出したマーケティングの一部に過ぎないのでは?と考えるようになり、かつて自分で作っていた「可愛くなるためのチェックリスト」に少しずつ抗うようになりました。だけど、体型だけはどうしても好きになれなかったんです。
そんな時に、ふと陶芸教室を見つけて、「私の体型が美しい花瓶になったら愛せるかもしれない」と思い立って、自分のおしりをモチーフにした花瓶を作るようになったんです。花瓶はお花を活けたら、毎日お水を替えないといけないですよね。その行為が、自分をケアしているような感覚になるとも思って。そこから2年間で300個ほど作り上げ、セラミックアーティストとしてのキャリアをスタートさせました。
——おしりの花瓶作りが、前田さんにとって一種のセラピーになっていたのですね。
前田さん:そうですね。この制作を通じて、私たちはどうしてひとつの基準に沿った体型になろうとしてしまうのか深く考える機会になりましたし、「みんな違う体型だからこそ面白い」と思い直すことができました。
現在は、一人一人の体型に合わせた花瓶を作るカスタムオーダーも受けています。例えば、大事故で体に傷跡が残り、それを気にしていた方が「この傷は消えないから、花瓶にその傷跡を再現してほしい」とリクエストしてくださったことがありました。ほかにも、火傷の跡がある方や、乳がんで乳房を失った方など、コンプレックスを抱えている方からの依頼を受け、その個性を反映した花瓶を作っています。
性やメンタルヘルスについて話しにくいのはなぜ? 30代で訪れた社会への反抗期

——おしりの花瓶でセラミックアーティストとしてのキャリアをスタートさせた前田さんは、ご結婚を機にフランス・パリへと30歳のときに移住されたそうですね。
前田さん:はい、パリに移住して、当然のようにメンタルヘルスやセクシャルヘルスなどについて友人とディスカッションする機会が増えたことで、これまで無意識のうちに従ってきた価値観やルールに対する「なぜ?」が次々と生まれてきて。30代に入ってから社会への反抗期が訪れたんです。
そして、そのエネルギーを糧に最初に取り組んだ作品が、快感を具現化した「Guilty Pleasure(ギルティープレジャー)」でした。この作品は、30歳のときにフェムテック企業で働いている友人から誕生日に、人生初のバイブレーターをプレゼントしてもらったことがきっかけで制作しました。私が10代、20代のときは「18禁」と大きく書かれたのれんの先にしかバイブレーターが売られておらず、「セルフプレジャー」=隠すべきもの、恥ずべきものというイメージがあり、興味はあったものの手を出せずにいました。
でも、友人にプレゼントしてもらい、実際に使ってみたら、「自分の体を知るきっかけにもなるセルフプレジャーって最高! 成人式のときに配ってほしかった!」と思って。そこで、性や快楽への偏見を取りのぞければと思い、快感をさまざまなフォルムで表現することにしたんです。

「Guilty Pleasure(ギルティープレジャー)」
性や快楽に対する偏見を解きほぐす作品。
自分のプレジャーを理解し、
それがタブーではないという想いが込められている。
Eri Maeda
——「Guilty Pleasure」の次に制作した作品が、自他境界線(バウンダリー)について表現した「Boundary Guardian(バウンダリーガーディアン)」シリーズですよね。
前田さん:はい。メンタルヘルスについて、友人同士でも気軽に話せるパリでの生活を通して、もっとメンタルヘルスについてオープンに語るきっかけになる作品を作りたいと思い立って制作しました。
日本は察するカルチャーが根付いていて、自分の欲しいものや気持ちをあえて口にしなくても過ごせますが、その分、気を使いすぎて心をすり減らしてしまっている人も多いですよね。それに対して、パリでは自分の意見や欲求をしっかりと言葉で伝えることが必要。相手に「NO」と伝えることが失礼ではなく、むしろ健全な人間関係を築くために大切にされているんです。
そうした自他境界線を持つことにインスパイアされて制作した作品が「Boundary Guardian」で、自分の心や境界を守るための甲冑や、硬い殻のようなものをモチーフに表現しました。

「Boundary Guardian(バウンダリーガーディアン)」
NOって言うのは失礼だって思うよね?私もそうだった。
でも、実はそれって全然違う。
『NO』を言うのは、自分を守るため、
そして相手に本当の自分を知ってもらうために必要なこと。
この作品「バウンダリーガーディアン」は、
そんな気づきから生まれた。
自然界では、蟹の甲羅や牡蠣の殻みたいに、
守るための境界があるからこそ、
内側の柔らかい部分が安心して存在できる。
境界は壁じゃない。
むしろ、お互いを尊重し合うための架け橋みたいなもの。
『NO』を言うのは怖いし勇気がいる。
でも、自分を大切にすることは、
相手とより良い関係を築くための第一歩だって、
この作品に想いを込めた。
Eri Maeda
撮影(人物)/Nobuko Baba(SIGNO) 取材・文・企画・構成/海渡理恵